生成AI

最終更新日:2024/04/09
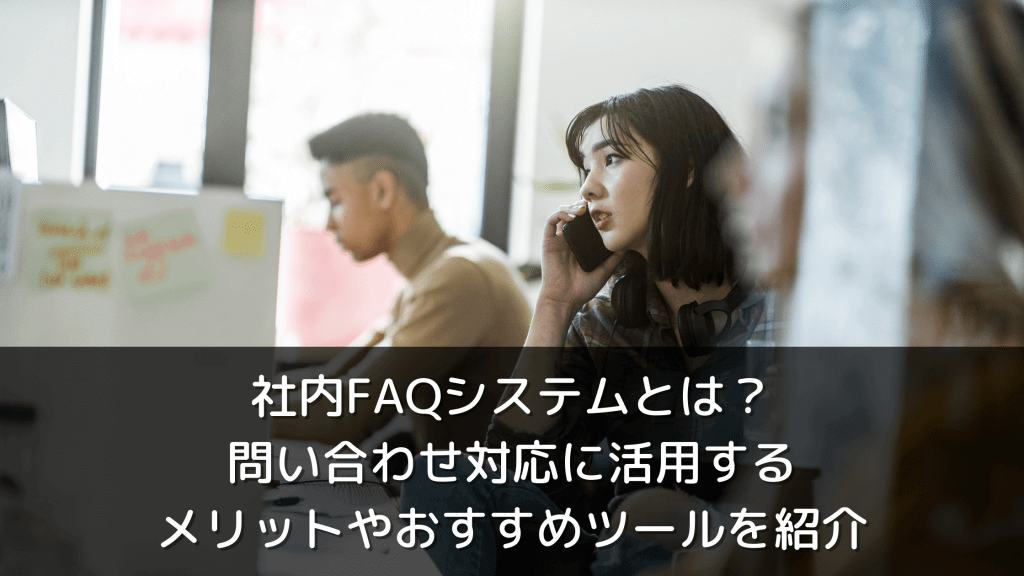
近年は働き方改革の促進に伴い、多くの企業で業務効率化を実現するためのさまざまな取り組みが行われています。その中でも特にAI(人工知能)を活用するケースは多い傾向にあり、これまでの俗人的な業務が一気に自動化・効率化され始めているのです。
その一例としては、問い合わせ対応の効率化を実現する「社内FAQシステム」が挙げられるでしょう。今回は、この「社内FAQシステム」を活用するメリットや、おすすめのツールなどを詳しくご紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
FAQの作り方について詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
問い合わせが来る前に顧客の疑問を解決するFAQの作り方とは?メリットやポイントをわかりやすく紹介

社内の問い合わせに対応するためのコールセンターを設置している企業では、日々さまざまな従業員から問い合わせが寄せられることになります。その問い合わせの中には、オペレーターの経験に左右されずに回答できるものや、知識・経験が豊富なオペレーターでなければ回答できない難しい問い合わせなどがあるわけです。
そのため、同じ内容の問い合わせが何度も寄せられるケースや、難しい内容の問い合わせに苦戦してしまうケースも少なくありません。同じ内容の問い合わせが何度も寄せられると、従業員の負担が増加してしまいます。また、難しい内容の問い合わせ対応に苦戦していると、他の問い合わせ対応に影響を及ぼしてしまう可能性もあるのです。
当然、問い合わせ対応に時間がかかってしまえば、問い合わせを行った従業員の業務にも悪影響を及ぼしてしまいます。その遅延が積み重なることで、企業全体の生産性低下を招いてしまう恐れさえあるわけです。
こういったリスクを避けるための方法として、最近では社内FAQシステムの活用によって業務効率化を実現する企業が多くなってきています。
社内FAQシステムとは、社内のさまざまな部署から寄せられる問い合わせに対応していくシステムのことです。「よくある質問」に対する回答をあらかじめ用意しておくことによって、システムにアクセスしたユーザー(従業員)が疑問を自己解決できるようになります。
従業員が多くない企業であれば、Excelを活用してQ&A方式でまとめていくことも可能ですが、規模が大きくなるにつれて検索数や更新数も多くなっていくため、Excelだけで従業員の疑問を解決していくのは難しいでしょう。そのような背景もあり、最近では社内FAQシステムを活用する企業が多くなってきているのです。
そんな社内FAQシステムは、主に以下の2種類に分けることができます。

一つは、総務、人事、財務・経理、情報シスといったバックオフィス部門に寄せられる問い合わせに対応するための社内FAQシステムです。有給休暇の取得方法に関する問い合わせ、取引先への発注申請の方法といった疑問を解決するために活用されることになります。
こういった疑問をスムーズに解決できない状態では、従業員の業務効率が著しく低下してしまいます。社内全体の生産性を高めるためにも、スムーズに疑問を解決できるFAQシステムの構築が重要といえるでしょう。

もう一つは、コールセンターなどのオペレーションに活用される社内FAQシステムです。コールセンターの現場では、常に顧客対応の品質を維持することが求められます。しかし、業務内容が変化するごとに対応すべき項目にも変化が生まれるため、日々対応マニュアルをアップデートしていく必要があるのです。
社内のオペレーションを統一するためには、一人ひとりがスピーディーに情報を共有することが大切になります。そのようなときに、社内FAQシステムによって最新の情報を共有できれば、コールセンターの対応品質も維持できるのです。

実際に社内FAQシステムを導入した場合、どのようなメリットが得られるのでしょうか。ここからは、社内FAQシステムの導入によって得られるメリットについて詳しく見ていきましょう。
大きなメリットの一つとして挙げられるのは、問い合わせの対応スピードを向上させられるという点です。社内FAQを導入すると、これまで寄せられていた電話での問い合わせの多くをシステムに対応してもらえるようになります。あらかじめ「よくある質問」への回答をシステムに登録しておくため、よりスピーディーに対応できるようになるのです。
これまでは、疑問を持ったユーザーが答えを得るための手段は「電話」もしくは「メール」に限られていました。メールでは回答を得るまでに時間を要してしまうことから、コールセンターに問い合わせが集中してしまうケースも少なくなかったわけです。
当然、コールセンターに問い合わせが集中すれば、オペレーターの負担も増してしまいます。その結果、問い合わせの品質にも悪影響を及ぼしてしまい、顧客の満足度低下を招いてしまうケースがありました。
その点、社内FAQで「よくある質問」の回答をあらかじめ示しておけば、従業員からの問い合わせ件数を削減させることができます。オペレーターは、FAQでは解決できない問い合わせだけに対応すれば良いため、オペレーターの負担軽減にも繋げられるのです。
一般的な社内問い合わせの対応方法は、オペレーターが一つひとつの問い合わせに対応していくというものです。しかし、状況次第では同じ質問ばかりが何度も寄せられるケースも考えられます。こういった「誰でも回答できる問い合わせ」にオペレーターが一つずつ対応していくのは、決して効率的な作業とはいえません。
その点、社内FAQシステムを導入すれば、何度も寄せられる質問への対応をシステムに任せられるようになります。そのため、「社内FAQシステムでは対応できない問い合わせだけにオペレーターが対応していく」という体制を整えることができるのです。属人化を防止・解消できる点は大きなメリットといえるでしょう。
社内での問い合わせ内容は多岐にわたるため、必ずしも簡単に回答できるものばかりとは限りません。場合によっては、知識や経験が求められる問い合わせが寄せられるケースもあるのです。
しかし、昨今は少子高齢化に伴う人手不足が深刻化していることもあり、新人を教育しながら問い合わせ対応の品質を維持していくのは現実的とはいえないでしょう。その点、社内FAQシステムを活用すれば、「よくある質問への対応」をシステムに任せられるようになるため、より効率的にオペレーター教育を行えるようになるのです。
今後AI(人工知能)の技術が発展すれば、FAQシステムが対応できる問い合わせの幅も広がっていくことになるため、将来的には「オペレーターの教育」という業務自体が削減される可能性もあるかもしれません。
社内FAQシステムを導入すれば、トラブルを未然に回避するためのデータ収集を行うことも可能になります。
たとえば、「A部署からの問い合わせで特に多い質問は何か」「その問い合わせは解決できたのか」「FAQシステムでは解決できず、オペレーターを呼び出したのか」といった情報をデータとして蓄積していくことで、問題の発生状況をより俯瞰的に眺められるようになるわけです。
また、人によっては、社内ヘルプデスクのオペレーターに質問することに気を遣ってしまう人もいるでしょう。そのような場合でも、チャットボットを設置しておけば、人に相談しにくい些細な疑問などを気軽に質問することができるようになるのです。
社内FAQシステムを導入することは、必ずしもメリットばかりというわけではありません。いくつかデメリットも存在するため、あらかじめどのようなデメリットがあるか把握しておきましょう。
社内FAQシステムのデメリットの一つとして挙げられるのは、導入コストがかかってしまうという点です。導入には初期費用がかかるだけでなく、必要に応じて機能を拡張させる必要もあります。また、問い合わせ内容は日々変化していく可能性が高いため、定期的なシステムの見直し、更新作業も必要になるのです。
こういった初期費用やランニングコスト、そして運用までの人件費がかかってしまう点は、社内FAQシステムのデメリットといえるでしょう。とはいえ、自社の業務効率化を実現できる社内FAQシステムを構築できれば、社内全体の生産性向上が期待できますので、コスト以上の成果を得られる可能性も十分に考えられます。
社内FAQシステムを導入する際は、事前に「どの程度の成果が見込めるのか」という点をできる限り明確にしておくことが大切になるでしょう。また、最近では運用までの設計を委託できる製品もあるため、それらの活用を検討していくのも一つの手段といえます。
社内FAQシステムは、従業員に使ってもらって初めて効果が得られるものです。そのため、使用率が低いままでは、システムの導入費用がすべて無駄になってしまう可能性もあります。そのリスクは、デメリットの一つといえるでしょう。
より多くの従業員に社内FAQシステムを使用してもらうためにも、従業員が使いやすいと感じられるシステムを構築することが大切になります。「社内FAQシステムを使えば手っ取り早く疑問を解決できる」と思ってもらうためにも、社内FAQシステムの使い方について学ぶ機会を設けていくことが重要になるでしょう。
社内FAQシステムは、常に最適な回答を示すことができるようアップデートを繰り返していく必要があります。業務内容の変化に伴って問い合わせ内容も変化するケースが多いので、定期的なメンテナンスが必要です。
とはいえ、そのメンテナンスにもコストが発生するため、考え方によってはデメリットの一つとして捉えられるでしょう。そのコスト以上の成果を生み出すためにも、適切な運用・メンテナンスが求められます。
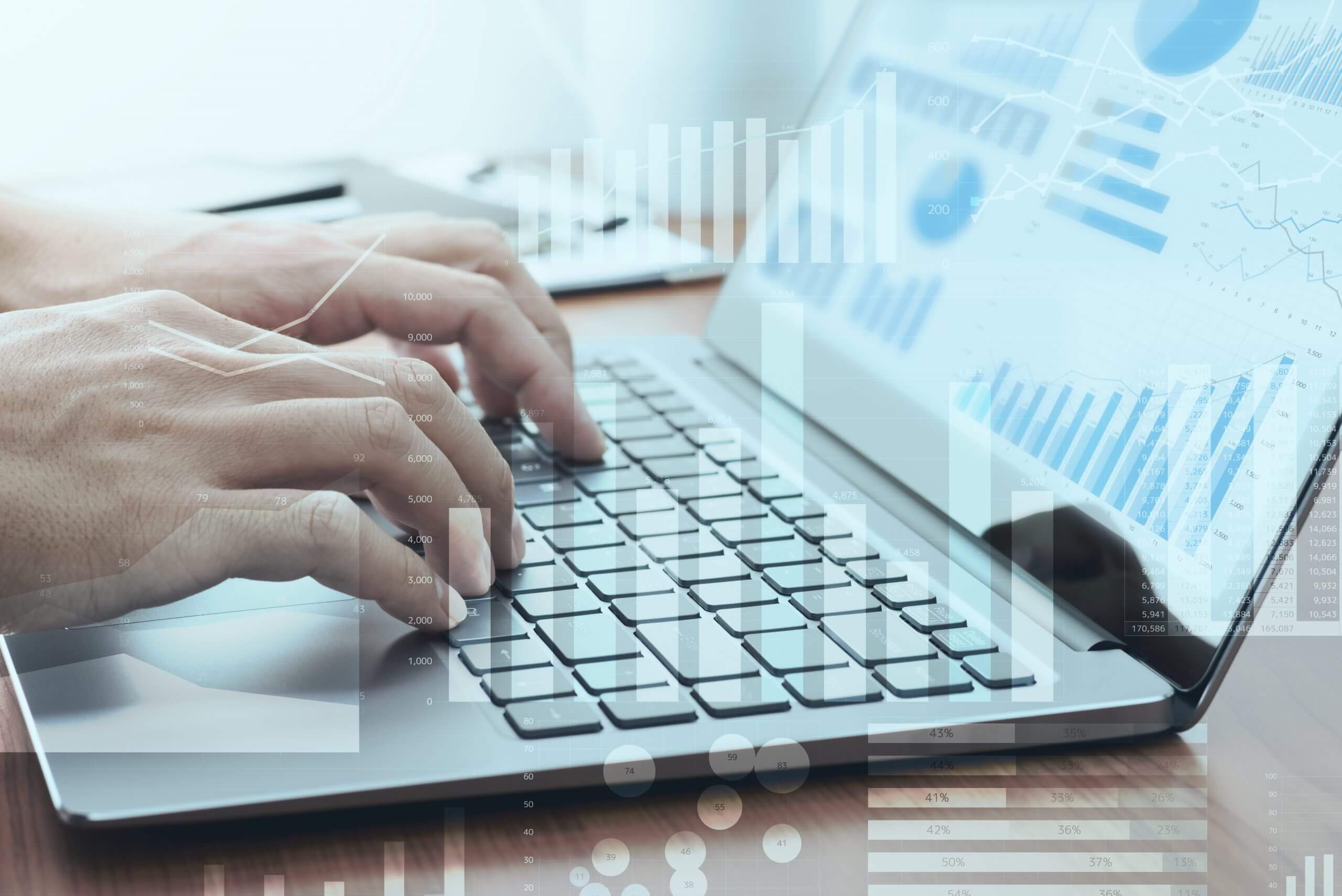
社内FAQシステムと似たものとして、社内向けチャットボットが挙げられます。これらの違いがよく分からないという人も多いのではないでしょうか。
大きな違いとして挙げられるのは、UI(ユーザーインターフェース)です。チャットボットの場合、メッセージアプリのようにチャット形式で気軽に質問を行えるため、気軽に問い合わせして欲しいときに最適といえるでしょう。
それぞれの具体的な活用ケースとしては、以下のような点が挙げられます。
社内FAQシステムを構築していく場合、どのような手順で進めていけば良いのでしょうか。作り方と運用方法について、詳しく見ていきましょう。
初めに行う必要があるのは、FAQ運用チームの結成です。社内FAQシステムを構築する際は、バックオフィスの声を積極的に取り入れる必要があるため、バックオフィスと情シスが協力しやすい体制を築くことが大切になります。
よりスムーズに情報共有を行うためにも、積極的かつ入念なコミュニケーションを実現できる環境を整えましょう。
従業員一人ひとりが適切に社内FAQシステムを活用するためには、しっかりと運用ルールを設けることが大切になります。たとえば、「いきなり問い合わせを行うのではなく、まず社内FAQを確認して解決を試みる」といったものです。
社内FAQで解決できずに問い合わせを行った場合には、その際の内容を社内FAQシステムに登録してもらうことまでルール化すれば、より高精度のシステムを構築することができるでしょう。
初めから完璧なFAQシステムを導入することなどできません。少しずつ使いやすいシステムに育てていく必要があります。そのため、いきなり大勢がFAQを登録してしまうのではなく、まずはQ&Aの蓄積を十分に行ってからFAQの選択期間を設けるようにすると良いでしょう。
FAQは量さえ増えれば良いわけではなく、質も伴っている必要があることを把握しておく必要があります。
FAQシステムを使っていると、重複する項目が生まれてしまうケースがあります。また、使われない古いFAQが増加するケースもありますので、定期的に傾向を分析し、アップデートしていくことが大切です。
より使いやすい社内FAQシステムにアップデートし続けなければ、業務効率化や生産性向上を実現できずにコストばかり膨らんでしまうリスクがあるため、注意しましょう。
現在は、さまざまな企業が社内問い合わせ対応AIツールを開発・提供しています。ツールごとに機能や特徴や大きく異なるため、自社にとって最適なツールを選択することが大切です。ここからは、おすすめの社内問い合わせ対応AIツールをご紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
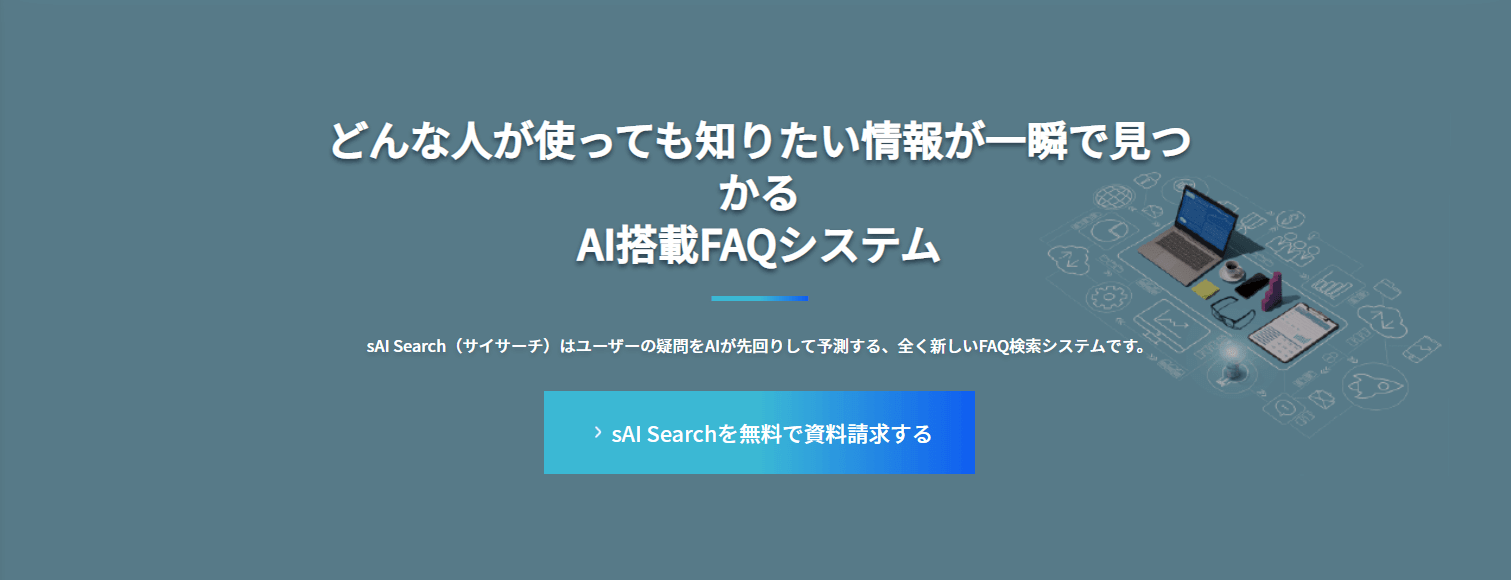
株式会社サイシードが提供しているsAI Search(サイサーチ)は、ユーザーの疑問をAIが先回りして予測する、全く新しいFAQ検索システムです。目的に合わせてUIを選定できるようになっている点は大きな魅力といえるでしょう。
また、ユーザーの求める最適な回答をレコメンドできる機能が搭載されている点も大きな特徴の一つです。ユーザーが検索に使用する検索ワードは多岐にわたるため、文章を柔軟に理解することが大切になります。優れたAIによってこまめなチューニングを実現できる点も大きな特徴といえるでしょう。
Nota株式会社が提供しているHelpfeelは、どんな質問にも答えられる検索型のFAQシステムです。グッドデザイン賞を受賞したことで大きな注目を集めました。
そんなHelpfeelは、製品・サービスサイトにある問い合わせページの検索精度の低さに着目。キーワードから「質問」を予測することで素早く知りたい情報にたどり着けるユーザーインターフェースを実現した独自性や既存の対話型AIチャットボットと比べ、高精度かつ軽量で高速な予測表示を実現しています。
言葉の表現や、感覚的な言葉の表現は一人ひとり微妙に異なるため、社内FAQは柔軟に文章の意味を汲み取る力が求められます。Helpfeelはその力に長けており、スペルミスなどにも対応できる革新的なFAQシステムです。
そのため、簡単に適正な回答にたどり着くことが可能であり、社内のさまざまな情報を効率良く取得できます。
株式会社オウケイウェイヴが提供する「OKBIZ. for AI FAQ Maker」は、AIが問い合わせ履歴を分析し、FAQ作成を支援してくれるツールです。効率的にFAQを作成したい企業にとって魅力的な機能が多く搭載されています。
たとえば、問い合わせデータのグルーピング、不要な単語などの除外、特徴があるキーワードの抽出といった作業をすべてAIに任せることが可能です。これにより担当者は負担が軽減されるため、目視チェックやQuestionデータ成文、そして分類案作成といった業務に力を注げるようになります。
AIに任せることができる業務を自動化し、AIには任せられない業務だけに集中できるようになる点は大きな魅力といえるでしょう。
Salesforceが提供するService Cloud Einsteinは、マウス操作だけで簡単にチャットボットを構築することができるサービスです。CRMに組み込まれたAIによって、すべてのサービス担当者の作業時間短縮と迅速な問題解決をサポートします。
Service Cloudの機能の一つであるEinsteinボットは、SalesforceのCRMと連携したチャットボットです。CRMとつながった独自のチャットボットはお客様のことを理解でき、これまでになく簡単に作成可能で、ビジネスプロセスとも容易につなげることができます。
ボットの構築には基本的にマウス操作だけで、複雑なフローの構築やコーディングは必要ありません。
また、Einstein Next Best Actionという機能を使えば、オペレータが最適なタイミングで、適切なレコメンデーションをお客様におすすめすることも可能です。コールセンター向けのアプリケーション Service Cloud、さまざまなチャネル、すべてのCRMデータ、AIによる予測、すべてを活用して、お客様にパーソナライズされたレコメンデーションを提案できます。
パナソニック ソリューションテクノロジー株式会社が提供しているWisTalkは、トピック推定技術を競う国際コンテストで世界1位を獲得した「パナソニック独自開発エンジン」を採用したAIチャットボットです。また、2020年度チャットボット市場BtoE用途でのベンダー別売上金額シェア1位を獲得したことでも注目を集めました。
そんなWisTalkは、感情分析を搭載し、利用者の苛立ちを緩和するなどの工夫がされています。導入の手間をなるべく軽くするため、「活用ノウハウを熟知したSEの運用サポート」や「活用実績のあるQ&Aテンプレート提供」を基本サービスとして受けることが可能な点は、これからチャットボットの導入を検討している方には嬉しい点だといえるでしょう。
WisTalkの無料トライアルでは、期間中担当SEの支援が受けられ、Q&Aデータが無い場合もサンプルデータで試すことが可能です。なお、サービスにより費用が発生する場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
ネオス株式会社が提供するOfficeBotは、社内の無駄なコミュニケーションを減らすための機能が多く搭載されている高性能AI搭載型チャットボットです。従来必要となる問い合わせ対応のシナリオ作成や、判定基準の定義・登録、類義語辞書設定などが必要なく、FAQを登録するだけですぐにOfficeBotを利用することができます。
実際にOfficeBotを導入している事例の一つとしては、帝人株式会社が挙げられます。帝人株式会社では、社内ポータルには豊富な情報が格納されているものの、必要な情報をすぐに探すことができず、担当部門への問合せが発生するという課題に直面していたそうです。
そこにOfficeBotを導入したところ、効率化に成功したといいます。FAQ登録だけで高精度なBOTを構築・運用できることから、複数の部門でさまざまな用途のBOTを運営しているそうです。
株式会社ワークスアプリケーションズ・エンタープライズが提供しているHUE Chatbotは、社内外の問い合わせ業務を効率化することができる全自動AIチャットボットです。
日本最大規模の辞書(290万語)とNLP(自然言語処理)技術の応用で、高い精度での対話を実現します。FAQや固有辞書はノーコードで登録、さらに利用状況や改善ポイントがダッシュボード化されているため、自社で簡単にPDCAを回すことが可能です。
HUE Chatboの大きな特徴としては、ワークスの徳島人工知能NLP研究所が開発した、国内最大規模の日本語言語処理のための辞書「SudachiDict」を搭載している点が挙げられるでしょう。
たとえば、以下のような違いがあるケースでも、同じ意味として理解することが可能です。
また、ユーザーごとに最適な辞書を作成していくため、業界固有の言葉の触れも柔軟に吸収していくことができます。
今回は、「社内FAQシステム」を活用するメリットや、おすすめのツールなどについてご紹介しました。さまざまなメリットを得られる一方で、把握しておくべきデメリットがあることもお分かりいただけたのではないでしょうか。
ただ、デメリットとして挙げられる部分は、工夫次第でいくらでも解消することができます。たとえば、「コストがかかる」というデメリットに関しては、適切な運用によってコスト以上の成果に繋げられる可能性も十分にあるのです。
また、昨今は少子高齢化に伴い、多くの企業で業務効率化が求められ始めています。そういった背景も踏まえると、社内FAQシステムは今後さらに重要な役割を担っていく存在といえるのではないでしょうか。
ちなみにアイスマイリーでは、人事・総務といったバックオフィス向けサービスの利用料金・初期費用・無料プラン・トライアルの有無などを比較できる資料を無料でお配りしております。AIサービスの導入をご検討の際は、ぜひお気軽にご活用ください。
チャットボットについて詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
チャットボットとは?意味やメリット、活用事例を徹底紹介
業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。
メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。
AI製品・ソリューションの掲載を
希望される企業様はこちら