生成AI

最終更新日:2024/04/05
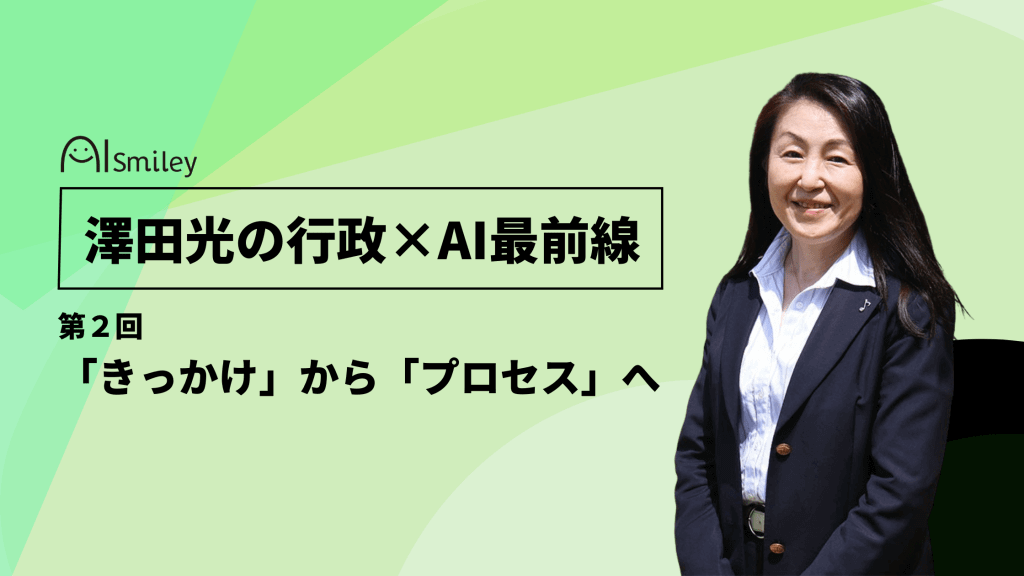 澤田光の行政×AI最前線 第2回
澤田光の行政×AI最前線 第2回
人工知能(AI)により、必要な情報が必要な時に提供されるようになるSociety5.0を目指して、行政の情報化が進められています。しかし、自治体の現場では、「実際何に取り組んだら良いのか?」、「やれと言われてもどうしたらよいか分からない」、「そもそも何から手を付ければよいのか?」など、戸惑う声も多く聞かれます。どうしたら自治体でAIの活用が進むのでしょうか。
【澤田光の行政×AI最前線】では、実際にAIを活用した取り組みを行っている自治体の事例をご紹介し、そうした疑問に答えていきます。
前回は、私の熊本県での実体験をもとに、AI活用のきっかけについてお話しました。でも、その「きっかけ」をどうやって発展させてAI活用に結びつけることができるのか?その点が知りたいところですね。今回は、小さなきっかけから、AI活用までのプロセスについてお話しします。
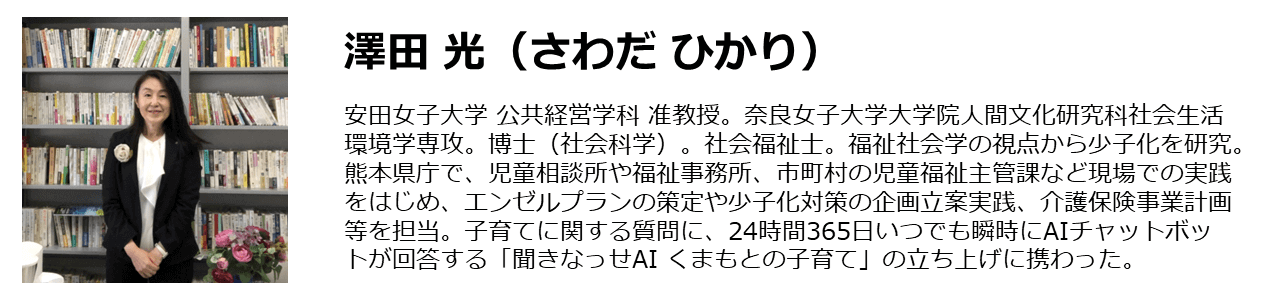

皆さんの業務における困りごとを進化させて、AI活用へと結びつけるためには、まず、5つの問いで徹底的に問題を掘り下げましょう。
これら5つの問いで、課題を可視化したり、文章化したりすることで、問題となっている事柄を徹底的に分析できます。そうすることで、課内での課題共有や、上司への説明、情報部門や財政部門への説明、パートナーとなる事業者への説明が可能になります。そして次に、分析された課題を下記2つの視点で検討します。
課題は、同じ部局内では問題意識を共有していることが多いので比較的説明が容易いですが、情報部門や財政部門に課題をしっかり理解してもらうには、この段階での分析がとても重要です。この作業を行わずして、最初から「AIを活用できそうな業務を探す」ことは、不可能とまでは言いませんが、難しいと考えます。なぜなら、ややもすると行政のひとりよがりであったり、利用者にとって本当に必要な課題なのかどうかが分からなかったりするからです。また、課題分析をすることで、実は業務の進め方に問題があったり、AIを活用しなくても解決できる方法が見つかることもあります。さらに、AIを活用し解決できることを発見することだけでなく、利用者の行動変容を促すことができる可能性もあります。

次に、上記の課題分析をしてデジタル化の有無が明らかになったところで、さらに、AIが活用できそうかどうかを検討します。
AIは万能ではありません。AIを使えば何でもデジタル化できるのではないかという妄想、いわば漠然とした期待があるようですが、実際には、AIは特化した能力を発揮するもので、現在のところ、全てのデジタル化をマルチにこなすものではありません。
現在活用されているAIは、機能別に4タイプに分けられます
(野口竜司, 2020,『文系AI人材になる』, 96-97)東洋経済新報社
デジタル化をするうえで、どの部分にどのAIが使えるかを検討します。つまり、【How】どのようにAIを使うのか?という発想がここで初めて出てきます。AIが活用できるのは、業務のほんの一部分だけなのです。しかし、たとえ一部分だけでも、AIを活用することで、利用者の満足度を上げることが可能ですし、行政にとっては、AIにその部分を任せることで、本当に人でなくてはならないところに、人力を集中させることができます。このことは、人材不足で苦しんでいる自治体にとって大きなメリットになるでしょう。
併せて、AI活用にどのような電子データが必要かも明らかになります。行政は、たくさんのデータを所有しています。ところが、紙によるデータしかなかったり、電子データ化されていなかったりするのが実情です。それらをどのようにして電子データ化するのか、これからの業務をいかに電子データ化して蓄積していくかも検討する必要があります。

AI活用の検討と並行して、AI活用のためのプロジェクトパートナーとなる事業者を探します。現在は、インターネットで、あらゆる情報を探すことができるので、まず、先進事例や先進自治体がないか探してみましょう。AI活用についての情報を提供しているサイトも便利です。
選定した事業者と、パートナーとしてやっていくうえで大切なことは、『こうすればうまくいく行政のデジタル化』で石井大地氏も述べているように、行政から事業者に「丸投げ」にするのではなく、また事業者が行政の「言いなり」になるのではなく、パートナーとして、一緒に考えていくことです。そして、情報部門との協力も欠かせません。常に相談できる協力関係を築き、情報を共有化することが必要です。
次いで、パートナー事業者と一緒にプロジェクトの検討を行っていきます。このとき、行政側で最も注意しなければならないのは、「時間」です。行政では、検討というと長い時間をかける傾向があります。ところが、民間の事業者と一緒にプロジェクトを進めていくには、スピード感が求められます。それは、人件費の考え方に起因すると言われています。行政の場合、プロジェクトの検討に職員の人件費は考慮されませんが、事業者では人件費が織り込まれているからです。私の場合も、パートナー業者の担当の方が、プロジェクトのスケジュールや処理手順のためのロードマップを作成し、きっちりとスケジュールを管理してくれていました。
また、検討を進めていく上では、できるだけ小規模のチームの方が、フットワークが軽くなります。どうしても多くの部署が関係するときは、最初にキックオフミーティングを行い、チーム全体の認識を共有したうえで、活動部隊は小規模にして、必要に応じて必要な部署に情報を共有しておくのが望ましいでしょう。
そして、エンドユーザーとなる利用者に対し実証実験を行います。実証実験の結果について、利用者にアンケートやヒアリングを実施することで、利用者の不満や改善点を把握し、システムに修正を施します。大切なことは、利用者にとって使いやすいかどうか、すなわちユーザーアクセシビリティを、実証実験の結果からしっかり検証、分析して、利用者にとってよりよいシステムを作り、実装に備えることです。ここまでくれば、AI実装は目前です。
今回は、AI導入の「きっかけ」からAI実装までの「プロセス」についてご紹介しました。行政においてAIの活用を進めていくには、AI人材の雇用はもちろんですが、AIを活用できるかどうか、業務担当者自らが関心を持ち、検討するプロセスが重要です。
参考
野口竜司著『文系AI人材になる』(東洋経済新報社)
石井大地著『こうすればうまくいく行政のデジタル化』(ぎょうせい)
馬渕邦美著『東大生も学ぶ「AI経営」の教科書』(東洋経済新報社)
本連載で取り上げて欲しいテーマや事例がございましたら、お問い合わせフォームにご意見をお寄せください。読者の皆様に寄り添った連載を目指して参ります。
編集:AIsmiley 編集部 中村優斗
【澤田光の行政×AI最前線】バックナンバー
業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。
メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。
AI製品・ソリューションの掲載を
希望される企業様はこちら