生成AI

最終更新日:2024/03/04
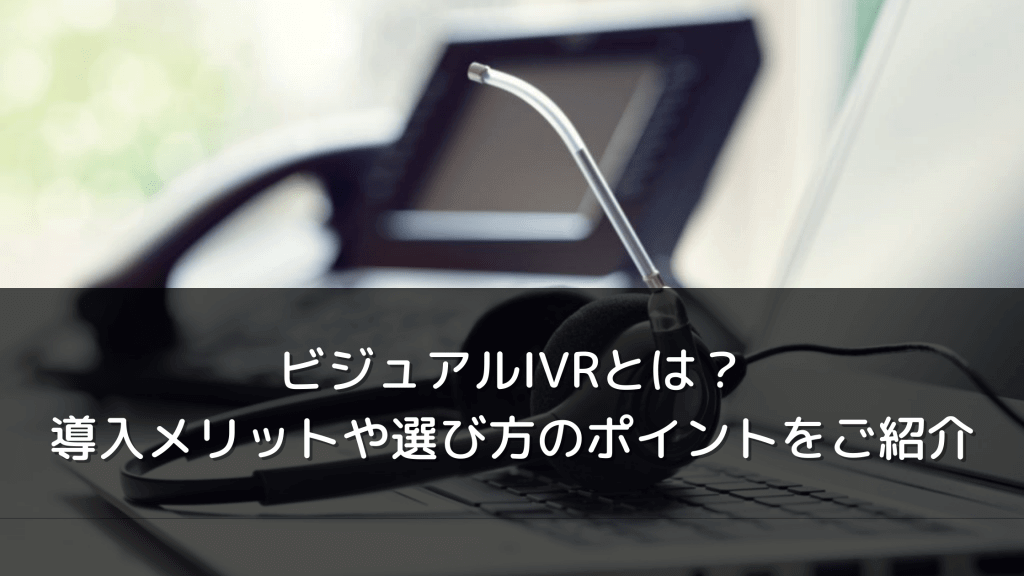 ビジュアルIVRの導入メリット
ビジュアルIVRの導入メリット
スマートフォンのメニュー画面からコールセンターに発信できる「ビジュアルIVR」の導入が増えています。ビジュアルIVR は音声ガイダンスよりも操作性が高い上、FAQページやチャットボットなどによって顧客の自己解決を促進することで、CX向上やオペレーターの負担軽減、コストカットなど多くのメリットが期待できます。
この記事ではAI活用やDX推進に取り組む経営者、管理職の方に向けて、ビジュアルIVRとは何か、メリット・デメリット、システム選定のポイント、企業の導入事例などを解説しています。従来のIVRとの違いや具体的な機能を交えて解説していますので、情報収集にお役立てください。

ビジュアルIVRとは、IVR(自動音声応答システム:Interactive Voice Response)の機能を、スマートフォンで表示するWebページ、または専用のアプリ上で実現するシステムです。視覚的にわかりやすいメニュー画面で操作できるIVRという意味で「ビジュアルIVR」と呼ばれます。ビジュアルIVRには、大きく分けて次の3タイプがあります。
| タイプ | 概要 |
| SMSで通知するタイプ | SMSでビジュアルIVRのWebページ(URL)を通知して利用してもらうタイプ |
| Webページに配置するタイプ | Webページの連絡先ボタンをタップしてもらい、 ビジュアルIVRのWebページを利用してもらうタイプ |
| 専用アプリのタイプ | 専用アプリをインストールしてもらい、 ビジュアルIVRを利用してもらうタイプ |
いずれの場合も、メニュー画面に「お問い合わせ」「商品申し込み」などのボタンが表示され、タップすると連絡先に発信できます。またFAQページやチャットボットなどを配置し、電話以外での自己解決をサポートすることも可能です。
従来の音声ガイダンス方式のIVRでは、操作に手間や時間がかかり、また電話のつながりにくさによって顧客にストレスを与えてしまう課題がありました。それらの課題に対してビジュアルIVRは以下のようなメリットがあります。
| 従来のIVR | ビジュアルIVR |
|
|
|
|
|
|
このようにビジュアルIVRを導入すれば、コールセンターで特に重要なCX(顧客体験価値)を向上できます。具体的なメリットは後ほど詳しく解説します。
顧客をビジュアルIVRに誘導するには、具体的にどのようにしたらよいのでしょうか。ここではSMSでアクセス先を教えてビジュアルIVRに誘導するタイプを例に手順を紹介します。
なおWebページに配置するタイプの場合は、企業のWebサイトにあるビジュアルIVRへの誘導ボタンを押すだけであるため、手順はよりシンプルになります。また専用アプリなら、起動すればすぐにビジュアルIVRを利用できます。ただしWebサイトや専用アプリの存在を知ってもらうための広告、連絡が必要となるため、自社の想定顧客に合ったタイプを選ぶとよいでしょう。

ビジュアルIVRを導入すると、企業側には以下の6つのメリットがあります。
コールセンターのサービスでは、問題解決までのスピードが短いほど、CX(顧客体験価値)を向上できることが知られています。ビジュアルIVRを導入することで、顧客がメニューを迅速に確認でき、目的の連絡先をすぐに見つけられます。
オペレーターに接続するまでの時間を1分程度から10秒程度に短縮できるため、顧客ストレスの軽減が期待できます。特に故障やトラブルなどの緊急対応がメインになるコールセンターにおいては効果的な対策になります。
ビジュアルIVRで顧客の行動履歴の分析や、CRMシステム(顧客管理システム)と連携できるビジュアルIVRなら、さらに高度な顧客対応も実現します。例えばオペレーターが着信を受けた時点で「おおよその要件」や「個人情報」、「過去の問い合わせ履歴」などがわかるため、スピーディーかつ的確なコミュニケーションが可能となります。
電話以外のチャネルを実装できる点も、従来のIVRにはないビジュアルIVRのメリットです。例えば「料金のご案内」などのボタン付近に、よくある質問への回答や、閲覧数上位のQ&Aコンテンツへのリンクを貼ることで自己解決を促せます。またチャットボットやボイスボットを備えたビジュアルIVRなら、自由形式のテキストまたは音声に応対できるため、オペレーターと話す前に問題を解決できることもあるでしょう。
近年はインターネットの普及によって、顧客自らが情報検索することに慣れているため、電話での直接的なコミュニケーションよりWebサイトやチャットボットで自己解決したい人も増えてきました。自己解決のチャネルを複数用意しておくことは、サービス向上の面でもメリットがあります。
ビジュアルIVRでは入電数がオペレーター数を上回った際、FAQページやチャットボットなどの違う手段で応対できます。また混雑時にコールバックの予約を受け付けて、オペレーターが対応できる時間帯に電話をかけられるビジュアルIVRもあります。これらの機能によってあふれ呼や放棄呼による機会損失を減らせることがビジュアルIVRのメリットです。
またビジュアルIVRを導入すると、適切なオペレーターにつなげられたり、顧客情報と連携させたりできることから、顧客とオペレーターとの会話がスムーズになり、通話時間が短くなる傾向があります。その結果、あふれ呼や放棄呼の数が減ることが見込めます。
ビジュアルIVRには、FAQページやチャットボットのように無人で運用できる機能を搭載でき、24時間365日稼働させられます。このため簡単な問い合わせや資料請求など、定型的な顧客ニーズを満たせます。
問い合わせ内容が複雑になりやすく、有人対応が必要になることが多い場合は、コールバック予約機能を備えたビジュアルIVRを導入するのがおすすめです。ビジュアルIVRでは希望日時の入力なども簡単にできるため、顧客の負担は従来のIVRより大きくありません。
ビジュアルIVRの導入により、顧客の自己解決を促進できるため、入電数の減少が想定されます。人員不足の状況を改善できるほか、「短時間で通話を終えなければならない」などのオペレーターのプレッシャーも軽減できます。
また音声ガイダンスより細かな条件分岐を設けられるのも、ビジュアルIVRの特徴です。分岐によって適切な窓口とオペレーターにつなげられるため、不慣れな問い合わせやクレームに対応する機会が減り、業務効率が向上します。また振り分け機能によって、難易度が高い問い合わせをベテランオペレーターにつなげられるシステムもあります。
ビジュアルIVRの導入によって、人件費と通信費の削減も見込めます。先に述べてきたように、入電数の減少や業務の効率化などによって、業務時間を短縮し、場合によっては人員の削減も可能となります。また通話時間が短くなることで、電話代の節約にもなります。
間接的な効果としては、オペレーターの研修コストを下げられるメリットもあります。従来のIVRよりも精度の高い振り分けを実現できるために、オペレーターに教えなければならない知識量を少なくできるからです。難易度の低い問い合わせをアウトソーシングする方法も検討しやすくなるでしょう。

ビジュアルIVRには以下のようなデメリットもあります。まずは課題の整理を行って、「現在のコスト」、「ビジュアルIVRの必要機能・要件」、「今後も人間が行う業務」などを可視化することが大切です。
ビジュアルIVRを導入するには、初期費用と月々のランニングコストがかかります。導入するシステムや規模によるため一概には言えませんが、初期費用は10万円〜50万円程度、月額利用料は2万円〜というのが相場です。ビジュアルIVRでコストカットできる分を上回る支出になるケースもあるため、導入前には費用対効果やROIをよくシミュレーションしておく必要があります。
特にコストが高くつくのは、専用アプリ型のビジュアルIVRを導入する場合です。iOSとAndroidの両方のアプリを開発しなければならないため、ビジュアルIVR 用のWebページを制作するよりコストが高額になります。独自機能やブランドイメージに合わせた画面デザインを導入したい場合は、さらに金額が高くなるでしょう。
オペレーターとすぐに話をしたい顧客も少なからずいます。こうした顧客にとっては、要件を絞り込むためにメニューを選んだり、「どのようなトラブルがありましたか?」などの質問に答えたりするのは手間に感じることでしょう。実際、分岐が長くなる場合は、すぐにオペレーターにつないでしまった方が、解決時間が短くなるケースが少なくありません。
また自己解決を促す仕組みも、顧客によっては面倒に感じてしまうでしょう。「自分で何とかしてください」と言われているようで、不快に感じる人もいるかもしれません。つまりビジュアルIVRの導入によって、CXを下げてしまうリスクもあるのです。ビジュアルIVRは万能なシステムではないため、自社のビジネスモデルや扱う商品によって向き不向きがあることを認識しておきましょう。
ビジュアルIVRで選択するメニューを間違えてしまった場合、システムの仕組み上、顧客が操作をやり直さなければならない場合があります。一方、直接オペレーターにつながるカスタマーサポートでは、一般的にオペレーターが正しい窓口に転送してくれます。顧客がこのような対応に慣れている場合は、ビジュアルIVRの導入前に丁寧に説明しておくか、一定期間、新旧のシステムを並行して稼働させるなど、対応を検討する必要があります。

ビジュアルIVRを選定する際には、以下の3つを軸で検討することで自社に合ったシステムを導入しやすくなります。
自社の商品カテゴリーやサービス形態などに合わせて、画面構成をカスタマイズできるかどうかが重要です。画面構成では、なるべく1ページ内で全体像が把握できるようにするのがポイントになるため、利用できそうなテンプレートとカスタマイズ性があるかチェックしておきましょう。
また導線設計のカスタマイズ性も重要です。特に分岐が複雑になりやすい自己解決用のメニューは、自社商品に合わせて柔軟に追加、修正し、顧客がスムーズに目的を果たせるように設計しなければなりません。条件分岐やデザインなどを自由に変更したい場合は、HTMLやCSSによる変更ができるビジュアルIVRを選ぶことをおすすめします。
分析機能と運用サポートが充実しているかどうかもチェックしましょう。ビジュアルIVRは一度作ったら終わりでなく、顧客の反応をみながら改善していくものであるからです。一部のビジュアルIVRには、顧客の行動履歴や問題解決までの時間などを分析できる機能が備わっており、画面構成や導線設計の改善に役立てられます。
とはいえデータ分析に慣れていなかったり、HTMLやCSSの知識がなかったりする場合もあるでしょう。このような時に重要になるのが「運用サポートの充実度」です。画面のカスタマイズやチャットボットのチューニングなどを請け負っている業者もあるため、自社の体制を考慮してサービスを選びましょう。
高度な機能を実装する場合には、自社のCRMシステム、電話自動応答システム(IVRやボイスボット)、有人チャット、Eメール配信などの外部システムとの接続が必要です。検討ポイントの例を以下に挙げます。
オペレーターにつながったときに重要になります。CRMシステムには、ビジュアルIVR以外の接点であるECサイトやSNS、電話などでのコンタクトの情報が記録されているため、質の高い顧客対応が可能です。
自社のFAQページとビジュアルIVRのFAQページを同期することで、運用管理の手間が減ります。
AIチャットボットが対応できない場合や、顧客がオペレーターとの対話を希望した場合に、有人チャットに切り替えられる機能が用意されていると便利です。
ビジュアルIVRの操作履歴や質問に対する回答内容などをオペレーターシステムに連携できればスピーディーな対応につながります。
各企業はどのようにビジュアルIVRを活用しているのでしょうか。ここでは顧客の自己解決推進の要となるチャットボット・ボイスボットの事例を取り上げます。これらはビジュアルIVR内に組み込まれることがあるほか、メニューボタンからツールを起動して利用することもできます。
パソコンスクールを営むピーシーアシスト株式会社では、申込みフォームからの離脱率が高いことに課題があったため、AIチャットボットを導入しました。電話対応でも申込みを受け付けていましたが、オペレーターの人員不足で、放置呼となるケースが多く発生していました。
導入したGenesys Cloud CXは、Google Cloud Contact Center AIと連携できるため、自社で一からAIを学習させる必要はなく、スムーズに運用を開始できます。そして個人情報の取得から交通アクセスのよい校舎を紹介するまでの業務をチャットボットに代替させることで、予約の離脱率を下げることに成功しています。
成功の要因は「チャットボットによる申込み完了までの時間を平均1分程度に短縮できたこと」です。電話申込みや申込みフォームよりも、顧客の手間を減らせたことで離脱率を下げた事例となります。
日本瓦斯株式会社(ニチガス)は、人的工数の削減や効率的な入居受付を実現するため、ビジュアルIVRから利用できる「AIコンシェルジュ」を導入しました。AIコンシェルジュは入居を開始する顧客から電話があった際に自動応答できるシステムです。
例えば「ガスを3月1日から使いたい」などと顧客が口頭で伝えると、ガスの立ち合い日や住所などをボイスボットが一問一答形式でヒアリングし、予約を確定できます。
AIコンシェルジュの導入によって24時間365日、自動受付できるようになったことで、オペレーターの業務時間が大幅に減りました。またAIコンシェルジュで応対した内容は自社システムに自動登録されているため、顧客情報の処理時間の短縮にも寄与しています。約4人分の人件費を節約できた事例となりました。
みずほ銀行はキャッシュカードなどの再送受付を実現するために、ボイスボットを導入しました。従来コンタクトセンターのオペレーターが応じていた業務を、ボイスボットとの音声のやり取りのみで代替できるシステムです。
AI音声自動受付サービスによって顧客は24時間365日、再送手続きを行えるようになりました。2021年11月に始まった当サービスは、メガバンクのコンタクトセンターにおけるボイスボット導入の先駆けであり、今後同じような事例が増えていくでしょう。
従来の音声ガイダンス方式のIVRに代わって、ビジュアルIVRを導入する企業が増えています。ビジュアルIVRの導入によって、顧客側には利便性向上のメリットがあり、企業側にはCX向上、放置呼数の改善、オペレーターの業務負荷軽減や人件費の削減などの効果が期待できます。
ビジュアルIVRのサービスをより詳しく知りたい方はAIsmiley(アイスマイリー)をご利用ください。利用料金・初期費用・無料プラン・トライアルの有無などを一覧で比較・確認でき、興味のあるサービスの資料をワンクリックで無料請求できます。
コールセンターの人材不足やストレス軽減などでお困りの方はコンサルタントが親身に対応しますのでお気軽にご相談ください。
業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。
メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。
AI製品・ソリューションの掲載を
希望される企業様はこちら