生成AI

最終更新日:2024/03/04
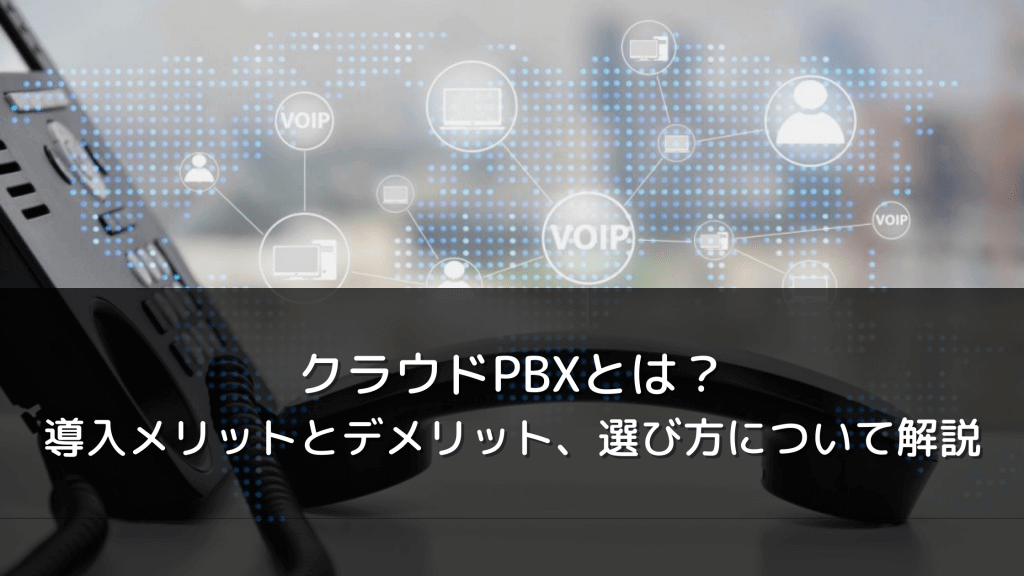 クラウドPBXの選び方とは?
クラウドPBXの選び方とは?
クラウドPBXとは、電話交換機がインターネット上にある仕組みのものを指します。クラウドPBXを活用すると、さまざまな機器を社内の電話として活用可能です。そのため、外出先でも内線が使える点が大きな特徴となります。
またクラウドPBXには、オムニチャネルに対応したものもあります。オム二チャネルに対応していれば、複数の問い合わせ方法がクラウドPBXに一元化され、より確実で効率のよい顧客対応が可能になります。本記事では、クラウドPBXの導入メリット・デメリットや選び方、導入事例を紹介します。

PBXとは、電話の構内交換機のことです。正式名称は「Private Branch Exchange」といいます。構内交換機という言葉にもあるように、会社の社内の電話をコントロールする機能があるのが特徴です。
PBXが会社内に設置されていることで、代表電話を受けたり、社内で電話を取り次いだりすることが可能です。また、フロアが別でも内線通話が行えます。
PBXには、どのような機能が搭載されているのでしょうか。主な機能について詳しくみていきましょう。
PBXでは、発信・着信の制御を行うことができます。それぞれの機能の特徴としては、以下の通りです。
発信制御とは、同一の回線で共有している複数番号のうち、使いたい番号を選んで使える機能のことです。例えば、社外に電話をかける際、同じ電話機で代表電話番号から電話をかけたり、部署の電話番号で電話をかけたりすることもできます。
なお、発信制限機能にはLCRとACRというものが存在します。LCR(Least Cost Routing)とは、電話番号によって通話料の安いプロバイダーを選択することであり、ACR(Automatic Carrier Routing)とは、あらかじめ決められたプロバイダーを選択することです。
着信制御とは、発信制御と同じく複数の電話番号で着信を受けられることです。代表電話である親番号のほか、部署で使う子番号でも着信ができます。
ダイヤルイン機能は、電話回線が1つの場合でも、いくつかの電話番号を利用できる機能です。この機能があることにより、親番号のほか、部署やチーム・個人につながる子番号が使えます。親番号・子番号を含めて「ダイヤルイン番号」と呼びます。
仮にダイヤルイン機能がないと、電話番号ごとに回線をひかなくてはならず、維持費がかかります。NTT東日本の「ダイヤルイン基本プラン」の場合、1番号あたり880円で利用可能です。そのため、コストの削減につながると考えられます。利用したいダイヤルイン番号が多いニーズ向けに、さらに上位のプランもあります。
PBXでは、PBXに接続された電話端末同士であれば、内線で通話ができます。内線であれば通話料もかかりません。フロアが分かれていたり、拠点が全国に複数あったりする場合でも、内線通話が可能です。
内線電話は、通話料の削減のほか電話の取次にも利用できます。内線電話をうまく活用することで、より効率良く電話が取次げると考えられます。
ただし、PBXの提供元によって利用できる内線の台数は異なります。上限がある点はおさえておきましょう。
代表番号着信機能とは、代表電話宛の電話を着信した際、指定した電話機につなぐ機能です。また、着信した電話番号に応じて、着信する電話機を選べる機種もあります。電話をつなぐ際は、空き電話に電話をつないだり、番号順につないだりすることも可能です。
ただし、iナンバーと組み合わせての利用はできない点に注意が必要です。
転送機能は、着信した電話機とは別の電話機・スマホなどに通話をつなぐ機能です。転送には6つの種類があります。
パーク保留機能とは、保留にした電話機以外で保留の解除や通話ができる機能です。通常の電話であれば、保留にした電話機でなければ保留電話の対応を行えませんが、パーク保留であればオフィス内のどの電話機でも対応できます。
仮に、電話を受けたA電話機の担当者では対応が難しい場合があるとしましょう。パーク機能があれば、社内にある別の電話機であるB電話機でそのまま保留を解除し、通話を引き継ぐことができるということです。
もしパーク機能がなければ、折り返し電話をするか、担当者がA電話機まで行き、通話を引き継ぐしかありません。そのため、保留電話のためにオフィス内を移動する必要がなくなるため、より本来の業務に集中しやすい環境を構築できます。

ビジネスフォンとは、会社で使われている電話のシステムの1つです。主装置と呼ばれる小型の交換機と、電話を実際に受ける端末のセットで利用できます。
PBXとビジネスフォンは用途が似ているため、混同してしまいがちですが、どのような違いがあるのでしょうか。違いを詳しくみていきましょう。
1つ目の違いは、接続できる機器が異なることです。PBXでは、会社にあるパソコンやスマートフォンと接続できます。パソコンやスマートフォンを内線として利用可能です。そのため、内線番号で社内と通話できます。ビジネスフォンでは、パソコンやスマートフォンなどのデバイスとつなぐことはできません。
2つ目の違いは、システムの安定性です。PBXは複数のCPUをもっていることが多く、1つのCPUに障害が発生しても、もう1つのCPUで通話が引き続きできます。しかし、ビジネスフォンはCPUが1台しかない場合が多く、障害が発生すると使えなくなってしまうこともあります。
3つ目の違いは、電話機の接続台数です。PBXのほうが接続台数が多く、数千台まで対応可能です。一方、ビジネスフォンは数十台から数百台程度の対応台数です。
クラウドPPXと混同されがちなものとして、IP電話というものも存在します。IP電話は、Internet Protocolを利用して音声や動画のやり取りを行えるサービスです。音声に加えて動画データも交換でき、固定電話と携帯電話の両方で利用できるという特徴があります。
IP電話とPBXの違いとしては、それぞれの形態が挙げられます。PBXは電話回線の交換システムのことを指しますが、IP電話は通話サービスを指します。そのため、これら2つは併せて活用していくことも可能であり、うまく導入すれば双方の機能をより効率的に利用できるのです。
なお、PBXとIP電話を両方利用する場合には、IP-PBXというサービスを利用するのが便利です。IP-PBXについては後ほど詳しく解説していきます。

PBXにはいくつかの種類が存在し、それぞれ特徴も異なります。ここからはPBXの種類と仕組みについて詳しくみていきましょう。
従来のPBXはレガシーPBXとも呼ばれており、オフィス内に電話線と電話機といった物理的な装置を設置するタイプが一般的です。レガシーPBXに搭載されている主な機能としては、外線との発信・着信の制御、内線同士の通話、転送機能、パーク保留機能、代表番号着信などがあります。
停電などが発生して回線を使えない場合でも利用できるというメリットがありますが、導入と管理のコストがかかる点はデメリットと言えます。
IP-PBXとは「Internet Protocol PBX」のことで、レガシーPBXと同じようにオフィス内に設置します。ただし、物理的に配線するのではなく、各端末にIPアドレスを割り当て構築するのが特徴です。IPネットワーク上で音声をやりとりするVoIP(Voice over IP)を用います。
IP-PBXには、ハードウェアとして提供されるタイプと、サーバーにインストールするソフトウェアのタイプがあります。席を変えても番号が変わらないことや、パソコンでも管理できること、スマートフォンも内線化できることなどがメリットとして挙げられます。
クラウドPBXとは、PBXをインターネット上に構築したものを指します。クラウド型であることから、インターネット上にPBXを設置するため、PBXの端末を社内に置く必要がありません。そのため、工事が不要です。インターネット環境があれば、従来のPBXと同じような機能を利用できます。
そして、クラウドPBXのサービスの中には、スマホ用アプリが用意されている場合があります。iPhone・Androidのストアで、スマホアプリをダウンロード・インストールし活用すると、スマートフォンがビジネスホンとして利用可能です。スマホ内にアプリが入れば、さまざまな端末で利用できます。
また、クラウド型であることから、ブラウザで専用Webページにアクセスすることで設定変更が簡単にできます。
クラウドPBXには、クラウド化したことによるメリットが多くあります。たとえば、以下の5つのメリットが挙げられます。
クラウドPBXはクラウド上にPBXを設置することから、工事が不要です。回線を増やす・減らすといった場合にも、従来のPBXのような工事がいりません。また、物理的なPBXの保守・点検の必要もないことから、初期費用や運用コストも抑えられます
そして、スマートフォンをはじめとしたさまざまな端末を電話機として利用できるため、便利に使えます。また、従来のPBXよりも多機能であるのも魅力です。
クラウドPBXには以下のようにデメリットとなり得る点もあります。
クラウドPBXの多くは月額課金型なので、利用状況によっては月の負担が大きくなることがあると考えられます。基本料金のほか外線の通話料金もかかります。そのほか、インターネット回線を利用していることから、通信環境によって音声品質が電話線よりも悪いと感じる可能性もあります。また、回線の種類によってはクラウドPBXを利用できないこともあります。
クラウドPBXが増えている理由としては、クラウドサービス自体の利用が増加傾向にあることが挙げられます。2023年5月に総務省が発表した調査によると、約7割の企業がすでにクラウドサービスを導入しているといいます。
働き方にも多様性が生まれた昨今において、柔軟な働き方はもはや必要不可欠な要素と言っても過言ではありません。そのような中で、通信環境の整備につながるクラウドPBXは、今後もさらに広まっていくことが予想されます。
参考:総務省「令和4年通信利用動向調査の結果」
クラウドPBXはリモートアクセスが可能な点も、大きなポイントと言えます。在宅勤務やコワーキング、フリーアドレス制度など、さまざまな働き方が定着しつつある現代において、そのニーズに応えられるクラウドPBXは非常に重要な役割を担っています。
最近は旅行需要の回復もあり、ホテル業界を中心に人手不足が深刻化しています。そのような背景もあり、予約や問い合わせ対応の効率化を実現するための手段として、積極的にクラウドPBXが導入され始めています。中には、問い合わせ対応や履歴などを一元管理できるCRM連携機能が搭載されたクラウドPBXも存在するため、抱えている課題に応じて最適なPBXを導入すれば、大幅な業務効率化が期待できます。

現在は、さまざまな種類のクラウドPBXが存在するため、課題や目的に応じて最適なクラウドPBXを導入しなければ望んだ成果を得られない可能性があります。そのような事態を避けるためにも、いくつかのポイントを押さえながら導入を検討していくことが大切です。
ここからは、クラウドPBXの選び方についてご紹介していきます。
クラウドPBXを選ぶ際には、管理画面の設定・カスタマイズが簡単にできるものを選びましょう。クラウドPBXを導入した後に、管理画面の設定やカスタマイズがしにくいと、自社に合わせた使い方ができません。
また、クラウドPBXの管理画面を設定・カスタマイズできる場合には、どれくらい簡単にできるかも確認しておきましょう。サービスによっては、複雑なコードを使うのではなく、ノーコードでレイアウト変更できるものもあります。ノーコードの場合、直感的な操作で設定・カスタマイズが可能です。
できるだけ簡単に設定・カスタマイズができるサービスを選ぶと、導入後の運用もしやすくなります。
クラウドPBXを選ぶ場合には、必要な機能をすぐに使えるかも確認しましょう。クラウドPBXは多機能なサービスを提供している場合が多いです。そのため、中には必要な機能を探し出すだけで時間がかかってしまうこともあり得ます。
必要な機能を使うのに時間がかかってしまうと、それだけで時間的なコストがかかります。1回あたりの時間は大したことがなくても、毎回手間取ってしまった場合には、時間のコストが大きくなります。
クラウドPBXを選ぶ際には、必要な機能がすぐに利用できるかを実際にお試し利用させてもらうことをおすすめします。
クラウドPBXを選ぶ際は、オムニチャネルの顧客対応を想定しているかどうかも重要です。多機能なクラウドPBXの中には、音声通話だけでなく、チャットや、メール、SNSなどに対応しているものもあります。そのため、通話のほかさまざまなチャネルを利用する場合には、オムニチャネルに対応しているものを選ぶのがおすすめです。
オムニチャネル対応のクラウドPBXを選ぶと、クラウドPBXのアプリ上でメールやSNSなどのメッセージのやりとりができます。異なるチャネルのメッセージを確認する度にアプリを変える必要がなくなるので、対応の際の業務効率向上が期待できます。コールセンターなどの利用におすすめです。
クラウドPBXの中には、チャットボットやボイスボットとシステム連携できるサービスもあります。チャットボットやボイスボットと連携ができると、チャットボットやボイスボットで対応した後、電話対応へスムーズに移行できると考えられます。通話履歴と紐づけられる機能を備えているものもあります。
一次対応にボットを活用している場合には、クラウドPBXと連携できるかどうかを確かめるのがおすすめです。
また、ボット連携のほかにも、外部システムをAPIなどの拡張機能で追加できるクラウドPBXを選ぶことをおすすめします。自社で既に使っているサービスが、クラウドPBXのサービス上で一元管理できる可能性があるからです。

業務改善の事例として、企業や自治体の電話自動応答に必要なすべての機能をカバーしたボイスボットソリューションの「MOBI VOICE」を紹介します。株式会社横浜銀行様は、融資業務を取り扱う融資課がある店舗ににかかってくる電話が非常に多く、他の事務もやりながら電話に出るため即座に対応できないことが課題でした。そこで、電話の問い合わせを1件も取り残さないボイスボットの効率性から「MOBI VOICE」の導入を決め、電話対応の大きな効率化に成功しています。
MOBI VOICEを導入した店舗では融資に関する電話がほぼ0件になったほか、内容を電話で聞いてからまた折り返しのご連絡をするという工程がなくなったことで、電話対応を1回に抑えることを実現しました。導入前と比較して受電件数は変わっていないものの、想定していた以上に自動音声に対して吹き込む事自体は顧客にかなり受け入れられている印象だということです。また、実際に現場で対応している従業員からは「MOBI VOICEの管理画面で内容が分かってとても楽」「何回も聞かなくていい」というポジティブな反応もあったということです。
MOBI VOICEは、誰がどれを対応しているかをスムーズに認識できるメモ機能があることや、記録期間が長いことも特徴です。注文や手続きの一次受付、自由自在に追加・分岐できるシナリオ作成、IVRでの自動音声対応、アウトバウンドコールなど必要な電話業務をもれなく実現できます。さらに、有人チャットシステムやチャットボット、セグメント配信システムやAI電話自動応答システム、ビジュアルIVRを自由に組み合わせることでことで、顧客満足度の向上も期待できます。
より詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
「MOBI VOICE」を活用した業務改善事例
本記事では、クラウドPBXについて紹介しました。クラウドPBXにはメリット、デメリットがそれぞれ存在するため、しっかりと特徴を理解した上で導入を検討していくことが大切になります。
業務効率化につながる職場環境を実現し、人手不足を解消していくという点も、クラウドPBXは重要な役割を担うツールの一つです。ぜひこの機会に、クラウドPBXの活用によって各々の従業員がより働きやすい環境の整備を始めてみてはいかがでしょうか。
チャットボットやボイスボットのテキストデータを扱う際には、検索システムがあると、情報の検索を効率化できます。検索にかかる時間的なコスト削減も可能です。コンサルタントが無料で相談を承りますのでまずはお気軽にご相談ください。
業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。
メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。
AI製品・ソリューションの掲載を
希望される企業様はこちら