生成AI

最終更新日:2024/01/04
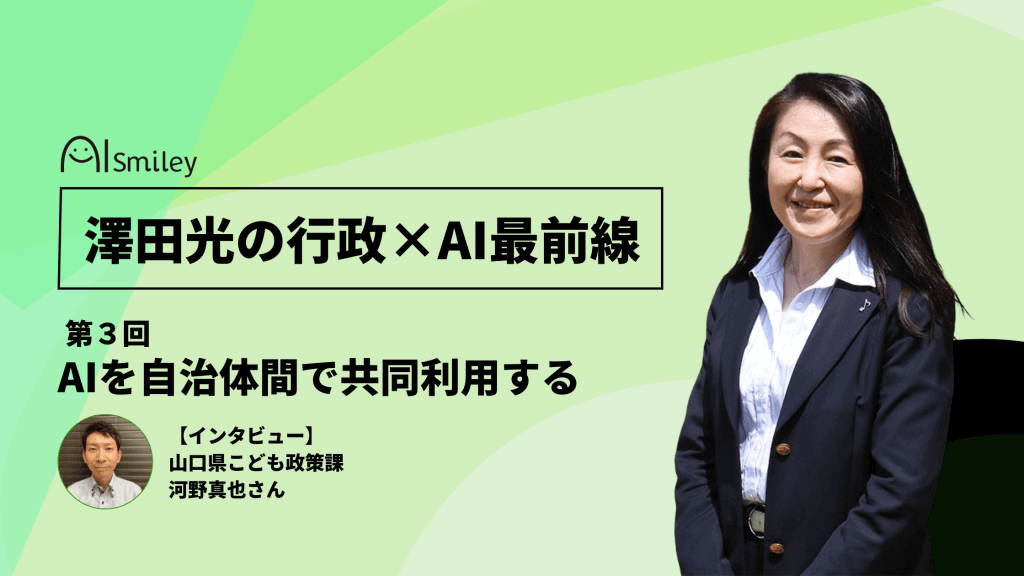 澤田光の行政×AI最前線 第3回
澤田光の行政×AI最前線 第3回
人工知能(AI)により、必要な情報が必要な時に提供されるようになるSociety5.0を目指して、行政の情報化が進められています。しかし、自治体の現場では、「実際何に取り組んだら良いのか?」、「やれと言われてもどうしたらよいか分からない」、「そもそも何から手を付ければよいのか?」など、戸惑う声も多く聞かれます。どうしたら自治体でAIの活用が進むのでしょうか。
【澤田光の行政×AI最前線】では、実際にAIを活用した取り組みを行っている自治体の事例をご紹介し、そうした疑問に答えていきます。
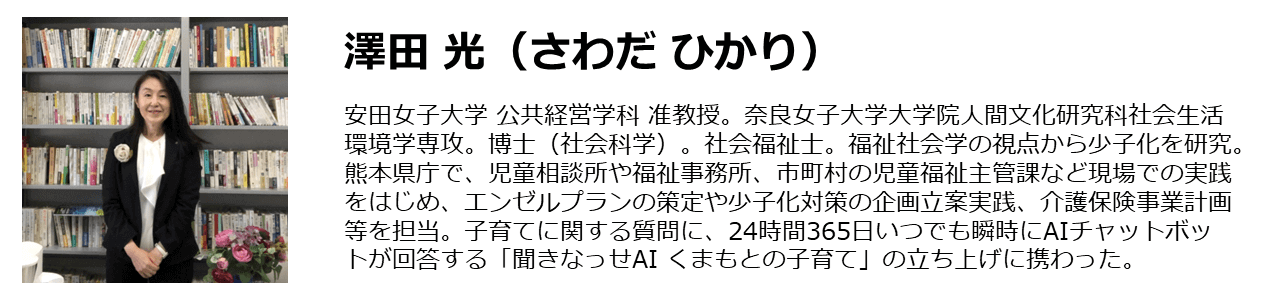
前回まで、自治体でAIを導入するときの「きっかけ」から「プロセス」をお話ししてきました。今回からは、ちょっと目線を変えて、どうしたらAIを手軽に導入できるかということについてお話しします。
AIを手軽に導入する手段の一つに「共同利用」があります。山口県は、AIチャットボットの共同利用を開始し、「やまぐち子育てAIコンシェルジュ(愛称:ちょるなび)」を開設しました。「ちょるなび」は、子育てに関する疑問や質問にAIが回答するサービスです。LINEの友だち登録で利用できます。

あれ?どこかで聞いたことがあると思われた方も多いのではないでしょうか。実は、「ちょるなび」は、第1回でご紹介した熊本県の「聞きなっせAI くまもと」と同じAIチャットボットを共同利用しているのです。
今回は「ちょるなび」を担当されている山口県こども政策課の河野真也(かわのしんや)さんに、お話を伺いました。

山口県こども政策課
河野真也さん
――なぜAIを共同利用しようと思われたのですか?
――河野さん
2020年、新型コロナウイルスの感染拡大により対面による事業ができなくなりました。「対面業務をデジタルに置き換えることはできないか」という全庁的な検討の指示が「ちょるなび」ができたきっかけです。
子育て支援において新しい取り組みはできないかと課の皆で考え、AIの活用を模索していました。ちょうどそんな折、九州・山口地域戦略会議の子育て支援プロジェクトチームで、熊本県の「聞きなっせAI くまもと」を知りました。山口県、熊本県の双方で、AIチャットボットの利用検討を経て、共同利用をすることが決まりました。
――AIの共同利用のメリットは何ですか?
――河野さん
AIを共同利用するメリットは、熊本県が先行して導入していたAIを活用すれば、準備期間が短縮されるうえに、初めから高い正答率が期待できることです。AIは、導入してもすぐに使えるものではありません。AIの正答率を確保するには、多くのデータや実証試験が必要です。
共同利用することで、作り込みが少なくて済んだというアドバンテージがありました。熊本県と共同利用できるデータは山口県でも利用しましたが、熊本県のユーザーに山口県の回答が表示される混乱を避ける必要がありました。ですから、チャットボットのシナリオを構築する際は市町に関連する内容を各県に紐づけ、適切な情報に案内できるような仕組みにしました。
また、山口県でのAIチャットボットの導入の際には、新たに市町独自のデータをAIに学習させる必要がありました。ですが、市町の担当者に「聞きなっせAI くまもと」での事例を紹介することで、山口県の新しい取組みについて、すんなりと理解し受け入れてもらえました。
その後、2022年1~3月に3,000名のモニターキャンペーンによる実証試験を行い、3月末にリリース。4月から本格運用開始という、スピーディーな実装を実現できました。2022年9月時点では登録者が6,100人を超え現在急増中です。
――共同利用することで、正答率が高いAIを最初から使えたうえに、市町の協力も得やすかったのですね。準備段階からリリースまでの期間がとても短いことが印象的です。また、ユーザーが急激に増えていることにも驚きました。他にも何かメリットはありますか?
――河野さん
共同利用のおかげでランニングコストを低く抑えられています。また、「おでかけ」機能については、山口県、熊本県双方の子育て応援の店や、おでかけスポットを探すことができるようになりました。山口県と熊本県は地理的に少し離れていますが、九州新幹線を利用すれば1時間ほどで行き来ができる距離です。
「ちょるなび」や「聞きなっせAI くまもと」を使うことで、子連れでも安心して出かけられるので、ユーザーがそれぞれの県に関心をもってもらえるのではないかと期待しています。
――共同利用がきっかけで、観光にも一役買いそうです。共同利用の副産物ですね。「ちょるなび」の特徴について教えてください。

LINEのメニュー画面
――河野さん
LINEのメニュー画面には、「お父さんの育児手帳」、「医療・救急情報」、「子育て応援パスポート」、「市町の子育てサイト」、「市町のSNS」、「県のSNS相談窓口」、「県からのお知らせ」など、12種類のコンテンツが並んでいます。子育ての分野だけで、これだけたくさんのコンテンツを持つ自治体のLINEはまだないでしょう。
スマートフォンは画面が小さいので、視認性を考慮するとメニュー項目は12個までが限度だと思い、コンテンツを厳選しました。本当はもっとたくさんのリンクと連携させたかったんですよ。
また、管内の市町との連携も重視しました。各市町では様々な子育て支援をきめ細かく取り組まれていますので、WebサイトやSNSとリンクするようにしています。さらに、母子手帳アプリ「母子モ」を活用し、市町と連携した子育て支援情報発信を行っています。
――可愛いくて見やすいメニュー画面ですね。使いやすそうです。今後はどのようなことに力を入れていかれますか?
――河野さん
ユーザーにもっと使い方を理解していただき、どんどん活用してもらいたいですね。「ちょるなび」は、ユーザーとのコミュニケーションを行うために、DAC社のDialogOne(ダイアログワン)を活用しており、初心者ユーザーや、登録したもののあまり活用していないユーザーをセグメントして、積極的に働きかけることが可能になっています。
今後はこの機能を活かして、ユーザーをもっと掘り起こしていきたいです。課題としては、Google検索との競合だと考えています。自治体のAIコンシェルジュだからこそ、信頼できる内容の情報発信を続けていきますので、ぜひ子育てに役立てていただきたいです。
――貴重なお話をありがとうございました。
河野さんにお話を伺い、AIチャットボットの共同利用のメリットがいかんなく発揮されていることが分かりました。共同利用をすれば、学習コストや経済コストが少なく、手軽にAIチャットボットを導入することができます。AIの共同利用が、今後さまざまな自治体で取り組まれると、より安心して子育てできる環境が日本中に広がるのではないかと期待しています。
\LINE公式アカウント/
「ちょるなび」はこちら
本連載で取り上げて欲しいテーマや事例がございましたら、お問い合わせフォームにご意見をお寄せください。読者の皆様に寄り添った連載を目指して参ります。
編集:AIsmiley 編集部 中村優斗
【澤田光の行政×AI最前線】バックナンバー
業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。
メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。
AI製品・ソリューションの掲載を
希望される企業様はこちら