生成AI

最終更新日:2024/06/11
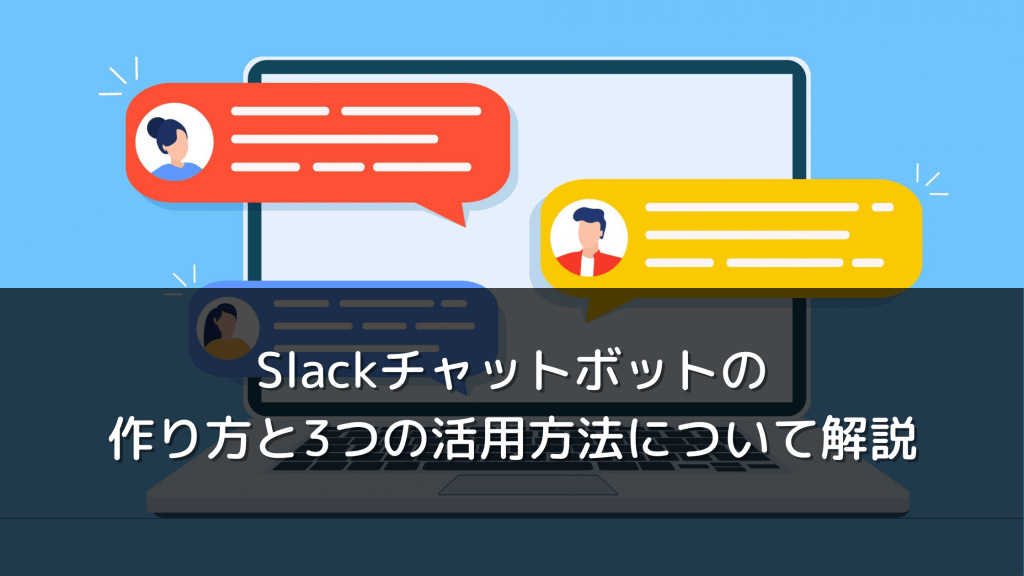 Slackチャットボットの作り方
Slackチャットボットの作り方
メジャーなビジネスチャットツール「Slack」には、自動で会話に応対できる「チャットボット」を搭載できます。チャットボットの導入によって「ヘルプデスクの問い合わせ件数を8割以上減らせた」などのケースもありますので、経営者やDX推進担当者としては、一度は導入を検討しておきたいツールです。
そこで本記事は、Slackのチャットボットとは何か、活用メリット、導入方法、注意点、おすすめのチャットボットなど、必要な知識を一通り解説します。この記事を読めば、Slackのチャットボットを導入する具体的なイメージがつかめるようになるはずです。

Slack(スラック)のチャットボットとは、Slack上で動作する自動会話プログラム、またはAI(人口知能)を指しています。Slackはアメリカのスラック・テクノロジーズ社が提供しているクラウド型ビジネスチャットで、全世界で1,000万人以上のユーザーがおり、日本でも社内チャットツールとして導入する企業が増えています。
Slackにチャットボットを追加すると、これまで人が行ってきた連絡や問い合わせ対応などを代替できるようになります。また、直接的な対話がしにくいリモートワークでのコミュニケーション活性化にも応用できるでしょう。
Slackのチャットボットは、一般的に社内用ツールとして組織全体に導入し、以下のように階層を作って管理します。
これらを適切に管理すれば、自社に合ったコミュニケーション体制を整えられます。メンバーを指定して投稿したい場合は、「メンション」機能を使います。

Slackにチャットボットを導入すると、業務効率化や社内コミュニケーションの活性化、情報発信・収集に役立てられます。
| 用途 | チャットボットの活用例 |
| 業務効率化 |
|
| 情報発信・収集 |
|
| 社内コミュニケーションの活性化 |
|
このようにチャットボットを活用すれば、手間がかかるルーティンワークを減らし、本業に集中できる環境を整えられます。結果として生産性が上がったり、残業時間が減ったりするなどの成果を期待できるでしょう。
また、Slackのチャットボットはコミュニケーションを刺激するような遊び心のあるものが多いのも特徴です。例えば、おもしろ画像を自動で表示したり、ランチのお誘いを代行してもらったりできるボットがあります。「職場の会話が少ない」などの悩みを持つ企業は、試しに使ってみてはいかがでしょうか。

Slackのチャットボットを導入して活用する方法は、3つの方法があります。
方法によって、導入のハードルや工数などが変わってきますので、自社に適した方法を選びましょう。それぞれの方法を説明します。
Slackに標準で搭載されている「Slackbot」を使う方法です。Slackbotでは次の2つの機能を実装できます。
例えばSlackbotに応答メッセージを登録するには、次のようにします。
ご覧のようにSlackbotでは誰でも簡単に登録できますが、複雑な処理はできません。また、会話フローを1つずつ登録する必要があります。もう少し自由度を高めたいなら、次の見出しで紹介する「Slack API」を使うことになるでしょう。
「Slack API」を使えば、外部環境で作成したチャットボットと連携できます。Slack APIとはSlackとのやりとりをパーツ化したプログラムで、必要なSlack APIを組み合わせることによって、さまざまな機能を実装できます。
「Google Apps Script(GAS)」はSlack APIと簡単に連携しやすいプログラミング言語で、Slackのアプリ開発によく用いられるプラットフォームです。GASには「SlackApp」というライブラリがありますので、これらを用いるとSlack APIへのリクエストが数行で作成できます。
一例を挙げれば、
などの処理が可能です。
とはいえ、アプリ作成にはプログラミングの専門的な知識が必要ですし、実用的なアプリを完成するには手間と時間がかかります。専任の人材がいない場合は、かえって開発リスクやコスト増大が起きるケースもめずらしくありません。
このような場合におすすめなのが、ベンダーが提供しているチャットボットを利用する方法です。
外部ベンダーが提供しているSlack連携対応のチャットボットを利用する方法です。外部ツールの場合、ベンダーから導入方法や使い方についてサポートを受けられるため便利です。専門的な知識を持った人材がいない企業も、安心して運用できるでしょう。
導入する際は大きく2つのケースに分かれます。
既にベンダーのチャットボットを使用している場合は、Slackに対応していれば流用可能です。多くのチャットボットはSlack、LINE WORKS、Microsoft Teamsなど複数のコミュニケーションツールの連携に対応していますので、確認してみてください。
一方、新たにベンダーのチャットボットを購入する場合は、Slack連携対応のものを選びます。この際、業務システムやメールソフトなど、他に連携したい外部システムがあれば、併せて調べておくことをおすすめします。

Slackbotは追加料金なしで利用でき、FAQのような簡単な機能なら手軽に実装できるのがメリットですが、次のような問題点もあります。
本格的に業務効率化やDXなどを進める場合、Slackbotでは物足りなくなるケースが多いでしょう。
Slackbotでは機能が不十分、かといって、Slack APIでプログラムを作成するのはハードルが高い場合はベンダーのチャットボットを利用するのが一般的です。
そのメリットの1つ目は、ベンダーのサポートによってプログラミングや各種設定のハードルをなくせる点です。応対シナリオのテンプレートも用意されているため、準備負担も減らせます。
2つ目はAIによって複雑な処理に対応できる点です。製品にもよりますが、社内文書やチャットボットとのやりとりなどで学習を続けるため、Slackbotでは実現できない高度な応対ができます。
3つ目はSlackをプラットフォームにしてOffice365や業務システムなどとチャットボットを連携できる点です。例えば「チャットボット経由でZoom会議室を予約して、参加メンバーにメールで通知する」などが可能です。
外部のチャットボットはSlackbotより高性能で、使い勝手もよいのは確かですが、幾つかのデメリット、注意点もあります。
本格的なツール選定に移る前に、以下の3点は確認しておきましょう。
ツールを選定しやすくするには、どのような目的でチャットボットを導入するのか、どの業務を自動化したいのかなどを明確にしておくことが大切です。
ここでは、ベンダーが提供しているSlack連携が可能なチャットボットを紹介します。
それぞれ特徴がありますので、導入事例を交えながら詳しく解説します。
上記のおすすめチャットボットの資料をまとめて請求したい場合は、AISmileyをご利用ください。

Benefitterは働き方を進化させられるチャットボットを開発するための開発プラットフォームです。環境を視覚的に設定できる操作画面が用意されていますので、短期間で高度なAIを作成できます。
開発したチャットボットは、Slackをはじめとしたコミュニケーションツールや、他のAIチャットボット、業務システム、Webサービスなどと連携できます。連携設定は外部サービスのURLやメソッド、データ形式などを登録するだけで実行できるため、開発工数を大幅に削減可能です。
例えば、「この質問は人事?総務?法務?」といった内容の質問や、「Webサイトをリニューアルできる人材を探したい」などの要望をSlackのチャットボットを窓口にして解決できるようになります。

QuickQAは純国産の日本語AIを搭載したQA(品質保証)ソリューションです。学習済みのAIが質問者の表現ゆれ、あいまいな言い回しを吸収してくれるため、Slack上での自然な対話を実現します。また、AI学習、チューニング作業も、クリックボタンによる直感的な操作で実現できますので、特別な専門知識も要りません。
QuickQA導入が向いているのは、ヘルプデスクの業務負荷の軽減、コストカットを目指したい企業です。
実際の導入事例では、ヘルプデスクやサポートセンターなどへの問い合わせの解決率は75~85%にも及びます。対応できない内容は有人チャットで解決できますので、利便性を下げずに、業務を効率化できます。
-お問い合わせ対応自動化-pep.work_-1024x463.png)
PEPは複雑な情報をスピーディーに抽出できる「業務自動化チャットボット」です。Slack上で動作するPEPを通じて、各種マニュアル(業務マニュアル、申請書類、ナレッジデータベースなど)にアクセスします。
例えば、全日空商事株式会社では、複雑な社内イントラ情報やマニュアル探しをPEPに一元化しました。その結果、メールや電話で回答していた割合を10%程度削減できたということです。
PEPは導入のしやすさにも強みを持っています。PEPの管理画面から簡単にSlackチャットボット化できるため、導入コストやプログラミングなどのハードルがとても低いのが特徴です。導入サポートも受けられますので、すでにSlackを利用していれば、約1カ月で運用スタートできます。
Slackにチャットボット機能を追加すれば、人が実施してきた連絡や問い合わせ対応などの一部を代替できるようになります。単純な応答なら、標準搭載のSlackbotやSlack APIを使った自作アプリで実現可能です。
しかし、中長期的なビジョンで業務効率化やDX推進を目指すなら、やはりベンダーが提供しているチャットボットをSlackに連携させる方法をおすすめします。ベンダーからは高度なAIを搭載したものや、他のシステムとの連携性に優れたものなどが提供されています。ぜひ自社にあったチャットボットをみつけてください。
チャットボットについて詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
チャットボットとは?意味やメリット、活用事例を徹底紹介
業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。
メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。
AI製品・ソリューションの掲載を
希望される企業様はこちら