生成AI

最終更新日:2024/11/20
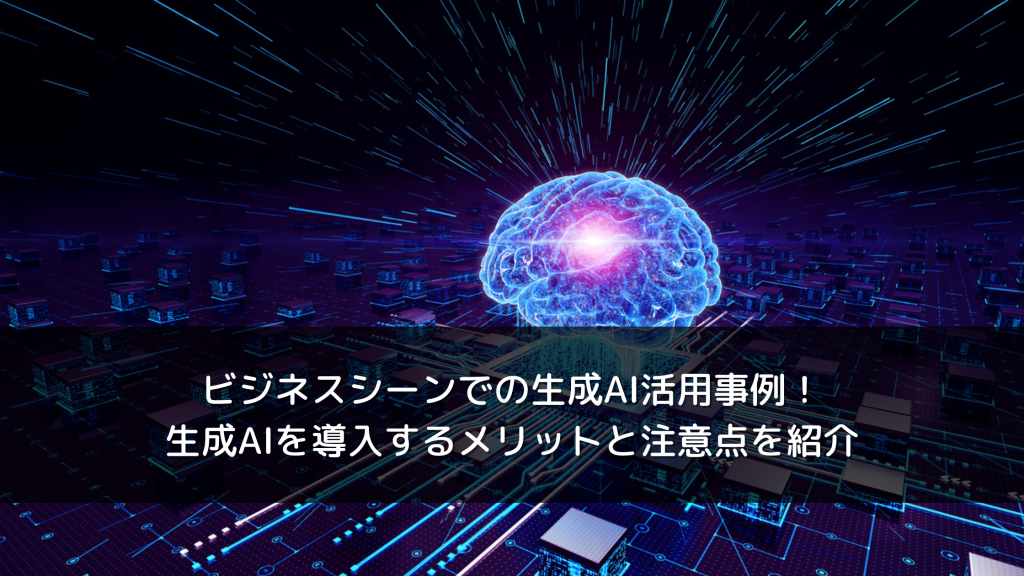 ビジネスでの生成AI活用事例
ビジネスでの生成AI活用事例
生成AIの技術進捗により、ビジネスシーンでの活用が急速に広がっています。本記事では、生成AIの具体的な活用事例やメリット、注意点について詳しく解説します。生成AIをビジネスに取り入れたい企業や、生成AIの可能性に興味がある方にとって有益な情報をお届けします。

生成AIは、大量のデータを学習し、そこから新たな情報やコンテンツを生成する能力を持っています。具体的には、テキスト・画像・音声・プログラムコードなどの出力が可能です。
大きな特徴は、少ないデータから創造的なアウトプットを生み出せることです。従来のAIが大量のデータを必要としたのに対し、生成AIは限られた情報からでも、人間の創造性に劣らない表現を生み出すことができます。
AI自体は約60年前から存在していましたが、近年の技術革新により大きく進化しています。初期のAIは単純な計算や定型的なタスクの処理に限られていましたが、機械学習やディープラーニングの発展に伴い、より複雑な判断や予測が可能になりました。そして現在、生成AIの登場により、創造的なタスクまでもAIが担えるようになりました。
| これまでのAI | 生成AI | |
| 学習方法 | 特定のタスクや分野に特化 | 幅広い知識と文脈理解 |
| 目的 | 分類・予測・最適化など | 新しいコンテンツの創造・問題解決 |
| 学習データ | 構造化されたデータが中心 | 非構造化データを含む多様なデータソース |
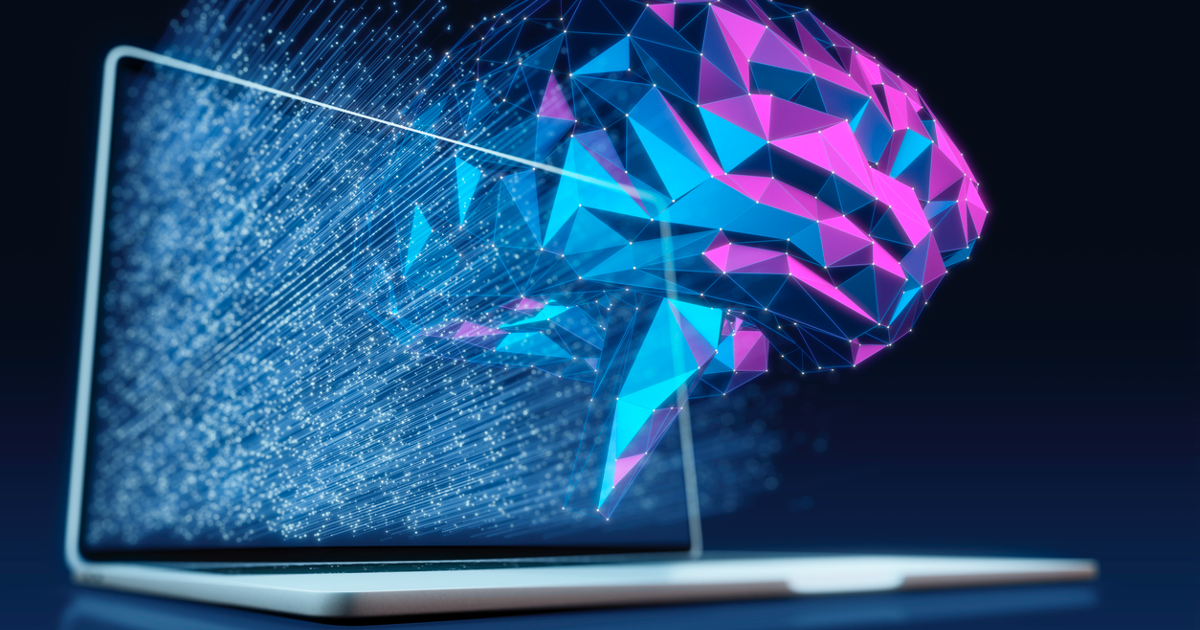
生成AIは様々な業界で活用され始めており、多岐にわたる業務で効率化や革新をもたらしています。ここでは、具体的にどのような企業が生成AIを活用し、どのような効果を得ているのか、実際の事例として、以下の7つを紹介していきます。
これらの事例を通じて、生成AIがビジネスにもたらす可能性と実践的な活用方法を理解することができます。
フリマアプリ大手のメルカリは、生成AIを活用して出品者のサポートに取り組んでいます。「メルカリAIアシスト」という機能を導入し、出品済みの商品情報を分析して、売れ行きを向上させるための商品名や説明文の自動生成し・提案をしています。
この取り組みにより、出品者は効果的な商品紹介文を簡単に作成できるようになりました。結果として、商品が購入者の目に留まりやすくなり、取引の活性化につながっています。生成AIの導入により、ユーザー体験の向上と取引量の増加という二つの効果を同時に実現しています。
学研ホールディングスは、生徒の学習をサポートするために生成AIを活用しています。同社のオリジナル学習システム「GDLS」にChatGPTを組み込み、個別に最適な学習アドバイスを提供します。その結果、生徒の学習効果を最大化し、学習への意欲を高めることに成功しています。さらに、毎日ログインする習慣を促すことで、継続的な学習をサポートしています。
大林組は、建築設計の初期段階における効率化を目指して、生成AIを活用したツールを開発しました。このツールは、建物の大まかな形状を描いたスケッチや3Dモデルをもとに、建物の外観デザインを複数提案することができます。
この技術により、設計者は迅速にデザイン案を生成し、顧客の要望をすぐに形にすることが可能になりました。顧客との意見のすり合わせがスムーズに行えるようになり、最終的なデザインへの合意を迅速に進めることができるようになりました。結果として、設計プロセスの大幅な短縮と顧客満足度の向上を実現しています。
SMBCグループは、ChatGPTを活用して開発した独自のAIアシスタントツール「SMBC-GPT」の実証実験を開始しました。このツールは、SMBCグループ専用の環境で動作し、文章の作成・要約・翻訳・ソースコード作成など、多岐にわたる業務をサポートします。
この取り組みにより、従業員の生産性向上が期待されています。特に、定型的な文書作成や情報検索の効率化が図られ、従業員がより創造的な業務に集中できるようになります。また、AIアシスタントの回答内容の正確性を従業員が判断し、外部AIの利用禁止などの規制も順次見直していく予定です。
KDDIが提供するauは、2024年のお正月を祝して、人気の「三太郎シリーズ」CMを生成AIを使ってアニメーションにリメイクし、話題を呼びました。このCMは単なる視聴だけでなく、特設サイトで視聴者が自分だけのオリジナル三太郎MVを生成AIを使って作成できるという、参加型の新しいCM形態を実現しました。
この革新的な取り組みは、通常のCM以上に視聴者のロイヤリティを向上させ、先進的な企業イメージの訴求に大きく貢献しました。生成AIを活用することで、顧客との双方向のコミュニケーションを実現し、ブランド価値の向上につながっています。
パナソニックは、電動シェーバー「LAMDASH」シリーズに、AIがゼロベースで設計した新構造のモーターの採用を検討しています。このAI設計のモーターは、熟練技術者による最適設計と比較して、出力が15%高いという優れた性能を示しています。
この成果を受けて、パナソニックはAI設計の有効性を確認し、今後は電動工具や車載用のモーダー、さらにはシーリングファンなどにも適用範囲を広げる方針です。生成AIの活用により、従来の人間の設計を超える性能を持つ製品の開発が可能となり、製品競争力の大幅な向上が期待されています。
セブンイレブン・ジャパンは、商品企画の時間を大幅に削減するために生成AIの活用を開始しました。この取り組みでは、店舗の販売データやSNS上での消費者の反応を分析し、新商品に関する文章や画像を迅速に作成することが可能となりました。
生成AIの導入により、商品企画にかかる時間が最大で90%削減されました。これにより、市場のトレンドや顧客のニーズに迅速に応える新商品の提供が可能となり、競争力の強化につながっています。また、商品開発サイクルの短縮により、より多くの商品のアイデアを試すことができ、ヒット商品を生み出す確率も向上しています。
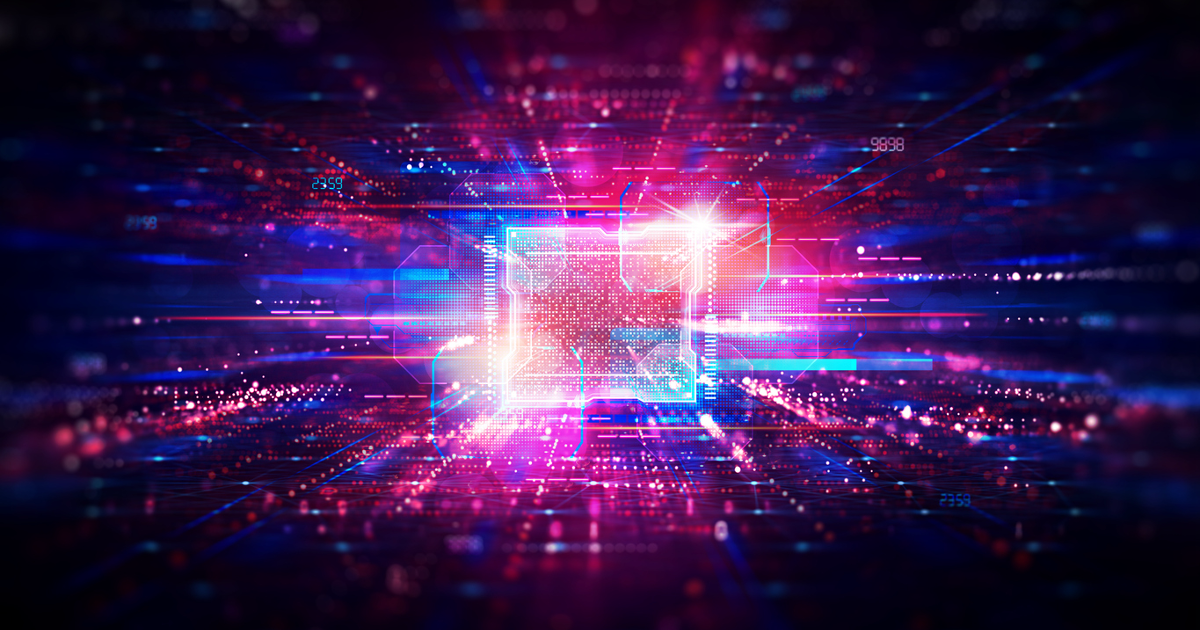
生成AIをビジネス利用するメリットには、以下の点があります。
作業効率の大幅な向上・収益の拡大・新たな価値創造の機会など、生成AIがもたらすメリットは計り知れず、多くの企業が導入を検討し始めています。
従来の業務プロセスを根本から変革し、人間の創造性をさらに引き出す生成AIは、ビジネスの未来を形作る重要な要素となっています。これらのメリットを理解することで、生成AI導入の意義がより明確になります。
生成AIを活用す ることで、企業の生産性と作業効率が大幅に向上します。従来、人間が時間をかけて行なっていた作業を、AIが数秒から数分で完了することができるようになりました。例えば、文書作成・データ分析・画像生成などの業務において、生成AIは人間の何倍もの速度で高品質な成果を生み出すことが可能です。
具体的には、営業資料の作成や顧客向けのプレゼンテーション資料の準備など、通常であれば数時間かかる作業を、生成AIを使用することで数分で完了させることができます。また、大量のデータから有用な情報を抽出し、わかりやすくまとめる作業も、AIが瞬時に行うことができます。
これにより、従業員は創造的な業務やより高度な判断を必要とする業務に集中することが可能となり、企業全体の生産性が飛躍的に向上します。
生成AIの活用は、企業の利益拡大に直結します。AIによる業務効率化によってコスト削減が実現するだけでなく、新たな収益源の創出も可能となるからです。例えば、マーケティング分野では、生成AIを使用して顧客の購買パターンやトレンドを分析し、より効果的な広告やキャンペーンを立案することができます。
具体的には、生成AIを活用して顧客の嗜好に合わせたパーソナライズされた商品提案や広告コピーを作成することで、顧客の購買意欲を高めるこことができます。また、カスタマーサポートの自動化や効率化により、24時間365日の対応が可能となり、顧客満足度の向上と同時に人件費の削減も実現します。
これらの取り組みにより、企業の売り上げ増加とコスト削減の両面から利益拡大が期待できます。
生成AIの活用は、単なる業務効率化にとどまらず、新しい企業価値を創出する可能性を秘めています。AIの創造力と人間の専門知識を組み合わせることで、これまでにない革新的な製品やサービスを生み出すことができるのです。例えば、AIが大量のデータから新たな市場トレンドを発見し、それに基づいて人間が新事業を構想するといった協働が可能となります。
具体的には、製薬業界での新薬開発において、AIが膨大な化合物データを分析し、有望な候補物質を提案することで、開発期間の短縮と成功率の向上が実現しています。また、金融業界では、AIによる高度なリスク分析に基づいた新しい金融商品の開発が進んでいます。
さらに、エンターテインメント業界では、AIが生成した斬新なストーリーやキャラクターデザインを基に、人間のクリエイターが新たな作品を創造するといった取り組みも始まっています。このように、生成AIは企業に新たな創造の可能性を提供し、従来の業界の枠を超えた価値創造を可能にしています。
生成AIの活用により、企業は顧客満足度や顧客体験を大幅に向上させることができます。AIの高度な分析能力と迅速な対応力を活かすことで、個々の顧客ニーズにきめ細かく対応し、パーソナライズされたサービスを提供することが可能になります。例えば、eコマース分野では、AIが顧客の購買履歴や閲覧履歴を分析し、各顧客の嗜好に合わせた商品推奨を行うことができます。
具体的には、オンラインショッピングサイトで、AIが顧客の好みを学習し、その人に最適な商品を提案することで、購買率の向上と顧客満足度の増加を実現しています。また、カスタマーサポートにおいても、AIチャットボットが24時間体制で迅速かつ的確な回答を提供することで、顧客の待ち時間を削減し、サポート品質を向上させています。
さらに、金融機関では、AIが顧客の資産状況や投資目標を分析し、最適な投資プランを提案することで、顧客の資産運用を効果的にサポートしています。このように、生成AIは企業と顧客との関係を深め、より良い顧客体験を創出することに貢献しています。
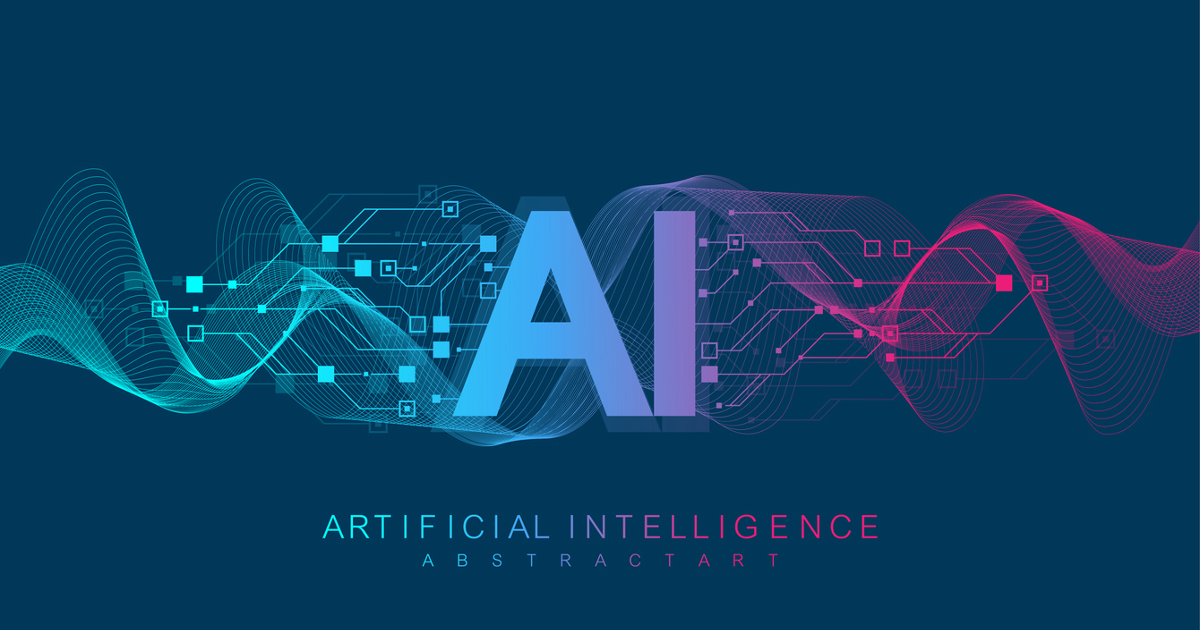
生成AIをビジネス利用する上での注意点には、以下のものがあります。
生成AIは革新的な技術ですが、ビジネスで活用する際には慎重な姿勢が求められます。個人情報の取り扱いや出力内容の精査、責任の所在といったいくつかの重要な注意点があります。これらを十分に理解し、適切に対処することで、生成AIの潜在力を最大限に引き出せるようになります。
生成AIを活用する際に最も注意すべき点は、個人情報を含む機密情報の取り扱いです。多くの生成AIサービスは、入力されたデータを学習に使用する可能性があるため、個人情報や企業の機密情報を不用意に入力してしまうと、重大な情報漏洩リスクにつながる恐れがあります。
例えば、ChatGPTなどのオープンな生成AIプラットフォームに、顧客のメールアドレスや社内の機密文書の内容を入力してしまうと、その情報がAIの学習データに取り込まれ、他のユーザーに共有されてしまう可能性があります。このような事態は、個人情報保護法違反や企業の信頼失墜につながる深刻な問題となります。
したがって、生成AIを使用する際は、個人を特定できる情報や企業の機密情報を絶対に入力しないよう、厳重な注意が必要です。また、企業内で生成AIを活用する場合は、専用の閉じた環境を構築し、情報セキュリティを確保した上で利用することが重要です。
生成AIが作り出す内容は、非常に自然で説得力のあるものが多いですが、必ずしも正確性や信頼性が保証されているわけではありません。そのため、AIが生成したコンテンツを使用する前に、人間が必ず内容を精査し、著作権侵害や倫理的な問題、フェイク情報の有無を確認することが極めて重要です。
例えば、生成AIが作成した文章や画像が、既存の著作権物と類似している可能性があります。これを無自覚に使用してしまうと、著作権侵害のリスクが生じます。実際に、AIが生成した商品名やロゴが、すでに商標登録されていたケースも報告されています。このような事態は、企業の信頼性を大きく損なう可能性があります。
また、AIが生成したコンテンツには、時として偏見や差別的な表現が含まれています。これらを見逃して公開してしまうと、企業の評判に深刻なダメージを与える可能性があります。さらに、AIが誤った情報や架空の事実を含む文章を生成することもあり、これらをそのまま使用すると、フェイクニュース拡散につながる恐れがあります。
したがって、生成AIを活用する際は、必ず人間による内容チェックのプロセスを設けることが不可欠です。特に、公開前の最終確認では、法務部門や広報部門など、複数の目で精査することが推奨されます。
生成AIで作り出されたコンテンツに関して、何らかのトラブルが生じた場合、責任の所在が不明確になるケースがあります。これは、AIが自律的に作成したコンテンツに対して、誰が最終的な責任を負うべきかという問題が生じるためです。
例えば、AIが生成した広告コピーが誤解を招く表現を含んでいた場合、その責任は広告を出稿した企業にあるのか、AIシステムを提供した企業にあるのか、それともAIを操作した担当者個人にあるのか、判断の難しい状況が発生する可能性があります。また、AIが生成した製品デザインに欠陥があり、事故が起きた場合の責任の所在も同様に不明確になる可能性があります。
このような事態を避けるために、生成AIを活用する前に、想定されるさまざまなケースについて責任の所在を明確に定義しておくことが重要です。具体的には、以下のような対策が考えられます。
| 対策 | 内容 |
| 利用規約の整備 | AIの使用に関する社内規定を作成し、生成したコンテンツの使用に関する責任の所在を明確に定める |
| 承認プロセスの確立 | AIが生成したコンテンツを使用する前に、必ず人間による承認を経るプロセスを確立する |
| 保険の検討 | AIの使用に伴うリスクをカバーする保険の加入を検討する |
| 契約の見直し | AIベンダーとの契約において、責任の分担を明確に規定する |
| 教育・トレーニング | AIを使用する従業員に対して、適切な使用方法と責任に関する教育を行う |
これらの対策を講じることで、生成AIの活用に伴うリスクを最小限に抑えつつ、その利点を最大限に活かすことが可能となります。責任の所在を明確にすることは、企業がAIを安全かつ効果的に活用するための重要な前提条件と言えます。
本記事では、IT・教育・建築・金融・通信・製造・小売などさまざまな業界での生成AI活用事例を紹介しました。生成AIのビジネス利用には、生産性向上・利益拡大・新しい企業価値の創出・顧客満足度向上などのメリットがある一方、個人情報の取り扱い・生成内容の精査・責任の所在の明確化などの注意点があります。
生成AIは多くの可能性を秘めており、適切に活用することで、ビジネスに大きな変革をもたらす可能性があります。企業は、これらのメリットと注意点を十分に理解し、自社の状況に合わせて導入・活用していくことが求められます。
業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。
メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。
AI製品・ソリューションの掲載を
希望される企業様はこちら