生成AI

最終更新日:2025/07/24
 AIエージェントの例
AIエージェントの例
企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)や業務効率化が加速する中、「AIエージェント」の導入が注目を集めています。本記事では、AIエージェントの基礎知識から、さまざまな業界での活用例、導入時の注意点までを詳しく解説します。自社の業務課題を解決するヒントとして、ぜひ参考にしてください。

AIエージェントとは、人工知能を活用して人間の代わりに情報処理や意思決定を行うプログラムのことです。自然言語処理、機械学習、画像認識などの技術を用いて、ユーザーとの対話や業務支援を行います。
AIエージェントは人工知能の応用形態のひとつであり、特定の目的やタスクに対して自律的に行動できる点が特徴です。つまり、AIエージェントは単なる分析ではなく、行動を起こす能力がある点が違いとも言えます。
さらにAIエージェントとはなにか?を知りたい場合は、こちらの記事をご覧ください。
AIエージェントとは?特徴や生成AIとの違い、種類や活用シーンを紹介

具体的なAIエージェントの活用例について解説しましょう。
ECサイトや通信業界などでは、AIチャットボットが顧客からの問い合わせに即時対応することで、年間3万件以上の問い合わせに対して約60%の自動解決率を実現しています。これにより、オペレーターの負担軽減だけでなく、顧客の満足度向上にもつながっています。
音声認識と感情分析を組み合わせたAIエージェントにより、顧客の発言から感情を読み取り、対応トーンを最適化することで、クレーム件数の削減や応答時間の短縮が可能です。ある金融機関では、1件あたりの対応時間が平均30%短縮され、業務コストの削減にもつながりました。
AIエージェントが顧客の過去の購買履歴やWebの閲覧行動を分析し、最適なアプローチ方法を提示します。SaaS企業においては、AIによるリードスコアリングにより営業の成約率が15%向上した事例もあります。営業活動の質とスピードが大幅に改善される効果があります。

次に、企業でAIエージェントを活用した事例について解説しましょう。
三菱電機では、もともと生産設備の故障によるライン停止や緊急修理対応が発生し、生産効率の低下が課題でした。そこで、AIエージェントが工作機械の稼働データをリアルタイムで解析し、異常兆候を早期に検知。すると故障前のメンテナンスが可能となり、生産停止リスクを大幅に低減できました。具体的には、刃こぼれ検知による加工不良の98%削減や、刃具経費の約60%削減できています。
日本酒を作っている津南醸造では、スペースシードHDと協力し、自社製品マーケティング支援用AIエージェントのβ版テスト運用を開始しました。今後の展望としては、 購買データやSNSでの反応と連携した施策の最適化も視野に入れ、地方発の酒蔵が持つ独自の魅力をより効果的に伝え、新たな市場との接点創出を目指すとしています。
具体的な内容については、下記の記事をご覧ください。
津南醸造、AIエージェントを活用した自社製品プロモーション支援のテスト運用を開始
無印良品のオンラインショップでは、売上拡大にあたり画一的な商品表示では顧客の購買意欲を喚起しにくいという課題がありました。そこで、AIエージェントによるパーソナライズドマーケティングを導入し、ユーザーの閲覧履歴・購買傾向をもとに最適な商品をレコメンド。これにより、アプリの記事からCTRが0.5%向上しました。
JAPAN AIでは、プレスリリースの作成に関して10時間程度かかっている点が課題でした。
そこでJAPAN AIでは、「プレスリリース作成エージェント」を導入。「プレスリリース作成エージェント」の活用により、作業時間を2〜3時間に短縮し、最大約80%の削減に成功しました。これにより、プレスリリースの作業時間の大幅な短縮に加え、メディアリレーション時間の確保、開発チームとの連携強化、情報発信スピードの向上、広報リソースの最適配分も実現しました。
より詳しい情報が知りたい方は、こちらの記事もあわせてご覧ください。
JAPAN AI、自社開発AIエージェントでプレスリリース作業時間を10時間から2時間へ短縮
株式会社ANOBAKAでは、スタートアップ企業からの多数の問い合わせに対し、それぞれ異なる質問やフィードバックがあるため、リソースの制約から全てに対応しきれていない状況でした。
そこでANOBAKAではAIエージェント「AIキャピタリスト”ANOくん”」を導入。その結果、「AIキャピタリスト”ANOくん”」の導入により、入社わずか2週間で50社との面談に対応しました。さらに、次回面談への接続率が20%に達し、初回面談の標準化と業務効率化を同時に達成しました。
選定に至るまでの理由や実際の運営方法については、こちらの記事で解説しています。
新卒入社した「AIキャピタリスト”ANOくん”」が優秀すぎた。入社わずか2週間で50社対応、次回面談率20%!ANOBAKA×カリスマAIが挑んだ生成AIエージェント開発の裏側
その他にも、AIエージェントを活用している事例については以下の資料で紹介しています。AIエージェント活用のトレンドなども解説しているため、関心がある方は資料請求フォームからお問い合わせください。

AIエージェントには、導入のメリットがあります。導入するとどのような効果があるのかについて解説します。
AIエージェントはルーティン業務やデータ入力、定型処理などを正確かつ迅速にこなします。その結果、社員はより付加価値の高い業務や創造的なプロジェクトに集中できるようになります。特に業務プロセスが標準化されている分野では、効率化のインパクトが大きくなります。
AIエージェントの導入によって、人件費や業務運用にかかるコストを削減できます。例えば、チャットボット導入により1件あたりの問い合わせ対応コストを数十円〜数百円単位で抑える事例もあり、年間数百万円規模のコスト削減が見込まれることもあります。また、人的ミスの削減や業務再設計の効果も加味すると、ROI(投資対効果)も高くなる傾向があります。
AIエージェントはリアルタイムかつパーソナライズされた対応を実現できるため、顧客満足度を高める重要な手段となります。待ち時間の短縮や24時間対応といった利便性に加え、ユーザーごとの最適な提案が可能になることで、リピーターの獲得やブランドロイヤリティの向上にもつながります。

AIエージェントの導入には、メリットだけでなく注意すべきポイントも存在します。適切な配慮を怠ると、導入効果が得られないばかりか、逆に業務に混乱を招くリスクもあるため慎重な準備が必要です。
AIエージェントは先行投資を伴うため、導入時の費用対効果を見極めることが重要です。目的が曖昧なままでは、費用だけがかさみ、十分な成果が得られない可能性があります。導入前に明確なKPIを設定することで、投資の妥当性を判断しやすくなります。
AIエージェントは大量のデータを取り扱うため、情報漏洩リスクが高まる点に注意が必要です。とくに個人情報や機密データを扱う業種では、法令遵守や内部統制を強化する仕組みの構築が不可欠です。
AI導入が業務フローに適合していない場合、かえって作業の煩雑化や混乱を招くおそれがあります。現場の課題を正確に把握し、既存システムや人の動きと齟齬がないか事前に確認しておくことが成功への近道です。
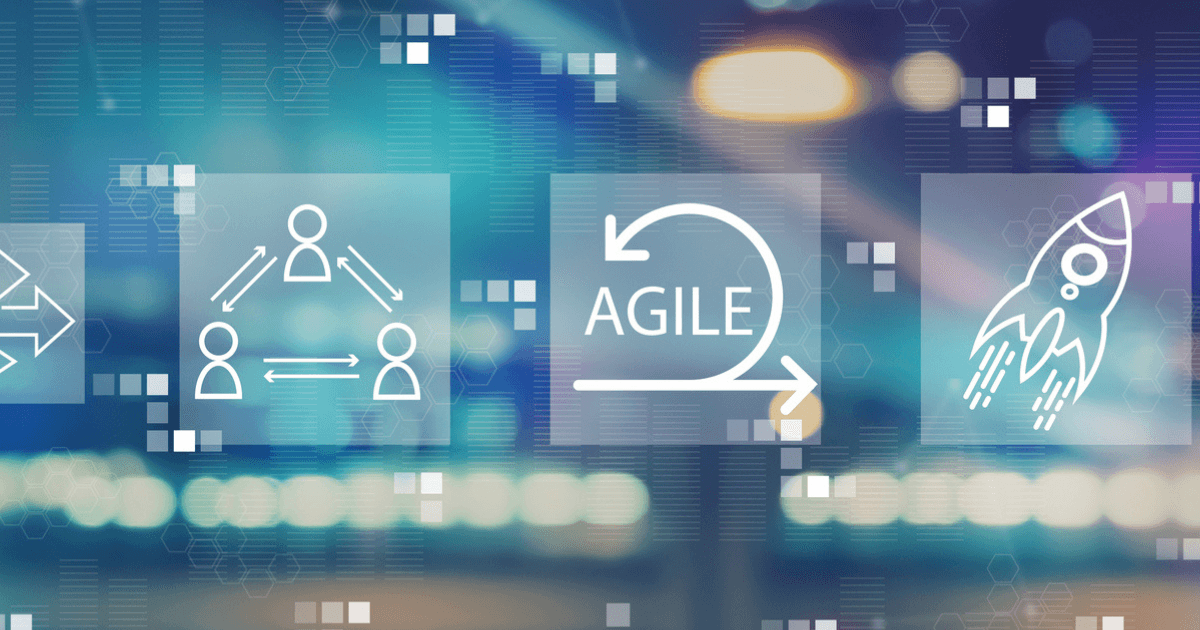
AIエージェントを有効に活用するには、計画的かつ段階的な導入が欠かせません。導入後すぐに成果を出すことは難しいため、効果的な進め方を理解することが成功の鍵を握ります。
まずは特定業務でのPoC(概念実証)を実施することで、現実的な効果や課題を明確しましょう。PoCで導入することにより、いきなり全社導入して失敗するリスクを回避できます。
AIを業務に活用するには、現場の理解と協力が欠かせません。社員がAIを信頼し、正しく使えるようにするためには、導入目的の共有や継続的な教育が必要です。AIが人の代わりになるのではなく「補助的存在」であるという認識を広めることがポイントです。
自社だけでAIエージェントを構築・運用するのは現実的ではない場合もあります。信頼できるベンダーとの連携により、技術支援・運用サポート・改善提案といった包括的な支援を受けることで、導入プロジェクトの成功率を高められます。

AIエージェントは、さまざまな業務領域において業務効率化や顧客体験の向上に貢献する有望な技術です。導入にあたっては、目的や体制を明確にし、段階的かつ戦略的に取り組むことが成功の鍵となります。
アイスマイリーでは、AIエージェントサービスの企業一覧を無料配布しています。自社での業務効率化やDX推進に活用できる、最適なAIサービスを選定するためにぜひご活用ください。
業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。
メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。
AI製品・ソリューションの掲載を
希望される企業様はこちら