生成AI

最終更新日:2023/12/15
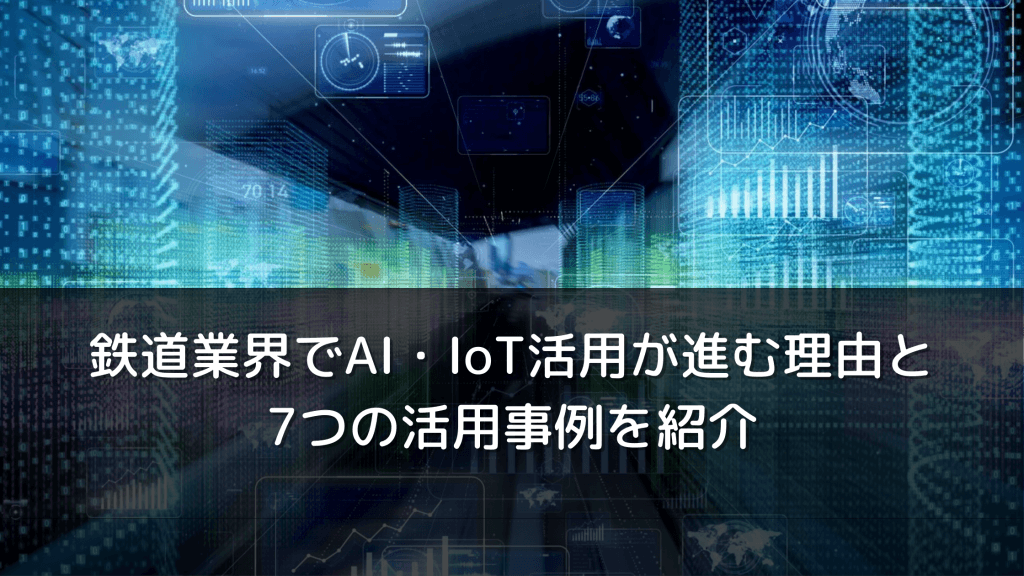 鉄道業界でAI・IoT活用が進む理由とは?
鉄道業界でAI・IoT活用が進む理由とは?
アナログなイメージの強い鉄道業界ですが、運行ダイヤや時刻表、駅ホームのカメラなど、さまざまな部分でAI・IoTの活用が進んでいます。労働力不足やコスト高騰などが深刻な課題として浮かび上がる中で、AIやIoTの導入は、多くの課題を解決に導く可能性を秘めています。
需要予測や画像認識、異常検知など、多様な分野で活躍が期待できるAI技術は、今後ますます必要不可欠な存在となっていくでしょう。本記事では、鉄道業界でAI・IoT活用が進む理由や、具体的な7つの活用事例を紹介します。
AIの活用事例について詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
AI・人工知能とは?定義・歴史・種類・仕組みから事例まで徹底解説

近年では、鉄道業界においてもAI(人工知能)やIoTの活用が期待されています。一見すると、鉄道業界とAI・IoTは関連性が低いように思える方もいらっしゃるかもしれません。しかし、鉄道業界の裏側では、さまざまなデジタル技術が私たちの日々の生活を支えています。
例えば、運行ダイヤは代表的なデジタル技術のひとつです。当たり前のように線路を走る電車は、線路を同時に走行する車両台数や、リアルタイムな運行状況、乗客の利用状況など、あらゆるデータを参考にしながら運用されています。
また、天候や天災などの情報も、鉄道会社が高い安全性を維持しながら電車を運行させるための大切なデータです。このように、多種多様なデータを総合的に活用することで、鉄道業界は動いているのです。近年では電子マネーのデータ分析を行ったり、AIカメラを利用して駅の混雑状況などを知らせたりといった技術も登場しています。

昨今の鉄道業界はさまざまな課題を抱えており、AIやIoTを活用した解決が急がれています。
人口減少による労働力不足はどの業種・業態でも課題となりつつありますが、鉄道業界においても、労働力の確保やリソース不足の補填は深刻な課題です。AIやIoTを導入することで、これまでは人間が行っていたオペレーションをシステムが自動化・最適化し、労働力不足の解消につなげることが期待されています。
また、スキル継承問題の解決も重要です。熟練した技術を持つ現場の従業員が、何らかの理由で休職や退職してしまうと、後進の人材にスキルを継承することは難しくなります。しかし、AIやIoTの活用によってデータをシステムに蓄積し、スキルを定量化することによって、ナレッジの共有を容易にし、スキルを安定的に継承できる体制を整えられます。
他にも、サービスが複雑化して従業員の負担が増加していることや、コスト高騰と旅客収入の減少による利益率低下問題も、早期の解決が不可欠です。従業員の負担軽減には、AIやIoTの導入による自動化が役立ちます。
コスト高騰に対処するためには、社内のデータを蓄積し、コスト削減につながるポイントを割り出す企業努力が必要になるでしょう。顧客データを収集できれば、より効率的なマーケティングも可能になります。蓄積したビッグデータを活用することで、新たな市場の開拓など、これまでには難しかった分野へのチャレンジができるようになり、利益追求の幅が広がります。
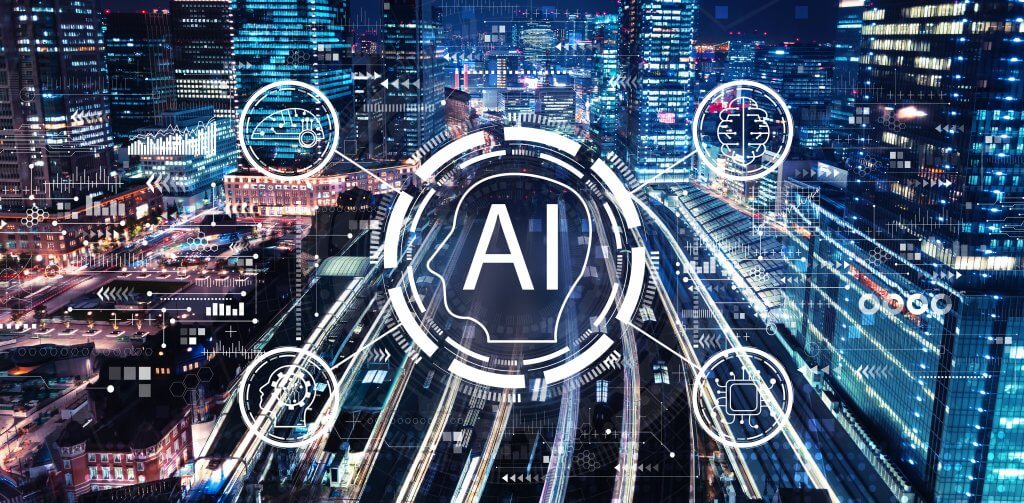
鉄道業界に関係が深いAIサービスとして、需要予測や異常検知・予知保全、画像認識などが挙げられます。細やかなフォローが必要になる業界だからこそ、AIサービスの活躍の幅は広いといえるでしょう。ここでは、特に関連性の高い9種類のAIサービスを紹介します。
過去の鉄道の利用データを活用すれば、需要予測が可能になります。ある駅の乗客の過去数年間の利用状況をAIが分析することで、早朝・昼間・夜間などさまざまな時間帯の利用人数や混雑度合いを予測できるため、運行ダイヤの決定や、混雑緩和策の決定に役立ちます。
将来的に利用人数が増加しそうであれば増便を行い、減少傾向にある場合は減便を行うなど、柔軟な対応が可能になるため、顧客利便性の向上とコスト効率化を同時に達成できます。
異常検知・予知保全は、安全に鉄道を運行させる上で重要な役割を果たします。
従来は、整備担当の従業員が目視で機器の点検やメンテナンス作業を行っていました。この作業は、基本的に鉄道が運行していない終電~始発の間の短い時間で行われるため、従業員の負担が大きいという課題があります。
AIカメラを活用して鉄道の異常をいち早く検知できれば、目視では発見が難しい異常も自動的に検知でき、最適なタイミングでメンテナンス作業を行えるだけでなく、従業員の負担も軽減できます。
画像認識技術は、駅の見守りなどに大きな効果を発揮します。例えば駅のホームにAIカメラを設置しておき、ホームから誤って線路上に転落してしまった人を検知したとき、即座にアラートで通知できる体制を整えておくことで、事故が起こる前に速やかに緊急停止を行えます。
駅員が常に全域を見張ることが難しい、広い駅などでは、AIカメラによる見守りが特に高い効果をもたらすでしょう。他にも、不審物が放置されているのをいち早く発見したり、点字エリアの停滞をチェックしたりすることも可能です。
チャットボットやボイスボットは、Webサイトやアプリのサービス品質向上に貢献します。
チャットボットとは、利用者が画面上に質問をテキストで書き込んで送信すると、ロボットが自動的に回答を返してくれる仕組みのことです。ボイスボットはテキストではなく、音声入力に対してロボットが回答を返してくれます。
Webサイト上の「よくある質問」コーナーにチャットボットを設置し、質問を打ち込むことで、Q&Aから答えを探さなくても自動的にロボットが目的の回答を教えてくれるイメージです。

エッジAIとは、クラウドのようにネットワーク経由でデータを送信して処理するのではなく、デバイスやサーバーに近い場所でデータ処理を行うAI機器のことです。
エッジAIを導入することで、膨大なデータをクラウドに送る必要がなくなるため、帯域幅の圧迫やネットワーク遅延の問題を解消し、スムーズかつリアルタイムなデータ処理が可能になります。
特に鉄道業界では多種多様なデータを広範囲で送受信し続けなければならないため、常時ネットワーク接続が必要になるクラウドではなく、エッジAIの活用が効果的です。
AIモデル作成によって、AIに効率的な学習を行わせて、より処理能力の高いAIシステムを構築することができます。鉄道業界では、AIモデルの活用によってダイヤの乱れを自動的に是正できる仕組みの構築が進められています。
AIに熟練したスキルを持つ従業員の過去の業務データを投入し、機械学習させることで、災害が起こったときでも、まるで現場経験が豊富な熟練者が指示しているかのような効率的なダイヤ変更が可能になります。
顔認証システムも、鉄道業界と相性が良いAI技術のひとつです。例えば改札機に顔認証システムを設置することで、AIがデータベースに登録されている情報と改札を通過しようとしている人の顔を自動的に照合し、通過をしても問題がないかどうかを判断させることが可能です。
2022年12月現在ではまだ本格的に導入されているエリアはありませんが、2023年3月から、大阪府に開設予定の新駅である「うめきた(大阪)地下駅」(仮称)に、顔認証を採用した改札が導入される予定です。
鉄道業界における音声認識は、駅構内の案内システムへの応用などが考えられます。駅構内にAI案内を設置しておき、利用者が案内してほしい内容を話しかけると、AIが自動的に利用者の疑問へ回答します。
案内システムを設置することで、これまで配置していた案内員をAIに転換できるため、従業員の負担軽減やリソース不足の解消が期待できます。近年では、カメラの目の前に立った人の表情から感情を分析する「感情認識システム」との併用も検討されています。
AIカメラは、鉄道業界におけるAI・IoT技術の中でも、特に幅広い場面で活用が期待できます。駅にAIカメラを設置して混雑状況を自動的に割り出したり、利用者の滞在時間や属性・年齢などをデータとして蓄積したりすることが可能です。
また、現在は電車内へのカメラ搭載は行われていませんが、将来的には電車内にAIカメラを設置して、不審な動きを見せている人物の情報をいち早く検知し、犯罪防止などに役立てる使い方も考えられます。

昨今の鉄道業界では、既に数多くのAI・IoTの活用事例が生まれています。ここでは、画像認識やチャットボット、AIカメラなど、さまざまなAI・IoTを活用して事業変革に役立てている、7つの事例を紹介します。
日立とJR東日本は、AI技術を活用して、鉄道設備の復旧対応支援システムを開発・実用化しています。2020年3月から実証実験が行われていましたが、有効性が確認できたことから、2023年4月からは山手線をはじめとした首都圏の一部の在来線で本番運用が予定されています。
このソリューションでは、鉄道の運行障害が起こったときに、指令員が障害の内容や現場で実施した確認事項をシステム上で入力すると、自動的に過去の事例の中から近い事例をピックアップしてダッシュボードに表示します。
同時に、過去の事例の原因や具体的な対策を表示することで、現在起きている障害の速やかな解消につなげる狙いがあります。レコメンド技術を活用したもので、人間が手動で検索する方法では見つけ出せないような過去のデータを、AIが自動的に抽出して「気づき」を与えてくれる点がメリットです。
日立は、今後もAI技術を活用して輸送障害の早期復旧や、日本の安全・安定輸送を実現していきたい考えです。
日立とJR東日本、AIを活用した鉄道設備の復旧対応支援システムを実用化
西日本鉄道では、YEデジタルが開発・提供するモビリティサイネージクラウド「MMvision」を春日部駅の新ホームに導入しました。
MMvisionは、一般的なデジタルサイネージと同様に広告やお知らせを画面上に表示する機能だけでなく、鉄道の運行情報や時刻表なども表示可能な、鉄道業界に特化したデジタルサイネージサービスです。
運行情報や時刻表の表示によって顧客利便性をアップさせるだけでなく、デジタルサイネージの稼働状況はリアルタイムで遠隔監視でき、データの送信や編集もまとめて制御できるため、管理やメンテナンスの手間を削減する狙いもあります。
西日本鉄道がMMvisionを導入するのは春日部駅が初めてで、導入によって駅サービスの品質向上が期待されています。また、ニュースや広告、天気予報なども併せて配信することで、利用者の待ち時間をより快適なものにする効果も期待されています。
西日本鉄道がYEデジタルの「モビリティサイネージクラウド」を初導入
阪神電気鉄道では、列車内防犯カメラ設置試験にAI画像解析を活用しています。防犯カメラはアイテック阪急阪神が開発したもので、設置試験・画像解析の一部業務も同社が委託を受けています。
今回の列車内防犯カメラ設置試験で実施されたのは、映像録画、音声録音、映像・音声の遠隔監視です。列車内の映像を音声とともに録画し、かつ遠隔からリアルタイムでモニタリングできるかどうかを検証して、実用性の評価を行いました。
また、AIカメラが映像を分析することによって混雑状況を自動的に把握し、その精度を確かめるための実証実験も兼ねています。カメラの設置場所は列車の出入口上部で、実験にあたって利用者にはステッカーで実施の旨が周知されました。
実証実験は2022年5月24日から8月31日にかけて大阪梅田駅~新開地駅間で行われました。この実証実験の実施によって、安心・安全な車内環境を整備するとともに、顧客の利便性向上も期待されています。
株式会社ジェイアール東日本企画(jeki)では、鉄道路線利用者データを活用して、交通広告とスマホ広告を連携する取り組みを実施しています。
株式会社unerryが提供している、リアル行動データプラットフォーム「Beacon Bank」を導入することで、鉄道利用者データの将来予測を行い、交通広告を通して利用者とのコミュニケーションを図りたい考えです。
また、配信した広告における各種データを蓄積することで、交通広告によって実施したキャンペーンにどの程度の効果があったのかを可視化する目的もあります。コロナ禍の影響で鉄道の利用者数は減少しており、広告の出稿者にマーケティング上のメリットを感じてもらうため、交通広告のDX促進が期待されています。
Beacon Bankは、jekiが取り扱っている「Jビーコン」を活用して収集した山手線利用者の緯度・経度、移動速度、移動方向などの位置情報データを活用し、「参考にした位置情報データと近い位置情報」をAIで抽出して、将来的な鉄道の利用者数を推測する仕組みです。
jeki、鉄道路線利用者データを活用し交通広告とスマホ広告を連携
JRや私鉄などの鉄道分野では、チャットボットの活用が広がりを見せています。JR東日本の「えきねっと」や、神奈川県内の相模鉄道が運用する「相鉄線アプリ」には、チャットボットが導入されています。
JR東日本のえきねっとでは、オウケイウェイヴと連携し、自社のWebサイト上にAIチャットボットを設置しました。ユーザーからチャットボットに質問があると、データベース上から適切な回答を探し出し、ユーザーへ自動的に回答します。
相鉄線アプリに導入されているのは、オムロン製のAIチャットボットです。路線別のきっぷの料金をはじめとした、さまざまな駅窓口業務をAIチャットボットに代行させることで、従業員の負荷軽減を目指しています。
相鉄線アプリのAIチャットボットの特徴はディープラーニングと自然言語処理を使用している点で、表記ゆれによってチャットボットが正確な答えを返すことができない、という問題を解消できます。
東京メトロでは、2022年9月28日から、早稲田駅でAIカメラによる混雑状況の表示を行う実証実験を開始しました。
東京メトロが提供している「東京メトロmy!」アプリでは、号車別の混雑状況が表示されています。この混雑状況を東西線早稲田駅西船橋方面行きのホームにも表示することで、利用者の行動がどのように変化するのかを検証する狙いがあります。
実際に検証に使われるのは、東西線高田馬場駅に設置しているデプスカメラです。号車単位で混雑状況を把握できるため、利用者はホームで列車の到着を待ちながら、空いている号車の乗車口へと移動することが可能になります。
混雑状況は4種類で表され、「座席に座れる程度」「ゆったり立てる程度」「肩が触れ合う程度」「かなり混み合っています」に分かれています。実証実験は2023年3月末頃までの予定で、現在のところ、東京メトロはデプスカメラとAIを活用した混雑状況把握の実証実験を行っている唯一の鉄道事業者です。
東京メトロ AIとデプスカメラを用いて混雑状況をホームに表示する実証実験開始
Ideinは、JR東日本が運営する「Eki Tabi MARKET」にてサービスを開始する予定の、オンライン接客型店舗「JRE MALL Meet」で、AIカメラを活用した実証実験を開始しました。AIカメラを活用して、店舗へ来店した人数のデータ記録や顧客の属性分析を実施するほか、店内に設置したデジタルサイネージの効果測定や、商品の視認率の測定を行う予定です。
また、ビジネス向けチャットツール「Slack」と連携されている点も特徴的で、JRE MALL Meetに利用者が来店すると、オンライン接客担当のスタッフにSlackで自動的に通知が届くようになっています。自動で通知が届くため、接客担当のスタッフがスムーズに接客準備に入ることができ、業務効率化や顧客満足度の向上につながります。
利用されているAIカメラのプラットフォームは「Actcast」で、データを蓄積する段階で個人情報が特定されないなど、プライバシーへの配慮が為されている点も特徴的です。
Idein JR東日本とAIカメラを活用した実証実験を6月30日より開始

鉄道業界とAI・IoTには、さまざまな分野で親和性があり、今後大いに活用が期待されています。労働力不足の解消や業務効率化、サービス多様化への対応など、さまざまな課題を解決できる可能性を秘めたAI技術は、ますます必要不可欠な存在となっていくでしょう。
現場では多くの実証実験が行われており、顔認証システムを利用した改札など、一部の技術は既に本格的な導入が決まっているものもあります。今後もAI技術の発展とともに、さらに広範囲にあらゆるサービスが展開されていくと考えられます。
AIについて詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
AI・人工知能とは?定義・歴史・種類・仕組みから事例まで徹底解説
業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。
メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。
AI製品・ソリューションの掲載を
希望される企業様はこちら