生成AI

最終更新日:2024/01/12
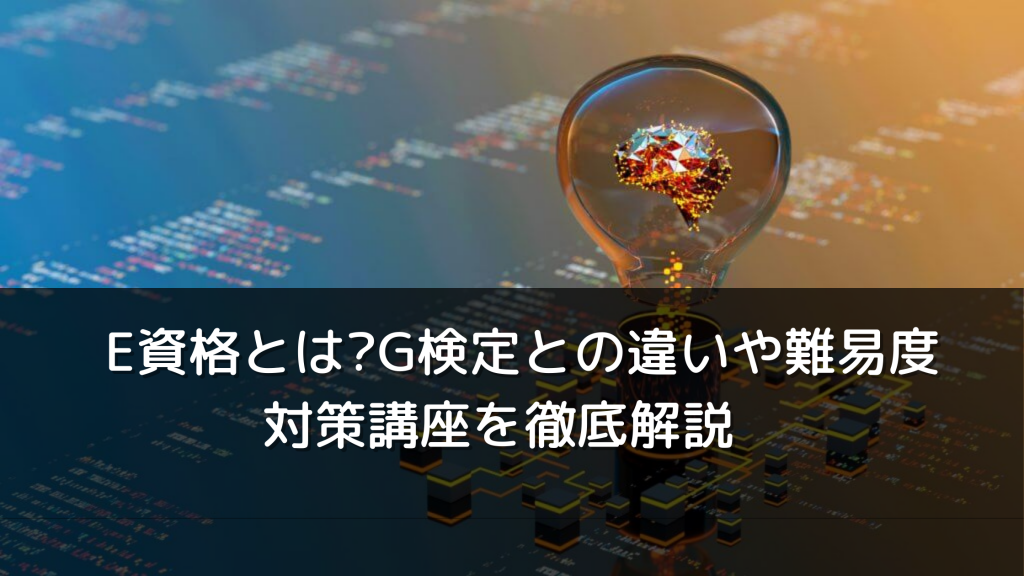 E資格とは?G検定との違いを解説
E資格とは?G検定との違いを解説
一般社団法人ディープラーニング協会が主催するE資格は、ディープラーニングを活用してシステム構築やデータ分析を行うデータサイエンティストなど、現場で働く人におすすめの資格です。
E資格を受検するためには、JDLA認定プログラムを受講し、ディープラーニングに関する知識を深める必要があります。本記事では、E資格の概要やG検定との違い、試験の難易度、おすすめの対策講座など、E資格について徹底解説します。
ディープラーニングについて詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
ディープラーニングとは?特徴や仕組み、活用事例をわかりやすく解説

E資格とは、一般社団法人ディープラーニング協会(JDLA)が主催する、ディープラーニングの知識やスキルを問う民間資格です。同協会では、E資格の目的を下記のように紹介しています。
ディープラーニングの理論を理解し、適切な手法を選択して実装する能力や知識を有しているかを認定する。
JDLA認定プログラムを試験日の過去2年以内に修了している人が受検できる資格で、同協会が主催している「G試験」と比べると、ディープラーニングの開発に関わるより実践的な内容が出題されます。
試験が開催される回数は毎年異なりますが、2023年度は2回(各3日間)実施されます。試験会場は全国各地で、コンピューターを使ったCBY方式で行われます。
2023年の試験日程は、次のとおりです。
E2023#1
2023年2月17日(金)
2023年2月18日(土)
2023年2月19日(日)
E2023#2
2023年8月25日(金)
2023年8月26日(土)
2023年8月27日(日)
E2023#1は2023年2月現在、申込期間中であり、受検日の前日まで申し込みを受け付けています。
なお、受検費用は一般、会員、学生によって異なります。
G検定(ジェネラリスト検定)は、AI(人工知能)や機械学習、ディープラーニングを活用して事業へ応用するときに役立つ資格です。経営者やシステム設計を担当する上流工程のエンジニア、システムコンサルタントなどにおすすめの資格です。
一方、E資格の出題範囲は、より開発現場の実態に近いものとなっており、データサイエンティストやAIエンジニアに適しています。業務でディープラーニングを活用し、実際にシステム構築やデータマイニングを行う人におすすめです。
データサイエンティストやAIエンジニアであっても、まずはAIやディープラーニングの基礎的な知識をG検定で身につけた後、より実務に近い知識やスキルを習得する目的でE資格を受検することもあります。

ITによる機械化や自動化が当たり前になってきた近年では、世界的にAI人材の不足が課題となっています。AI技術自体が登場からまだ間もないこともあり、AIを自在に扱うことができる人材は需要に対して圧倒的に不足しています。
日本においては、世界に比べるとAIの導入が遅れていますが、最近になって多くの企業でAI人材やDX人材が求められるようになってきています。とはいえ、世界の傾向と同様に、日本国内のAIエンジニアも不足しており、人材の確保は簡単ではありません。
今後もAI導入の流れは拡大していくと予測されることから、AI人材の需要はますます高まっており、将来性は非常に高いと考えられます。AIや機械学習、ディープラーニングの知識や技術を持つ人材は、当面、多くの企業で引く手あまたの状況が続くでしょう。
市場に存在するAIエンジニアの絶対数が少ないことから、自社でAI人材を育成する必要に迫られている企業も少なくありません。このような流れのなかで、E資格がAI人材として高いスキルを持っていることを証明するための手段として、高い注目を集めています。

E資格を受検するメリットには、次のようなものがあります。
ディープラーニングを活用して現場で働きたいと考えている人にとって、E資格の取得は役立ちます。ここでは、上記の5つのメリットについて詳しく解説します。
前述の通り、E資格はディープラーニングを現場で開発する人向けの資格です。資格試験の勉強を通じて、ディープラーニングを実装レベルで学ぶことが可能です。
AIや機械学習、ディープラーニングに関連する資格試験はいくつかありますが、基礎知識を問う試験など、初心者向けの資格が比較的多く見受けられます。
前項で紹介したG試験も、現場で活躍するエンジニア向けの資格ではありますが、開発スキルよりも、ディープラーニングの基礎知識や、AI市場の動向など、倫理面などを問われる問題が多い傾向にあります。
E資格は、プログラミング言語のPythonを活用した開発に関する問題など、実際のAI開発により特化した内容の試験であり、十分に経験を積んだエンジニアが資格取得するのに適したレベルになっています。
E資格を取得すると、ディープラーニングの開発スキルが十分に身に付いていることを証明できます。そのため、E資格の取得者は、AI人材やDX人材として市場で重宝されるでしょう。
近年、業種や業態を問わずに多くの企業がAIの導入やDX推進を重要課題としており、AI人材やDX人材は枯渇状態にあります。このことから、現場で活躍できるAI人材やDX人材であることを示すE資格の所有者は、さまざまな企業からの採用が期待できます。
社内でAI人材やDX人材としてますますスキルアップしたいと考えている人や、今後、ほかの開発現場への転職を検討している人にとって、E資格の取得はおすすめです。
E資格の学習を通して、ディープラーニングを現場で活用するためのさまざまな方法を学ぶことになります。これによって、AI活用を前提として自社ビジネスの課題を解決する方法や、自社製品のバリューを向上するための施策を立案できるスキルが高まります。
AIはあくまでも「手段」に過ぎず、具体的な活用方法を考えるのは人間です。AIを活用してどのような課題を解決するのか、また、どういったビジネスモデルを展開していくのかについて良いアイディアを出すためには、ディープラーニングについてより多くの知識を学び、活用方法を導き出せる人材を育成することが大切です。
JDLAには、同協会が主催するG検定やE資格に合格した人のみが参加できる「CDLE(シードル)」というAIコミュニティが存在します。試験の合格によってコミュニティに参加できるのは、メリットのひとつです。
CDLEは現在5万人以上の会員が在籍しており、AIやディープラーニングの学びの場としてさまざまな活動を行っています。
ディープラーニング全般のニュースや論文の共有、著名人を招いたCDLEメンバー限定の講演、メンバー主催の勉強会、地域別のミートアップなど、会員ならではのさまざまな取り組みが展開されています。
会員同士が知識や技術を持ち寄り、さらなる研鑽につながるので、合格した暁にはぜひ参加してみると良いでしょう。
E資格に合格すると、「E資格合格」のロゴを名刺に追加することができます。名刺にロゴを掲載しておくことで、初めて交流を持つ相手にもAIやディープラーニングに精通している人材であるとアピールすることが可能です。
転職で自分をアピールする材料として活用したり、新たな営業先にアピールする武器になったりと、さまざまな面でメリットがあるため、合格した際には積極的に追加することをおすすめします。
なお、合格者用のロゴはJDLAのWebサイトからダウンロードできますが、合格者に通知されるパスワードが必要です。ロゴの発行時期については受検結果メールに記載されているため、送られてきたメールは大切に保管しておきましょう。

E資格のWebサイトによれば、試験範囲は「シラバスより、JDLA認定プログラム修了レベルの出題」と記載されています。
JDLA認定プログラムとは、JDLAが主催するいくつかのプログラムで、ディープラーニングの理論を理解し、状況に応じて適切な手法を活用できる人材を育成するための講座を指しています。
試験の具体的な出題範囲は、下記の4つのカテゴリです。
統計学や情報理論などの応用数学のほか、機械学習やディープラーニングなどのAI開発に関わる知識やスキルを身につける必要があります。また、開発したAIを実際に運用するための環境構築に関わる知識も問われます。
最新のシラバスは、Webサイトから無料でダウンロードすることもできるため、受検を検討されている方は一度確認してみることをおすすめします。

E資格の試験は、120分の試験時間内に100問を解いていく多肢選択式の試験です。非常にハイペースな回答速度が求められる試験なので、基礎知識が十分に身に付いていることが前提になります。このことから、事前準備が重要であり、全く知識がない状態で受検し合格することは難しいと考えられます。
基本的には、現場で機械学習やディープラーニング技術を活用して、実際に開発を行えるレベルの知識とスキルが求められると考えておくとよいでしょう。
AIの初学者や、現場での開発経験がほとんどない人でも合格の可能性はゼロではありませんが、ある程度の開発経験を積んでいる人の方が合格しやすい試験です。
全くの初心者から合格を目指す場合は、十分な勉強時間を確保し、対策講座などを受講して現場で通用するレベルの開発スキルを身につけてから受検することをおすすめします。
なお、 JDLA認定プログラムを試験日の過去2年以内に修了していることが受検資格にもなっているため、講座を通して試験対策を進めるのが効率的な合格への近道です。

2022年8月26日(金)、27日(土)、28日(日)の3日間で行われたE資格は、全体で897名の受検者数に対して、合格者数が644名でした。合格率は71.79%で、資格試験としては比較的高い水準にあります。
2018~2020年の試験では合格率が60%代後半で推移していましたが、2021年以降の試験では、70%台を切っていません。
合格者の年代は20代と30代が大半を占めており、20代が32.76%、30代が38.82%です。次いで多いのが40代の17.24%で、実際に現場で働いている人の合格率が高いと考えられます。
職種別の合格者数を見てみると、突出しているのが「研究・開発」の40.99%です。次いで「情報システム・システム企画」が26.24%となっており、上位2つの職種で7割近くを占める結果となりました。とはいえ、幅広い職種で合格している人がおり、経営層や製造現場、学生など、さまざまな立場の人がチャレンジしている資格です。
E資格の受検には、ディープラーニングの知識を深め、より高度な開発レベルを目指す人が向いています。E資格は、同社が主催するG検定と比べても、専門性が高い試験です。そのため、現場でAIを活用しながら実際に開発を行っており、知識やスキルを高めたいと考えている人に適しています。
合格者の職種にも表れているとおり、研究・開発職や情報システム・システム企画職の人に特に人気の資格ですが、高レベルなAIの知識を必要とする営業部門やマーケティング部門、専門的なAI人材を必要とする職種の人も、E資格の受検が役立つでしょう。
役職別に見ると、一般社員級の合格者が55.28%です。次いで主任・係長級や課長級もそれぞれ10%以上を占めており、現場で活躍する社員の受検が目立ちます。
これからディープラーニングを活用したAI開発に携わる予定がある人や、AI人材として成長していきたいと考えている人にとっては、実践的な知識とスキルを身につけられる資格です。
E資格の試験対策・勉強法としておすすめなのは、E資格に対応した基礎講座や応用講座を受講する方法です。資格講座を受講することで、実践的なプログラムに沿って現場で活用できる知識やスキルを学べます。
「JDLA認定プログラム」に認定されている対策講座を受講すれば、シラバスに則った試験対策を行えます。また、書籍は販売されていないため、基本的に独学はおすすめできません。ここでは、E資格の対策・勉強法について解説します。
JDLAのWebサイトには、全部で17種類の「JDLA認定プログラム」が掲載されています。E資格を受検するためには、これらのプログラムのうち1種を修了する必要があります。ここでは、E資格の試験対策としておすすめの2つの講座を紹介します。
「AI STANDARD」では、株式会社STANDARDがAI人材を育成するためのさまざまな講座を提供しています。なかでもAIエンジニアリング講座は、AIプロダクトを開発できるエンジニアを育成することに主眼を置いた講座となっています。
AIエンジニアリング講座は、実際に開発を行うエンジニアを対象としており、オプションとして「E資格対策講座」も受講が可能です。JDLA認定プログラムに指定されているため、「E資格対策講座」を追加で受講すると、E資格の受検資格を獲得できます。
現場で即戦力として活躍するための網羅的なコンテンツや、知識の定着を確実にするための演習課題、講師による充実したサポート体制で、AI人材として活躍できるエンジニアを育てられます。
Study-AIでは、最短12時間の学習でE試験の合格を目指す「最短2日!E資格合格コース」を提供しています。学習方法は3ステップで、「動画視聴」→「修了試験」→「E試験を受検」の順で進んでいきます。
動画視聴のステップでは、E資格の合格に向けてポイントを押さえた動画教材を利用し、AIの基礎知識を徹底的に学習します。続いて、動画で学んだ内容が身に付いているかどうか確認するための修了試験を受検し、本番のE資格を想定した試験問題に取り組むことで、合格のためのステップアップをはかります。
修了試験に合格できたときには、実際のE資格に合格できるだけの実力が身に付いているという流れです。実際に、本講座の新規受検者のうち、85%以上がE試験に合格するという成果を4期連続で達成しています。
12時間でE資格合格を目指す!苦手分野を徹底的に学べる「最短2日!E資格合格コース」提供開始
資格試験の勉強というと、本を購入して独学する方法を思い浮かべる人も多いでしょう。しかし、E資格に限っては、JDLA認定プログラムの受講が受検資格のひとつとなっており、本で学ぶ方法はおすすめできません。
そもそもE資格の過去問は公開や市販がされていないため、本を使って十分な試験対策を行うことは難しいのが実情です。現在のところ、前項でも紹介したJDLAによる認定講座を受講するのが、合格への近道となっています。
JDLA認定プログラムでは、E資格に合格するための基本的な知識以外にも、本試験を想定した演習問題などが用意されているものも数多くあります。受講した講座の内容をしっかりと復習し、十分な演習を重ねることで、合格に大きく近づきます。
データサイエンティストやAIエンジニアなど、ディープラーニングを用いて開発現場でシステム構築やデータマイニングを行う職種にとって、E資格は自身のスキルを証明するために有用です。
E資格を受検するためにはJDLA認定プログラムの受講が必須となるため、試験対策は基本的に講座の受講を通して行うと良いでしょう。研究・開発職や情報システム・システム企画職だけでなく、AI開発の高いスキルを求められる仕事であれば、誰でも挑戦する価値がある資格です。
E資格の取得以外にも、AI人材の育成や自社ビジネスへのAI活用方法を考える手段はいくつかあります。AIsmileyではAI人材育成・教育サービスの提供事業者を比較できるページを用意していますので、下記のURLもご参照ください。
機械学習について詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
機械学習とは?種類や仕組み、活用事例をわかりやすく簡単に説明
AIについて詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
AI・人工知能とは?定義・歴史・種類・仕組みから事例まで徹底解説
業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。
メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。
AI製品・ソリューションの掲載を
希望される企業様はこちら