生成AI

最終更新日:2024/03/08
 「Google AI for Japan」とは?
「Google AI for Japan」とは?
近年、さまざまな分野でのAI・人工知能導入が進められており、ビジネスの効率化という側面において、もはやAIは必要不可欠な存在になると言えます。特に最近は人手不足が深刻化していることもあるため、「いかにAIを有効活用できるか」が重要な鍵であると言っても過言ではないでしょう。
より有効にAIを活用していくためには、AIをしっかりと使いこなせる人材が必要ですが、その「AI人材」にフォーカスした取り組みとして、Googleは2019年7月に「Google AI for Japan」という、AI人材育成および技術活用支援プログラムの開始を発表しました。
この「Google AI for Japan」とは具体的にどのようなプログラムなのでしょうか。今回は「Google AI for Japan」の内容について詳しく解説していきます。
AIについて詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
AI・人工知能とは?定義・歴史・種類・仕組みから事例まで徹底解説
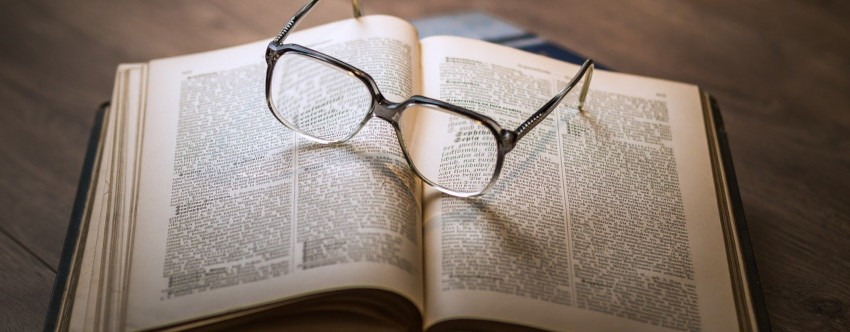
この「Google AI for Japan」では、主に3種類の取り組みが行われることが発表されました。そのうちのひとつが、「日本の次世代AI人材の育成」です。Googleは、AIに関連する研究を行っている以下の6名に対し、5万ドルずつ助成金を提供しました。
1. 国立情報学研究所 国立情報学研究所 コンテンツ科学研究系 教授 山岸順一氏
(研究内容:頑健かつ汎用的なニューラルソースフィルタモデルの研究)
2. 京都大学 情報学研究科 教授 河原達也氏
(研究内容:意図のモデル化を用いた End-to-End 音声言語理解と対話生成)
3. 東京工業大学 科学技術創成研究院 教授 奥村学氏
(研究内容:単一文書要約としての文脈アウェア文圧縮)
4. 東京大学大学院 新領域創成科学研究科 複雑理工学専攻 教授 杉山将氏
(研究内容:限られた情報からの機械学習)
5. 東北大学 大学院情報科学研究科 システム情報科学専攻 教授 乾健太郎氏
(研究内容:知識ベースとしての言語モデル:知識の表現・獲得・検索・推論の統合に向けて)
6. 奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 教授 中村哲氏
(研究内容:視覚聴覚情報を統合するマルチモーダルスピーチチェーンの研究)
なお、支援は2020年までの2年間となっており、追加支援のオプションも用意されているといいます。
また、Googleは上記の助成金提供に加え、東京大学で情報科学を学んでいる学生に向けてAIの授業を行ったり、Googleの東京オフィスでAI研究者やエンジニアと一緒に研究を進められるインターンシップを設けたりと、AI人材の育成に力を注いでいます。
さらにGoogleは、子ども向けのイベントにも積極的な姿勢を見せており、文部科学省、経済産業省、総務省が2019年9月に実施した「未来の学び プログラミング教育推進月間」には協力企業として参加しました。この際には、AIの仕組みや開発といった部分を授業で分かりやすく教えるための教材提供などが行われたといいます。
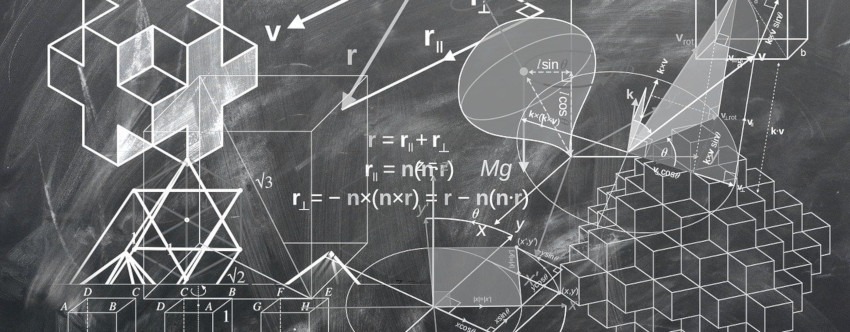
Googleの東京オフィスでは、2018年4月にAI研究者のチームが発足され、それ以降さまざまな研究の成果を発表してきました。その研究の中には「強化学習の基礎研究」「日本語の高低アクセントのための音声モデリング」「ニューラル機械翻訳」といったさまざまなテーマが含まれており、すでに10本以上の論文として公開されています。
また、2019年4月にGoogleが発表した「End-to-Endの音声翻訳モデル」に関しては、東京オフィスに勤務している研究者も関与しており、モデルの開発に大きな貢献を果たしているのです。
さらに、東京オフィスの研究チームは日本の学術機関とタッグを組んだ研究活動にも力を注いでおり、国立情報学研究所の研究者が発表した「古典文学の分析への機械学習技術の応用に関する研究」はその代表例といえるでしょう。
こういった例を見ても、Googleの「日本におけるAI研究への貢献度」は極めて高いことがお分かりいただけるのではないでしょうか。

そして3つ目の取り組みとして、AI活用によって「ビジネスや社会的課題の解決」に導くための支援が行われています。
すでに日本ではさまざまな分野において、AIツールを活用した問題解決の取り組みが行われている状況です。その一例として、福島県南相馬市の事例が挙げられるでしょう。南相馬市では、テクノロジー企業のエアロセンス株式会社と協力し、除去土壌の仮置き場の安全性を高め、管理するための取り組みを行っています。この安全管理にGoogle のオープンソース機械学習プラットフォームである「TensorFlow」が活用されているのです。
Googleは、「医療」「農業」「製造」などをはじめとするさまざまな分野において、AIが社会的課題の解決に貢献できると考えているといいます。まさにこの3つ目の取り組みは、社会にとって重大な課題を解決していく中で、AIを有効活用するための支援なのです。
Googleは、こういったAI活用を促進させていくためには、ツールやリソースをより自由に利用できるような環境整備が必要であるとしています。また、それだけでなく、これから日本が直面するかもしれないさまざまな社会的課題をスピーディーに解決へと導くために、さらなる研究支援とさまざまな機関との協力が必要不可欠だと考えているそうです。
実際、現在の日本では少子高齢化に伴う人手不足が深刻化しており、中にはその問題を解決に導くことができず倒産に追い込まれてしまったケースも存在します。そのような事態を避けるためにも、業務効率化につながるAI活用の知識を深めていくことは欠かせないでしょう。
どれだけAIの技術が進歩しても、その技術を最適な形で活用することができなければ意味がありません。GoogleがAI人材の育成に力を注いでいるのと同じように、各企業の担当者もAIへの知識を深め、より柔軟に対応できるような準備に力を注いでいくことが大切といえます。
Googleは、今後も積極的にAI人材の育成に力を注いでいくことが予想されます。つまり、今後はよりさまざまな分野で高精度のAIが活用されるようになる可能性があるということです。
そのような未来にも順応し、AIの適切な活用方法で業務効率化を図っていくためにも、社内全体でAIについての理解を深める機会を設けるなど、対策を講じていくことが重要になるかもしれません。
業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。
メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。
AI製品・ソリューションの掲載を
希望される企業様はこちら