生成AI

最終更新日:2024/04/05
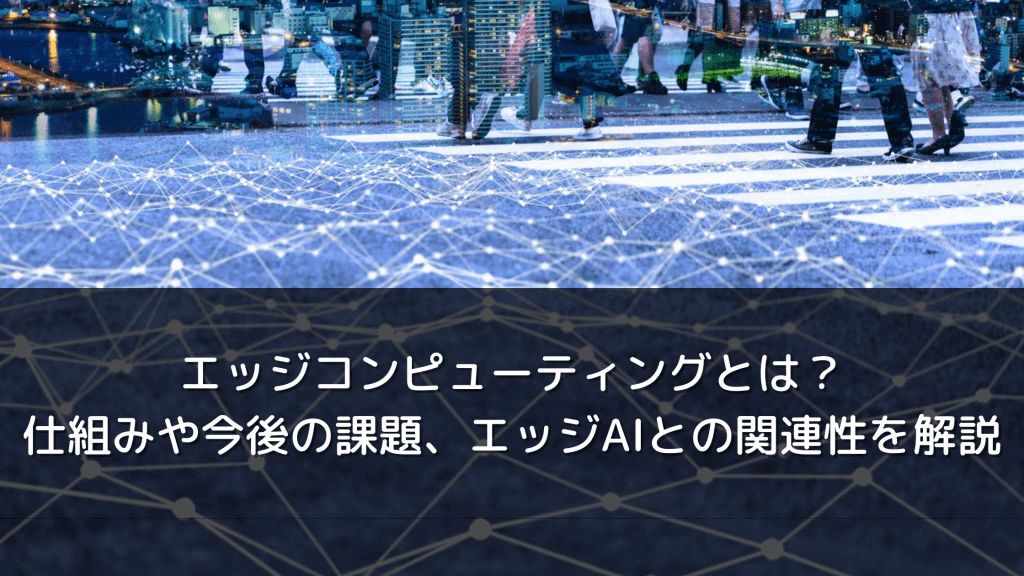 エッジコンピューティングとは
エッジコンピューティングとは
カメラやセンサーなどのネットワーク端末(エッジ)で、データを分散処理する「エッジコンピューティング」の活用が広がっています。サーバーにデータを集めて一元処理するクラウドコンピューティングの通信負荷や処理の遅延などの課題を解決できることから、昨今注目されている技術です。
本記事では、主にエッジコンピューティングに関心を持つ企業担当者の方に向け、エッジコンピューターとは何か、仕組み、注目される背景、活用シーン、課題やデメリット、エッジAIやエッジクラウドなどの関連技術について解説します。是非自社のエッジコンピューティング活用に役立ててください。
AIについて詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
AI・人工知能とは?定義・歴史・種類・仕組みから事例まで徹底解説

エッジコンピューティング(Edge computing)とは、「エッジ処理」と呼ばれる分散処理の一種で、IoT端末またはIoT端末近くのサーバーなどのネットワーク端末(エッジ)にデータ処理を実行させる技術です。IoT端末の急増や5Gの普及などによる「爆発的なデータ量増大」に対応するために、エッジコンピューティングの活用が不可欠とされています。
エッジコンピューティングは、クラウドコンピューティングと対をなすデータ処理に関するネットワーク技術です。エッジコンピューティングは、エッジ側に処理を任せて特定のデータだけをサーバーに送信します。
エッジコンピューティングのネットワーク構成は「エッジデバイス~エッジサーバー~クラウドサーバー」です。ただし、エッジサーバーは省略されることもあります。
それぞれの機器の役割は次のとおりです。
| 構成機器 | 役割 |
| エッジデバイス | カメラやセンサーなどのIoT機器 |
| エッジサーバー | エッジデバイスのデータを取りまとめて、分析したり、クラウド側に送信するデータに加工したりするサーバー |
| クラウドサーバー | エッジサーバーのデータを取りまとめて、分析、加工するサーバー |
例えば、製造現場でエッジコンピューティングを実現する場合、各製造機器や産業機器がエッジデバイスとなります。そして、工場内に設置されたエッジサーバーにデータが集められ、生産状況のモニターや異常検知などの処理が行われます。さらにエッジサーバーからクラウドサーバーに必要なデータを上げることで、全工場を対象にした生産の最適化などが可能になっていきます。
このエッジコンピューティングの仕組みのメリットは、
などです。これらは後ほど詳しく説明します。

先に述べたように、クラウドコンピューティングは、エッジ側で取得したデータをそのままデータセンターに送信する一元集約型のシステムです。一方、エッジコンピューティングはなるべくエッジ側に処理を任せる、情報分散型のIT技術です。
2つの違いを以下に示します。
| 項目 | エッジコンピューティング | クラウドコンピューティング |
| 処理遅延リスク | 少ない (エッジ側で処理するためリアルタイム処理が可能) |
多い (通信による処理遅延、停止が発生しやすい) |
| 通信による情報漏えいリスク | 少ない | 多い |
後ほど説明しますが、エッジコンピューティングには課題・デメリットもあるため、どちらの技術が優れているか、といったことは一概にいえません。エッジコンピューティングの活用は今後広がっていくと想定されますが、企業の活用シーンに応じて、クラウドコンピューティングとの使い分けが進むと予想できます。
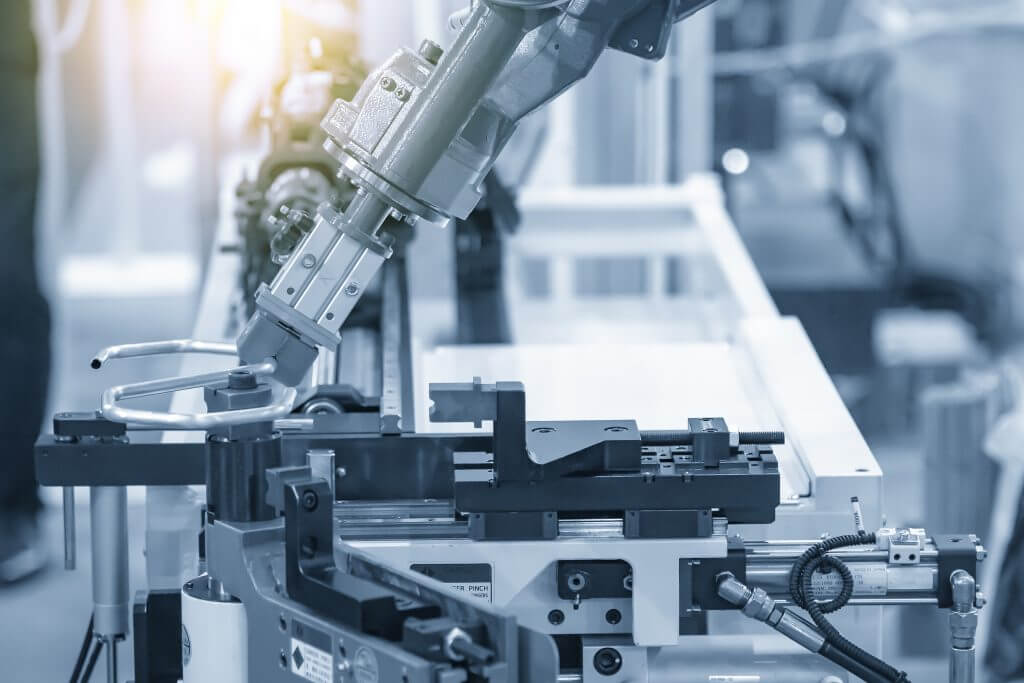
エッジコンピューティングは、IoT社会を実現するための中核技術のひとつに位置付けられています。その大きな理由は、従来インターネットに接続されなかった家電や極小のセンサーなどが接続されるようになったからです。また、高速通信技術(5G)が導入されたことによって、通信量が爆発的に増大している背景があることから、通信量の縮小が求められています。
そして、エッジコンピューティングが注目されるもう1つの理由に、IoT端末が私たちの生活に密着するようになったために起きた「新たなプライバシー侵害の問題」があります。
IoT端末の台数は急速に増加しており、総務省の調べによると、世界のIoT端末は2020年時点で253億台と膨大な数に上っています。
インターネットに接続される台数が増えるほど通信量は多くなり、現在のインターネット環境やサーバー性能では対応できなくなる懸念があります。このため分散処理技術のエッジコンピューティングが注目を集めるようになりました。
仮にエッジコンピューティングを使わないなら、利用価値のないデータもすべてインターネット上に流れます。これでは、通信コスト増大のみならず、通信網全体の混雑を引き起こしてしまいかねません。このため、エッジコンピューティングの普及は、インフラ整備としても捉えることが可能です。
次世代データ通信技術「5G」が浸透すると、ネットワークコンピューティングにも変革が求められるようになってきました。
5Gには次の特徴があります。
この5Gによって、IoTの活用対象が今後ますます広がってくると予想されています。代表的なのは車の自動運転や、ビックデータを活用した気象予測などです。
このような技術を実用化するにあたっては、クラウドサーバーの負荷を減らしつつ、かつリアルタイムで処理できる性能を確保しなければなりません。そこでクラウドに依存せず、自律的に判断、実行できる部分が多いエッジコンピューティングを活用しようとする動きが加速しています。
データセキュリティやデータガバナンスの要求が厳しくなったことも、エッジコンピューティング化を推し進めています。先にも解説したように、エッジコンピューティングには、通信による情報漏えいが起きにくい特徴があります。
IoT端末が私たちの暮らしに深く入り込むにつれ、エッジコンピューティングの必要性は高まっていきます。極端な話、スマートスピーカーや防犯カメラのデータなどがそのままクラウド上に転送されていれば、誰も使いたくないでしょう。企業のコンプライアンスとしても大いに問題があります。
実際、国際的にデータ保護を厳しくする動きが進んでおり、日本も2022年に個人情報保護法が改正されました。IoT関連の製品を提供する側としても、ソリューションの利用側としてもエッジコンピューティングの重要性が高まっています。

エッジコンピューティングは業界や規模を問わず、活用の範囲を広げています。代表的な事例を3つ紹介します。
自動運転機能にはリアルタイム処理が必須で、通信不具合による遅延、停止も発生してはいけません。例えば障害物の自動回避機能などに、低遅延のエッジコンピューティングが活用されています。
農地や作物の生育状況などを、多数のカメラやセンサー類でモニターします。このようなシステムには大規模なサーバー設備が必要でしたが、エッジコンピューティングによって小規模な農家でもスマート農業を実現しやすくなりました。
店内カメラを用いた行動分析サービスはクラウドコンピューティングでもありますが、個人を特定できるデータを送信するため、データ保護の観点で問題がありました。エッジコンピューティングを活用すれば、エッジ側で人物の座標データや滞留時間などに加工したうえでクラウドサーバーに送信するため、セキュリティレベルを高められます。
企業がエッジコンピューティングを活用する際には、コストと管理運用の手間の増大リスクがあります。ここでは、次の3つの角度から、エッジコンピューティングの課題・デメリットを解説します。
開発規模によっては、「ヒト・モノ・カネ」の経営資源を確保・配分しなければならないため、概要を把握しておくことが重要です。
エッジコンピューティングのIoT端末は、クラウドコンピューティングのIoT端末より多くの技術を搭載するため、端末1台あたりの導入コストが大きくなります。サーバー側の設備費用は削減できますが、システム構成によっては、IoT端末のコスト面のデメリットが大きくなってしまいます。
また、情報管理の場所が分散されるため、管理運用コストも大きくなります。例えば、以前は本社のコントロールセンターに集めていた情報を、各工場のエッジサーバーで管理するようにすれば、保守・修理のコストが増えやすくなります。
IoT端末が高性能になれば、それだけ開発コストやメンテナンスの手間が増えることが想定されます。具体的な失敗事例としては、「IoT端末に搭載するAIのアーキテクチャやアプリケーションを自社開発してチューニングしたため、実用化までの工数が予想外に増えてしまった」などがあります。
このため、開発済みのAIやボード、あるいは開発プラットフォームを利用するなど、工数を減らすために自社に合った方法を検討する必要があります。
エッジコンピューティングによってセキュリティを高めても、ネットワークに接続されている以上、セキュリティリスクはゼロではありません。IoT端末やエッジサーバーに重要なデータがあると分かれば、それらが狙われるケースもあるでしょう。
例えば、データを保存してあるIoT端末が物理的に盗まれるなど、クラウドコンピューティングにはないリスクが伴います。また、ウイルス対策ソフトがないIoT端末の脆弱性を狙ったサイバー攻撃も増えています。自社や顧客が求めるセキュリティレベルを満たせるか、事前に検討しておきましょう。
エッジコンピューティングの技術は進化を続けていますが、そのなかで現在、重要になっているのが「エッジAI」と「エッジクラウド」の2つの技術です。
エッジAIとは、IoT端末やエッジサーバーにAIを搭載する技術です。サーバー側から命令がなくても自律的に処理できるため、エッジコンピューティングの領域を拡大できると期待されています。
既にドローンの自動運転や製造現場のロボット、警備業界の監視カメラなど、さまざまな分野で実用化が進んできました。エッジAIはリアルタイム性が担保できるうえ、ディープラーニング(深層学習)を搭載したエッジAIなら、自ら学習して新たな処理フローを生成することで性能が向上します。
エッジクラウドとは、ローカルネットワークにエッジデバイスを結んだクラウド環境を作る技術です。エッジコンピューティングとクラウドコンピューティングのメリットを両取りした技術とも言えるでしょう。
2020年からはエッジクラウド構築に向く「ローカル5G」サービスが開始されました。無線局の免許を取得する必要がありますが、工場や農地など特定のエリアに限った5G通信を実現できるため、エッジクラウドの可能性が広がっています。
エッジコンピューティングは、あらゆるものがインターネット上につながり、私たちの暮らしやビジネスを活性化させていくIoT社会に必須の技術です。ネットワークの末端(エッジ)で処理を分散すれば、クラウド上の通信量を増やさず、高度な動作を低遅延で実現できます。
その反面、導入・運用コストがかかってしまう課題が残っているため、既存の製品、サービス、開発プラットフォームの活用検討もおすすめします。エッジコンピューティングやエッジAIのサービス比較と企業一覧の資料は以下のリンクからダウンロードできますので、一度じっくり見比べてみてはいかがでしょうか。
業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。
メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。
AI製品・ソリューションの掲載を
希望される企業様はこちら