生成AI

最終更新日:2024/03/01
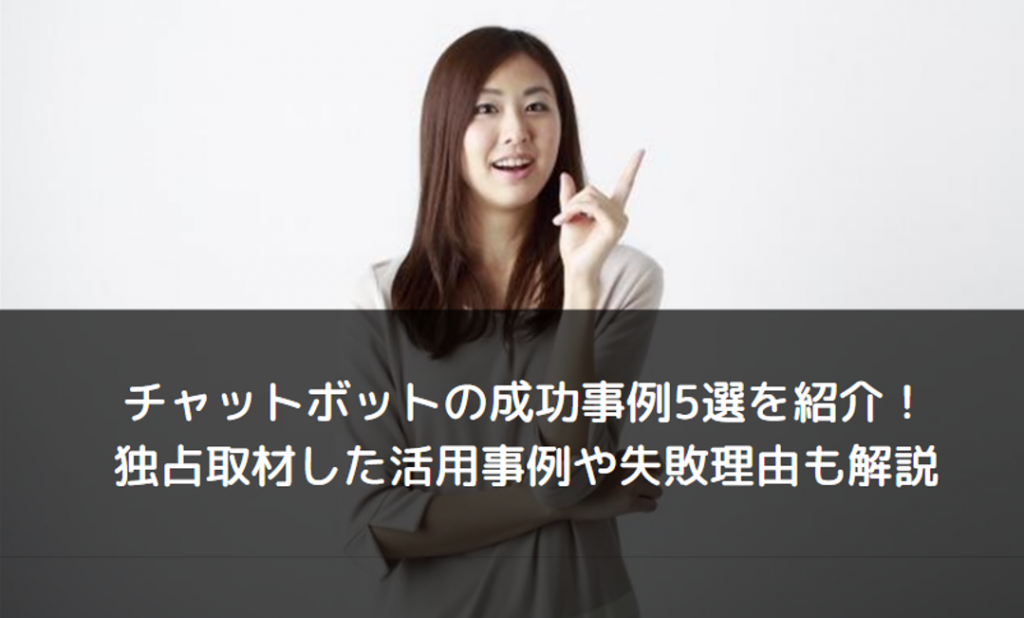 チャットボットの成功事例を紹介
チャットボットの成功事例を紹介
昨今は少子高齢化に伴う人手不足が深刻化しているため、業務効率化や生産性の向上が大きな課題となっている企業も少なくないでしょう。そのような中で、業務効率化を図るための手段として「チャットボット」を導入する企業が増えています。
では、実際にチャットボットを導入している企業は、どのように成功を収めているのでしょうか。今回は、チャットボットの成功事例や失敗理由などをご紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
チャットボットについて詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
チャットボットとは?意味やメリット、活用事例を徹底紹介
そもそも、チャットボットはどのようなシーンでの活用が適しているのでしょうか。まずは、チャットボットが活用されるシーンについて詳しくみていきましょう。
サッポロビールでは、問い合わせ対応や社内資料の作成などの業務に追われ、顧客訪問など、付加価値を生むための本来の業務に十分な時間が割けないという課題を抱えていました。
2016年12月~17年4月に実施した実証実験では、社内問い合わせ管理サイトにおいて、FAQを一元管理する仕組みを構築。ただ仕組みを構築しただけでは、社内に新システムが普及せず結局廃止となってしまう事例も多いものですが、同社では実施する目的とアウトプット・イメージを社員に伝えるほか、FAQを継続的に活用するためのマネジメント研修も実施し、利用率の向上に努めました。
その結果、当初の想定よりも多い約600件のFAQデータが集まったほか、適切なFAQの作り方を指導する研修を実施したことで、回答精度も当初の60~70%から80~90%まで高めることに成功しました。間接部門では問い合わせ対応業務が45%も削減し、情報検索時間も80%短縮したそうです。
チャットボットは、社内のナレッジ共有を目的に導入するのも効果的です。チャットボットを導入することによって、社員が知りたい情報に素早く辿り着けるようになり、自力で解決できる可能性も高められます。
社内に蓄積された情報やスキルを共有し、有効活用できるようになれば、仕事の属人化を防ぎつつ生産性向上を図ることができるのです。そのため、人手不足が深刻化しつつある現代において、非常に大きなメリットが得られるでしょう。
カスタマーサポート(お客様対応)においても、チャットボットを活用することでさまざまなメリットを得られます。というのも、チャットボットを導入することによって、「頻繁に寄せられる簡単な質問はチャットボットに対応させる」「難易度の高い質問はオペレーターが直に対応する」といったように振り分けることが可能になるからです。そのため、オペレーターはすべての問い合わせに対応する必要がなくなり、負担を削減できるようになります。
また、ユーザーがいつでも気軽に問い合わせを行える環境を構築することも可能です。そのため、「問い合わせたいことがあるのにカスタマーサポートの電話が混み合っていて解決できない」といった事態に陥るのを防ぐことができます。
ユーザーを待たせる時間が長くなると、ユーザーの満足度も低下してしまうため、企業としてのブランディングにも悪影響を及ぼしかねません。顧客満足度を高めるという意味でも、待ち時間短縮や24時間対応を実現できるチャットボットには大きなメリットがあるといえるでしょう。
広告のコンバージョンアップを図りたい場合においても、チャットボットは役に立つでしょう。AI搭載のチャットボット型広告には、ユーザーからの「ヒアリング」や「対話」を重視していくという特徴があります。
例えば、不動産会社の広告の場合、ユーザーがバナーなどをクリックするとチャットボットが立ち上がり「どんな部屋に住みたいですか?」などとユーザーに問いかけます。ユーザーが「広い部屋」「●●駅に近い部屋」などと希望を告げると、チャットボットが希望条件に近い部屋を提案してくれます。それらが広告として機能するという仕組みになっているのです。
チャットボットがあらかじめユーザーの希望をヒアリングしてから広告を表示するので、押しつけがましさがなく、より自然な提案を行うことができます。これにより広告のコンバージョンアップが期待できるというわけです。
では、チャットボットを導入することで、具体的にどのような効果やメリットが得られるのでしょうか。ここからは、チャットボットの導入によって期待できる効果・メリットを詳しくみていきましょう。
チャットボットを導入すれば、24時間365日対応できるようになります。これは、チャットボットを導入することで得られる最大のメリットと言っても過言ではないでしょう。というのも、近年はスマートフォンが普及したことにより、ユーザーがいつでもインターネット検索を行ったり、気に入った商品を購入したりできるようになったからです。そのため現在は、深夜に「この商品についてもっと詳しく知りたい」と思い立つケースも少なくありません。
そのような場合に、チャットボットが疑問を解消してくれるため、顧客満足度向上にもつなげていくことができます。低コストで問い合わせ対応の環境を整えられるという点は、大きなメリットといえるでしょう。
ユーザーから似たような問い合わせが頻繁に寄せられることは、決して珍しくありません。その質問に毎回担当者が回答していくのは、決して効率的とはいえないでしょう。その点、チャットボットであれば問い合わせ対応を自動化できるため、従業員は他の業務へ力を注ぐことが可能になります。
特に近年は、少子高齢化に伴う人手不足問題が深刻化していることもあり、多くの企業が「人的コストの削減」が課題となっている状況です。業務効率化によって人的コスト削減を実現できることは、大きなメリットといえるでしょう。
最近では、さまざまな企業がチャットボットを導入し、成功に繋げています。ここからは、実際にチャットボットを導入し、成功に繋げた企業の事例をいくつかご紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
DMM.com証券では2021年6月18日より、カラクリが提供する「KARAKURI chatbot」を「DMM FX」に導入し、AIチャットボットを用いてお問い合わせ対応をしました。
「KARAKURI chatbot」は、ユーザーからのお問い合わせに対して24時間365日自動対応するAIチャットボットです。導入から運用までのプログラミングスキルが不要、また UI特許を取得した誰にでも扱いやすい管理画面を備え、AIトレーニングを効率的に行えることが特徴です。そのほか、チャットボットのQAデータでFAQを自動生成することが可能です。
チャットボットはお客様から寄せられた質問を継続的に学習し、より精度の高い回答を行えるよう成長し続けます。また、チャットボットが回答できなかった質問については、有人チャットに切り替えることで、カスタマーサポートのオペレーターにチャットでお問い合わせすることが可能です。
株式会社稲葉製作所では、顧客ニーズの多様化に合わせて商品ラインナップや営業所を増やしていく中で、取引先からの問い合わせが増大するとともに多様化しました。そして、「営業の現場では即答が要求されるため、開発部門にその都度電話で問い合わせる」という状況は、 営業・開発部門双方にとって業務を逼迫させていました。
そういった課題を解決すべくチャットボットを導入したところ、問い合わせに対する回答スピードや効率が向上したそうです。チャットボットを導入することで24時間365日いつでも気軽に使用できるようになり、「こんなレベルの低い質問をしてもいいのだろうか」と悩むこともなくなり、本当は聞きたかったのにわからなかったことが解決できているといいます。同時に、本来質問されていた内容も、新人が自力で解決できるようになった結果、育成担当の工数削減にもつながっているそうです。
株式会社ゆうちょ銀行は、社内向け問い合わせ対応業務の効率化実現に向けて、富士通株式会社のAI技術を活用したナレッジサービス「FUJITSU Cloud Service Know-Flow DX」を2022年1月に導入し、ゆうちょ銀行233店舗およびゆうちょ銀行の商品サービスを取り扱う一部の郵便局にてチャットボット機能を利用。今般、郵便局においてサービスの利用範囲を拡大し、5月30日から、全国約2万4千局の郵便局にて利用を開始しました。
ゆうちょ銀行のパートナーセンターでは、店舗社員および貯金窓口を担当する郵便局社員からの問い合わせに対応しています。このサービスにより、パートナーセンターで蓄積された多岐に渡る商品サービスの膨大なFAQを店舗や郵便局とチャットボット形式で共有し、貯金窓口担当社員が直接検索できるようになります。これにより、パートナーセンターへの問い合わせ件数を削減し、オペレーターの負荷を軽減。また、全国の貯金窓口担当社員が整備されたFAQを活用することで、業務スキルを平準化し、顧客への速やかな対応を実現するなど、さらなる満足度向上につなげていくことができます。
パートナーセンターで、オペレーターが貯金窓口担当社員から電話問い合わせを受けると、その応対内容が「Contact Center Knowledge Assistant」の音声認識機能でリアルタイムにテキスト化され、画面に表示されます。調べたい内容を含む会話ブロックを検索文としてクリックすると、AIを活用したFAQ検索機能により、適切な回答候補を確認することができます。さらに、同一画面で応対記録も作成できるため、入電から電話応対、FAQ検索、記録作成までの一連の業務を一画面で完結することが可能。これにより、1応対当たりの対応時間の削減が期待できます。また、50拠点に及ぶオペレーターの応対スキルの平準化や、新人オペレーターが早期に即戦力として活躍が見込めます。
今回、新たに導入した「Know-Flow DX」は、「Contact Center Knowledge Assistant」で蓄積されたFAQを、貯金窓口担当社員がチャットボット形式で直接検索することを可能にします。これにより、パートナーセンターへの問い合わせ件数や問い合わせ時間の削減を見込んでおり、オペレーターや貯金窓口担当社員の負荷軽減を図るとともに、問い合わせ内容や傾向分析が可能なダッシュボード機能により、追加が必要なFAQの更新を的確に判断し最新化することが可能になり、業務が効率化。さらに、ゆうちょ銀行や郵便局を利用される顧客への迅速な対応を実現し、さらなる満足度向上に貢献します。
emol株式会社は、 2020年9月〜11月までの3ヶ月間、第一生命保険株式会社と共同でAIがユーザーの悩みに合わせて保険商品をレコメンドするデジタルトランスフォーメーションの実証実験を行いました。 実証実験はemolのアプリ上で行い、ユーザーとAIとのチャットで 保険と関連性のある話題が上がった際にAIからヒアリングを行いユーザーに合った保険をレコメンドし、第一生命の保険商品webサイトまで案内するという仕組みです。
第一生命の保険商品webサイトまでのクリック率(CTR)計測を行った 結果として、チャット上から第一生命の保険商品webサイトへは、twitter広告やFacebook広告などのSNS広告のCTRを圧倒的に上回る数値となりました。
実証実験の流れを踏襲し、emolアプリ上でユーザーがチャットでAIに悩みを話した際に保険に関連する話題に合わせて保険をレコメンドする機能と、emolアプリ上にAIが保険の診断をする保険の窓口を設置し、いつでも対象の保険についてAIに質問できる場を提供します。
ピーシーアシスト株式会社では、問い合わせフォームにアクセスして申し込みに至るまでに離脱する人が非常に多いという課題を抱えていました。この課題を解決すべく、クラウドCXプラットフォーム「Genesys Cloud CX」を導入したところ、電話では短くても3分ほどかかっていた予約作業を、チャットにより最短で約1分に短縮することに成功したといいます。
導入前は、メインとなる問い合わせ電話を時間によって当番制にしていたものの、当番のオペレーターが他の電話の対応をしていたり、他の業務を行っていたりすると、取れないことがありました。また、時間や曜日によって件数も異なり、不公平感が生じてしまうことがあったそうです。
その点、現在はGenesys Cloud CXが手の空いているオペレーターに機械的に振り分けることができるため、不公平感が解消されたといいます。
チャットボットを導入しても、成功に繋げられるとは限りません。場合によっては失敗に終わってしまうケースもあります。そのような事態を防ぐためには、どのような点に注意すれば良いのでしょうか。チャットボット導入が失敗する理由や注意点を詳しくみていきましょう。
チャットボットを導入してしまえば業務効率化を実現できますが、導入する際には手間と時間がかかることを忘れてはいけません。とくに精度の高いチャットボットを導入する場合には、その開発にも手間と時間がかかるため、事前にどれくらいの時間がかかるのか、計算しておく必要があるでしょう。その計算を怠ってしまうと、想定外の事態に巻き込まれたときに上手く対応できず、失敗に終わってしまう可能性が高まってしまいます。
また、基本的にチャットボットはすべての業務を自動化できるわけではありません。そのため、オペレーターとの連携を取りながら業務効率化を図っていくことが大切になります。これらをあらかじめ想定し、チャットボットの実用化には時間がかかることを把握した上で計画を進めていくことが大切になるでしょう。
高精度のチャットボットを利用する場合は、適切なシナリオの設定やAI仕様の設定など、定期的なメンテナンスが必要になります。このメンテナンスを怠ってしまうと、AIが適切ではないデータをもとに学習し、問い合わせ対応の質を低下させてしまう可能性が高まるからです。最悪の場合、ユーザーが抱える問題を解決することができず、クレームに繋がってしまうケースも考えられます。
そのような事態を避けるためにも、チャットボットが対応できなかった質問を定期的に確認し、改善していく作業が大切になります。
チャットボットを導入すれば、的確に問い合わせ対応を行っていくことが可能になりますが、オペレーターのような柔軟性を持ち合わせているわけではありません。あくまでも、データベースに登録された質問にしか答えられないからです。そのため、場合によっては対応に「人間味」を感じられず、親切心を感じられないユーザーが出てきてしまう可能性もあるでしょう。
とくに、普段から電話で問い合わせを行っているユーザーなどは、チャットボットの対応が機械的に感じられてしまう可能性が高いので、返答内容を慎重に作成していくことが大切になります。より丁寧かつ分かりやすい文章で返答内容を作成していくようにしましょう。
また、質問内容に応じてオペレーターが直接回答できるよう棲み分けを明確にしておくことも、ユーザーの満足度を高めるための手段として有効になります。
今回は、チャットボットの成功事例や失敗理由をご紹介しました。さまざまな企業がチャットボット導入を成功に繋げている一方で、失敗のリスクもあることがお分かりいただけたのではないでしょうか。
チャットボットの導入を成功に繋げるためには、成功事例や失敗事例を把握した上で、適切な戦略を立てていくことが大切になります。以下の記事では、チャットボットの導入によって課題を解決することに成功した企業の成功体験集を掲載していますので、チャットボットの導入をご検討の際はぜひこちらも参考にしてみてください。
業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。
メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。
AI製品・ソリューションの掲載を
希望される企業様はこちら