生成AI

最終更新日:2024/04/04
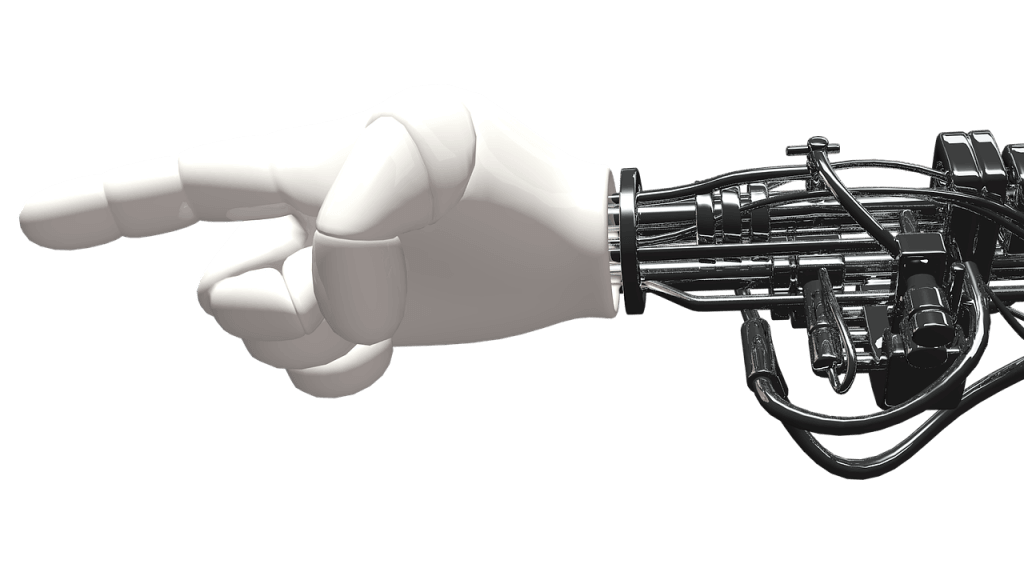
近年、ホワイトカラーのオフィスワークを効率化する手段として、「RPA:Robotic Process Automation(ロボティック・プロセス・オートメーション)」が注目を集めています。
ただ、RPAは注目分野だけに参入も多く、価格や機能面からどうやって絞り込めばよいのか分からないという方も多いでしょう。今回はそうした方向けに、RPAの選定基準を紹介します。
RPAについて詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
RPAとは?導入によって期待できる6つ効果と自動化できる5つ業務

RPAには「デスクトップ型」「サーバー型」という2つの種類が存在します。そんな2つの提供形態があるRPAですが、実はこの提供形態によって価格も異なります。それぞれがどのような特徴を持っており、またどのような価格差があるのか、詳しくみていきましょう。
デスクトップ型RPAとは、PCにRPAツールをインストールして自動化の作業を行うというタイプです。「RDA(ロボティック・デスクトップ・オートメーション)」と呼ばれることもあります。
サーバーに接続するわけではなく、PCだけで作業を完結するという点が特徴です。そのため、ネットワーク環境がなくても作業をすることができます。
ただし、PC端末ごとにライセンス契約を結ばなくてはならなくなるため、導入規模が拡大するにつれてコストは膨れ上がってしまうでしょう。
一方のサーバー型とは、PCとサーバーに接続し、ロボットによる自動化を図るRPAツールです。
サーバー上で複数のロボットを一括管理することができるので、PC端末の負荷を高めることなく別の作業に打ち込めるという点は大きなメリットといえるでしょう。
デスクトップ型よりも1ライセンスの価格は高額な傾向にありますが、端末ごとにライセンスが増えていくわけではないため、導入規模の拡大によるコスト拡大のリスクはデスクトップ型よりも低いといえます。
これらの具体的な選定基準については、後ほど詳しくご紹介します。

RPAにはデスクトップ型とサーバー型という2つの種類が存在することをご紹介しましたが、RPAはサービスの提供形態によっても分けることができます。主に分けられるのは、「オンプレミス(オンプレ)型」と「クラウド型」の2種類です。
実はこのサービスの提供形態によって価格も異なります。それぞれの提供体系にはどのような特徴があり、またどのような価格差があるのか、みていきましょう。
「オンプレミス(オンプレ)型」とは、自社のサーバー上にソフトウェアをインストールしてシステム環境を構築する形態のことです。
ソフトウェアによってある程度テンプレートは決まっているものの、プログラミングの知識と技術があれば、カスタマイズの範囲を広げることもできます。
ただし、既存の自社システムとの連携を図りやすいというメリットもある一方で、開発にかかる工数や時間、導入コストがかかる点がネックです。
一方のクラウド型は、ソフトウェア提供事業者のサーバーにアクセスしWebブラウザ上で操作します。
既に提供されているソフトウェアを利用するだけなので、導入初日からすぐに使うことができ、料金体系もライセンス数に応じた月額の使用料ベースとなることが多いでしょう。

海外発のRPAツール、UiPathやRPA Expressのように、無料で使えるツールもあります。
「RPAについてよく耳にするけど実際使いこなせるか分からない」「まずはスモールスタートで始めたい」といった場合には、こうしたフリーソフトを使ってみて自社のニーズに合うかどうかを見極めてみるのもよいでしょう。
このほか、国産RPAの「RPA Robo-Pat(ロボパット)」はフリートライアル期間も設けています。
これらのツールに関心を持っている方は、まずは無料で試してみてはいかがでしょうか。
RPAのフリーソフトはこちらの記事で一覧にして紹介しています。

RPAツールを導入する際、どういった点を検討すべきなのでしょうか。
デスクトップ上で自動化するRPAツールであれば、数ライセンス購入したとしても、年間数10万円から数100万円で導入できるでしょう。
一方で、サーバー管理をするタイプであれば、年間数100万から数1,000万円かかることもあります。
また、導入するためのコンサルティング費用や保守管理費用が発生する可能性も念頭に置きましょう。
社内で大々的にRPAツールによる業務効率化を図るのであれば、「オンプレミス(オンプレ)型」を選択して、サーバーで中央管理するのも良いかもしれません。
一方、自動化すべき業務がそれほど特殊でも広範囲でもなく、一部署やチームのみでの導入で数ライセンス単位というのであれば、クラウド型という選択肢もあるでしょう。
もし、個人レベルで定型作業を自動化したいというニーズであれば、フリーソフトを活用するのがおすすめです。
高セキュリティを要求されるような業務であれば、サーバーで管理するRPAツールが適しているといえます。
そういった業務でなければ、一般的なRPAツールでもセキュリティ面でそう神経質になる必要はないでしょう。
RPAツールは非効率なオフィス業務を自動化し、生産性を高める狙いがあります。
一方で、間違ったツールを選択してしまうと、かえって業務の足を引っ張る可能性もありますし、将来的に業務手順が変わったときなどにシナリオの見直しが煩雑すぎてできない、といった問題が発生する可能性もあります。
その場合、導入にかかったコストが無駄になってしまうことになりますし、別のRPAツールを選び直すとなれば、さらにコストが膨らんでしまうのです。
そのような失敗を避けるためにも、「自動化を図るべき業務は何なのか」といった点を明確にしておく必要があります。とくに最近はさまざまな種類のRPAツールが存在しているため、しっかりとリサーチすることが大切です。
そのため、RPAツールの導入を検討する際は、さまざまな部署の担当者との話し合いを重ねて自社の方向性を明確にしておいたほうが良いでしょう。
「RPAなら自動化できる!」とやみくもに導入するのではなく、業務範囲や自動化の目的、数年先の利用範囲までを見据えた判断を下すことが大切です。ぜひ、今回ご紹介した価格・機能・選定基準などを参考に検討していってみてはいかがでしょうか。
AIについて詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
AI・人工知能とは?定義・歴史・種類・仕組みから事例まで徹底解説
業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。
メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。
AI製品・ソリューションの掲載を
希望される企業様はこちら