生成AI

最終更新日:2024/04/04
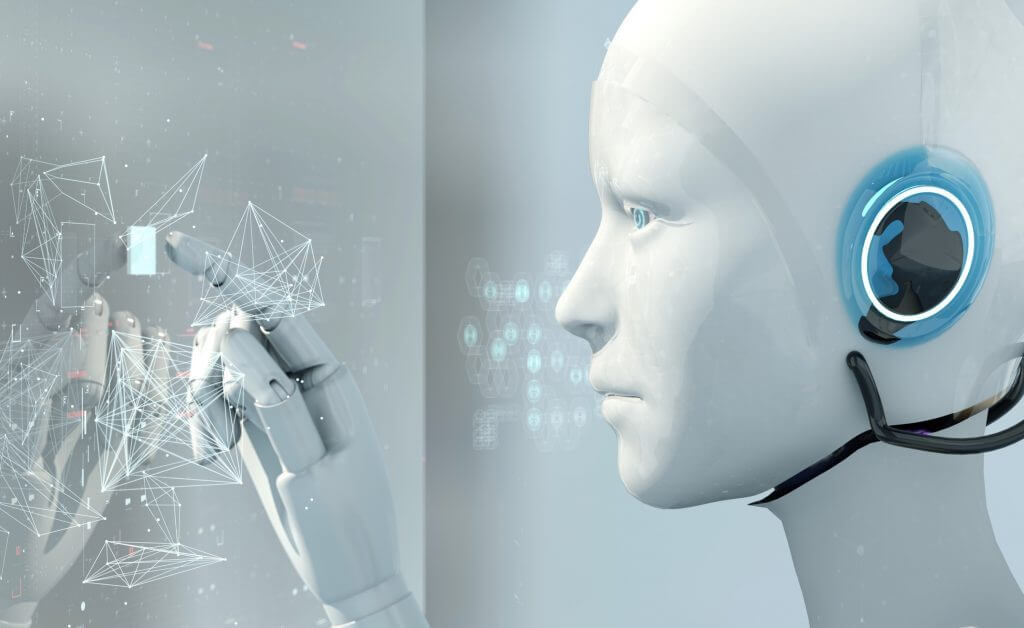
ホワイトカラーの業務効率化の切り札として語られることも多い「RPA(Robotic Process Automation)」。金融業界などではとくに導入が進んでおり、行政機関やさまざまな業種・業界にも波及しています。しかし一方で、RPAの導入は「対症療法」と揶揄され、根本的な業務効率化につながらないとの指摘もあるのです。そこで今回は、拡大するRPAの導入事例についてまとめました。
金融業界は、メガバンクがそれぞれRPAを導入するなど、活用が進んでいる業界です。大量の書類を扱う必要があり、かつ定型業務も多いことから、導入メリットが大きいのでしょう。
三菱UFJ銀行はいち早くRPAの可能性に着目し導入を決めた金融機関です。同行の東京の本部には、企画や管理などを担当する6000人が在籍していますが、RPAの導入で事務作業を自動化した結果、2023年度までに約3000人分に相当する業務量を削減できる見込みだといいます。
なお、RPAの導入によって浮いた人員は、人手不足が見込まれる営業部門や米国やアジアなどの海外部門へ配置するとのことです。長期金利がゼロ%前後で推移する中、従来型の銀行のビジネスモデルでは収益確保が難しくなっています。同行ではIT部門などの人員強化を図る一方で、新卒の採用人数の絞り込みや銀行窓口での行員対応の削減なども進め、業務効率化に向けた改革を目指します。

一方、RPAの導入を支援する新会社を立ち上げて、本格導入を目指すのが三井住友銀行です。 同行では2017年からRPAの活用を始め、2018年9月末時点で800人分(160万時間)の業務自動化を達成。2020年3月末までに1500人分(300万時間)の業務量を削減する計画です。新たに設立する全額出資子会社「SMBCバリュークリエーション」では、こうした経験をもとに地方銀行や証券会社、事業会社向けのRPAシステムの設計や開発、運用を請け負います。

楽天グループの金融サービスにおいて中核をなす「楽天カード」も、RPAを導入しています。楽天カードでも膨大なデータを処理する作業の自動化は進んでいたそうですが、それに伴い手作業によるPC作業も増えていたといいます。
そこで、楽天カードはRPAツールの「WinActor」を導入し、業務自動化を始めました。
楽天カードには、ハンドオペレーションによる作業が数多くあり、その数は約200種類に及ぶそうです。そんな多種に及ぶ業務が存在することは大きな問題であったため、いかに作業工数を圧縮するか検討した際に浮かび上がったのが、「WinActor」の導入だったといいます。
そして、約2ヶ月の検証期間を設け、約200種類存在するハンドオペレーションのうち、PC操作がメインであり顧客データなどの更新をすることがない12種類が業務自動化に選ばれたそうです。
楽天カードが導入した「WinActor」はプログラミングの専門的な知識を持ち合わせていなくても、シナリオを制作できるというメリットがあります。最近はこのようなメリットを持つRPAも多く存在するため、この点を比較検討の材料にするケースも多いでしょう。
ただし、楽天カードのシステム運用部担当者によれば、「簡単にシナリオ制作ができるからこそ、シナリオが乱造されることもある」といいます。そのため、制作者や目的が不明なシナリオを放置しないようにするための責任者を設けることが重要になります。
とはいえ、RPAを導入せずにすべてハンドオペレーションで対応する場合と比べれば、遥かに業務自動化を進められます。そのため、やはりRPA導入のメリットは極めて大きいといえるのではないでしょうか。
このように、業務削減効果が次々と報告されているRPAですが、一方で「対症療法」と揶揄され、根本的な業務効率化につながらないとの指摘もあります。
その理由として、日本でのRPA導入は「ボトムアップ型」であることが指摘されています。日本の雇用契約では、各人の業務範囲を明確にする「ジョブディスクリプション」が明示されていないことがほとんどです。責任の範囲があいまいなまま業務が属人化するため、業務内容全体の整理が行われていないケースも多々あります。そこに、RPAを導入して効率化を図ったところで、目に見えている範囲の作業が自動化されるだけで、ボトルネックの発見など根本的な解決にはなっていないという指摘です。
ジョブディスクリプションによって各々の業務範囲が明確化されている海外では、トップマネジメントが全体を俯瞰し、トップダウン型でRPAなどの新たな取り組みを推進するスタイルが多くみられます。一方で、日本では部署ごとでまず導入し、横展開していくボトムアップ型が多いようです。こうしたやり方では、部分ごとの作業が自動化されたとしても、全体としてはつぎはぎだらけになってしまう恐れがあります。そのため、「対症療法」と揶揄されてしまうのでしょう。
また、トップマネジメントがRPAを推進するケースでも、「RPAによる自動化」が導入の目的と化してしまい、現場の意見を吸い上げずに導入を決めてしまったため、現場のニーズに合わず、かえって生産性が低下するという残念な例もみられます。これは、トップマネジメントが業務全体を俯瞰していないために起こることで、業務改革には、マネジメントが現場を理解しているということが極めて重要です。
現場を理解したうえで、RPAの導入が根本的な課題解決につながるのかどうかを検討するべきだといえるでしょう。
今回ご紹介した導入事例で、RPAによって業務効率化を実現できていることがお分かりいただけたかと思います。ただし、最近はさまざまなRPAが存在していおり、それぞれ機能が異なるため、自社が抱えている問題の本質を理解した上でRPAを選ばなければ問題を解決できない可能性もあります。
そのような失敗を避けるためにも、まずは現場の担当者とのコミュニケーションを図り、現場の課題を洗い出すことが重要になるでしょう。そして、その課題を解決できるRPAをしっかりと比較検討することが大切になります。
現場の意見を尊重し、生産性を最大限高められるRPAを選択できるかどうかが、RPAの導入を成功に導く鍵となるでしょう。
業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。
メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。
AI製品・ソリューションの掲載を
希望される企業様はこちら