生成AI

最終更新日:2024/02/29
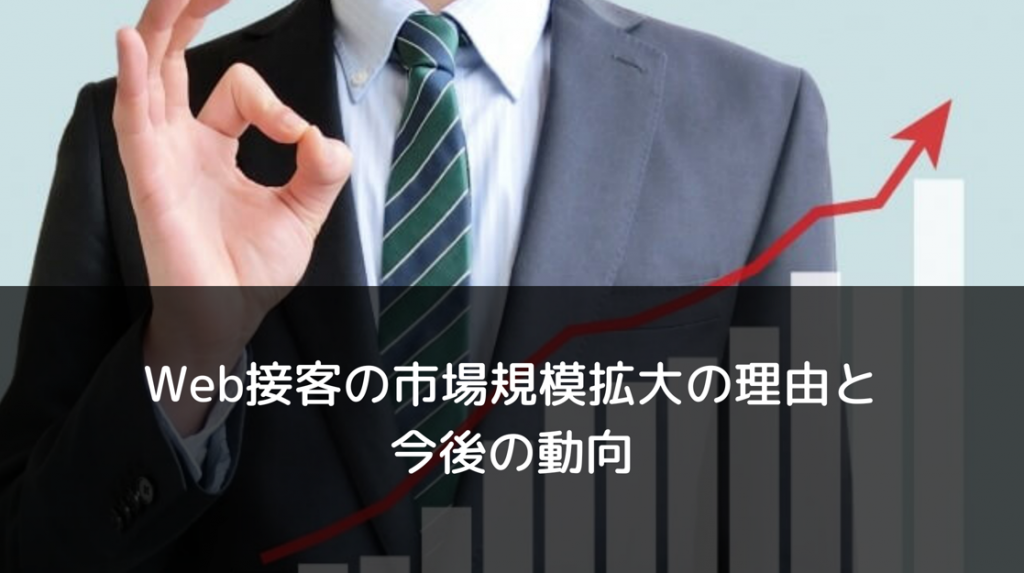 Web接客市場の今後は?
Web接客市場の今後は?
調査会社のアイ・ティ・アールによると 、チャット機能を利用してWebサイトやECサイトで顧客へのサポートを行うWeb接客ツールの売上金額(2016年度)は、前年度比142.9%増の17億円となりました。これは、新規ベンダーの参入により認知が高まったことが背景にあります。また、2017年度も129.4%増の高成長を維持し、2016~2021年度の年平均成長率(CAGR)は34.6%と予測されています。今回は急速に発展するWeb接客市場について、最近の動向や事例などを見ていきましょう。
株式会社アイ・ティ・アールが発表したWeb接客市場規模推移および予測によると、Web接客市場の2016年度の売上金額は17億円、前年度比142.9%増の急速な伸びとなり、その後も年々市場規模が拡大されている状況です。
そんな、大きな注目を集めるWeb接客市場ですが、どのような理由で市場拡大につながっているのでしょうか。まずは、Web接客の市場が拡大している4つの理由をご紹介していきます。
IBMが2022年7月に発表した「世界のAI導入状況 2022年 (Global AI Adoption Index 2022)」によると、世界のAI導入率は前年の2021年と比較して着実に高まっており、2022年は導入率が35%に達したそうです。これは、AI実装のハードルが下がったことにより、よりAIの成長が加速していることを示す数字といえるでしょう。
近年は、取り扱うデータの種類や量が大幅に増加していることもあり、データを活用した分析・予測なども複雑になってきています。そのため、少子高齢化に伴う人手不足が深刻化している現代において、データを効率的に扱うことが大きな課題となっていたわけです。
そのような中で、労働効率化を目的にAI導入に踏み切る企業が多くなっていることに加え、最近ではAI導入の成功事例が多くみられるようになったことから、AI導入を検討する企業数も増加しているのです。
新型コロナウイルスの感染拡大に伴いテレワークを導入する企業が増加したことも、Web接客の市場規模拡大につながった理由の一つといえるでしょう。また、新型コロナウイルスの影響で外出を控える人が増え、オンラインで買い物をする人が増えたことも、Web接客の市場規模に大きな影響を与えているわけです。
業務効率化を実現したり、オンラインショッピングでも実店舗同様のサポート体制を実現したりと、多くのメリットを得られることから、今後は新型コロナウイルスの影響に関係なくWeb接客の需要が高まっていくことも期待されています。
新型コロナウイルスの影響により、多くのユーザーの「ウェブ上でモノを買うことへの抵抗」が下がってきており、リアル店舗からの購買と遜色ないレベルに感じる人も多くなってきている状況です。また、店舗での対面接客よりも、AIチャットとのコミュニケーションのほうが気楽に感じるというユーザーも多くなってきています。そのような点も、Web接客の市場規模拡大につながっている理由の一つといえるでしょう。
サービス系EC市場規模は、2019年に19兆3,609億円にまで伸びたものの、2020年には19兆2,779億円と微減しました。しかし、2021年には20兆6,950億円と再び増加傾向にあります。
今後サービス系EC市場が成長していくことにより、Web接客の需要もさらに高まっていく可能性が高いでしょう。先ほどもご紹介した通り、近年はネットショッピングに抵抗を感じるユーザーも少なくなってきているため、今後のさらなる市場規模の拡大が期待されます。

Web接客ツール市場が成長している背景には、コミュニケーションツールが多様化していることがあります。若い世代を中心に、メールや電話、問い合わせフォームだけでなく、チャットでのコミュニケーションが増えています。LINEやFacebookメッセンジャーなどの普及などがその後押しをしたことは間違いないでしょう。企業側としても、チャットでのコミュニケーションの方が1人のオペレーターがより複数の問い合わせに対応できるため、業務効率が向上できます。
さらにチャットボットと呼ばれるWebスクリプトや、機械学習やディープラーニングでよりコミュニケーション能力が進化したAIアシスタントなどを用い、顧客サポートの省人化を進める企業も増えています。ITテクノロジーの発達とともに、Web接客ツールはさらに普及すると考えられるため、今後の市場規模も年々拡大すると予測されているのです。
Web 接客には大きく分けて4つの分野があるとされています。1つ目は、Web上での接客に軸足を置いたもの。2つ目は、離脱防止を目的としたサービス。3つ目は、よりチャット機能を重視したタイプ。そして4つ目は、CRMやマーケティングオートメーションサービス(MAツール)の中でのWeb接客です。ここからは、これら4つの分野それぞれの代表的な製品をご紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
・ec-CONCIER(イーシーコンシェル)
日本を代表するIT企業のひとつ、NTTドコモとディープラーニングの最先端技術を持つ「PKSHA Technology」(パークシャテクノロジー)が共同開発したAIを搭載し、CVR改善の精度とスピードに特化したWeb 接客ツールとして人気を集めています。2018年5月時点で導入社は5,000社を超え、市場シェアはNo.1となっています。
・flipdesk(フリップデスク)
このサービスでは専用のタグを自社のサイトに埋め込むだけで訪問者の行動履歴を参照でき、よりパーソナライズされたWeb 接客が可能となります。まさにスマホ時代に最適化されたWeb 接客ツールとして、人気を集めています。提供元が通信大手のKDDIグループ企業なので、広告や検索と連動した総合的なソリューションが提供できることも強みです。この「flipdesk」は、2014年のリリース以来、800社1,100サイト以上での運用実績があります。
・KARAKURI chatbot(カラクリチャットボット)
カラクリ株式会社が提供する「KARAKURI chatbot」は、国内88あるチャットボットの中で、使いやすさNo.1に選ばれた管理画面のわかりやすさが特長のサービスです。サポートもNo.1に選ばれており、徹底サポートではじめての方でも安心してかんたんに運用できます。
そんなKARAKURI chatbot は、CRMとチャットボットの連携により顧客情報をリアルタイムに見られ、顧客対応時間の短縮に繋げられるのも特徴の一つです。また、FAQとの一元管理により、重複する内容の転記の手間や漏れが防げ、各ツールにかかる教育やコミュニケーションコストの削減も実現できます。
・ZenClerk(ゼンクラーク)
motion Intelligence株式会社が提供するZenClerk(ゼンクラーク)は、コンバージョン率を自動で改善するサービスとして2014年12月にサービス開始し、現在では導入実績が700社を超えるなど大きな注目を集めています。
独自の人工知能「Emotion I/O」が自社のサイトを訪問した人の行動データを元に感情の高まりを解析し、適切なタイミングでの販促を支援します。例えば、ネットショップで購入を迷っているユーザーを見極め、適切なタイミングでのクーポン提示する、といった接客を行うため、購入率の向上が期待できるのです。

Web接客ツールの市場が急成長する一方で、ここで紹介した以外にも数多くのサービスが登場しています。そのため、サービス提供側にとっては、価格競争に陥りやすいという厳しい状況も予想されます。その反面、Web接客ツールの導入する企業にとっては、自社の課題に合わせたサービスの選択肢が広がるメリットがあります。導入を検討する企業には、「多くのサービスの中からより適切なものを選ぶ選択眼」が必要となってくるでしょう。
今回は、Web接客の市場規模が拡大している理由や、分野ごとのおすすめWeb接客ツールなどをご紹介しました。今後も、需要とともにWeb接客の市場規模は拡大していくことが予想されています。
業務効率化や顧客満足度向上といったさまざまなメリットを得られることから、実際にWeb接客ツール導入を検討し始めている企業も少なくありません。オンラインショッピングやリモートワークが増加した現在だからこそ、新たな接客の手段としてWeb接客ツールの導入を検討してみてはいかがでしょうか。
業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。
メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。
AI製品・ソリューションの掲載を
希望される企業様はこちら