生成AI

最終更新日:2024/04/08
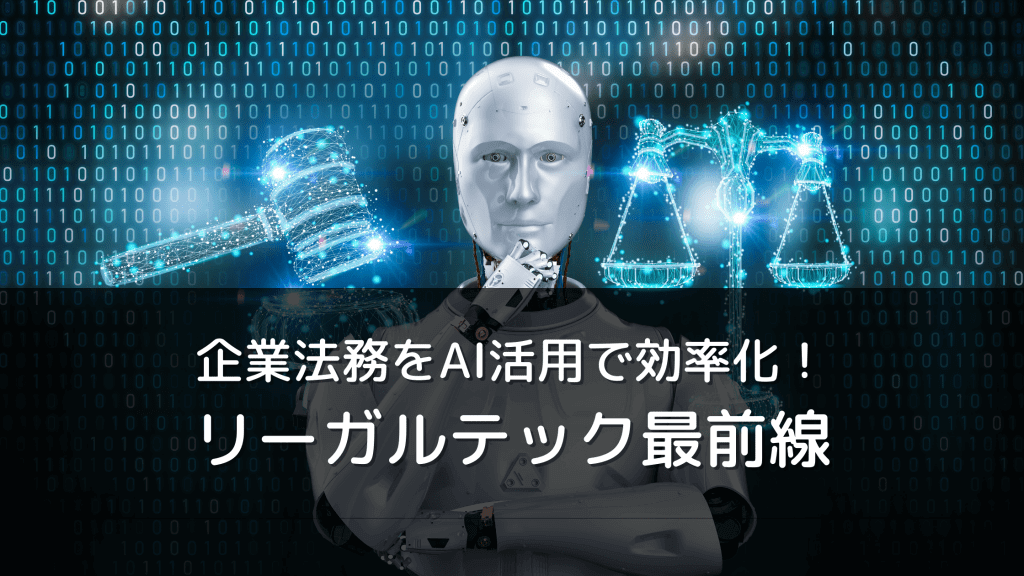 企業法務のAI活用事例を紹介
企業法務のAI活用事例を紹介
AI(人工知能)の技術は日々進歩を続けており、さまざまな業界で積極的にAIが導入され始めています。それは「法務」の分野も例外ではなく、AIの活用によって業務効率化(省人化)を実現するケースが増加しているのです。
しかし、AIの活用によって効率化が実現される一方で、「法務の仕事はAIに奪われてしまうのか?」といった不安の声も少なくありません。今後、AIの導入が加速することで、法務の仕事がAIに奪われてしまう可能性はあるのでしょうか。
今回は、リーガルテックの現在と将来の見通しについて詳しくご紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
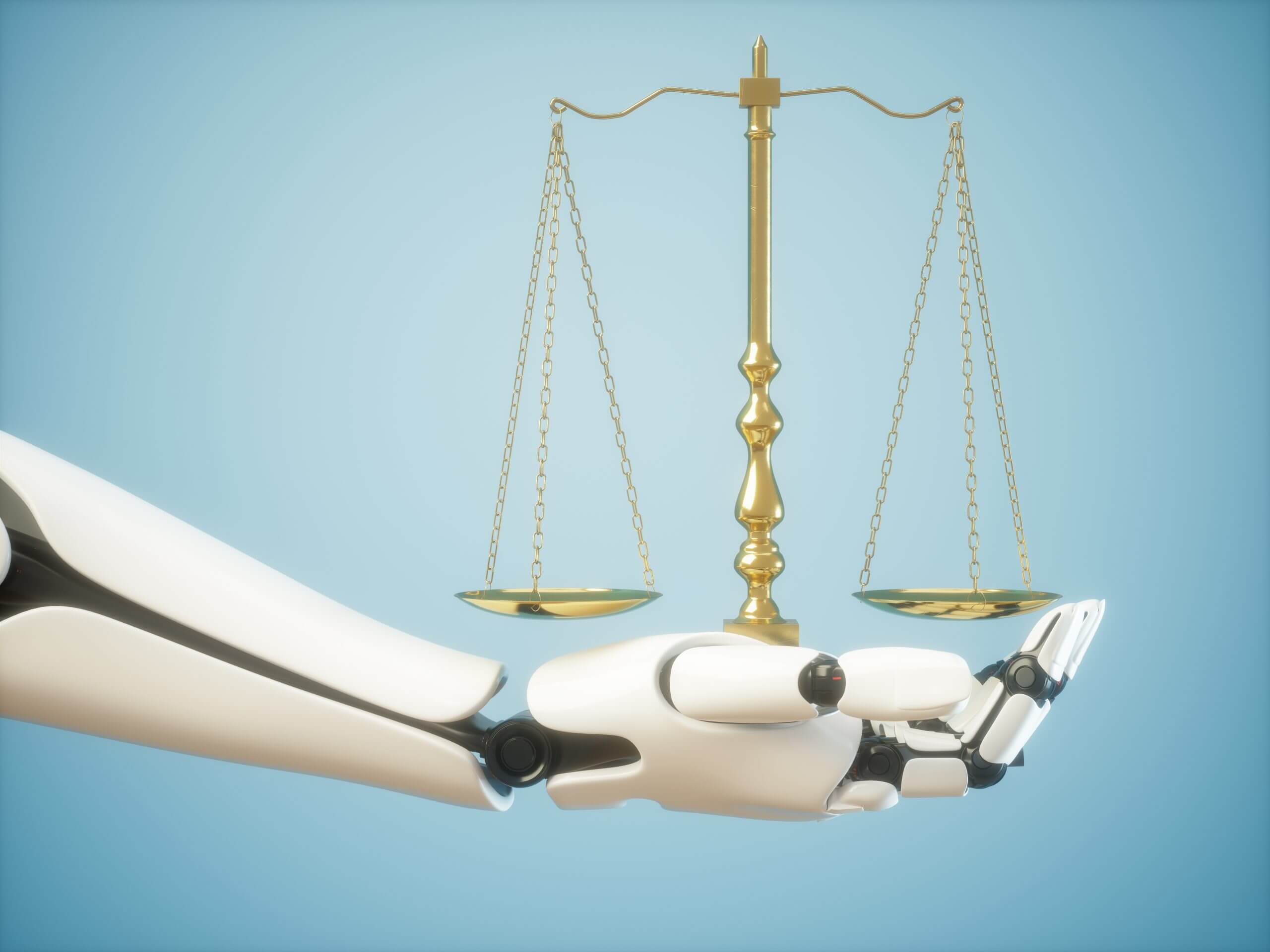
近年はAIの技術発展に伴い、さまざまな分野でのAI活用が進んでいる状況です。それは法務(法律)という分野においても言えることであり、最近では法務エキスパートシステムが「AI弁護士」という形で重要な役割を担っていくことも期待され始めています。
エキスパートシステムとは、特定の問題に対し、専門家のような受け答えをする機械のことです。人工知能の研究を通じて生まれたコンピューターシステムとして大きな期待が寄せられています。
エキスパートシステムは、システム内で専門家と同じ意思決定手順を模倣することができます。たとえば、「AであればB(IF-THENルール)」といった推論を通して、答えを導き出すわけです。この方法は、近年ECサイトで普及され始めている「レコメンドシステム」において導入されているものでもあり、私たちにとって身近な方法になり始めているのです。
エキスパートシステムの歴史は古く、1965年まで遡ります。エキスパートシステムの父と呼ばれている「エドワード・ファイゲンバウム氏」を中心に、「DENDRAL」というエキスパートシステムが作られたことで大きな注目を集めました。この「DENDRAL」は、未知の有機化合物を質量分析法によって分析し、有機化学の知識を用いて特定していくというもの。化学者の判断と問題解決の過程を自動化することができるのです。
また、「DENDRAL」から派生した「MYCIN」というエキスパートシステムでは、伝染性の血液疾患を診断し、抗生物質を推奨するようにデザインされていました。この「MYCIN」では診断精度65%を記録し、最近感染を専門としない医師よりは高い結果となったそうです。
ただ、「MYCIN」による誤診が起きた場合のリスクを鑑みて、実用化は見送られる結果となりました。その後もさまざまなエキスパートシステムが開発され、商用利用されるケースは増加していきましたが、現在に至るまで法律分野における「AI弁護士」は実現されていません。
その理由としては、法令のルール化が極めて難しいことが挙げられるでしょう。また、弁護士という職業には高いコミュニケーション能力も求められます。依頼者の相談を親身に聞いたり、相手の抱える悩み、問題を汲み取って行動に移したりする必要があるため、円滑なコミュニケーションが得意ではないAIによって弁護士の業務を完全自動化するのは難しいと言わざるを得ません。
そのため、AIが法曹三者の代わりになるような未来はまだまだ遠いと考えるべきでしょう。

それでは、弁護士の補佐的な仕事を行うパラリーガルの仕事は、AIによって奪われてしまう可能性があるのでしょうか。パラリーガルにもさまざまな業務があるため、一概にすべての仕事がAIに奪われてしまうとは言い切れません。ただし、パラリーガルの重要な業務である「過去の判例を調べる作業」に関しては、AIが非常に得意とする業務であることから、将来的にAIが担当していく可能性は十分に考えられるでしょう。
というのも、AIは過去のデータを蓄積し、分析・予測を行うことが非常に得意だからです。そのため、一度AIに過去のデータ(判例)を学習させれば、条件検索を行うだけで瞬時に過去の判例を提示することも可能になるのです。
ただし、過去の判例を調べる業務は、これまでの弁護士におけるキャリアパスでもあったため、優秀な弁護士を育てるという観点においては、今後も人間が担当すべき業務と考えることもできます。
そのため、AIによる完全自動化が難しい弁護士という職業の人材不足を防ぐという点では、うまくAIを活用しながら「効率化」と「人材育成」の両立を実現していくことが大切になるでしょう。
少子高齢化に伴う人手不足は深刻化しており、法務の分野においても業務効率化を目的としたAIが多く導入され始めています。ここからは、法律業務を支援するAIがどのような特徴を持ち、どのような役割を果たしているのか、詳しくみていきましょう。

契約書の作成・管理は、法律業務において重要な業務の一つです。これまで契約書の作成・管理は人の手で行われるのが一般的でしたが、担当者の知識、経験によってはミスが生じてしまうケースも少なくありません。
そのようなミスを最小限にして、より効率的に契約書の作成・管理を行うためのシステムとして、最近では「AI契約書レビュー支援サービス」や「AI契約管理システム」が積極的に導入され始めています。
AI契約書レビュー支援サービスとは、AIの活用によってリーガルチェックの効率化、自動化を図ることができるものです。契約書をアップロードすることによって、AIが自動で契約書のリーガルチェックを行ってくれるため、法務担当者がチェックを行う時間を大幅に削減することができます。
サービスごとにチェックできる項目は異なりますが、一般的には「リスクの有無(大小)」「トラブル例の表示」「リスクのある条項の有無」「不足条項の指摘」「修正例の提示」といったフィードバックを受けることができるため、より確実に契約書に潜むリスクを排除させることが可能です。
また、法務担当者など契約書レビューを行う人の省人化に加え、品質にばらつきが生じてしまいがちな契約書レビューの均一化を図ることができるのは大きなメリットといえるでしょう。
AI契約書管理システムは、契約書の管理を適切に行うための機能が搭載されたシステムのことです。具体的には「入力機能」「検索機能」「更新期限通知機能」などが搭載されています。
契約書は、締結した時点ですべての役割を終えるわけではありません。締結した後も、内容を見返したり、別の契約の参考にしたりするケースがあるため、いつでも確認や修正などが可能なように適切な方法で管理しておくことが大切になるのです。
AI契約書管理システムには、契約書をアップロードするだけで文章を自動読み取りしてくれる機能や、目的の契約書を検索することができる機能、契約期限が近づいた契約書を知らせてくれるアラート機能などが搭載されています。そのため、契約書業務のミスを減らしながら、さらなる効率化を実現することが可能です。
なお、以下の記事ではAIによって契約書業務を効率化する方法、流れについて詳しくご紹介していますので、ぜひこちらも併せてご覧ください。
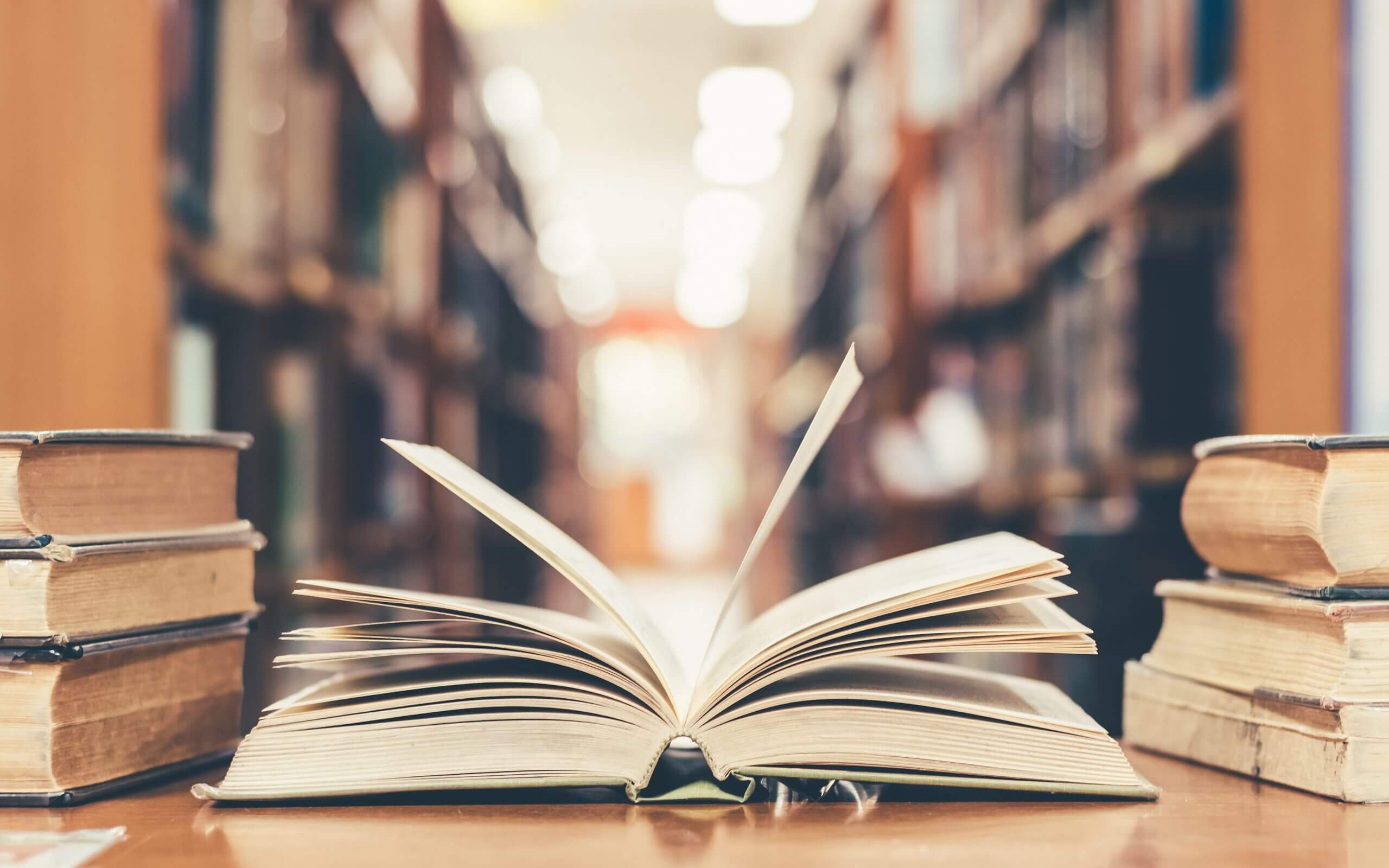
先ほどもご紹介したように、法律業務においては過去の判例を調べる作業を中心に、さまざまなリサーチ業務が発生します。そのリサーチをすべて人の手で行うのは決して簡単ではありません。多くの時間と労力を消費することになるため、いかに効率化を図れるかが重要なポイントになるのです。
その点、AIを活用すればスピーディーかつ正確にリサーチを行えるようになります。AIは、膨大なデータを蓄積することを得意としているため、扱う情報量が多くなればなるほどAIを活用するメリットも増加していくのです。
また、近年のデジタル技術の発展を踏まえると知財の取り扱いにも注意を払う必要があります。そのような中で、AIは知財関係のリサーチという点においても大きな役割を担っていくでしょう。
さらに現在はさまざまな企業がそれぞれ技術開発でしのぎを削っていますが、他社との連携を深めるため、データや技術の「オープン化」と「クローズ化」がカギになることも忘れてはなりません。従来であれば技術はすべて社外秘でクローズドとなっていたところのうち、情報連携を強めるために、ある程度の部分をオープン化する必要に駆られるようになるからです。
そのため、どこをクローズドにしてどこをオープンにするか、また、オープンにする部分について知財の取り扱いをしっかりとリサーチしていく必要があるでしょう。知財におけるトラブルを未然に防ぐためにも、AIを活用したリサーチは重要な役割を担っていくわけです。

今回は、法務におけるAI活用の現状についてご紹介しました。すでにさまざまな形でAIが活用され始めている一方で、AI弁護士のように完全な自動化を図ることはできていない状況であることがお分かりいただけたのではないでしょうか。
とはいえ、AIの活用によって大幅な業務効率化を実現できることは間違いありません。また、デジタル技術の活用が広がることによって、知財に関する考え方も改めていくことが大切になります。
AIの活用によって得られるメリットだけに目を向けるのではなく、発生し得るトラブル、リスクにも事前に目を向けることで、より効果的にAIを活用していくことが可能です。法務において、最大限AIを活用していくためにも、AIの強みと弱み、それぞれの理解を深めてみてはいかがでしょうか。
業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。
メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。
AI製品・ソリューションの掲載を
希望される企業様はこちら