生成AI

最終更新日:2024/04/05
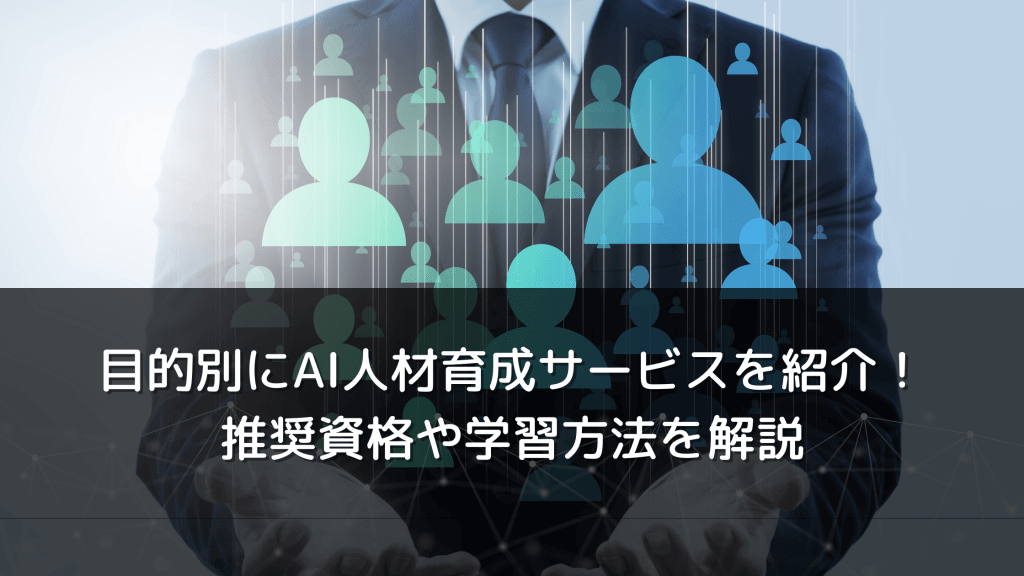 人材育成 おすすめAI資格と講座
人材育成 おすすめAI資格と講座
第三次AIブームの到来により、さまざまな分野で積極的にAIが活用され始めています。しかし、少子高齢化に伴う人手不足は深刻化している状況にあり、AIに関する専門知識を持つ人材を雇用することは難しい傾向にあるのです。
そのような状況を踏まえ、最近では「AI人材」を育成するためのサービスが多くなってきています。この「AI人材育成サービス」とは、一体どのようなものなのでしょうか。今回は、AI人材育成サービスの種類や学習方法などを詳しくご紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
AI人材について詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
年収3000万円!AI人材とは?IT人材不足に対する国と企業の取り組み
AI人材とは、AIに関する専門知識を持つ人材のことです。企業がAIの開発・活用を進めていくためには、目的に応じた最適なシステムを開発していく必要があります。そのシステム開発を行うための知識や、システムを適切な方法で活用していくための知識を求められるのがAI人材なのです。
この「AI人材」に関しては、以下の記事で詳しくご紹介していますので、併せてご覧ください。
年収3000万円!AI人材とは?IT人材不足に対する国と企業の取り組み
AI人材育成サービスの特徴としては、基礎知識はもちろんのこと、具体的な活用方法やビジネスへの応用方法なども含めて学べることが挙げられるでしょう。
AI人材を目指していく上で、AIの中核を担う技術ともいえる「機械学習」に関する知識は必要不可欠です。そのためAI人材育成サービスでは、機械学習を機能させるための「ニューラルネットワーク」、ニューラルネットワークを多層に構築していくためのアルゴリズムである「ディープラーニング」といった基礎知識を学んでいくことになります。
また、これらの基礎知識に加えて、機械学習に用いられるプログラミング言語の「Python」は、AIにデータを学習させる上で必要となる「統計」の知識なども欠かせないものです。これらを学習し、深く理解することによって、AIエンジニアとしてAIの特性を把握した上でシステム構築を行えるようになります。AIの活用によって収集したデータを解析し、製品(サービス)の課題や問題点を明らかにしていく「データサイエンティスト」としても活躍できるようになるのです。
さらに自社で提供する製品(サービス)の課題、問題点を題材にしながら実践的にAIの活用方法を学んでいくことができるケースもあります。AIの基礎知識を学ぶことができても、その知識を実際の業務に活用することができなければ意味がありません。
そのため、研修の中で「実際のビジネスにどう活かしていくか」という点をカバーしていくことで、よりAI人材としての価値を高めていくことが可能になるのです。
AI人材サービスには、さまざまな種類が存在します。そのため、目的に合うAI人材育成サービスを利用することが大切です。ここからは、具体的にどのようなAI人材育成サービスが存在するのか、その種類についてみていきましょう。

「1からAIに関する知識を養っていきたい」という場合には、AIリテラシーや知識の習得を行うことができる入門的なAI人材育成サービスが最適といえるでしょう。たとえば日本ディープラーニング協会では、AIやディープラーニングについてまず「知る」ための「AI For Everyone(すべての人のためのAIリテラシー講座)」という無料講座を開催しています。
オンラインでのビデオ講座形式となっており、無料聴講コースでは約5時間のビデオ講座を無料で受講することが可能です。ビデオ講座に加えて確認テストを受験することができるCoursera修了証付きコースを受講する場合には、49ドルの支払いが発生します。(修了証発行を希望する場合)
AIリテラシーについて学んだ上で、基礎的な「機械学習」「ディープラーニング」について理解したり、データ活用したりしたい場合には、プログラミング言語の「Python」やデータ分析に欠かせない「統計」なども学ぶことができるAI人材育成サービスが最適といえるでしょう。
これらを理解することによって、システムの企画立案を行ったり、構築を行ったりすることができるようになります。また、AIを活用したデータ解析を行い、事業の課題や問題点を抽出したり、改善案を出したりする「データサイエンティスト」として活躍したい人にとっても最適といえるでしょう。
AIに多く用いられるPythonなどのプログラミング言語を習得した上で、システムを具体的にプログラミング言語によって実現できるように進めていくAI人材育成サービスも存在します。自分で構築したAIモデルが実際の業務においても問題なく活用できるか、評価しながらAIの精度を高めていくスキルを養うことが可能です。
講義と実習を繰り返しながら、実際にプログラミングを体験できるため、効率的にAIの実装方法を習得したい人にとっては最適なサービスといえるでしょう。
より実践的にAIの活用方法を学んでいきたい場合には、AI実装だけでなくコンペ参加まで行えるAI人材育成サービスが最適といえるでしょう。研修の中で「実際のビジネスにどう適用させていくか」という部分まで体験できるため、ビジネスへの活用を目的としている人には特に価値のあるサービスといえるでしょう。
AIsmileyとSkillup AI、AI検定学習サービスカオスマップを公開
ITパスポートとは、ITに関する基礎知識について問う国家資格のことです。インターネットの普及に伴い、さまざまな業界においてITが積極的に活用され始めました。また、IT業界自体も進化を続けており、さまざまな製品(サービス)によって価値を生み出し続けているのです。
そんなIT社会において求められる「ITに関する基礎知識」を身につけていることの証明となるのが、ITパスポートです。ITパスポートの試験は、120分の試験時間で行われます。計100問が出題され、4つの選択肢から回答を選択する形になるため、記述式ではありません。
G検定とは、一般社団法人日本ディープラーニング協会(JDLA)が実施している資格試験です。ディープラーニングの基礎知識を有し、適切な活用方針を決定して、事業活用する能力や知識を有しているかを検定する資格試験です。出題範囲は人工知能の歴史から、機械学習の基礎・具体的な手法、基礎数学、ディープラーニングの手法・研究分野、倫理・時事問題と幅広く出題される試験となっています。
データサイエンティスト検定とは、データサイエンティストとして求められるスキル、知識についてまとめた「スキルチェックリスト・タスクリスト」に定められている素養が身についているかどうかを確認する資格試験のことです。一般社団法人データサイエンティスト協会によって行われています。
このデータサイエンティスト検定は、2021年9月に第1回目が実施された新しい検定なのですが、今後さらにデータ活用人材の需要が高まっていくことを踏まえると、受講者数もますます増加していく可能性が高いでしょう。
なお、デジタルリテラシー協議会の「Di-Lite」でも、「デジタルを使う人材」の全員が持つべきスキルを提案しています。こちらは「ITパスポート試験」「G 検定」「データサイエンティスト検定(DS検定)」の取得を推奨するなど、かなり具体的な内容になっています。スキル開発、再教育の施策を検討する際に役立てられるでしょう。

参考:デジタルリテラシー協議会
E資格とは、「ディープラーニングの理論について理解し、適切な手法によって実装できる能力・知識を有しているか」を認定する資格です。日本ディープラーニング協会(JDLA)が行っている試験であり、機械学習やディープラーニングに関する知識、実装技術などへの理解が問われます。
注意点としては、E資格には受験資格が設けられている点が挙げられるでしょう。E資格の受験資格を得るには、JDLAが定めた教育プログラムに認定された「E資格対策講座(認定講座)」の修了試験に合格しなければなりません。この修了試験に合格していないと、E資格の受験資格は得られないため注意しましょう。
統計検定とは、統計に関する知識と活用力を評価するための全国統一試験です。AI人材として活躍するためには、AIにデータを学習させる際に必要となる統計の知識が欠かせません。そのため、統計検定の資格を取得しておくことで、データサイエンティストとしても評価されやすくなります。文系出身者では学習する機会のない数学的データ解析法を身につけられることも大きなメリットといえるでしょう。
+DXとは、初めてDX推進を行うユーザーに対応するスキルレベルを明確化する認定資格です。IoT/AI/ビッグデータ等の技術やマーケットについての知識やスキルを可視化する検定を行う団体であるIoT検定制度委員会によって生まれました。
+DXの資格認定証は、Lustrust株式会社によるブロックチェーン証明SaaS「CloudCerts」にて発行されます。CloudCertsは「証明」をセキュアにデジタル化できる技術で実績をブロックチェーンに記録。一度書き込んだ情報を変更できない耐改ざん性に富むため、ペーパーレスの実現や環境面への配慮とサスティナビリティ(SDGs)の確保はもとより、個人の実績をブロックチェーンの技術で永続的かつセキュアに担保します。また、試験合格者には+DXロゴも進呈。SNSや名刺への貼り付けに使用することも可能です。
ちなみに、試験範囲や試験のレベルがわからないという方のために模擬試験も用意されています。本番の試験と同じ出題範囲・レベル・出題形式で模擬試験を無料で受験することが可能です。
基本情報技術者試験とは、システムエンジニアやプログラマーに求められる基本的な知識を体系的に学習できる資格のことです。IT関連の業界で働いている人や、これからIT関連の業界で働きたいと考えている人を対象とした試験といえるでしょう。というのも、基本情報技術者試の内容は、コンピュータやシステムの動作に関する基本的な内容から、データベース、ネットワーク、セキュリティといった基礎知識に加え、システム開発の流れや、そのプロセスの中で検討すべきポイントについてもしっかりと押さえることができるからです。
これらの知識やスキルは、IT関連の業界で活躍したいと考えている人にとって大きな価値があるといえるでしょう。
人工知能プロジェクトマネージャー試験とは、一般社団法人 新技術応用推進基盤が行っている日本初の本格的AIマネージャー職向けの資格試験です。AIのビジネス活用を推進するリーダー層に必要な知見やスキルを網羅的に問う資格となっています。
試験はCBT方式により開催され、申込み後、受験者の都合に合わせて自宅のパソコンで受験することが出来ます。ただし、受験申込みは月に1回に限定され、不合格等で再受験を申し込む場合は、翌月以降の申込み・再受験となります。
元々、2020年春から集合受験式での開催を予定していましたが、新型コロナウイルスの流行に伴う社会的な要請に応じ、1年延期のうえWEB試験型に改変し、2021年から開始されています。
回答の為に計算が必要なものがあるが、出題は択一式。出題範囲はいくつかの小分類に分かれており、小分類毎に制限時間が設定されます。制限時間内に回答の上、次の小分類に進む必要があり、すべての小分類で制限時間いっぱいまで使用した時間が、各分野に設定されている合計制限時間。すべての分野で制限時間いっぱいまで使用した場合、試験全体の合計時間は90分です。
AWS 認定とは、「Amazon Web Services」関わる専門知識、スキルを有していることを認定する資格のことです。近年はAWSのクラウドサービスを利用してサービスの開発を行う企業が多くなりました。そのため、AWSクラウドサービスの運用・保守を行うことができる人材の価値も高まってきている状況なのです。
こういった背景もあるため、AWS 認定資格を持つことによって「AWSの専門家」としてさまざまな場所で活躍できるようになる可能性が高まります。就職、転職活動においても有利に働く可能性があるでしょう。
Google Cloud 認定資格とは、Google Cloudに関する知識やスキルについて問う公式の認定試験のことです。この認定試験は、分野ごとにいくつかの資格試験に分かれています。そのため、クラウド分野の専門知識や、サービスの設計・実装・管理に求められるスキルなど、分野ごとに求められるものが異なります。
Google Cloud 認定資格を取得することによって、それぞれの分野における専門知識や開発スキル、管理スキル、運用スキルなどを有していることが証明できるというわけです。
Azure 認定資格とは、Azureの専門知識をマイクロソフトが認定する資格のことです。Azureには「基礎」「管理者」「開発者」「DevOpsエンジニア」「アーキテクト」という5つの分野、そして「Fundamentals」「Associate」「Speciality」「Expert」のカテゴリが存在します。また、2つの試験に合格しなければならない認定資格も存在します。
さまざまな難易度の認定資格が存在するため、自身の知識に応じて最適な資格を取得していくのが良いでしょう。Azure 認定資格を取得することで、社内外からの信頼が高まるのはもちろん、自身のスキル・知識を証明するための材料にもなるため、今後AI人材として活躍していきたい人には大きな価値がある認定資格といえます。
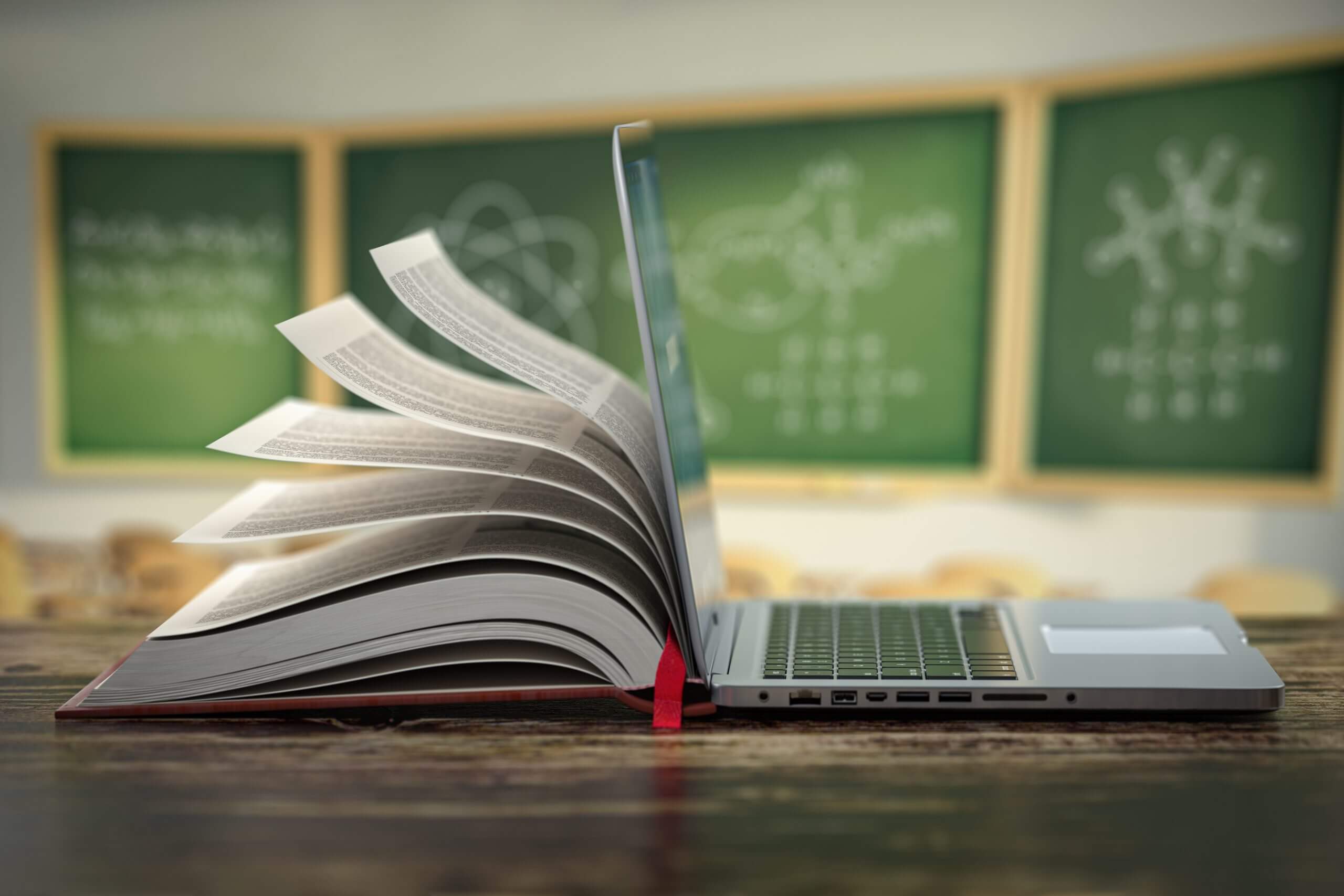
スキルアップAIが発売している『AIジェネラリスト基礎講座』と『徹底攻略ディープラーニングG検定ジェネラリスト問題集』は、G検定のシラバスが今春改訂されたことに伴い、2021年にリニューアルされました。AIと個人情報、知財、自動運転に伴う道路交通法との関係など、人工知能をめぐる法律や契約に関する内容を取り込み、事例とともにわかりやすく解説されています。
また、最近のG検定の出題傾向をふまえ、XAI、DX、自然言語処理、音声認識、強化学習などの最新技術に関する設問を追加。問題集には模擬試験「総仕上げ問題」も収録し、万全の体制で試験に臨むことができます。
なお、『AIジェネラリスト基礎講座』は無料のトライアル版として一部の動画が視聴できます。まずはトライアル版でスキルアップAIの講座の雰囲気やわかり易さを体験してみてはいかがでしょうか。
書籍で学習を行うのが難しい場合には、Eラーニングで学習するのも一つの手段です。最近では、オンラインで研修が行われるAI人材育成サービスも多くなってきています。新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、テレワークが多く普及され始めていることもあり、オンラインで学習できる環境が整うのは非常に大きなメリットといえるでしょう。
また、場所だけでなく時間やデバイスを選ばずに受講できるというポイントも、大きなメリットの一つといえます。ただ、Eラーニングの中にも、動画視聴で学習していく自習型、リアルタイムで講師とコミュニケーションが取れる講義型など、さまざまなスタイルがあるため、より最適なスタイルを選択することも重要になるでしょう。
AI人材育成サービスの中には、対面形式で研修が行われるサービスもあります。ハンズオン研修の大きな魅力は、実際にコミュニケーションを図りながら情報共有を行ったり、ディスカッションを行ったりすることができる点です。
受講者同士の刺激によって学習効果を高められるという点は、対面型研修ならではの魅力といえるでしょう。受講者同士が競い合うコンペティションを開催しているAI人材育成サービスもあるため、高いモチベーションでAIに関する知識、スキルを養っていきたい人には最適な手段といえます。
AI人材が集うコミュニティに参加することも一つの手段となりますが、代表例としては、エクサウィザーズが運営している「exaBase コミュニティ」が挙げられるでしょう。このコミュニティは、AI・DXで成果を創出する国内最大級のプラットフォームとして位置付けされ、国内時価総額トップ100社の半数以上を含んだ500社以上の企業にソリューションなどを提供しています。
AIアルゴリズムやソフトウェアなど、エクサウィザーズが保有している100以上の技術アセットを搭載したプラットフォームとなっており、AIアプリケーションの共同開発や社内システムへのAI実装など通じて、事業インパクトを創出しているのが特徴です。
また、JDLA(一般社団法人日本ディープラーニング協会)が実施するG検定・E資格に合格した人だけが参加できるAIコミュニティ「CDLE」も、5万人を超える人に利用されている大規模なものです。「CDLE」では、ディープラーニングの社会実装の日本代表として、社会を発展させるエバンジェリストたちが集まっています。そういった優秀な人材たちのなかで学び合い、アウトプットできる環境となっているのが大きな魅力です。
現在は、無料のAI人材育成プログラムも数多く存在しています。それぞれに異なる特徴があるため、プログラムごとの強みを把握した上で参加を検討していくことが大切です。ここからは、無料のAI人材育成プログラムを4つご紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
「マナビDX(デラックス)」は、社会人の必須スキルと言っても過言ではないデジタルスキルに関する情報を掲載しているポータルサイトです。これまでデジタルスキルを学ぶ機会が無かった人であっても新しく学んでいくことができるように、デジタルスキルに関するさまざまな学習コンテンツが掲載されています。
「新しい知識・スキルを習得したいけど、何をどのように学べば良いのか分からない」という人に向けて、経済産業省で策定した統一基準(DXリテラシー標準)が掲載されているのも特徴です。ちなみに、マナビDXはもともとAI Questという名称で運営されていましたが、2022年に名称変更とともにリニューアルされています。
日本ディープラーニング協会では、AIやディープラーニングについてまず「知る」ための「AI For Everyone(すべての人のためのAIリテラシー講座)」という無料講座を開催しています。
オンラインでのビデオ講座形式となっており、無料聴講コースでは約5時間のビデオ講座を無料で受講することが可能です。ビデオ講座に加えて確認テストを受験することができるCoursera修了証付きコースを受講する場合には、49ドルの支払いが発生します。(修了証発行を希望する場合)
スキルアップAIキャンプは、JDLA認定プログラム1号のスキルアップAI株式会社が主催している勉強会です。G検定・E資格の取得はもちろんのこと、実務でのAI活用に必要となるさまざまな実践的テーマを取り上げ、AI人材としての知識・スキルを磨いていきます。
データ拡張や特徴量エンジニアリングといったデータ分析・AI開発で多くみられるキーワードを掘り下げるテーマで勉強会をしたり、人間参加型機械学習、MLOps、説明可能なAIといった今後の活用が期待される最先端技術をテーマに勉強会をしたりと、データ分析・AI開発の実務力アップにつながるヒントを多く得られる機会が提供されています。
Aidemy Freeは、無料で始められるオンライン形式のAIプログラミング学習サービスです。機械学習やデータ分析などの知識を持っていない人でも、基礎から学習できるカリキュラムが整っています。そのため、プログラミング未経験の人でも安心です。
Aidemy Freeの特徴としては、テキストを主とするコンテンツをメインでラインナップしているものの、動画やイラストも要所で使われているため分かりやすい点が挙げられるでしょう。文字だけだとなかなか頭に入らないという人でも、Aidemyであればスムーズに学習を進められます。
現在は、企業向けのAI人材育成研修サービスも数多く存在します。ここからは、おすすめのAI人材育成研修サービスを7つご紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
株式会社エクサウィザーズが提供する「DXアセスメント&ラーニング」は、3ヶ月でDX人材を育てるAI人材育成研修サービスです。DX人材のスキル診断・マインド醸成・育成を1つで行えます。
独自開発のデジタルイノベーターアセスメント(DIA)によってデジタルイノベーターに必要なスキル×素養をWeb上で診断し、DX人材・組織の現状を可視化することが可能です。そのため、育成の効果検証や今後の育成方針の検討に役立ちます。
また、継続した学習のためには欠かせないマインド醸成に関しても、DXの興味関心を醸成する”ワクワクするコンテンツ”によって、マインド・モチベーションを醸成し、eラーニングにより自発的で継続的な学習をサポートします。
ブレインズコンサルティング株式会社が提供する「データサイエンス・AI教育マネジメント支援」は、企業状況に合わせ、データ分析・AIの教育の計画策定から教育推進までの支援を受けられるサービスです。
「教育計画策定」では、企業もしくは特定部門での目標設定からカリキュラム計画の作成を行います。「教育推進支援」では、教育計画の遂行における推進室の運営、目標達成状況に合わせた提言、課題対策などを行います。オーダーメイドのサービスだからこそのスピード感で、教育を進めていくことができるのは大きな魅力といえるでしょう。
ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社が提供する「Prediction One」は、ソニー社内のAI教育にも用いられるAI予測分析ツールです。機械学習やプログラミングなどの専門知識がなくても数クリックの簡単な操作で予測分析が実現できます。
勘や経験に頼りがちだった業務をAIで行い、業務効率化や属人化解消のサポートをします。予測分析による顧客行動や需要などの予測結果は、ビジネスアクションにつながりやすいため、高い費用対効果を実現できるでしょう。
SAS Institute Japan株式会社が提供している「SASスターターパック」は、今すぐ始められるオールインワン・データ分析基盤の決定版です。ソフトウェア、クラウド環境、トレーニングをオールインワンで提供してもらえるため、クイックに運用開始することができます。
ホスティングサービスはもちろん、充実した教育プログラムによるAI人材育成も可能です。ユーザーが必要なのは業務知識のみ。知りたい項目をツールに教えるだけでAI技術を使用した高度な分析を、ツールが裏で自動的に実行します。
ソフトバンク株式会社が提供する「Axross Recipe」は、エンジニアの教育と実務のスキル格差に着目し、現役エンジニアによる実践的なプログラミング教材を提供する技術ブログとE-Learningを掛け合わせた人材開発サービスです。 AI・機械学習テーマで、様々な業務領域で活用できる教材を揃えています。
従来型の企業研修や書籍等での体系的な学習の課題として、一律で基礎知識を習得できますが、実務への応用力が課題でした。Axross Recipeでは、現役エンジニアの知識・ノウハウが教材化されています。繰り返し演習することで、業務で活かせる知識を習得できます。
株式会社SIGNATEが提供する「SIGNATE Cloud」は、スキルアセスメント・オンライン学習講座・社内コンペティションを通じて、社員のデータ活用リテラシー向上とデータ活用カルチャー醸成を実現できるサービスです。
組織のDX推進は、社員のデータ活用リテラシー向上とデータ活用カルチャーの醸成を両輪で進めていく必要があります。
そこで「SIGNATE Cloud」は、社員のデータ活用スキルを客観的に測定する「スキルアセスメント」、スキルの強みを伸ばして弱みを補強する「オンライン学習」、全社的にデータ活用カルチャーを醸成しながら優秀人材の発掘・育成にも寄与する「コンペティション」の3つの機能を提供することで、計測→立案→実行サイクルを回すことができる仕組みを確立しています。
スキルアセスメント・オンライン学習・コンペティションの3つの機能を通して、組織内のデータ人材育成サイクルを回し、組織のDX加速を実現していく唯一無二のサービスといえるでしょう。
株式会社ABEJAが提供する「DX人材育成支援」は、300社以上のDXを支援した実績を持つABEJAが企業のDX化を「人材育成」の側面からサポートしていくサービスです。ABEJAのノウハウを駆使した知識研修、ワークショップをもって、DX関連のプランニングとPJT推進を担う「DX企画人材」を育成します。この他に、今あるDXプロジェクトにABEJAがアドバイザーとして参加し、実践の場でのOJTを通じてキーパーソンを育成するサービスを提供していることも大きな特徴の一つです。
また、ABEJAのノウハウを用いた研修とワークショップによって、ヘッド組織や事業部門の部課長および企画者を、DX企画人材へと育成していくこともできます。集合研修サービスではLMSやAI開発/データ分析プラットフォームを用い、AI企画研修、データ活用研修、PdM育成研修などのカリキュラムを実施。事前事後でDXスコア計測テストを実施することで、受講者のスキルを可視化し、レポートとして提出します。

今回は、AI人材育成サービスの資格内容や学習方法などを詳しくご紹介しました。現在はさまざまな資格、サービスが存在するため、自分の目的に合った資格やサービスを選択することが大切になります。
自身の強みを証明できる資格を取得することで、社内外での評価が高まりやすくなったり、より信頼関係を深めやすくなったりする可能性も十分に考えられますので、ぜひこの機会にAI人材育成サービスの利用を検討してみてはいかがでしょうか。AIsmileyではAI人材育成の進め方や他社動向、サービス比較などについて無料で相談を受け付けています。無料の事例集やカオスマップもございますのでお気軽にお問い合わせください。
AIについて詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
AI・人工知能とは?定義・歴史・種類・仕組みから事例まで徹底解説
業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。
メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。
AI製品・ソリューションの掲載を
希望される企業様はこちら