生成AI

最終更新日:2024/02/14
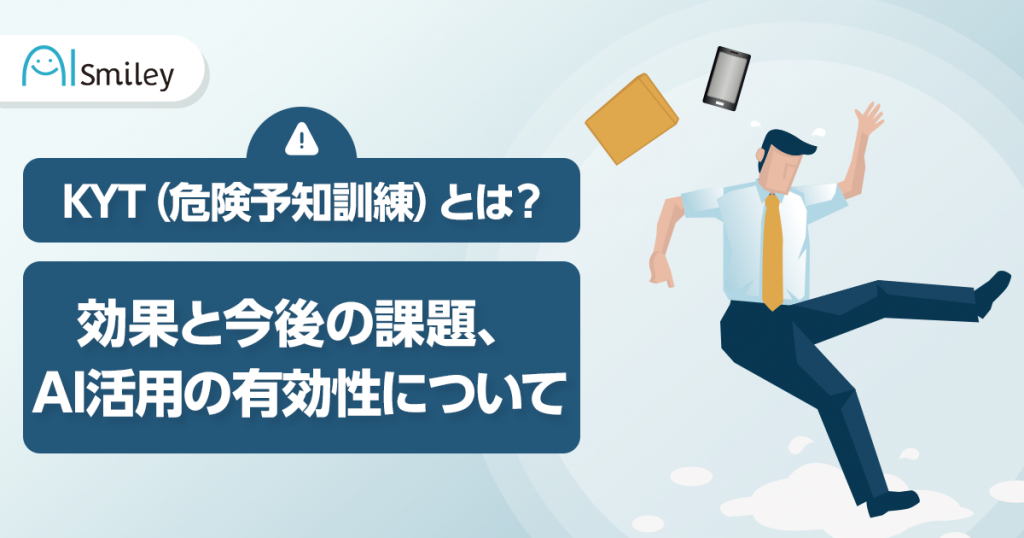 KYT(危険予知訓練)とは?効果と今後の課題、AI活用の有効性について
KYT(危険予知訓練)とは?効果と今後の課題、AI活用の有効性について
現場や作業に潜む危険を明らかにし、防止するための対策を組織内で話し合う「KYT(危険予知訓練)」は、作業員の安全への意識を高めて、労災事故を削減するために有効な手法です。安全を先取りできる職場風土を醸成するために、積極的に取り入れることをおすすめします。
近年では、安全な労働環境を実現するためにAIソリューションの導入も活発化しています。本記事では、KYT(危険予知訓練)の概要や具体的な効果に加え、今後の課題とAI活用の有効性について解説します。
予知保全について詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
予知保全とは?予防保全との違いやメリットとおすすめサービスを紹介

KYT(危険予知訓練)とは、現場環境や作業手順の中に隠れている危険と、その危険によって起こり得るリスクを事前に洗い出し、組織内で事前に対策を行うための訓練のことです。
KYTは、「危険(Kiken)」「予知(Yochi)」「トレーニング(Training)」の3つの単語から頭文字を取って名付けられました。
KYTは通常、「イラストシート」と呼ばれる現場環境や作業状況を具体的に示した道具を使用し、危険が起こり得る状況を明示しながら組織内で議論を交わします。危険なポイントについて組織内で認識を擦り合わせ、作業前に重点確認項目を唱和をしたり、作業時に指さし確認を行ったり、実際に危険に見舞われる前に回避することを目的としています。
ゼロ災運動とは、現場作業に関わる全員が参加して安全を確保し、「ゼロ災害」と「ゼロ疾病」を目指すための運動のことです。中央労働災害防止協会においては、ゼロ災運動の考え方を下記のように説明しています。
ゼロ災運動は、人間尊重の理念に基づき、全員参加で安全衛生を先取りし、一切の労働災害を許さずゼロ災害、ゼロ疾病を究極の目標に働く人々全員が、それぞれの立場、持ち場で労働災害防止活動に参加し、問題を解決するいきいきとした職場風土づくりをめざす運動です。しかしそのためには、自主活動の活発な展開が必要となります。
引用元:「ゼロ災運動・KY(危険予知)」|中央労働災害防止協会
ゼロ災運動では、「ゼロの原則」「先取りの原則」「参加の原則」の3つの原則を軸に、現場に潜むさまざまな危険を防止し、被災者を生まないための取り組みを掲げています。「死亡災害や休業災害が起こらなければそれで良い」というものではなく、現場に隠れたあらゆる危険を洗い出し、根本的に解決することが目的です。
前述のKYTはゼロ災運動の一環として行われる取り組みのひとつであり、危険をあらかじめ予知した上で防止することによって、災害や疾病をゼロに近づけます。

KYTを実施することで、現場における安全確認の標準化や、作業員の意識向上を促すなどの効果が期待できます。日頃の意識づけによって危険な労働災害が起こるリスクを軽減できるため、組織全体が団結してKYTの意義を理解し、積極的に実施することが大切です。
また、KYTの実施には、熟練者やプロの知見を行動目標として顕在化する目的もあります。ここでは、KYTを実施すべき3つの理由と目的を解説します。
KYTを実施する際は、現場や作業手順における危険ポイントを作業員同士が持ち寄って、具体的な内容について話し合いを行い、解決に導きます。
話し合いの中で「具体的にどの部分が危険なのか」「危険を解決するためにはどのように行動すれば良いのか」を詳しく協議することで、作業員一人ひとりが危険ポイントを明確に意識することで、潜在意識に訴え、安全確認を標準化する効果が期待できます。
また、危険を認識して作業前や作業時に指さし確認を行うと、作業に対する集中力が高まると同時に、KYTで確認した危険をあらためて意識するようになります。KYTを実施することは、作業員に日頃から安全を意識させる習慣づけを行うために重要です。
人間は「習慣」によって行動する性質があり、ある程度の行動を無意識に判断しています。全ての作業を「これから〇〇という行動を取ろう」と意識して行うことは多くなく、これまでの経験から次の行動を無意識に判断し、自然と身体を動かす場面が多々あります。
そのため、KYTを行って潜在意識に危険回避のための行動を叩きこみ、無意識であっても安全な作業を行えるような習慣作りが非常に大切です。
潜在意識下で危険を理解しないまま行動すると、自身が危険な行動を取っていると理解しないまま、習慣的に危険な作業を行ってしまう可能性があります。「どのような行動が危険なのか」をKYTによって理解し、身の回りの危険を常に意識して作業を行う体制を整えることが求められます。
KYTは熟練者・プロの知見を行動目標として顕在化する役割も担っています。人間の行動は、一度習慣化されると簡単に是正されることはありません。例え誤った行動であっても、本人がその行動を正しいものだと信じ込んでしまえば、無意識に誤った行動を取り続けてしまいます。
そのため、KYTによって熟練者やプロの知見を現場の作業員に明確な形で示し、「どのような行動が正しいのか」を顕在化して、他の作業員に意識させることが重要です。
KYTによって協議される危険ポイントは、熟練者やプロの知見が集められた、正確性の高いものです。KYTの場で示された危険を作業員一人ひとりが徹底的に潜在意識に覚え込ませることで、作業の安全性を向上できます。

KYTの実施には、感受性を鋭くしたり、集中力を高めたり、問題解決能力を向上させたりする効果があります。
KYTを通して自身が働く現場の危険要因を理解し、意識的に危険を回避する行動を取るようにすることで、感受性が研ぎ澄まされ、集中して作業に取り組めます。また、現場や作業に潜む危険をどのように回避・防止できるのかを積極的に考えることで、問題解決能力の向上が見込めるでしょう。
さらに、KYTには実践への意欲を高めたり、安全を先取りする職場風土づくりを促進したりする効果も期待できます。
KYTによって現場や作業の問題点が明らかになり、解決方法を探る中で、「実際に危険防止・回避のための行動を実行してみよう」という意識が生まれやすくなります。組織全体で団結し、行動に移すことで、一体感を持って安全を実現するための行動に取り組むことが可能です。
KYTによって安全への意識づけを行い、一人ひとりが高い自覚を持って作業に向き合えれば、危険を回避するための行動を事前に取るようになり、安全を先取りする職場風土を醸成できます。

KYTの習熟度を測る指標として、中央労働災害防止協会が公開しているピラミッドがあります。
KYTが最終的に目指す着地点は、「安全を先取りし、組織の作業員が参加的で明るく、ゼロ災を実現する職場風土」の醸成です。そのためには、ピラミッドの最上段にある「指差し呼称」の定着から、順番に一つひとつのKYT習熟度を高め、現場に定着させていく必要があります。
現場の危険をいち早く予知・予測して、危険回避・防止する行動を取るための感受性を育てるには、作業員一人ひとりが自主的に問題解決に取り組む姿勢を促すことが重要です。
KYTを通して作業員同士が本音で話し合い、「指差し呼称の定着」→「危険予知」→「ルールの浸透」→「マナー・エチケットの定着」→「職場風土の醸成」→「企業体質の改善」を実現するための取り組みが求められます。

KYTを進めるにあたって、「KYT基礎4R法」という考え方が参考になります。KYT基礎4R法では、組織内で話し合いを行う際に、イラストシートを活用して危険の発見や把握、問題解決を進めていきます。
KYT基礎4R法を通して訓練を繰り返し、個々の作業員の感受性を育てることで、作業時の集中力を高めると同時に、問題解決能力や実践意欲の向上を図れます。ここでは、KYT基礎4R法について詳しく解説します。
ラウンド1で行うのは「現状把握」です。現場の作業状況が描かれたイラストシートを参照しながら、「イラストシート内の状況にはどのような危険が潜んでいるか」をKYTの参加者全員で話し合います。イラストシートを参照しながら、考え得る危険を次々と列挙していきましょう。
ある作業員が脚立を使って窓拭きを行っている図を例に取ると、考え得る危険としては「脚立から飛び降りて足をひねる」「離れた場所の窓を無理に拭こうとして、脚立から落ちる」などの危険が挙げられるでしょう。他にも、下記のような危険が考えられます。
組織全体で話し合うことで、一人だけでは思いつかなかったような危険が隠されていることに気がつく可能性もあります。ラウンド1の段階では「何が正しいのか」ではなく、考えられる危険を思いつくままに挙げていきましょう。
ラウンド2においては、ラウンド1で列挙した危険の中から「本質はどれなのか」を追及します。ラウンド1で明らかになった危険を参照しながら、重要であると考えられる危険に〇印を付けていきましょう。
重要と思われる危険に〇印を付けられたら、その中からさらに絞り込みを進めて、「危険の本質と捉えられるものはどれか(危険ポイントはどれか)」を明らかにし、◎印を付けます。絞り込みが完了し、危険ポイントを確定できたら、そのポイントをKYTの参加者全員で指差し唱和しましょう。
前述の脚立の例を挙げると、〇印は下記の項目に付けることが考えられます。
〇脚立から飛び降りて足をひねる
〇離れた場所の窓を無理に拭こうとして、脚立から落ちる
〇脚立から下りるときに、窓の拭き具合を確認しながら後ずさったため、バケツに足を引っかける
全員で危険ポイントを唱和することで、「作業において何が危険なのか」を潜在意識に落とし込み、意識づけを促す効果が期待できます。
3ラウンドにおいては、2ラウンドで絞り込んだ内容について「危険のポイントを解決するための方法」を話し合います。KYTの参加者全員で促しあって、どのような解決策があるのか意見を募りましょう。
前述の脚立の例で「離れた場所の窓を無理に拭こうとして、脚立から落ちる」の項目が◎印に設定されたとすると、下記のような解決策が考えられます。
具体的に実施する対策を確定するのは次項のラウンド4となるため、ラウンド3においては、ラウンド1と同様に意見の正誤を気にせず、思いついた意見を次々と列挙していきましょう。積極的に自分の意見を発信することで、より良いアイディアが浮かんでくることも少なくありません。
どのような対策を実施すれば危険を回避・防止できるのかを考えることで、問題解決能力も高まります。
ラウンド4では、ラウンド3で上げられた意見を取りまとめて、実際にどの対策を実施するのかを決めていきます。挙げられたアイディアの中から危険防止効果が期待できそうなものはどれなのかを絞り込んで、採用する対策案に※印を付け、アンダーラインを引きましょう。
※印を付けた対策案は「重点実施項目」として、実際に現場で取り入れて実施することが重要です。重点実施項目を決定できたら、その項目を「チーム行動目標」に具体化して落とし込む必要があります。
チーム行動目標を具体化した後は、その目標を指差し唱和することで、あらためて作業員全員に対する意識づけを行います。設定したチーム行動目標は作業時に早速取り入れて、一人ひとりが高い意識を持って実践しましょう。
ここまでの全てのラウンドを終えたら、「タッチアンドコール」でKYTを締め括ります。代表的な掛け声には、「ゼロ災で行こう、ヨシ!」などがあります。
KYTに活用できるイラストシートの例として、前述のラウンド解説の際に使用した「脚立作業」や、チェーンソーで枝を切る様子を表した「伐採作業」などが挙げられます。
「脚立(三本足)で作業している状況」や、「チェーンソーで枝を切っている状況」をイラストで参照しながら、KYTを実施できます。
他にも、KYTに使えるイラストシートにはさまざまなものがあります。活用したい方は、こちらからダウンロードが可能です。

KYTには作業員の意識向上を促し、問題解決能力を育んだり、職場風土の改善を図ったりすることが可能です。日頃から危険に対する意識づけを行うことで、より安全な作業環境の醸成につながります。
しかし、KYTには限界もあり、全ての労災事故をゼロにすることは難しい点や、安全対策の省力化を図る必要に迫られている点は、今後の課題といえるでしょう。ここでは、KYTが抱えている2つの課題について詳しく解説します。
KYTを実施し、そこで設定した行動目標を習慣化できたとしても、労災事故をゼロにすることは難しいと考えられます。
KYTの実施には労災事故を減らす効果が期待できる一方で、新たな作業員を採用したり、熟練者が退職などの理由で現場を離れたりすると、KYTの実施が停滞するケースもあるでしょう。これまで使用していなかった機材やツールを導入し、新たな危険が生じる可能性もあります。
人間が作業を行う以上は、KYTを実施しても、労災事故を完全にゼロにできない事実は押さえておくことが大切です。本格的にゼロ災害を目指すのであれば、人間の作業を減らして機械に作業を代替させる「画像認識AIソリューション」などのサービスを利用することも選択肢のひとつです。
近年では、少子高齢化や働き方改革による労働時間の短縮に伴って、人手不足が深刻化しています。今後はさらに労働人口が減少していくと予測される状況において、人間の労働力に依存した現場作業を続けるよりも、システムやツールを導入し、安全対策そのものを省力化する方向に舵を切る対策が効果的です。
KYTを通じて現場の安全対策を強化しても、管理者の目が届かない場所で作業を行わなければならない場面は多々あります。このような場面で事前に危険を予知することは難しく、ヒューマンエラーによって深刻な労働災害が起こる可能性は高まるでしょう。
管理者が感知しにくい場所で作業を行う場合に、機械やAIソリューションを活用して危険予知の一部を担うような仕組みを構築できれば、現場作業の安全対策を省力化しつつ、安全対策をさらに強化できます。

画像認識AIソリューションを活用した安全対策事例として、高所の建築現場における安全帯の装着チェックと、印刷ラインにおける危険領域侵入警告の2つの事例を紹介します。尚、2つの事例は下記のインタビュー記事から抜粋していますので、興味をお持ちの方はこちらもぜひご覧ください。
建設業においては、高所の建築現場における安全帯の装着チェックの事例が挙げられます。
AIの導入前は、装着チェックのために人員を増員したいという課題を抱えていました。そこでAI画像認識ソリューションを導入し、作業員が高所作業の際に安全帯を装着していない状態を早期発見するとともに、安全帯が正しく装着されていることを判断する業務を自動化しました。
画像認識AIソリューションの導入によって、人の手に頼らず、AIが作業員の安全状況を判断できるようになり、精度の向上も期待できます。事故を未然に防止したり、安全帯の装着チェックを行うために増加した人件費の削減を見込んでいます。
製造業においては、印刷ラインにおける危険領域侵入警告の事例があります。印刷を行う現場では、回転体の通過前に印刷物に付着しているごみやホコリなどを取り除かなければなりません。この作業を行う際に、機械が停止していなければ、回転体に触れたタイミングで重大な事故が発生するおそれがありました。
そこで、機械が停止しているかどうかを事前に検知するために、深度を計測可能なカメラを取り付け、回転体の近くに手が近づくとアラートを通知するAIモデルを導入しました。
これにより、機械が停止していないために重大な事故が起こる可能性を事前に知らせることが可能になります。現段階では危険を検知してアラートを発するのみの機能を実装していますが、将来的には危険を検知した段階で機械を自動停止する機能を実装したい考えです。

ここからは、危険予知・安全対策AIソリューションのおすすめ5選を紹介します。AIソリューションはさまざまな場面で活用が可能で、業種・業態を問わず多くの現場に導入されていますので、これから活用を検討されている方はぜひ参考にしてください。
SOLIZE株式会社が提供する「SpectA KY-Tool」は、建設業・エンジニアリング業の労働災害ゼロ達成を目的とした危険予知支援ツールです。現場で実施を予定している作業について、過去に起こった災害事例をAIが自動的に抽出し、予測できる危険を現場内で共有できます。
日々の安全ミーティングが形骸化している現場において、作業員が危険を「自分ごと」として捉えられるようになり、予測された危険の内容に合わせた柔軟な対応が可能になります。また、担当者によってリスク評価にばらつきが出る問題を解消したり、人の手でリスク分析を行う手間の軽減を図ったりする効果も期待できます。
作業情報の入力時に関連する災害事例を自動表示するため、作業員自身が思いつかなかった気付きを促す効果も期待できます。過去に蓄積された情報をもとに、AIが危険を抽出・レコメンドするため、熟練者やプロの知見に頼らず、精度の高い安全指示が可能になる点もメリットです。
エクシオグループ株式会社が提供する「安全品質AIソリューション」は、作業員が撮影した現場写真をもとに、画像認識AIが自動的に送信された写真を分析し、安全確保が行われているかどうかを判断するAIソリューションです。
従来のオペレーションでは、作業員が撮影した現場写真から安全確保が行われているかを判断するまでのプロセスにタイムラグが起こりやすいというデメリットがありました。これは、管理者が送信された写真をチェックし、危険を指示してから対策を行うまでに長い時間がかかるためです。
安全品質AIソリューションを導入することで、人間の判断を挟むことなく、送信された写真をその場で分析・判断できるため、安全確保とチェックにかかる時間を大幅に短縮できます。また、検査員の稼働工数削減や、熟練者・プロの知見を蓄積しやすいというメリットもあります。
実際に安全具の装着点検やバケット車作業点検、安全器具使用状況点検などの用途において、安全品質AIソリューションが活躍しています。
株式会社パル技研が提供する「大型車専用 巻き込み警告システム SEES-1000シリーズ」は、AI画像処理技術を活用して歩行者・自転車・バイクを自動検知し、大型車を運転しているドライバーに対して事故の危険性を警告するAIソリューションです。
左折時に事故に巻き込む可能性がある対象物を事前に検知し、人命にかかわる重大事故を未然に防止します。
SEES-1000シリーズの特徴は、「歩行者・自動車・バイクのみを検知できる」点にあります。従来型の超音波センサーを利用したシステムでは、人とモノの区別を付けられず、誤検知する場合がありました。しかし、AI画像処理技術を応用した本ソリューションでは、対象物を高精度で検知可能です。
ドライバーの運用に合わせて柔軟に設定変更を行える点も特徴のひとつで、ウインカーと警告音を連動させたり、駐車した際に自動的に検知を停止したりすることも容易です。後付けが可能で、現在利用している車両へ手軽に導入できます。
NDIソリューションズ株式会社が提供するnVisionは、画像認識AI技術を活用して、社内に眠っている使い道の無かった画像を活用するソリューション・サービスです。
NDKグループが保有する開発環境を活用して、蓄積した画像を活用したAI推論モデルを作成し、顧客環境に配置して業務システムへ組み込むことが可能です。PoC・実装サービスを中心に提供しており、検討中のAIソリューションを実装可能かどうか実証実験によって検討した後、実際に現場へ実装するまでの一連のプロセスをまとめてコンサルティングしています。
本番運用時の画像AI再学習サービスや、社内の業務改革支援・DXコンサルティングサービスも利用できるため、業務改革やDX推進をAIソリューションによって実現したいと考えている企業におすすめです。現状把握から取り組むべきテーマの設定まで支援してもらえるため、「どこからDXに手を付ければ良いのか分からない」という方でも安心して利用できます。
株式会社アラヤが提供する「セミカスタム/フルカスタム画像認識AI開発サービス」は、顧客の課題に合わせた柔軟なカスタマイズを実現する、画像認識AI開発サービスです。
多種多様な業種・業態に対応しており、資材の数量カウントやAIによる不審者検知、グループ属性・行動解析など、顧客の課題や目的に合わせてさまざまなAIサービスを開発できます。
「セミカスタムAI」と「フルカスタムAI」の2種類を用意している点が特徴的で、セミカスタムAIを利用すると、事前に用意されたテンプレートを活用した短期間でのAI開発が可能です。業界別にニーズが高いテンプレートが用意されているので、幅広い用途に応用できます。
自社の運用に合わせたAIを構築したい場合や、挙動が複雑なAIを必要とする場合は、フルカスタムAIで1からオリジナルのAIを構築することも可能です。無料画像診断を利用するとテンプレートを適用できるかどうかを判別し、具体的な開発プランを提案してもらえます。

KYTの実施によって、作業員一人ひとりの安全に対する意識を高め、問題解決能力を育むことができます。安全のための行動を習慣化させ、「安全を先取りする職場風土づくり」を推進しましょう。
とはいえ、KYTの実施で削減できる事故には限界があり、完全に労災事故をゼロにすることは難しい側面もあります。事故ゼロを目指すのであれば、人間に代替する画像認識AIなどのAIソリューション導入も視野に入れ、安全対策を強化することが大切です。
AIソリューションについて詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
AIソリューションの種類と事例を一覧に比較・紹介!
AIについて詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
AI・人工知能とは?定義・歴史・種類・仕組みから事例まで徹底解説
業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。
メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。
AI製品・ソリューションの掲載を
希望される企業様はこちら