生成AI

最終更新日:2024/04/05
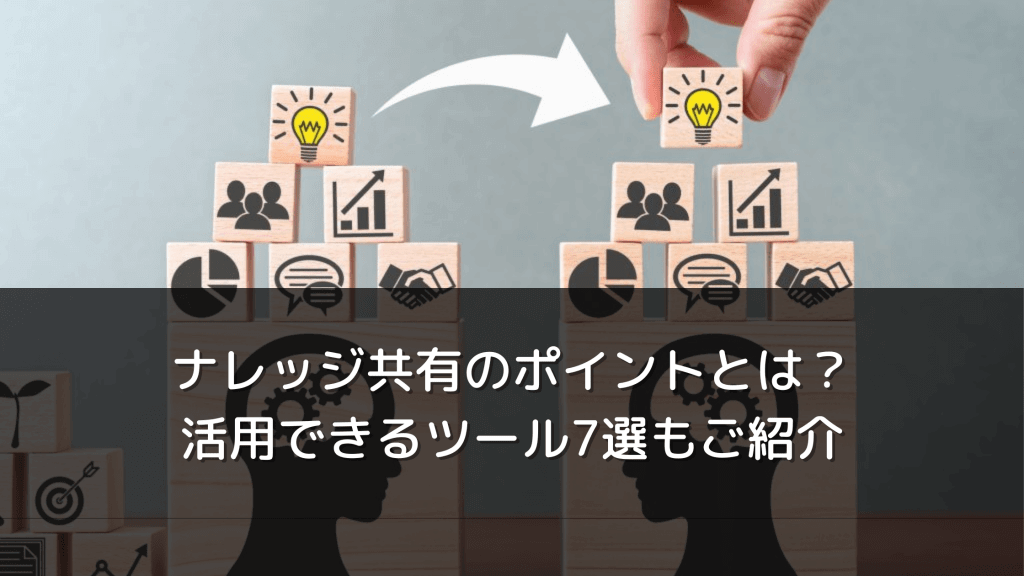 ナレッジ共有のポイントとツール
ナレッジ共有のポイントとツール
ナレッジ共有は、個人が持つ能力や知識を組織全体で共有し、効果的に活用するために有用な手法です。適切なツールを用いることで、ベテラン社員の勘や希少な知見などの知的資産を組織に還元でき、業務効率化やコスト削減といった幅広い影響が見込めるでしょう。
この記事では、ナレッジ共有のメリットやおすすめツールなどについて解説します。ナレッジ共有を有意義に活用するポイントを紹介しますので、組織改善や業績向上のためにお役立てください。
ナレッジマネジメントについて詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
ナレッジマネジメントとは?注目される理由や導入のポイントを解説

ビジネスシーンでの「ナレッジ(Knowledge)」とは、個人や企業に蓄積されたスキルやノウハウ、長年の経験や勘などの知見のことです。単純に何を知っているかだけではなく、特定の分野や業務における経験やテクニック、問題解決に役立つ実践的な知見を含んだ概念を意味します。
ナレッジの例としては、業務マニュアルや研修資料、仕様書、設計書、社外秘の事業方針、議事録などです。「ナレッジ共有」とは、社内スタッフや部署の間でナレッジを共有することを意味します。
社員や部署レベルのナレッジを組織全体で効果的に共有することは、意思決定のスピード化やリソース配分の改善につながり、個人の業績アップや組織全体の生産性向上に効果的です。
ナレッジは「暗黙知」と「形式知」の2種類に分けられます。両者について理解し、適切な変換と共有を行うことが、ナレッジ共有の基本です。それぞれについて詳しく解説します。
暗黙知とは、言語化が難しい技術やノウハウのことで、長年の経験で身につけた勘やフィーリングなどが例です。文章や図、数字などに変換することが難しく、同じ業務や経験を通して身につけられるものの、使いこなせるまでには時間を要します。
暗黙知の多くは、当人が何気なくできてしまう業務や考え方です。個人レベルのナレッジは属人化しやすく、意識的に言語化や図式化を行わない限り、企業や組織に共有されずに終わってしまいます。
ナレッジ共有では、暗黙知を伝達できる形に変換し、組織全体の知的財産として活用することが重要です。
形式知とは、暗黙知の対義語として使われる言葉で、言語化できるナレッジのことです。そのままでは共有が難しい暗黙知を、言語化・図式化することで、他の人や組織全体で活用できる形に変換することを「形式知化」と呼びます。
個人が持つナレッジを1箇所に収集・蓄積し、検索できる状態で公開することで、社内Wikiや百科事典として活用可能です。また、ナレッジ共有によって部署ごとのナレッジが他部署に共有されるため、効果的な業務方法の発見や確立につながるでしょう。

ナレッジ共有は、以下の4つのパターンに大別されます。
企業ごとに優先すべきパターンは異なるため、自社の現状を把握した上で、適した仕組みやツールを選ぶことが大切です。

ナレッジ共有の実践は、社員個人から部署、全社レベルまでさまざまなメリットが見込めます。ここでは、ナレッジ共有による4つのメリットについて詳しく見ていきましょう。
ナレッジ共有は、個人と組織両方における生産性向上に役立ちます。過去の成功事例や業務フローは、再現性の高い成功法則の1つです。ナレッジとして共有することで、他の社員にスキルやノウハウを後継できます。
ノウハウやスキルを業務マニュアル化すれば、ベテラン社員が新人教育に費やす時間が削減でき、業務効率化につながるでしょう。また、クレーム事例やシステムトラブルの解決策といった失敗事例も、ナレッジとして蓄積し、誰でも簡単に検索できる仕組みを構築しておくことで、急な事態にも同じ問題を防ぐことが可能です。
ナレッジ共有により、優秀な社員が持つノウハウや知識を社内に共有でき、社員のスキルアップに効果的です。雇用形態の多様化の影響で、人の入れ替わりが増えている現代、人材育成のスピードアップや即戦力となる人材のニーズが高まっています。教育や引き継ぎの時間や業務を大幅に効率化でき、教育コストの削減という効果も得られるでしょう。
ナレッジ共有は再現性が高く、効果的な活用によって新人の独り立ちや社員の伸び悩みの改善が実現します。社員間の能力差が埋まり、社内全体における業績の底上げも期待できるでしょう。
また、ナレッジ共有は、業務の平準化や属人化の防止にも役立ちます。個人に頼ることなく誰が取り組んでも一定のパフォーマンスを維持することが可能です。特定の社員がいないと業務が止まってしまう事態を予防でき、急に担当者が変わっても業務の質を下げることなく引き継ぎできます。
ナレッジ共有により、誰でも必要なタイミングでナレッジを検索できる仕組みを構築することで、問い合わせ対応業務の効率化や削減につながります。ナレッジ共有ツールを、社内データベースやFAQ(よくある質問集)として運用することで、個別の問い合わせが削減でき、疑問を自分で検索して解決へと導くことが可能です。
担当者の不在などで業務が止まってしまうリスクを回避すると同時に、在宅勤務やリモートワークへも応用できます。
ナレッジ共有は、部署間の連携強化にも有効です。組織の規模が大きくなると、他部署との連携が薄くなりやすいですが、ナレッジ共有の仕組みを構築することで、部署の垣根を超えたコミュニケーションが増えます。結果、新しいアイデアや発見により、生産性向上や業績アップにつながるでしょう。
また、社員同士の情報交換が活発化することで、チーム単位での連携意識や企業の競争力向上にも役立ちます。

ナレッジ共有のメリットを活かし、自社で最大限の効果を得るためには、コツを押さえてナレッジ共有を実践することが大切です。ここでは、ナレッジ共有のポイントを詳しく紹介します。
ナレッジ共有を始める前に、全社で目的を共有する必要があります。ナレッジ共有は、ナレッジを組織全体に還元するための仕組みです。特定の社員や部署だけでなく、全社で取り組んで初めて効果が得られます。
ナレッジ共有という新しいシステムを組織レベルへ浸透させるためには、経営陣が先頭に立って取り組むのと同時に、目的やメリットを社員に伝え、賛同と理解を得ることが重要です。
ナレッジ共有のハードルを下げ、誰でも取り組みやすい環境を構築することも大切です。ナレッジ共有について理解を得られても、具体的な方法がわからないと始められない人も多いでしょう。また、日常業務が忙しい人にとっては後回しにしやすい業務のため、実際に共有されない可能性があります。
メモ感覚でナレッジを蓄積・共有できるツールや、誰でも簡単にアレンジできるフォーマットを使えば、気軽に始められるでしょう。最初は雑多な話題も共有可とするなど、まずはナレッジ共有の仕組みに慣れることを目的とした運用でも、ハードルが下がります。
積極的にナレッジを共有できる仕組みづくりを意識しましょう。社員の中には、ナレッジ共有の必要性を理解していても、言語可や可視化は不要な人や、日常業務が忙しいなどでメリットを感じない人もいます。
知識やスキルを提供する側にとってもナレッジ共有がプラスに働くよう、組織内での工夫が必要です。例えば、ナレッジ提供者への表彰や報奨金の授与、評価制度の見直しなどが挙げられます。ナレッジのアウトプットに対して、SNSのようにリアクションできる機能を備えたツールも有用でしょう。
共有されたナレッジが検索しやすい仕組みやツールを導入しましょう。ナレッジが共有されても検索しにくいと、貴重なナレッジが活用されずに終わってしまう可能性があります。フォーマットなどでルールを明確化することもできますが、ルールが複雑化、あるいは形骸化するケースも少なくありません。
検索してもヒットしない、どこに情報があるかわからない、といった事態を避けるためには、操作性の高いナレッジ共有ツールを導入することが大切です。また、共有するナレッジの範囲や優先順位を定めておくことも、社内全体の業務レベルや生産性の向上に役立ちます。
ナレッジ共有の浸透と定着に向けて、専任の担当者(ナレッジリーダー)を決めましょう。ナレッジ共有は部署単位ではなく組織レベルで行われ、幅広い範囲をカバーします。そのため、ナレッジ共有の定義や目的、運用ルールを認識している人物を専任者として選ぶことが大切です。
ナレッジ共有の運用後は、現場におけるナレッジ共有の効果を専任者が主体となって検証する必要があります。1人の担当者でなく、プロジェクトチームを組んで複数人に任せることも可能ですが、いずれも善意に頼るのではなく、業務としてカウントすることも重要です。

ここからは、ナレッジ共有におすすめのツールを紹介します。ナレッジ共有はもちろん、ナレッジの蓄積や管理、コンテンツ作成といった多彩な機能を搭載したツールが多数あるので、目的や用途に合ったツールを選ぶことが大切です。各ツールについて詳しく見ていきましょう。
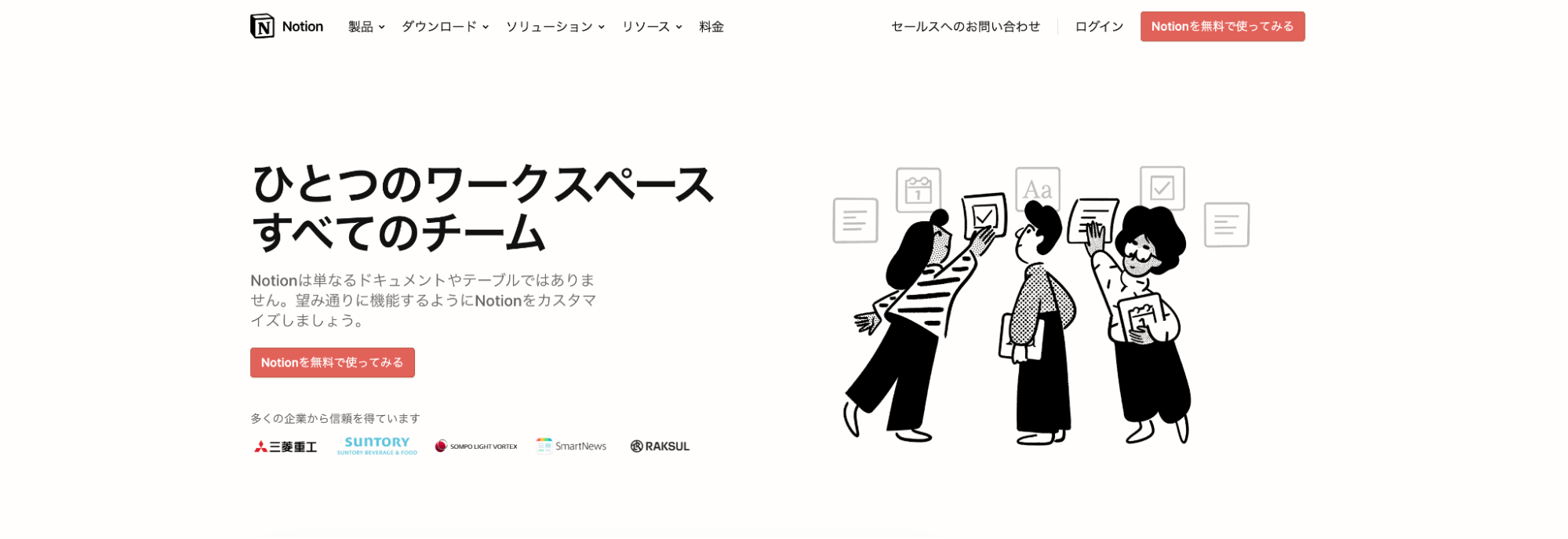
Notion(ノーション)は、「All-in-one workspace」というキャッチコピーの通り、多彩な機能を搭載したツールです。文書作成から管理・共有、プロジェクト・タスク管理、検索用データベースなど、ナレッジ共有に便利なあらゆる機能を1つに集約しています。
メモ感覚でのテキスト保存やアウトプットはもちろん、画像やURLを使ったリッチドキュメントの作成にも対応。情報量が多い場合は目次を付けておけば、必要な情報に簡単かつスピーディにアクセスできます。ほかにも、ロードマップの可視化など、プロジェクトマネジメントに有用な機能も充実しており、プロジェクト情報の一元管理が可能です。
多くの機能を使いこなせれば、ナレッジ共有による高い効果が期待できるでしょう。逆にITツールに不慣れな人が多いと、機能が多すぎて使いにくい場合もあるので、ある程度ITリテラシーを持つ社員がいる企業に向いています。

Docbase(ドックベース)は、文書の作成や共有に特化したツールです。テンプレートや編集履歴の保存、ピン留め機能、タグ付けによる分類などドキュメント作成・管理機能が充実。動画やスライドの埋め込み機能を使って、より見やすくわかりやすい文書を効率的に作成することが可能です。
複数人で同時に編集できるので、会議中の議事録や社内ブログ、日報や企画書などさまざまなシーンで活用できます。シンプルなUIデザインで、ナレッジ共有ツールを初めて導入する場合も使いやすいでしょう。ツール内のナレッジや文書は、社外にも記事単位で共有できます。
マークダウン記法が使えますが、入力アシスト機能があるため、知識がなくても文章のレイアウトや体裁を整えることが可能です。

NotePM(ノートピーエム)は、社内wikiデータベースの構築に特化したナレッジ共有ツールです。業務マニュアルやノウハウ、議事録など幅広い情報の一元管理が可能で、ナレッジの蓄積や共有を容易にしています。
ファイル内容の全文検索機能や、キーワードのハイライト、絞り込みも可能です。モバイル対応で、場所や環境を選ばず必要な情報にアクセスできます。
画像編集機能の付いた高機能エディタやテンプレート、スマホ動画の共有機能により、テキストや図解だけでは伝わりにくいナレッジの共有もスムーズです。ページ作成や更新時のユーザー通知や閲覧履歴の表示、リマインド機能は、共有漏れの予防にも役立ちます。
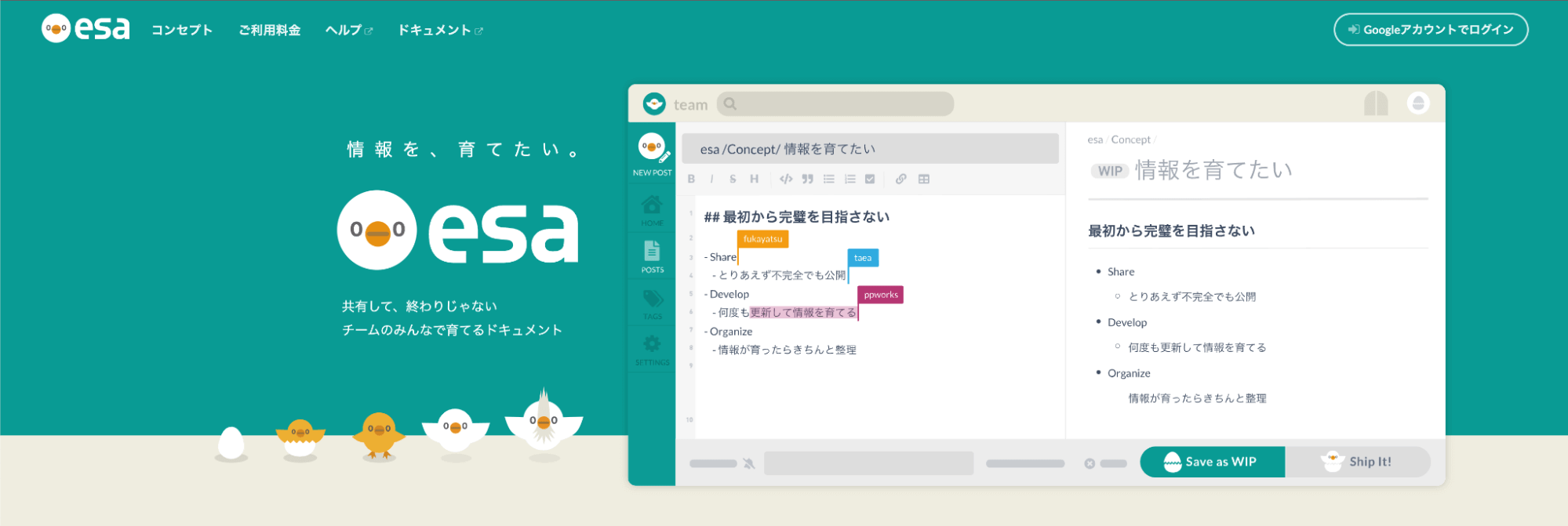
esa(エサ)は、「不完全な状態でも公開し、情報を育てていこう」というコンセプトの元で構築されたナレッジ共有ツールです。書き途中(WIP)の状態でも公開できるため、鮮度の高い情報共有を実現しています。
複数人での同時編集機能や記事のバージョン管理、カテゴライズ機能などを搭載。ファイルの更新を重ねて情報を育て、都度情報を整理するというフローで、関係者が気兼ねなく情報を共有できるようサポートしています。加えて、SlackやChatworkなど外部アプリとの連携も可能。英語表示のため、グローバル運用にもおすすめです。

Google Workspace(グーグル・ワークスペース)は、GoogleドライブやGoogleドキュメントなどGoogleアプリを使ったナレッジ共有ができるツールです。メールや文書ファイル、プレゼンテーション資料、カレンダーなど、関連アプリをまとめて管理・共有できます。
Google独自の高度な検索機能やフォルダ分けルールの設定機能を使うことで、必要な情報に簡単にアクセス可能です。ストレージ容量が大きく、画像や動画の共有にも便利でしょう。ファイル共有機能を使えば、1つのドキュメントを複数人で共同編集できます。
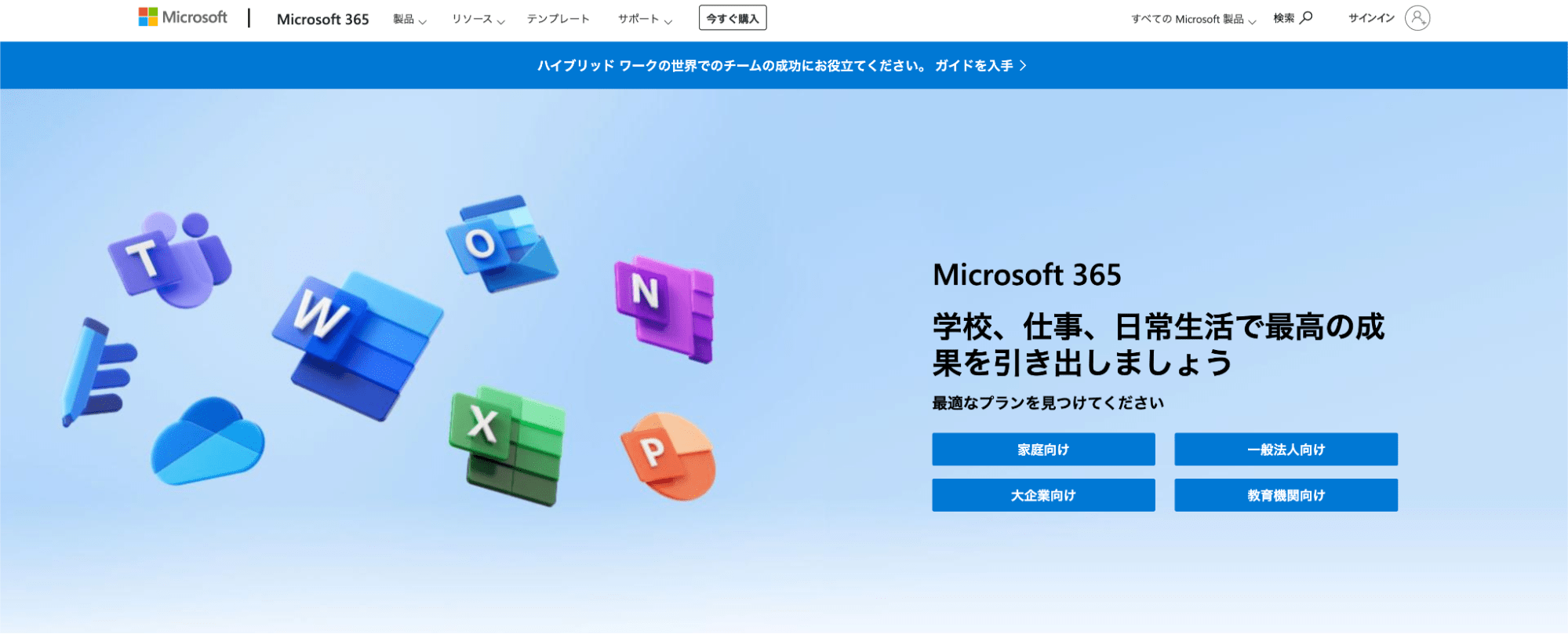
Microsoft 365は、Microsoftが提供しているクラウド型グループウェアです。多くの人が日頃から使っているWordやExcel、PowerPointといったOffice関連ツールや、ファイル共有サービスのOne Drive、メールボックスのOutlook、スケジュールなどを総合的に管理できます。
OneDrive上にファイル保存し、オンライン上で文章を共同編集することが可能です。マルチデバイス対応で、スマホやタブレットでも作業や確認が可能。新たなツールを導入するより、使い慣れたツールを使い続けながらナレッジ共有を進めたい場合におすすめです。
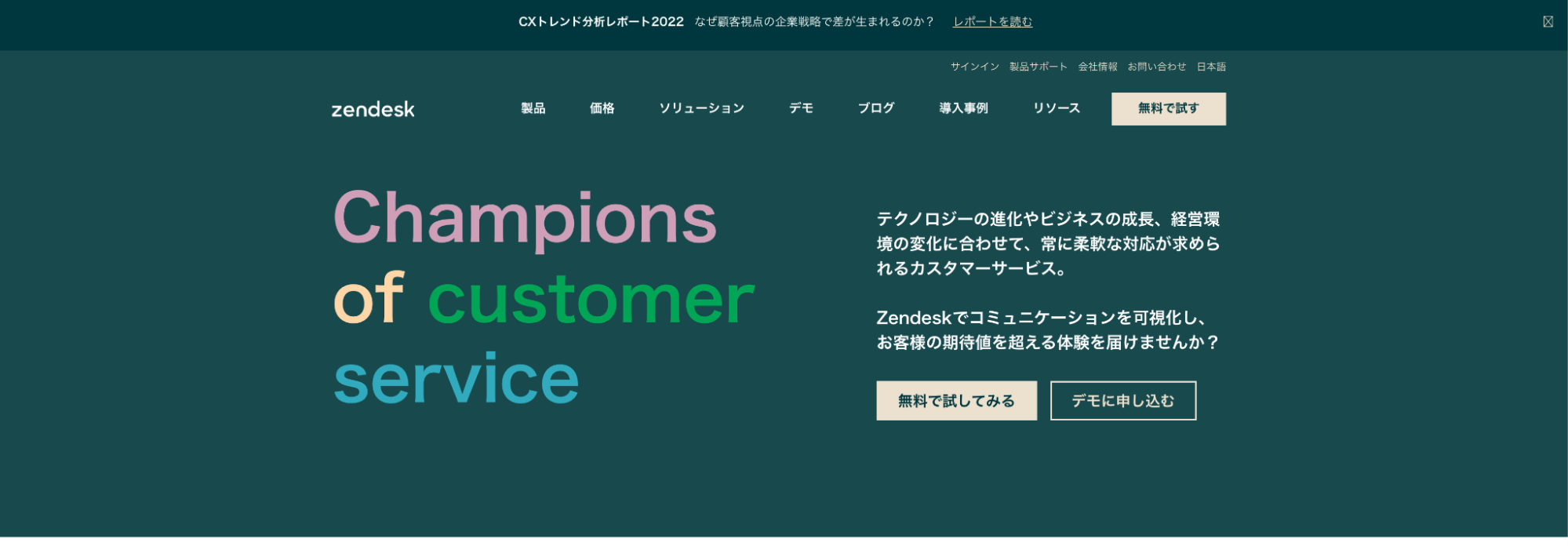
Zendesk(ゼンデスク)は、簡単な操作でナレッジの作成や共有、管理ができるツールです。操作性が高く、数クリックでナレッジの作成や公開が完了できるため、ITツールに不慣れな人でも使いやすいでしょう。
FAQ機能に適した高い検索性を備えており、共有すべき内容を必要な人に届けやすい仕組みです。AI技術搭載で、下書きのまま保存されているコンテンツや閲覧頻度の高い内容を自動判別し、迅速にナレッジ共有を実現しています。
グローバル企業の社内FAQや、国内外のプロジェクトにおけるサポートシステムといった用途でも活用可能です。
ナレッジ共有は、企業の業績向上や業務効率化に役立つ手法です。社員のスキルアップや属人化の防止、部署間の連携による組織の活性化など幅広いメリットが期待できます。
効果的なナレッジ共有のためには、経営陣やマネージャー層が率先して目的やメリットを共有するとともに、操作性の高いツールの戦隊や継続しやすい仕組みづくりに取り組むことが重要です。ナレッジ共有の専任者あるいは担当チームに一任し、運用後の検証や改善を行うことで、より高い効果が見込めます。
ナレッジ共有をスムーズに導入し、適切に運用するためには専用ツールが有用です。紹介したツールの他、社内ヘルプデスク用チャットボットも役立ちます。
社内ヘルプデスク用チャットボットの比較表を上記画像から無料ダウンロードいただけます。自社に最適なツールを選ぶために、ぜひご活用ください。
DXについて詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
DXとは?意味・定義や必要とされる背景、AI活用事例などを徹底解説
AIについて詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
AI・人工知能とは?定義・歴史・種類・仕組みから事例まで徹底解説
業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。
メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。
AI製品・ソリューションの掲載を
希望される企業様はこちら