生成AI

最終更新日:2024/04/04
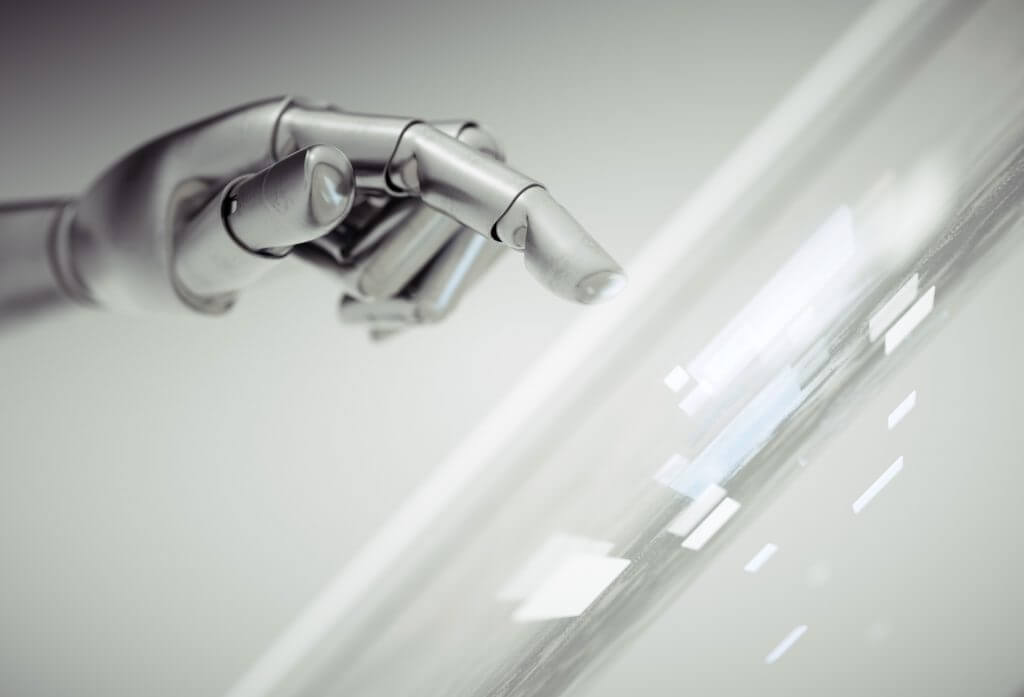
最近、オフィス業務の効率を上げるツールとして、RPA(Robotic Process Automation /ロボティック・プロセス・オートメーション)の導入が推進されています。国内で人気となっているRPAツールの多くは、専門的なプログラミング知識がなくても簡単な自動化ツールが作成できる点を売りにしています。
しかし、RPAで作られたさまざまなツールが増加するにつれ、スキルを持った人材の需要も増えています。そうした中、2018年からは国産RPAツールシェア首位の「WinActor」に準拠した国内初のRPA関連資格試験「RPA技術者検定」が開始されました。
RPAについて詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
RPAとは?導入によって期待できる6つ効果と自動化できる5つ業務
RPA関連資格試験の「RPA技術者検定」について紹介する前に、まずはRPAの仕組みや利用するメリットなど、基本的な情報からみていきましょう。
RPA資格の取得を検討されている方であれば既にご存知かもしれませんが、RPAとは「Robotic Process Automation」を略した言葉であり、バックオフィス業務などのホワイトカラー業務をロボットに代行させる取り組みや概念のことです。
そんなRPAを利用した業務は3つの段階に分けることができ、それぞれの段階で「できる作業」の内容や範囲などが異なります。では、具体的にどのような形で分類されているのか、詳しくみてみましょう。
今回のテーマでもあるRPAは、このclass1に分類されます。RPAは、定型作業を効率的に進めたり、いくつかのアプリケーション連携が必要となる単純作業の自動化を測ったりすることが可能です。人事・経理・総務・情報システムといった事務業務や管理業務、販売業務などに多く使われている傾向にあります。
EPAとは、Enhanced Process Automationを略した言葉です。データの収集や分析などに対応することができ、自由記述式のアンケートを集計したり、ログ解析を行ったり、複数の要因を加味した上での売上予測を行ったりと、さまざまなデータをもとにした分析の自動化を図ることができます。
CAとは、Cognitive Automationを略した言葉であり、RPAにAIのような自律的判断力を備えたものを指します。プロセスの分析・改善や意思決定などを自動化することができるのが特徴です。最近では、深層学習(ディープラーニング)や自然言語処理に対応しているものも多くなってきています。膨大な量のデータを整理したり分析したりするのはもちろんのこと、収集したデータを活用した経営改善などにも役立てていくことができるでしょう。
RPAを利用することで得られるメリットとしては、主に以下の3点が挙げられます。
RPAは人間とは異なり24時間365日稼働することができるため、これまで以上に業務効率化を進めることができます。単純作業をRPAに任せることで、人間はよりクリエイティブな仕事に力を注ぐことができるでしょう。
企業経営における経費として大きな割合を占める人件費を削減することができます。どのような形でRPAを導入するかで効果は変化しますが、一般的には25〜50%の人件費削減が可能です。
RPAは決められたルールに従って作業を的確に行うことができるため、人間のようにミスを起こしてしまう心配がありません。人為的なミスが減少することで、生産性の向上にもつなげられるでしょう。
上記のようなメリットを持つRPAは多くの企業で導入され始めており、それに伴いRPAを扱える人材の需要も高まってきています。そのような中で注目を集めているのが、RPA資格というわけです。
「RPA技術者検定」で準拠している「WinActor」とは、NTTデータが開発しているRPAツールです。NTTグループで開発・利用されてきた実績と信頼性から、2018年12月末時点で1900社以上が導入しており、国内シェアナンバーワンとなっています。
WinActor は「Windows端末上のアプリケーションの操作を学習して自動的に実行する、ソフトウェア型ロボット」として、アプリケーションによらずパソコン上でのあらゆる業務を自動化します。インターネットブラウザから、マイクロソフトのOffice製品(Excel、Access、Word、Outlookなど)、ERPやOCR、ワークフロー(電子決済)、個別システム、共同利用型システムなどにも対応しています。こうしたソフトウェアを用いた定型業務をRPAに任せれば、作業者は本来の業務やさらに付加価値の高い業務に専念できます。
WinActorで自動化ロボットを作成する場合、プログラミングの知識は不要です。ITシステム部門ではないユーザー部門の担当者でも、容易に取り扱える点が強みとなっています。また、PC1台からでも導入できるので、スモールスタートも可能です。
RPAは、これまでホワイトカラーが担当していたルーティンワークを自動化させることができる技術です。こういった部分の人員削減を行うことよって、人の創造性が求められる業務に多くのリソースを割けるようになります。
また、RPAは「一度作業を記憶させれば、同じ作業を一定のレベルで正確に再現できる」という強みもあります。人の手による作業では、どうしても体調やモチベーションなどによって生産性にバラつきが出てしまうため、RPAの「品質を一定に保てる」という点は大きな魅力といえるでしょう。
このような特徴があることから、近年ではRPAの導入を前向きに検討する企業が増えてきています。そんなRPA市場の高まりを受けて、「WinActor」の技能習得レベルを評価するためのRPA資格「RPA技術者検定」が生まれたというわけです。
この検定が生まれたことにより、「しっかりとWinActorを使いこなすことができるのか」という判断を下しやすくなりました。つまり、企業の人材採用における一つの指標になるということです。

RPA資格「RPA技術者検定」は、WinActorを利用して業務の自動化に取り組むユーザーや、WinActorの導入に関わる技術者を対象とした技術検定で、「入門講座」「アソシエイト」「エキスパート」「プロフェッショナル」の4段階に分かれています。
では、それぞれの段階について、詳しくみていきましょう。
WinActorについて学習したい方や概要を知りたい方は、まずインターネット上で気軽に受験できる「入門講座」から取り組んでみるとよいでしょう。「入門講座」は、インターネット上で無料の動画を視聴した後、20問の択一問題に回答し、80%以上の正答率で合格です。
「アソシエイト」は試験会場まで出向いて受験する必要があります。「アソシエイト」が対象となる方は、WinActorの基本的知識を有していること、WinActorでシナリオ作成経験があること、WinActorの基礎知識を体系的に学びたいと思っていることが条件になっています。そして、60分の試験時間内に50の問いに答え、うち70%正解すると合格になります。
「エキスパート」もアソシエイトと同様に、試験会場まで出向いて受験する必要があります。「エキスパート」の試験は年4回、全国8会場で実施されます。主にシナリオの新規作成(WinActorの基本機能を利用したもの)と、その修正について出題されます。RPA公式サイトによると、出題範囲は以下の通りです。
1)次のようなWinActor利用場面に関する問題を主に出題します。
・Webサイト検索、インターネットからの情報収集、Webサイト更新
・大量データの投入、転記作業
2)必要となる知識項目例は次のとおりです。
・WinActorのシナリオ開発ができるレベルのアルゴリズムとプログラミング知識
(フローチャートの理解、文字列処理、分岐、繰り返し、数値計算、画像処理、ファイル処理、例外処理 など)
・WinActorのシナリオの設計・製造・テストまでができるレベルのシステム開発技術
・WinActorの動作に必要なMicrosoft Windows 知識および WinActorと連携させるソフトウェアの知識
(Microsoft Office(Excel,Word,Internet Explorer,メモ帳) など)
※RPA 「WinActor」公式サイト(http://watest.jp/expert.html)より引用
「プロフェッショナル」については、現在準備中となっています。

RPA資格「RPA技術者検定」がどのような試験であるかはお分かりいただけたかと思います。では、この資格を取得することによって、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。
まず大きなメリットとして挙げられるのは、「RPAの技術を客観的に評価する基準になる」という点です。先ほども少しご紹介しましたが、この検定に合格して資格取得すれば、RPAに関する知識や技術をどの程度備えているかといった評価を客観的な立場から得られます。そのため、転職や独立をする際のアピールポイントとしても役立てることができるのです。
そして何より、「WinActorのプロフェッショナルになれる」という点が大きなメリットといえます。国内トップシェアのRPAをしっかりと使いこなせるようになれば、企業への貢献度も抜群にアップするため、より信頼を得られる可能性が高まります。また、多くの企業に導入されているので、転職先にも困ることはないでしょう。
ただし、全ての人にとってRPA技術者検定の資格取得がメリットになるかといえば、決してそうではありません。RPAの資格が特に役に立たない職業も多く存在するからです。
その代表例のひとつとしては、一般的なホワイトカラー業務を行う人が挙げられるでしょう。RPA技術者検定は、あくまでも「WinActor」を使用する人のために作られた資格ですから、「WinActor」を使用する機会がない人にとっては、特に重要な資格ではありません。
そのため、資格取得を目指す前に、まずはRPA技術者検定の必要性についてしっかりと考えた上で、行動に移していくことをおすすめします。もちろん、資格はあるに越したことはないものですが、資格を取得するためには少なからず勉強する時間を確保しなければなりません。場合によっては講座を受講するためのお金が必要になることもありますし、受験の際には受験料も発生します。
せっかく時間やお金をかけて資格を取得しても、それが宝の持ち腐れになってしまっては意味がありませんので、事前に「RPA技術者検定の資格を取得した場合に得られるメリット」について、しっかりと考えておくようにしましょう。資格取得のために費やす「お金・時間」と、資格取得によって得られる「メリット」を天秤にかけた上で、行動に移してみてはいかがでしょうか。
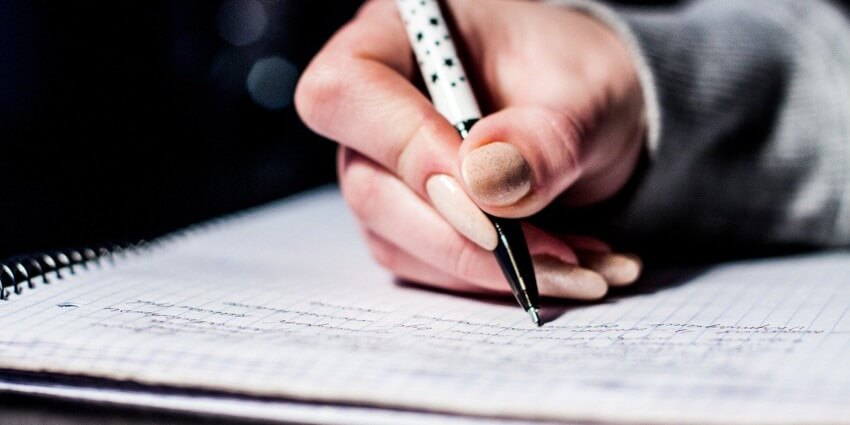
RPA技術者検定の資格を取るメリットについてはお分かりいただけたかと思います。しかし、特にRPAに関する知識を持ち合わせていない場合、そもそも方法で勉強に取り組んでいけば良いのか迷ってしまうこともあるでしょう。
そういった、ゼロから勉強を始めていく方におすすめなのは、「RPA入門講座」というものです。先ほども少しご紹介しましたが、「RPA入門講座」はRPA技術者検定のサイトで無料受講することができる初心者向けの講座となっています。その講座の具体的な流れとしては、約50分の概要紹介ビデオを閲覧し、その後、20問の習熟度確認テストに回答していくというものです。
この入門講座を受講すれば、RPAがどのようなものなのかを一通り学ぶことができますので、これからRPAの勉強を始めていく方にとっては非常に有意義なものになるでしょう。何より、無料で受講できるという点は大きな魅力ではないでしょうか。
ちなみに、RPA技術者検定の合格の目安は正答率8割以上と言われていますので、8割以上の正答率を目指しながら受講していくと良いでしょう。
RPA資格「RPA技術者検定」はまだ開始から日が浅く、世間的な認知も低い段階かもしれません。しかし業種・業界を問わず、さまざまな企業でRPAの導入が進む中、きちんとした取り扱いスキルをもつ人材への需要が高まると予想されます。
このように需要が高まりつつある状況で、客観的な評価を得られる「RPA技術者検定」を取得しておけば、企業からの信頼度が高まりますし、場合によっては転職や独立の際にも役立つ可能性があるのです。検定に合格すれば、合格者であることを示すゴロを名刺に印刷することが許可されるため、セルフブランディングの面からみても大きなメリットになります。
RPAでの業務自動化に関心をお持ちの方は、この機会に資格試験の勉強にも取り組んでみてはいかがでしょうか。
AIについて詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
AI・人工知能とは?定義・歴史・種類・仕組みから事例まで徹底解説
業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。
メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。
AI製品・ソリューションの掲載を
希望される企業様はこちら