生成AI

最終更新日:2025/06/04
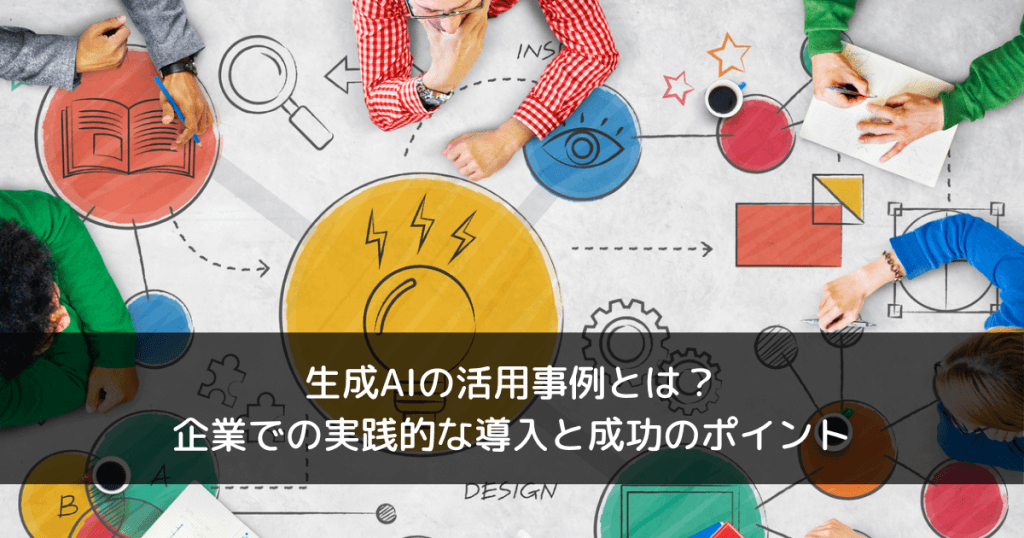 生成AIの活用事例
生成AIの活用事例
近年、ChatGPTやMidjourneyなどの登場により、生成AIの注目度が急速に高まっています。文章、画像、音声、動画など多様なコンテンツを自動生成できるこの技術は、業種・業界を問わずさまざまな分野で導入が進んでいます。本記事では、生成AIの基本概要から業界別の活用事例、導入時の注意点までを網羅的に解説します。今後、企業のDX推進のヒントを得られるかもしれません。
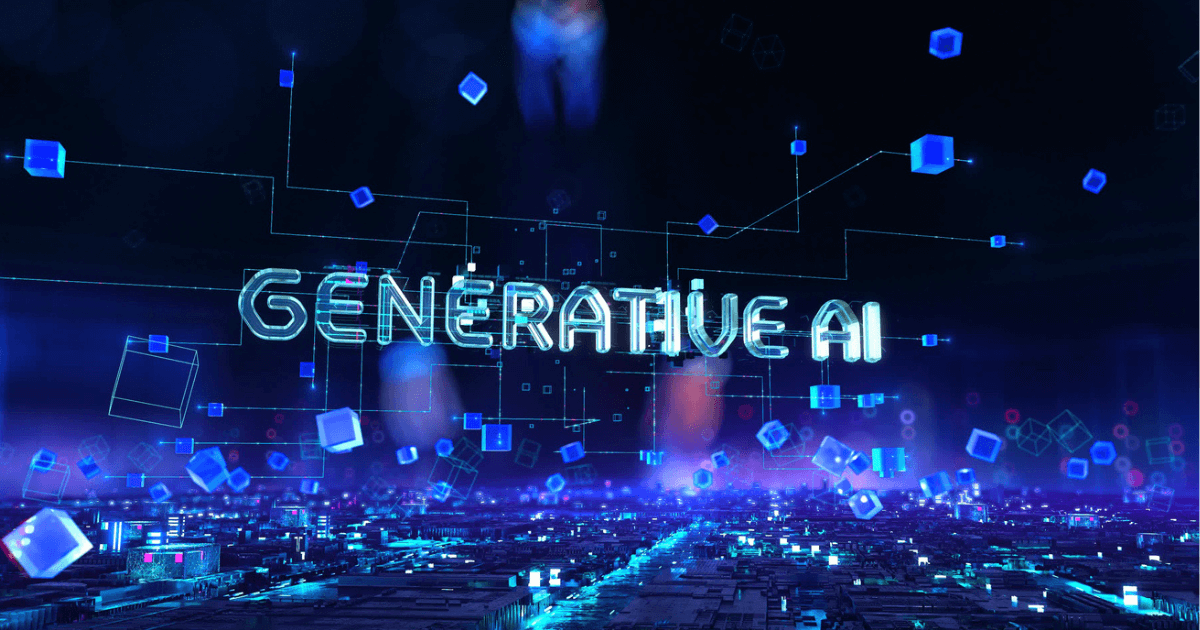
最初に、生成AIとは何か説明しましょう。
人工知能(AI)は広範な技術の総称ですが、生成AIはその中でも「新しいデータやコンテンツを作り出す」能力に特化した技術です。自然言語処理(NLP)やディープラーニングを活用して、テキスト、画像、音声などを生成します。もともと、企業ではコンテンツ制作の効率化や、カスタマー対応の迅速化、データ分析の自動化などが課題として上がっていました。生成AIはこれらのニーズに応えられるため、今や企業活動に欠かせない存在となっています。
生成AIは、大規模なデータセットを学習し、パターンを理解した上で新しいコンテンツを生成します。代表的な技術には、OpenAIのGPTシリーズやGoogleのGemini、画像生成のStable Diffusionなどがあります。
生成AIの特徴は、こちらの記事でも解説しています。合わせてご覧ください。
生成AI(ジェネレーティブAI)とは?使い方・種類・仕組み・活用事例を解説

生成AIは、現在様々な業界で活躍しています。ここで、生成AIのマーケティングにおける活用事例について、ライブドアでのケースを紹介します。
もともとYouTubeクリエイターの多くは、テキストベースの露出が難しく、SEOや検索経由の流入が限定的でした。また、動画コンテンツの要点を文章化し、第三者に届ける手段が乏しいという課題がありました。
そこで、生成AIにより動画の内容を自動で記事化し、ライブドアニュースに掲載することで、検索エンジン経由やSNSでの拡散が可能になりました。その結果、クリエイターの露出機会が広がり、視聴者以外の層にもアプローチできるようになりました。
24時間ニュース配信を維持するには、膨大な人員と編集コストが必要でした。特に深夜帯の更新や、速報性のあるニュース対応が困難でした。
そこで、生成AIが原稿作成から読み上げ、映像生成までを自動で行うことで、人的コストを抑えつつ24時間対応が実現。常に新しいニュースを届けられる体制を構築できました。
ユーザーはニュース記事の情報量の多さに圧倒され、特にスマホユーザーは全文を読む時間が限られていました。また、記事の内容把握までに時間がかかるというユーザー体験の課題もありました。
そこで生成AIが3ポイントに要約することで、読者は短時間で記事の要旨を把握可能になりました。その結果、滞在時間や記事閲覧数の増加に貢献し、読者満足度も向上しました。
詳細については、こちらの記事で解説しています。
ライブドアがニュースのAI要約機能「ざっくりポン」β版をリリース
インフルエンサーとのマッチングは、過去の実績やフォロワー数など定量的指標に偏っており、投稿内容の質的な判断が難しい状況でした。
そこで生成AIが投稿画像やテキストから商品の親和性を分析することで、より的確なインフルエンサー選定が可能に。マーケティングROIの向上とプロモーション効果の最大化が期待されています。

次に、生成AIの製造業における活用事例として、日立製作所での事例を紹介します。
日立製作所は、仕様書が存在せず、有識者もいないブラックボックス化したレガシーシステムの刷新するため、生成AIを活用した新たなアプローチを提供しています。同社は、現行システムの可視化から計画支援、システム構築・運用までをワンストップでサポートし、顧客と一体となってプロジェクトを推進しています。
生成AIの活用は、以下の3つのフェーズで進められています。
それぞれ、日立製作所が介入すると、以下のような段階で提案しています。
| 項目 | 導入前 | 導入後 |
| 現行資産分析 | 仕様書がなく、ブラックボックス化したシステムの解析に多大な時間と労力が必要。 | 生成AIを活用し、業務レベルでの仕様書を自動生成。解析時間と労力を大幅に削減。 |
| リライト | ルールベースでの自動変換後、人手による修正・改修が必要。 | 生成AIがコードを生成し、品質と効率が向上。コストも低減。 |
| 現新比較テスト | コンペアツールを作成し、手動でテストを実施。工数がかかる。 | 生成AIを用いてテストを効率化。特別なツールを用意せずに実施可能。 |
| プロジェクト推進体制 | 顧客とベンダーが分業体制で進行。情報共有や連携に課題。 | 顧客と日立が一体となり、知識を持ち寄ってプロジェクトを推進。 |
これらの取り組みにより、品質と効率の向上、コスト低減が期待されています。
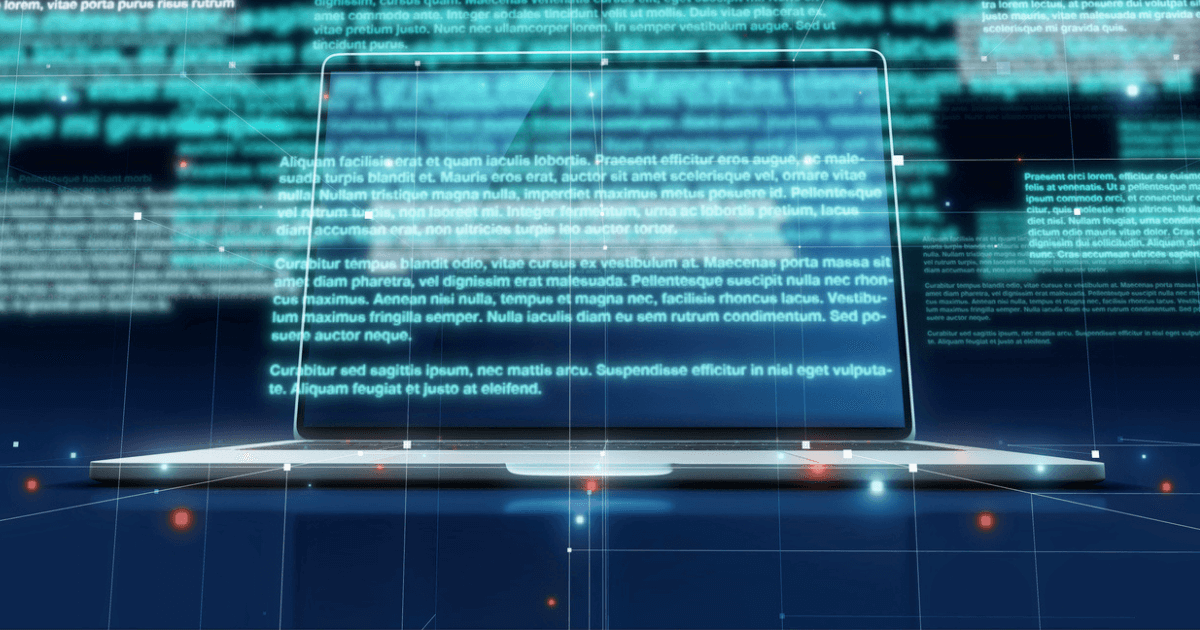
次に、生成AIの小売・EC業界で導入した事例を見ていきましょう。
ユニクロでは、オンラインストアにおける顧客の購買体験が画一的であり、個々のニーズに即した商品提案が難しいという課題がありました。
AIチャット接客機能「UNIQLO IQ」を公式アプリに搭載し、ユーザーの質問に対して即座に回答し、最適な商品を提案する仕組みを導入しました。これにより、ユーザーの購買体験が向上し、ECサイトへの誘導率が増加しました。
Amazonでは、取り扱う商品の数が数億点にもおよび、各商品に対して一貫性のある説明文を人手で作成・更新するには膨大な時間とコストがかかっていました。特に新商品登録や、仕様変更時の再編集作業は担当部門にとって大きな負担となっており、スピード感のある運用が難しいという課題がありました。
生成AIの導入により、商品カテゴリ・スペック・ブランド情報などを基に、自然言語でわかりやすくかつSEOを意識した説明文を自動生成する仕組みが整備されました。その結果、次のような結果が出ました。
また、季節やプロモーションに応じたテンプレート生成もAIが自動対応することで、マーケティング施策との連動性も高まりました。
ZOZOTOWNでは、商品説明文の作成や画像加工など、出店者の業務負担が大きく、作業効率の向上が求められていました。
生成AIを活用することで、商品説明文の作成工数が約70%削減され、画像加工の時間も大幅に短縮されました。また、AIを活用した広告運用により、広告の費用対効果(ROAS)が1.5倍に向上し、流通総額も前年比77%増加するなど、売上向上にも寄与しています。

次に、生成AIの金融や保険業界での活用事例について解説します。
みずほ銀行では、事務手続き照会や与信稟議作成に時間がかかり、業務効率の向上が求められていました。
そこでみずほ銀行では、行内向けテキスト生成AIを導入し、稟議作成にかかる時間を10分に短縮。業務の高品質化と速度向上が達成され、より高度な業務に人間の時間を割くことが可能になり、顧客サービスの向上につながっています。
この他にも、みずほ銀行が生成AIを活用した例についてはこちらもご覧ください。
みずほ、生成AIチャットツールに「GPT-4 Turbo with Vision」「DALL-E3」を導入。より一層の業務効率化へ
もともと楽天証券では、投資初心者から上級者まで、幅広い顧客のニーズに応えるための情報提供が課題でした。
そこで楽天証券では、生成AI「ChatGPT」を活用したチャット形式のサービス「投資AIアシスタント」を導入。投資の基礎知識や記事紹介など、楽天証券のウェブサイトに基づいた情報を提供し、24時間利用可能な自然な対話で投資の疑問を解消するサポートを提供しています。
アフラック生命保険では、社内情報の検索や営業支援、コールセンター業務の効率化が求められていました。
そこでアフラックでは、生成AIを活用した業務支援システム「Aflac Assist」を導入。社内情報の検索と営業支援、コールセンター業務の効率化の3機能を展開し、資料の検索や作成時間を30~40%短縮。2024年4月時点で全社員の約50%が利用しています。

次に、生成AIの医療・ヘルスケア分野の活用事例を見ていきましょう。
京都大学医学部附属病院では、カルテや診療情報提供書などの文書作成に時間がかかり、医師の負担となっていました。
そこで、生成AIを活用した文書作成支援システム「CocktailAI」を導入。カルテの内容をもとに定型文を自動生成し、医師が確認・補足するだけで文書作成が完了。これにより、文書作成の負担を軽減し、働き方改革に貢献しています。
大阪国際がんセンターでは、乳がん患者への疾患説明や同意取得に時間がかかり、医師の負担となっていました。
日本IBMと共同で、対話型疾患説明生成AIを導入。患者が受診前に疾患説明動画を視聴し、生成AIと対話形式で質問できる仕組みを構築。これにより、説明と同意取得の時間を30%短縮し、医療の効率化と地域格差の是正に貢献しています。
中外製薬では、治験に関わる書類作成に時間がかかり、創薬の期間や費用が増大していました。
そこで中外製薬では、NTTデータと協力し、治験に関わる文章を自動生成するAIを開発。これにより、「同意説明文書」では約60%、「症例報告書」では約40%の作成時間を削減し、創薬の効率化を実現しました。

企業が生成AIを導入するためには、いくつか注意点があります。
生成AIは、大量のデータを学習することでコンテンツや回答を生成します。しかし、元となる学習データの質が低かったり、誤った情報を含んでいた場合、そのまま出力にも反映されてしまいます。例えば、古いデータや信頼性のない情報を基に生成されたコンテンツは、誤解を生む可能性があり、ビジネスにおける判断や顧客対応にも影響を及ぼしかねません。
そのため、生成AIの導入にあたっては「どのようなデータを学習させているのか」を常に意識し、必要に応じて信頼性の高い情報源を使う、フィルタリングルールを設けるなどの工夫が求められます。企業にとっては、出力の正確性が業務品質やブランド信頼に直結するため、データ管理は極めて重要です。
生成AIの導入に際しては、個人情報や機密データを扱うケースも多く、セキュリティ上のリスクが伴います。たとえば、社内チャットボットに顧客の個人情報を入力した際、その情報が誤って学習データに取り込まれたり、外部へ漏洩する可能性があります。
このような事態を防ぐためには、生成AIの活用範囲を明確に定め、データの取り扱いに関するガイドラインやアクセス制御を徹底する必要があります。とりわけ、法令遵守(例:個人情報保護法やGDPR)への対応も不可欠で、事前にリスク評価と対策を講じておくことが求められます。
生成AIは、あくまで過去のデータをもとにパターンを学習する仕組みであるため、人間のような「常識」や「倫理観」を自律的に持っているわけではありません。その結果、事実と異なる情報や、意図しない偏見・バイアスが含まれる文章を出力する場合があります。
誤情報のまま公開すれば、企業の信用失墜や法的リスクにもつながりかねません。特に、意思決定や情報発信に生成AIを活用する際は、その出力結果を鵜呑みにせず、人によるチェックや修正を必ず行いましょう。
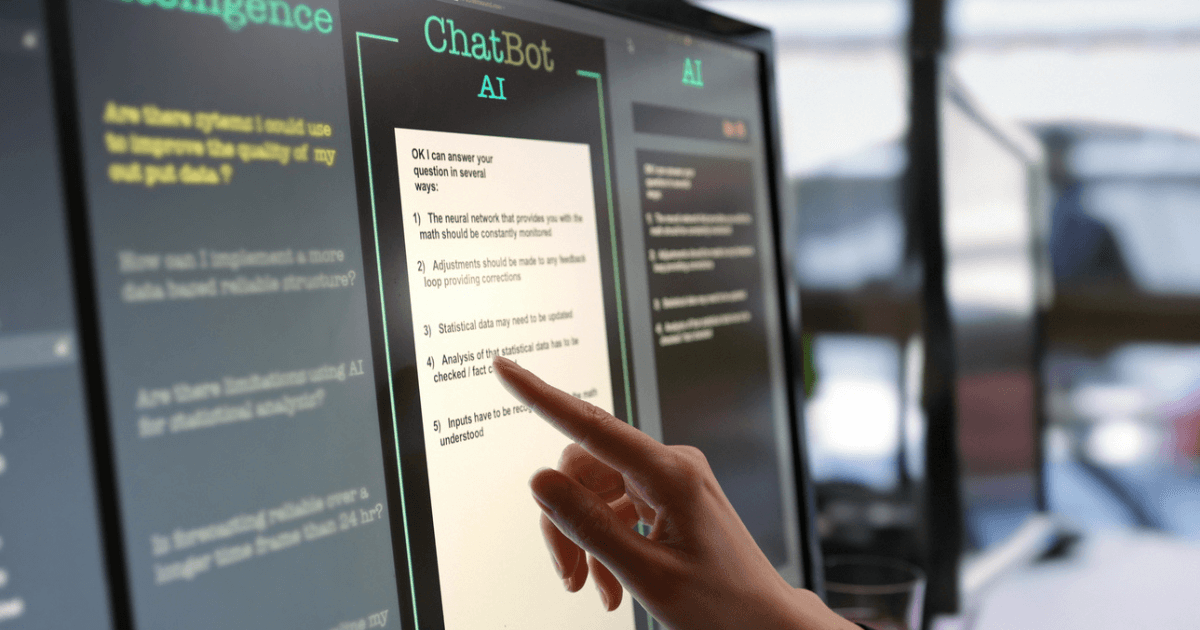
生成AIは、業務効率の向上、顧客体験の最適化、そして新たな価値創出を実現する強力なツールです。マーケティング、製造、医療、小売、金融といった多様な業界での活用が進む中、導入企業は自社の課題に応じたユースケースの選定が求められています。今後も進化が期待される生成AIを、自社の成長戦略にどう取り込むかが成功の鍵となるでしょう。
アイスマイリーでは、生成AIのサービスとその提供企業を紹介しています。自社での生成AI活用やDX推進に活用できる、最適なAIサービスを選定するためにぜひご活用ください。
業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。
メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。
AI製品・ソリューションの掲載を
希望される企業様はこちら