生成AI

最終更新日:2024/04/04
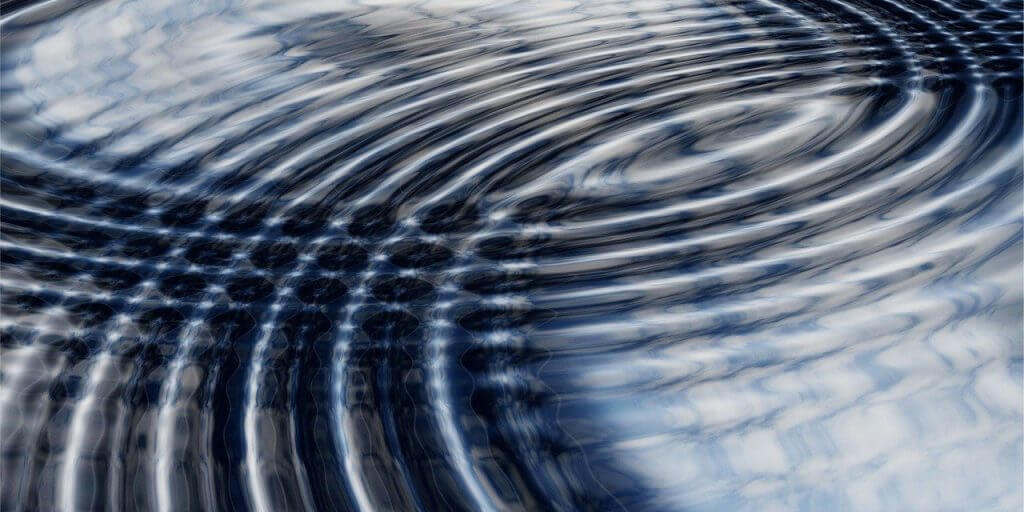
工場における「設備故障」は極めて重大な問題であり、一度生産がストップしてしまえば大きな損失につながってしまう可能性も少なくありません。そのため、近年は設備のメンテナンスが非常に重要視されており、生産停止を防ぐための「予知保全」などにも大きな注目が集まっています。
また、近年の少子高齢化に伴う人手不足という問題もあり、設備の管理やメンテナンスを行う保全部門の担当者が足りていない状況にあります。多くの経験を積み重ねたベテラン技術者の退職などもあり、ますます人手不足は深刻化しているのです。
だからこそ、工場において、いかにベテランへの依存度を減らしながら適切なメンテナンスを行っていくかという点に注目が集まっています。それを実現する方法として多くの企業に導入され始めているのが、「振動測定」という予知保全の手法です。今回は、この振動測定について詳しくみていきましょう。

振動測定は、生産設備の中でも台数が多い回転機械において、適切な時期・適切なタイミングでのメンテナンスを実現する技術です。突発的な故障や設備停止などが起きた場合、その対策として予知保全を導入したり、振動測定の機器を購入したりといった行動に出るケースが多いかと思います。
ただし、トラブルが発生したからといって焦って導入することは長期的にみて、決して効率的とはいえません。導入後の成果を評価するためにも、まずは現状についてしっかりと把握し、数値化しておくことが大切になるのです。成果を数字で評価していくことは、より客観的な目で物事を把握する上では欠かせません。また、担当者のモチベーションにも直結しますので、しっかりと数値化しておくことが重要になります。
次に行われるのが、設備にランクを付けるという作業です。生産に影響を及ぼす度合いをもとに評価を行い、最も重要度の高いものからランク付けしていきます。なお、仮にその設備が故障して1時間運転が停止しまった場合、生産にどれくらいの影響を与えるのか、具体的に金額で評価できることが理想的です。また、修理にかかる時間がどれくらいなのかという点も、この時点でできる限り明確にしておいたほうが良いでしょう。
その次に行われるのが、各設備の点検(メンテナンス)情報を整理する作業です。現段階で実施している各設備の点検項目や、具体的なメンテナンス方法(時間基準保全や事後保全など)、メンテナンスにかかる費用、メンテナンス実績(時期や部位など)を明確にしていきましょう。
そして最後に、メンテナンス全体像の把握を行います。主に以下のようなデータを調査し、比較や評価を行っていきましょう。
・年間で行われたメンテナンスの分類
年間で行われた修理の件数、計画内・計画外で行われた件数と費用を分類します。
・修理が頻繁に行われている設備の調査
具体的にどのような部分の修理が発生しているのかを明確にし、その費用を調べます。
・平均故障周期の計算
工場全体、プラント単位、ポンプ・ファン等の設備単位で平均故障周期を計算していきます。
・生産量に対する保全費用の比率の計算

上記の現状整理が終わったら、設備の重要度や期待できる効果などを明確にしていく必要があります。まずは、これまで整理した情報を参考に、対象設備を選んでいくところから始めましょう。ただし、設定の基準に関しては工場全体で共通していなければならないというわけではありません。なぜなら、それ以上に重要なのは、「どの設備に振動測定を適用させれば、突発的な停止の予防につながるか」という点をはっきりさせることだからです。
また、振動測定の対象が多ければ良いというわけでもありません。振動測定の対象設備が多くなれば、その分測定にかかる工数も増してしまいます。場合によっては、業務効率を悪くしてしまう可能性もありますので、限られた労働力と費用でいかに生産性向上を図っていくかという点にフォーカスしていくことが大切になるでしょう。

そして次に、ISO、JISの判定基準をもとに、速度を測定する箇所の設定を行っていきます。ベアリングのショックバルス診断においては軸径と回転数をもとに、判定基準を仮設定します。この仮設定した基準値は、実際に異常が発見された時の測定値としっかり比較し、見直しを行っていくことが大切です。
絶対的な判定基準が定まっていない時点では、「どのような傾向にあるか」をしっかりと捉え、状態の変化を察知していくことが重要になります。特に、モニタリングを開始した直後などは、運転条件の変化によって生まれる設備の挙動変化なども少なくありません。そのため、状況を正しく把握することは決して簡単ではないわけです。
また、同じ運転条件であっても、実際に測定を開始すると人為的な測定誤差だけでなく、他にも変動する要因が生まれることもあります。そして何より、異常が発生する周期がこれまでとは異なる可能性もあるのです。
そのため、異常による測定値の変化なのか、別の要因による測定値の変化なのかを誤認してしまわないためにも、できる限り短いサイクルでデータ収集(振動測定)を行っていくことが大切になるでしょう。
ここまでご紹介してきた点が、振動測定による予知保全を実行する際の手順ですが、実際に導入した上での重要なポイントとしては「異常発見時のルールを明確にしておくこと」が挙げられます。
振動値が上昇していたり、基準値が超えていたりといった異常が確認できた場合に、どのようなアクションを起こせば良いのか、社内で明確なルールを定めておかなければ生産性を大幅に低下させてしまいかねません。振動値の変化をグラフで確認したり、再測定を行ったり、測定値をもとにした処置決定をしたりと、然るべき「ルール」を作っておきましょう。
また、振動測定を導入したことで得られている成果がどれくらいなのかということを把握した上で、社内全体に発表していくことも大切です。成果につながっていることを周知すれば、社員一人ひとりのモチベーション向上につながる可能性もあります。予知保全による危機管理が万全でも、社員一人ひとりのモチベーションが低下してしまっていては生産性の向上は見込めませんので、しっかりと情報共有を行うようにしましょう。
業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。
メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。
AI製品・ソリューションの掲載を
希望される企業様はこちら