生成AI

最終更新日:2024/04/04
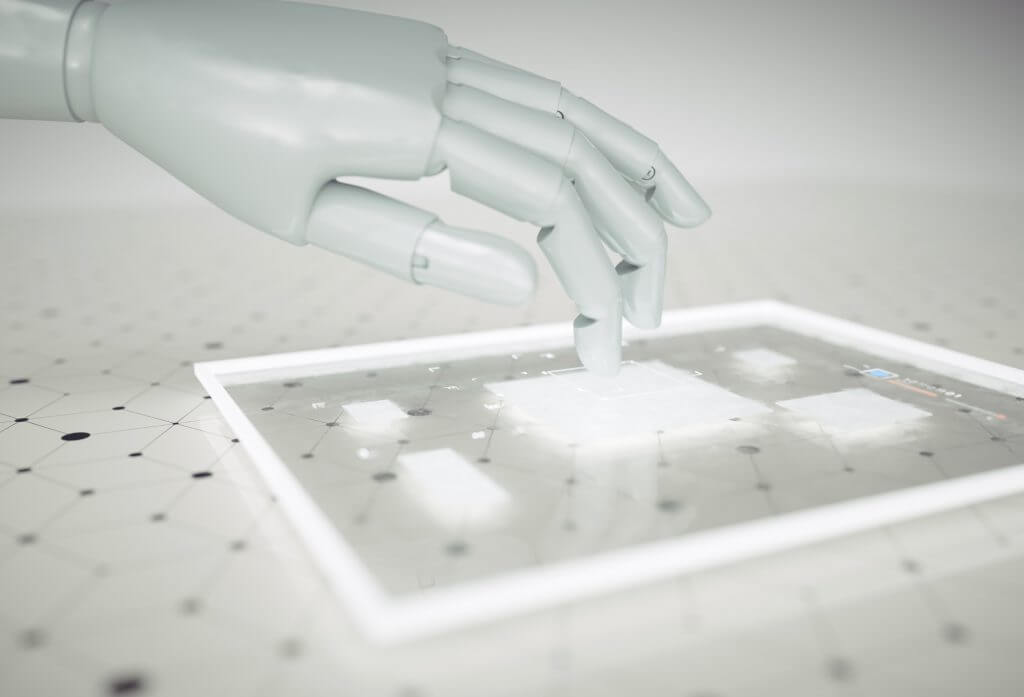
業務効率化の掛け声のもと、生産性を向上するための切り札として、RPAツールへの注目が高まっています。
一方で、人気製品だけに製品が乱立気味なのも事実です。初めてRPAツールを導入しようという方の中には、選択肢が多すぎて困惑している方もいるかもしれません。今回は、多くの企業の支持を集める人気のRPAツールはどれなのか、その実態をまとめました。
RPAについて詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
RPAとは?導入によって期待できる6つ効果と自動化できる5つ業務
MM総研が2020年1月に発表したRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)国内利用動向調査の結果によると、2019年11月時点でのRPA導入率は38%、年商1,000億円以上の大手企業に限定すれば51%という結果になったそうです。
また、RPAの導入率を業種別にみると、金融業界が59%と最も多く高くなったものの、それ以外の業界でも普及率が増加傾向にあるといいます。なお、2019年1月に行われた前回調査と比較すると、学校・医療福祉および流通業界が最も導入率が伸長していました。
そして2021年1月には、最新のRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)国内利用動向調査が発表されています。この最新の動向調査結果によると、年商50億円未満の企業のRPA導入率は10%となっており、50億円以上の企業(37%)とは大きな差があることが分かります。また、準備中・検討中企業と回答した企業は25%であり、未検討の企業が64%となったそうです。
この構成は、年商50億円以上の企業における2017年の中頃の状況と非常に似ているため、同じくRPAの認知が広がっていけば、さらに導入率も伸びていく可能性があります。
これらの調査結果を踏まえると、さまざまな業界でRPAが導入され始めており、特に大手企業では積極的にRPAが活用され始めていることがお分かりいただけるでしょう。年商50億円以下の中小企業は導入率が低い状況ですが、今後の導入率の伸長には期待できるのではないでしょうか。
高い市場シェアを誇るRPAツールについて見ていく前に、RPAツールを導入することで得られるメリットについても詳しく理解していきましょう。RPAツールを導入することで得られる主なメリットとしては、以下の4点が挙げられます。
近年は少子高齢化に伴い人材不足が深刻化しているため、人件費を削減できるという点は最大のメリットといえるかもしれません。RPAツールを導入すれば、これまで人が行っていた作業を代行させることができるようになります。ロボットによる自動化にもコストは発生しますが、人件費と比べれば遥かに安く、既存の30%から10%近くまで削減することが可能とされているのです。企業が抱えている問題にもよりますが、極めて大きなメリットであることは間違いないでしょう。
RPAツールは決められたルールに従って正確に作業していくため、人間による作業でありがちなミスを防止することができます。人の手で業務を行うと、集中力の低下や体調の変化などが原因となり、ミスが発生してしまうケースも少なくありません。その点、RPAツールであれば人為的なミスを防ぐことが可能になります。また、作業ミスは生産性にも影響を与えるため、長期的な業績という点でも大きなメリットがあるといえるでしょう。
人間の場合、疲労が溜まってしまうため長時間労働は行えません。特に近年は働き方改革が進んでいるため、残業で生産性を高めるという選択肢も現実的ではないでしょう。その点、RPAツールは人間と違って疲労することがありません。そのため、業務スピードを向上させ、スケジュールを大幅に短縮させることができるのです。
これまで社員の残業を減らすことができていなかった企業であれば、RPAツールによって残業を減らすきっかけを作り出すこともできるでしょう。
業務の中には、ロボットに任せられる作業と、人間にしかできない作業が存在します。ロボットに任せられる作業まで人間が行っていると、人間にしかできない作業の効率を高められず、生産性の低下させてしまいかねません。
その点、RPAツールを活用すれば、人間は「人間にしかできない作業」だけに集中できるようになるため、より生産性を高めながら、新たな事業戦略を生み出していくことも可能になるのです。そのため、RPAツールの活用がきっかけとなり、新規事業に踏み出すチャンスが訪れる可能性もあるかもしれません。
これらのメリットを踏まえた上で、ここからは高い市場シェアを誇るRPAツールの特徴やメリットを詳しくみていきましょう。
RPAツール導入のデメリットとして挙げられるのは、コストが膨らんでしまうという点です。全社的にRPAツールで業務改革する、もしくは高セキュリティーが要求される業務で活用するといったフェーズになると、デスクトップ型からサーバ型への移行を検討するようになるでしょう。サーバ型は集中管理ができるメリットがある一方で、両者の価格差は2~3倍では留まらないケースもあります。そのため、安価なサービスの登場が待たれている状況です。
とはいえ、コスト面で理想的なRPAツールであっても、機能面が自社の求めるものとは異なるようでは意味がありません。あくまでも「業務効率化」を最優先とした上で、自社の規模に適した費用のツールを選定していくことが大切になるわけです。
「コスト」「導入規模」「業務範囲」「セキュリティー」といった要素を複合的に判断し、自社の業務効率化を行う上で最適な機能を備えたツールを選択していくことが大切になります。また、最近では無料トライアルが設けられているRPAツールも存在するため、それらを一度利用し、業務効率化につなげられるかどうかを判断してみるのもひとつの手段といえるでしょう。
日本市場におけるRPAのシェアランキングは、2018年時点では以下のように推移しています。
それぞれのRPAにどのような特徴があり、どのようなメリットがあるのか、より詳しくみていきましょう。
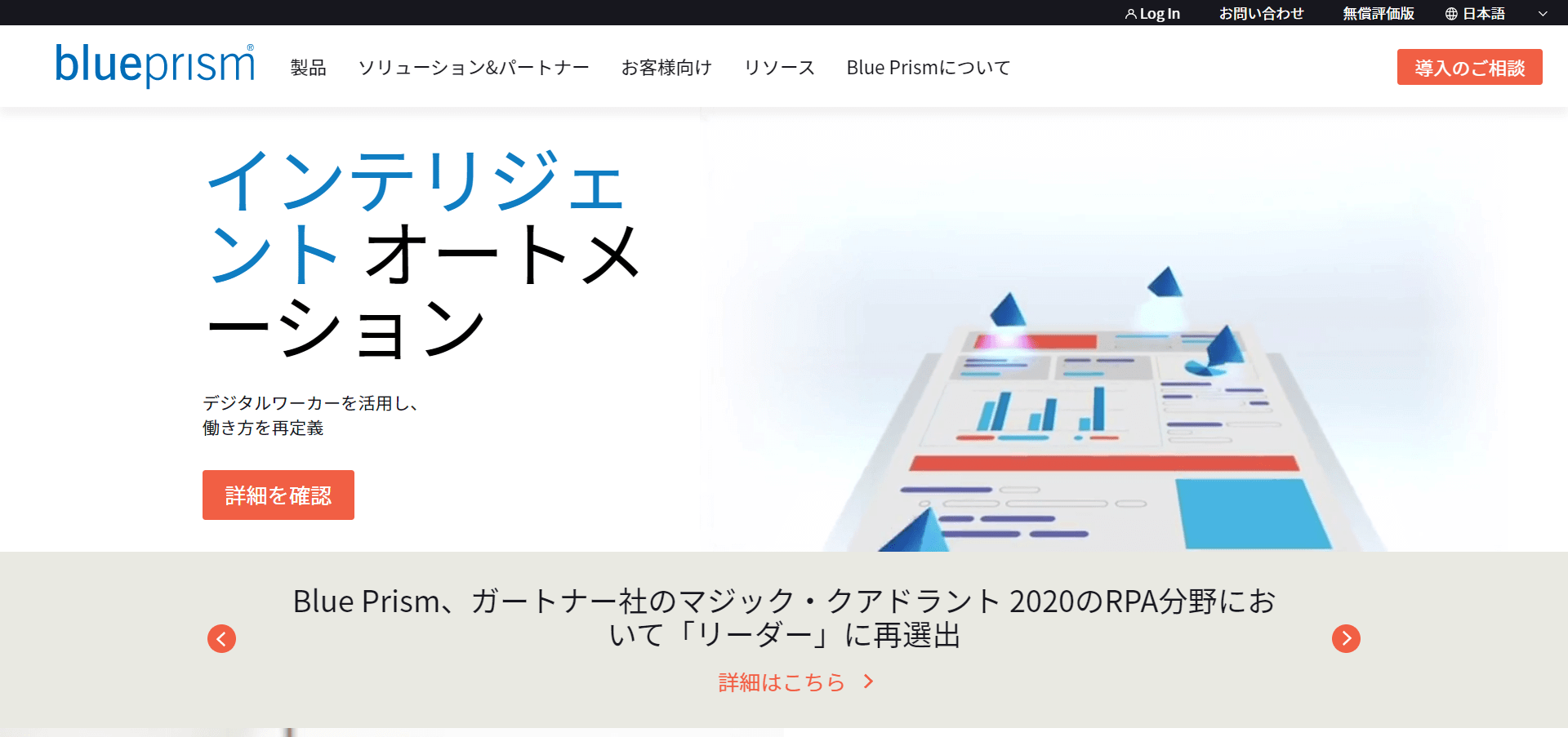
blue prismは、BizRobo!やUiPathと比較するとシェアが多くないRPAツールですが、イギリスの老舗RPAベンダーが提供しているツールであり、高い知名度を誇っています。そんなblue prismの大きな特徴としては、1,000台のロボットを一元管理できるほどの大規模なサーバが用意されていることでしょう。そのため、複数のロボットを一元管理したいと考えている企業にとっては大きなメリットがあるツールといえます。
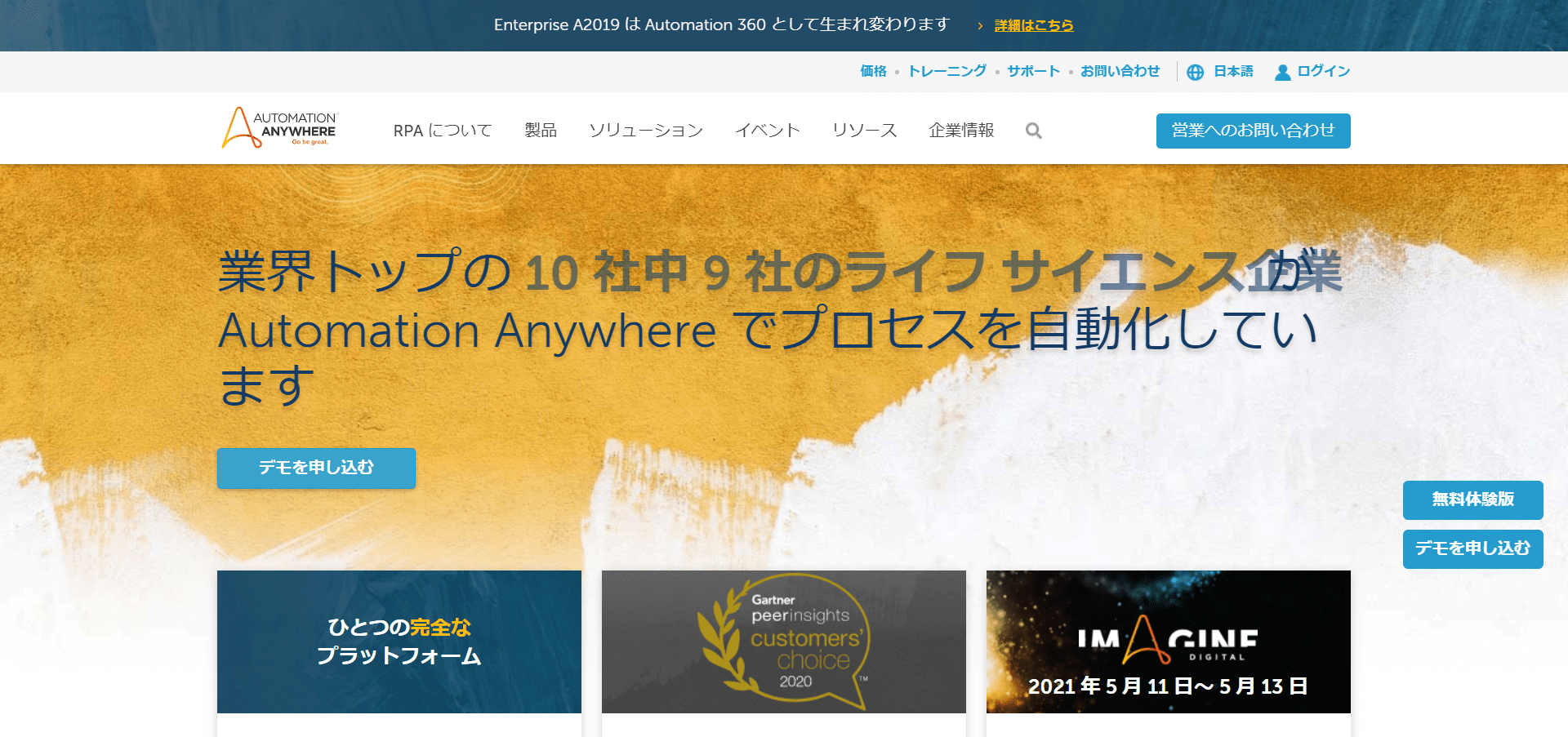
Automation Anywhereは、機械学習やBPM(Business Process Management)といった技術を導入しているRPAツールで、他のツールと比較すると難易度が高いのが特徴です。ただ、その分他のツールよりも優れた機能を備えているというメリットがあります。第一生命や日立物流といった大手企業が導入している点も注目すべきポイントといえるでしょう。
また、Automation Anywhereには無料で利用できるフリーソフト版が用意されているのも特徴のひとつです。「Automation Anywhere Community Edition」というフリーソフト版が提供されていますので、利用を検討される場合は、このフリーソフト版から試してみると良いでしょう。ただし、「Automation Anywhere Community Edition」には利用条件が定められているため注意しましょう。その利用条件というのは、次のいずれかに当てはまらなくてはならないというものです。
・開発者であること
・学生であること
・小規模の企業であること(250台以下、および年間売上500万ドル以下)
また、利用台数は1つの組織につき最大5台までという制限も設けられていますので、初めから大規模な運用を検討している場合には向かないかもしれません。サポートの面においても、有料版であれば電話やメールによるサポートが設けられていますが、フリーソフト版には「A-People」という総合プラットフォームだけしか設けられていません。そのため、手厚いサポートを必要とする場合には、初めから有料版を選択するか、他のツールを検討していくことも必要になるでしょう。
ただし、「Automation Anywhere Community Edition」には「Automation Anywhere University」と呼ばれるEラーニングが設けられており、これは無料で利用することができます。いわば「トレーニング」を積むことができるサービスですので、使い方に不安を感じている場合には、有効活用していくと良いでしょう。
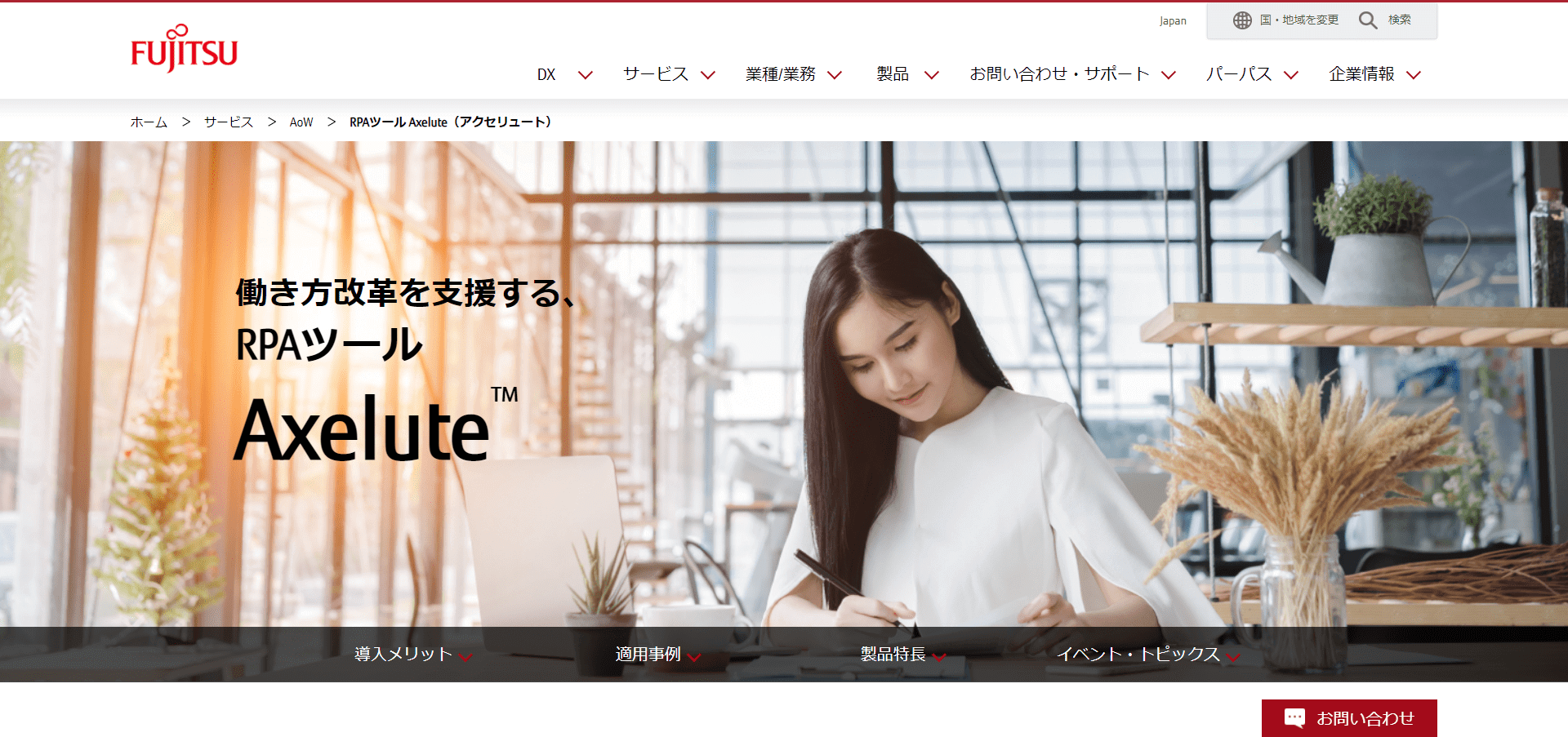
富士通が提供しているAxelute(アクセリュート)は、画面へのデータ入力作業や検索結果の取得作業など、これまでWindows上で行っていた定型作業を記録したり自動化したりすることができるツールです。「クライアント型」「フローティング型」「サーバー管理型」の3種類が用意されているため、RPA導入の規模や利用用途などに合わせて適切なタイプを選択することができます。
たとえばクライアント型の場合、利用者が増えるとライセンスも増加することになるわけですが、フローティング形であれば利用者が増えても「同時利用のライセンス分だけ」の利用料金となるわけです。同時利用分に最適化することでコストを圧縮できるのは大きな魅力といえるでしょう。

Googleの検索数においては、上記2つのRPAツールを抑えて「UiPath」が1位となっており、こちらも多くの注目を集める存在であるといえるでしょう。UiPathは、2017年に日本法人が設立され、ここ数年で国内企業での採用が急増しているRPAツールです。
国内のユーザー数はこれから増加していくことが予想されますが、すでに世界ではユーザー数が40万を超えており、Forbes Cloud 100においては3位という評価を得ています。そのため、今後日本においてもシェアNo.1を獲得する日は決して遠くないかもしれません。
また、トヨタ自動車株式会社やSMBCグループといった日本を代表する企業がUiPathを導入しているという点も、注目すべきポイントでしょう。
SMBCグループは、2017年4月からUiPathを導入し、RPAツールによる業務効率化を行っています。効果も数字に現れており、UiPathの導入から2年で1,000人分、現在は1,450人分の業務を代替することに成功しているのです。
こういった日本を代表する企業の導入事例が増えていくことにより、今後さらにUiPathのシェアが増していく可能性も十分にあるでしょう。
そんなUiPathの特徴は、専門的な知識を備えていない人でも扱いやすいという点にあります。直感的な操作が可能な「UiPath Studio」を使用することで、RPAツールが初めての方でもアプリ操作やデータ入力といった作業の自動化を図ることができます。
また、「UiPath Orchestrator」という管理ツールを活用すれば、社内でのロボット処理を一元管理することも可能です。
そして、スモールスタートで使用開始できるという点も、UiPathの特徴の一つです。1台から導入可能なので、コストをかけることができない企業でも手軽に導入することができます。
もちろん、業務の拡大に伴って利用規模も拡大させていくことが可能です。台数に応じたライセンス契約が可能になっているため、「現在は小規模だが、将来的には大規模な利用を検討している」という企業にも適したRPAツールといえるでしょう。

実際のところ、RPAツールの市場シェアは確固たるデータが発表されているわけではありません。
ただ、2018年にRPA総合プラットフォームを運営する「RPA BANK」とアビームコンサルティングが720社を対象に実施したRPA市場の動向実態の調査結果によると、 トライアル段階ではNTTデータの「WinActor」を導入している企業が多いようです。
WinActorは市場シェアナンバーワンをうたうRPAツールで、NTTグループで研究・利用を続けた技術とノウハウが詰まったツールという点を強調しています。 NTTグループの知名度と純国産のRPAツールという安心感にも裏打ちされ、さまざまな業種の1800社が導入しています。(2018年12月時点) 業種別の導入実績では、サービス・インフラ系、メーカー、IT系が多くを占めているようです。
WinActor は、Windows端末から操作可能なあらゆるソフトウエアに対応しているうえ、国産ソフトなので完全日本語対応が可能です。また、操作性が高く、プログラミングの知識も必要ありません。NTTデータ・パートナー企業による手厚いサポートや、PC1台にインストールするだけでも始められるというスモールスタートでも導入しやすい料金体系も魅力です。
このWinActorを活用した業務自動化では、まず「シナリオ自動記録」を行っていきます。WinActorをPCに導入すれば、通常通り業務を実施するだけで操作が自動録画されてシナリオも自動で作成してくれるため、特に難しい操作は必要ありません。
次に、「シナリオ編集」を行います。もちろん、生成されたシナリオをそのまま実行することも可能ですが、動作条件を編集することで、さまざまな場面で活用できるシナリオに仕上げることが可能です。このシナリオ編集に関しても、専用のエディタを利用したGUI操作で行いますので、比較的簡単に行うことができるでしょう。
そして、「シナリオ実行」へと移っていくわけですが、ここではWinActorが自動で業務操作を行ってくれるため、一切手をつける必要がありません。
こういった操作性の高さからも、RPAツール市場の中でWinActorが高く評価されており、多くの企業にも導入されている理由がお分かりいただけるのではないでしょうか。
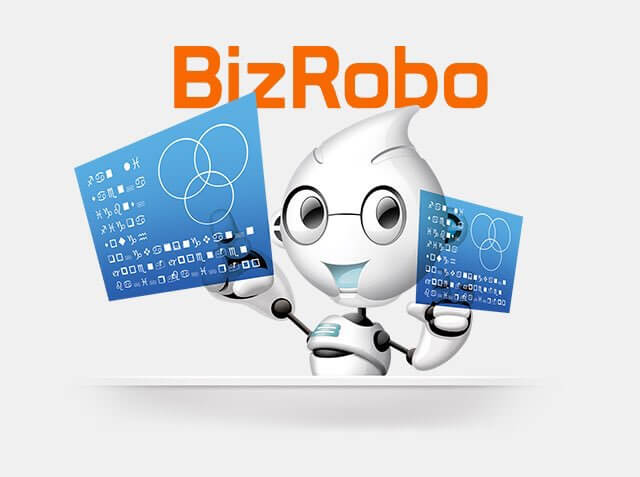
上記の調査では、従業員数300人以上の大企業や中堅企業が本格的にRPAツールを導入しようとした場合、WinActorでは機能が物足りなくなると「BizRobo!」を採用する割合が高くなるという実態も明らかになっています。
RPAテクノロジーズのBizRobo!は、1万ロボットの開発・運用実績とノウハウの積み重ねによって誕生したRPAツールで、 こちらも国内ナンバーワンをうたっています。10業界20業種40社とパートナー連携し、業界・業務に合った活用方法を提案できるのが強みです。すでに、国内1,000社以上の現場で活用されています。
2018年11月からは、クライアント型RPAでスモールスタートに適した「BizRobo! mini」の提供も開始され、ますます使い勝手がよくなっています。
「BizRobo! mini」の大きな特徴としては、やはり低コストで導入できるという点が挙げられるでしょう。ベーシックなタイプの「BizRobo! Basic」では複数台でロボットの操作を行っていくことができますが、「BizRobo! mini」はロボットの同時実行が1台に制限されているため、コストも低く設定されているのです。そのため、複数のPCでロボットの操作を行いたい場合には向きませんが、RPAツールのスモールスタートを検討している場合であれば最適なプランと言えるでしょう。
もちろん、「BizRobo! mini」を導入した後に「BizRobo! Basic」などでスケール展開していくことも可能であるため、将来的な規模拡大を想定している場合でも気軽に導入することができます。
ちなみに「BizRobo!」は、2018年国内RPAソフトウェア市場シェアには掲載されていませんが、これはIDC Japan社とRPA ホールディングスとの間で売上データのもとになる考え方の部分に相違があり、日本国内の独特のRPA市場を十分に考慮できていないことから、シェアの掲載が見送られたそうです。
実際には2019年1Q終了時点で、「BizRobo!」のOEM製品も含めて1,560社を超える導入実績があるため、多くの企業に導入されているRPAと判断して問題ないでしょう。
RPAツール市場において特に多くのシェアを獲得しているのは上記でご紹介した2つのツールですが、それ以外にも魅力的なRPAツールは数多く存在します。ここからはいくつか代表的なRPAツールをご紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
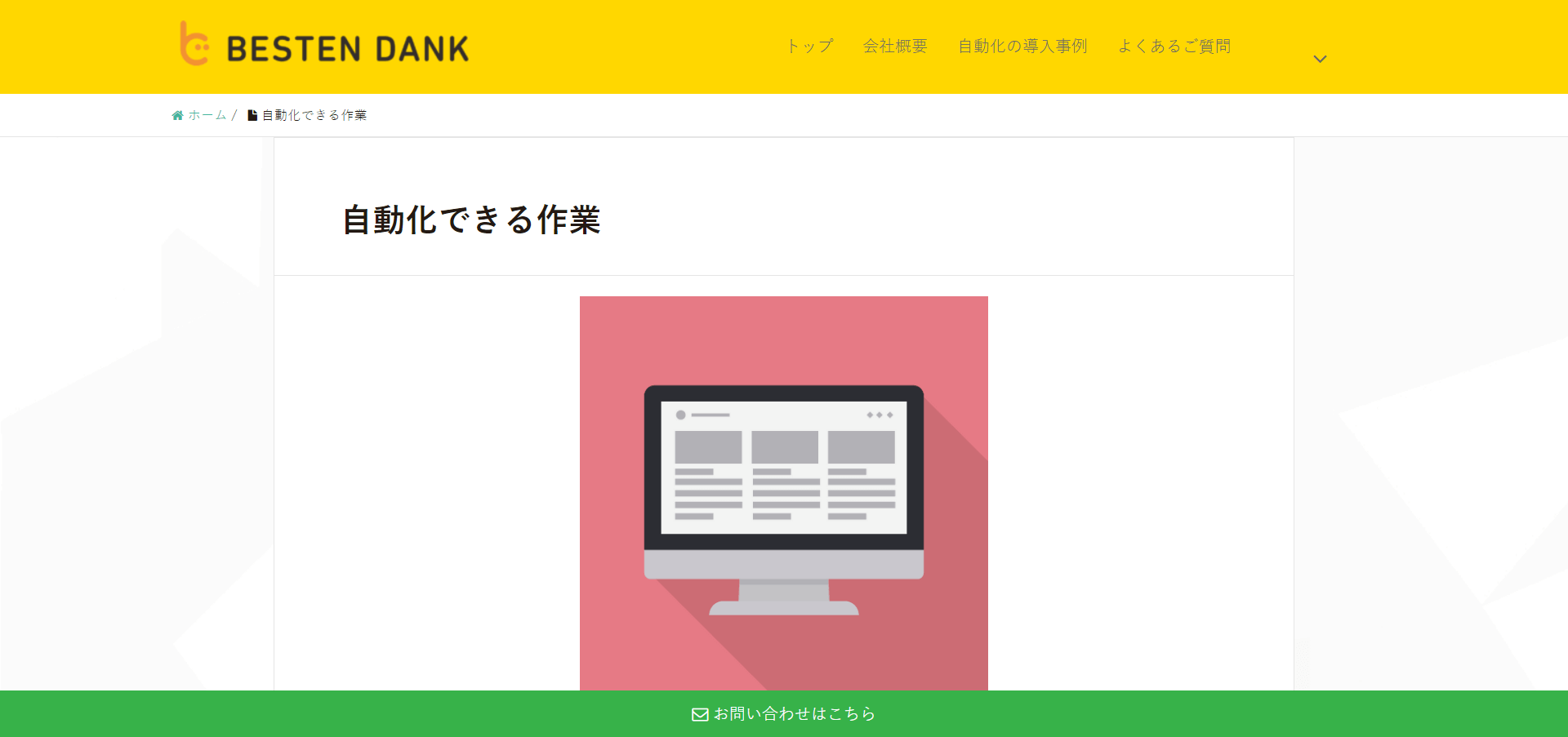
合同会社ベステンダンクが提供している「ベステンダンク」は、あらゆるルーチン作業を自動化することができるRPAです。RPA導入費用業界最安値を謳っており、導入費用2万円から運用を開始することができます。運用費用も必要な分だけを支払う仕組みになっているため、0円にすることも可能です。
そんな「ベステンダンク」は、ブラウザでできることは基本的にすべて自動化が可能であり、たとえば「ブラウザでの入力、クリック、選択、保存、解析」「FTPのアップロード」「画像の一括加工」といった作業も自動化させることができます。
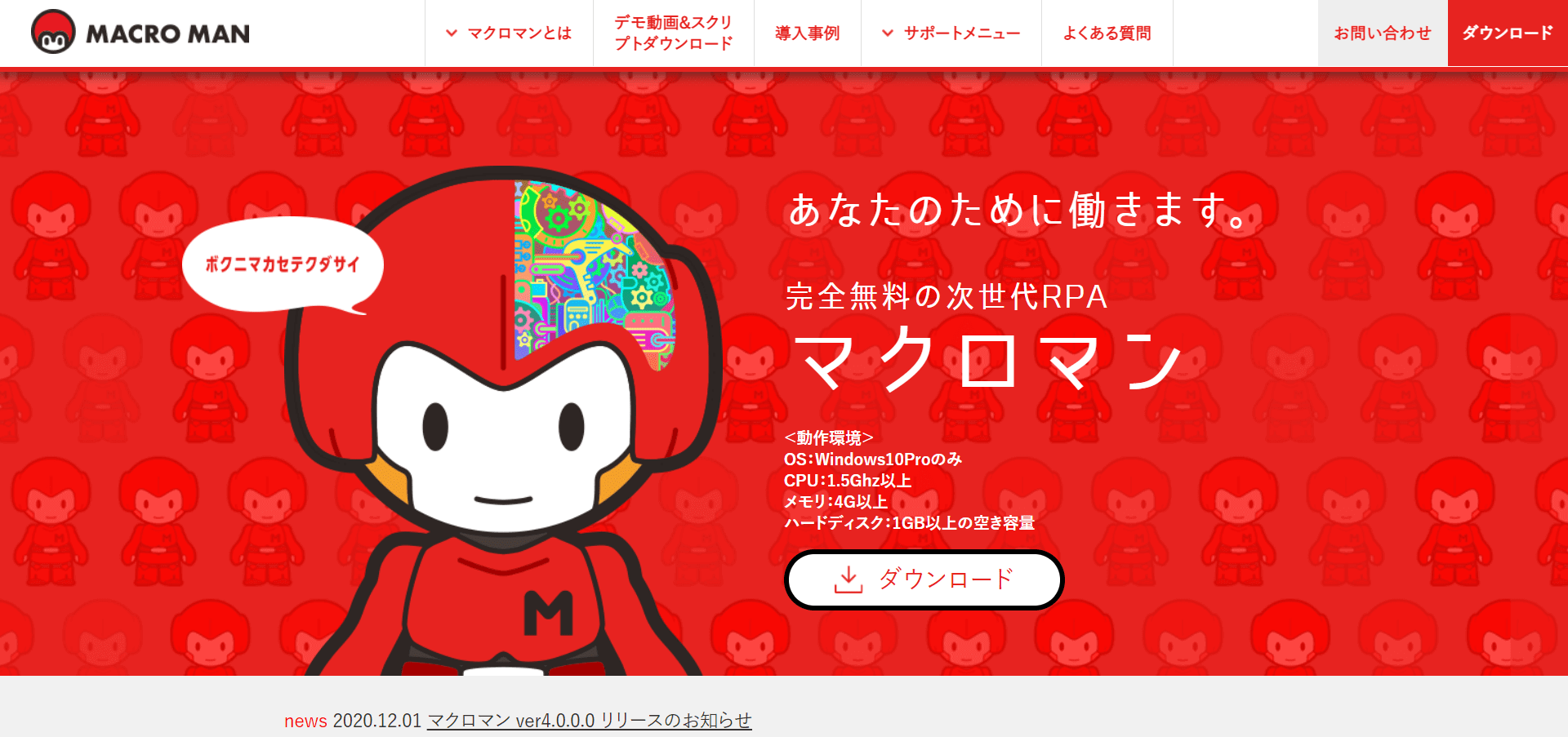
次世代RPA「マクロマン」は、プロダクト費用が不要の完全無料型RPAです。マクロマンのRPAは主に以下のような業務タイプに分けることができ、人事・総務の業務効率化に役立てることができるでしょう。
・データ入力(Excel、業務システム、Webなどへのデータ入力業務)
・データ集計、分析
・データ照合
・メール送信、受信
・情報検索(ユーザーからの問い合わせ内容を確認して検索方法を振り分け、回答を検索)
また、人材派遣会社だからこそ実現できるユニークなサービスも備わっています。それは「RPA女子」によるサポートサービスです。電話やチャットのサポートはもちろんのこと、スポット派遣やフルサポート(常駐派遣)といったサービスも設けられているため、「RPAを導入したいものの運用リソースが足りていない」といった問題を抱えている企業でも問題なく活用していくことができます。ただプロダクトで業務効率化を実現させるだけではなく、サポートによって効果を出すことが使命であるという理念があるからこそ、マクロマンはプロダクト費用が完全に無料となっているのです。これは、人材派遣会社が運営するRPAならではの強みといえるでしょう。
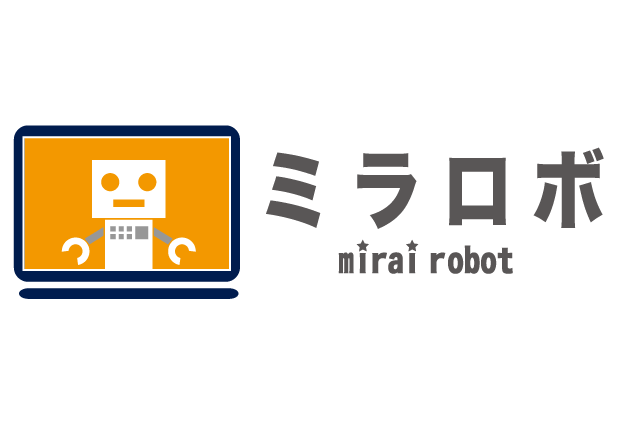
株式会社タイタンコミュニケーションズが提供するミラロボは、2つの画面しかなく、各ボタンの位置も一箇所に集約されている洗練されたつくりになっています。プログラミング知識不要で、業務担当者が自分で自分の業務を早期に自動化できます。
RPAの導入を検討する際、コスト負担と対象業務選定の2点が問題として浮上するケースは少なくありません。しかし、ミラロボは月額5万で月契約なので、気軽に始めて、少しずつ自動化範囲を広げていくことができます。
また、ミラロボマネージャーとの連携で、業務の洗い出しや対象業務選定の負担が軽減されると同時に、ユーザー業務を理解した無償サポートが受けられます。そのため、初めてのシナリオ作りでも安心して進めることができるでしょう。

エス・アンド・アイ株式会社が提供するVerint RPA(ロボティック プロセス オートメーション)は、最初から最後までを全自動処理する「全自動化」と、自動処理と人による判断やAIエンジンとの組み合わせによる「部分自動化」を選択することができるRPAです。
サーバーでRPA設定とシナリオを一元管理できるため、進捗管理も簡単に行うことができ、端末変更や追加も容易です。時間のかかる手作業を解消し、ルールに基づいた反復処理の手順を自動化し、従業員の付加価値の高い工程への配置を実現します。

六元素情報システム株式会社が提供するATgo自動テストRPAは、WEBシステムのブラウザバリデーションテスト、レグレッションテストに特化したシステム開発効率化ソリューションです。システム開発会社の現場から生まれたATgoは、現場のニーズに合わせて随時に改善します。
また、マルチプラットフォーム対応なので、インストールを行う必要がありません。Windows、Macはもちろん、スマホiOS、Androidにも対応しています。IE/Edge/Safari/Chrome/Firefoxなど主なブラウザにすべて対応している点は大きな魅力といえるでしょう。
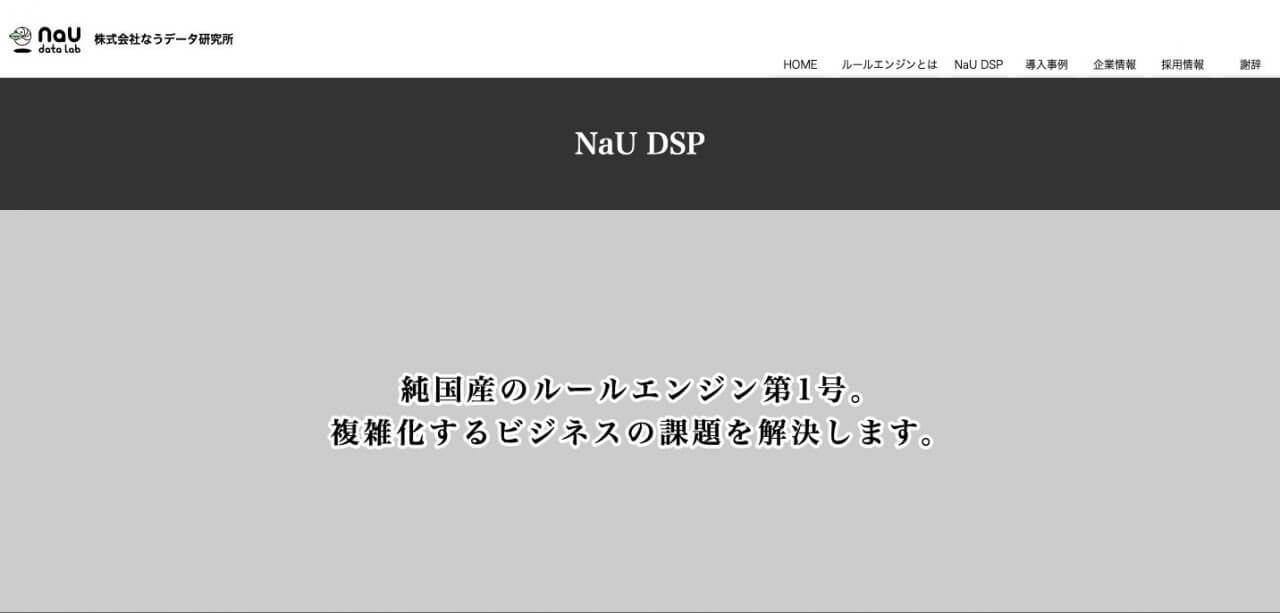
一般的なRPAツールの場合、人間があらかじめ設定を行い、その設定にしたがって業務を反復するわけですが、この「NaU DSP」というRPAツールには「前進判断」「後進判断」「提案型判断」という3種類の判断機能が備わっています。そのため、従来のRPAツールでは難しい「高精度な提案」をRPAツールに行わせることができるのです。
その一例としては、観光客一人ひとりの「好み」「予定時間」などを考慮した上で観光ルートを複数提案したり、建物の利用状況を考慮した上でエアコンの最適な運転計画を提案したりすることが可能になります。
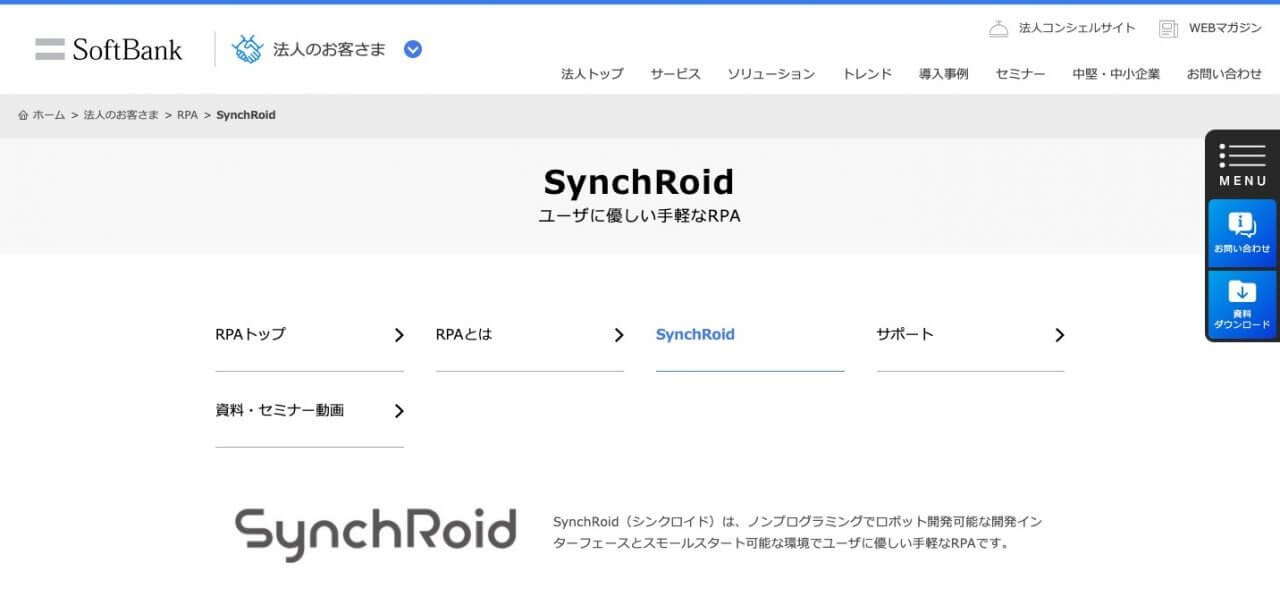
SynchRoidは、ソフトバンクが提供しているRPAツールです。ツールがリリースされる前にソフトバンク社内で試験的に導入され、実際に効果が実証されたことでも知られています。そんなSynchRoidの大きな特徴としては、ソフトバンク社が提携しているサービスとの互換性が強いことが挙げられるでしょう。そのため、ソフトバンク社のサービスを活用している企業などにはおすすめのツールといえます。また、e-learningやスキルトレーニングも提供しているため、RPAツールに関する知識が少ない場合でも問題なく活用することができるようになるでしょう。
ipaSは、マウスもしくはキーボードの操作のみで使用することができるRPAツールです。そのため、難しい操作が求められるRPAツールに対して不安を感じている人にはぴったりのツールといえるでしょう。また、社内に専門知識を持つ担当者が存在しない企業などにもおすすめのツールといえます。
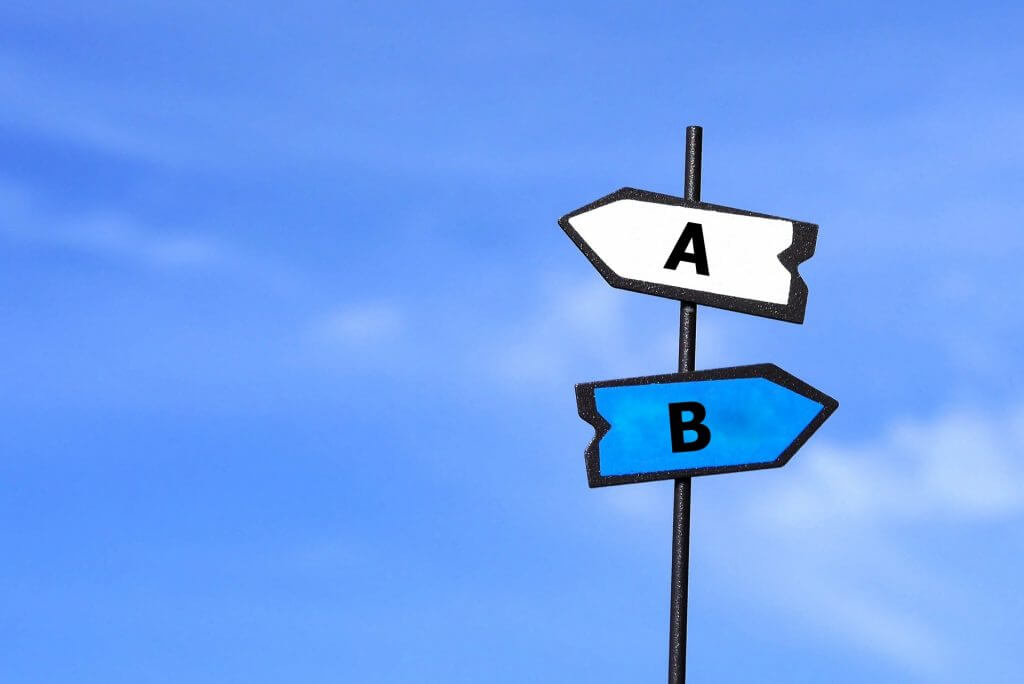
RPAツールを検討する際に着目しておきたいのは、「コスト」「導入規模」「業務範囲」「セキュリティー」といった面です。
新しいツールを導入する際にネックになりがちなのは、コスト面でしょう。その点、RPAツールは昨今クラウド型での提供が普及しており、比較的安価な料金体系で導入できるようになっています。また、中には無料で活用できるものもあります。
導入規模で言うなら、1台のデスクトップパソコンから導入できるオンプレミス型やクラウド型、集中管理が可能なサーバ型といった選択肢があります。また、業務内容が特殊だったり広範囲にわたったりする場合、カスタマイズをしたい場合などは、サーバ型を選ぶことになるかもしれませんが、開発工数や費用が跳ね上がることも念頭におく必要があるでしょう。
こういった点を踏まえた上で、自社にとって最適なものを選択していくことが大切です。現在は数多くのRPAツールが存在しているため、上記のようなポイントを踏まえてしっかりと比較検討しなければ、「せっかくRPAを導入したのに業務効率化につなげられていない」といった事態を招く可能性も否めません。
また、どれだけ優秀な機能を備えているRPAツールでも、そのツールをしっかりと使いこなせる人材がいなければ宝の持ち腐れとなってしまうでしょう。したがって、RPAを導入する業務に携わる担当者とのコミュニケーションなども大切にしなければなりません。

MM総研が2020年1月に発表したRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)国内利用動向調査によれば、RPAを導入している企業の約半数が、2つ以上の製品を使用しているといいます。そして、その理由として最も多かったのは、「比較検討・テスト(36%)」というものでした。つまり、多くの企業は複数のRPAを使いながら「自社にとって最適なRPAを見極めている」ということです。
もちろん、すべての企業が比較検討を目的に複数のRPAを導入しているわけではありません。「互換性・使い分け」といった理由で複数導入している企業も27%存在し、「安定稼働・リスク分散」といった理由で複数導入している企業も17%存在しています。
そのため、必ずしも初めから1つのRPAに絞り込む必要はなく、必要に応じて複数のRPAを使い分けたり、比較検討の期間を設けたりしながら、自社にとって最適なスタイルを見出していくのがベストといえるのではないでしょうか。
ちなみに、RPA導入企業に今後の利用方針を質問したアンケート部門では、約80%が「利用拡大に前向き」と答えたそうです。反対に、利用中止などといった後ろ向きの回答を行った企業は約2%と非常に低くなっています。この回答を踏まえると、多くの企業はRPAを導入したことが「プラス」になっていると考えられるでしょう。今後は、さらに多くの企業がRPAを活用するようになるかもしれません。
もちろん、RPAを最大限活用するには「予算」や「業務プロセス」といった課題をクリアしなければなりませんが、それ以上にRPA人材をしっかりと整えることが重要になります。いかにしてRPA人材の不足を補っていくかという点も、重要なポイントになるかもしれません。
今回は、RPAツールの市場シェアについてご紹介しました。大企業を中心に、中小企業でもRPAの導入が増加していく可能性が高いことがお分かりいただけたのではないでしょうか。
また、RPAを導入している企業の50%が、業務自動化の適用範囲を広げるための取り組みとしてAI-OCRを導入検討しているというデータもあります。ERP(Enterprise Resource Planning)と組み合わせて効率化を図っている企業も少なくありません。そのため、今後はさらに「AIによる自動化」が重要な役割を担っていくことになるでしょう。
昨今はRPAの数も豊富であり、多くの企業がRPAの開発・提供を行っている状況です。ぜひこの機会にRPAの導入、そしてAI-OCRをはじめとするAI製品の導入も検討してみてはいかがでしょうか。
AIについて詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
AI・人工知能とは?定義・歴史・種類・仕組みから事例まで徹底解説
業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。
メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。
AI製品・ソリューションの掲載を
希望される企業様はこちら