生成AI
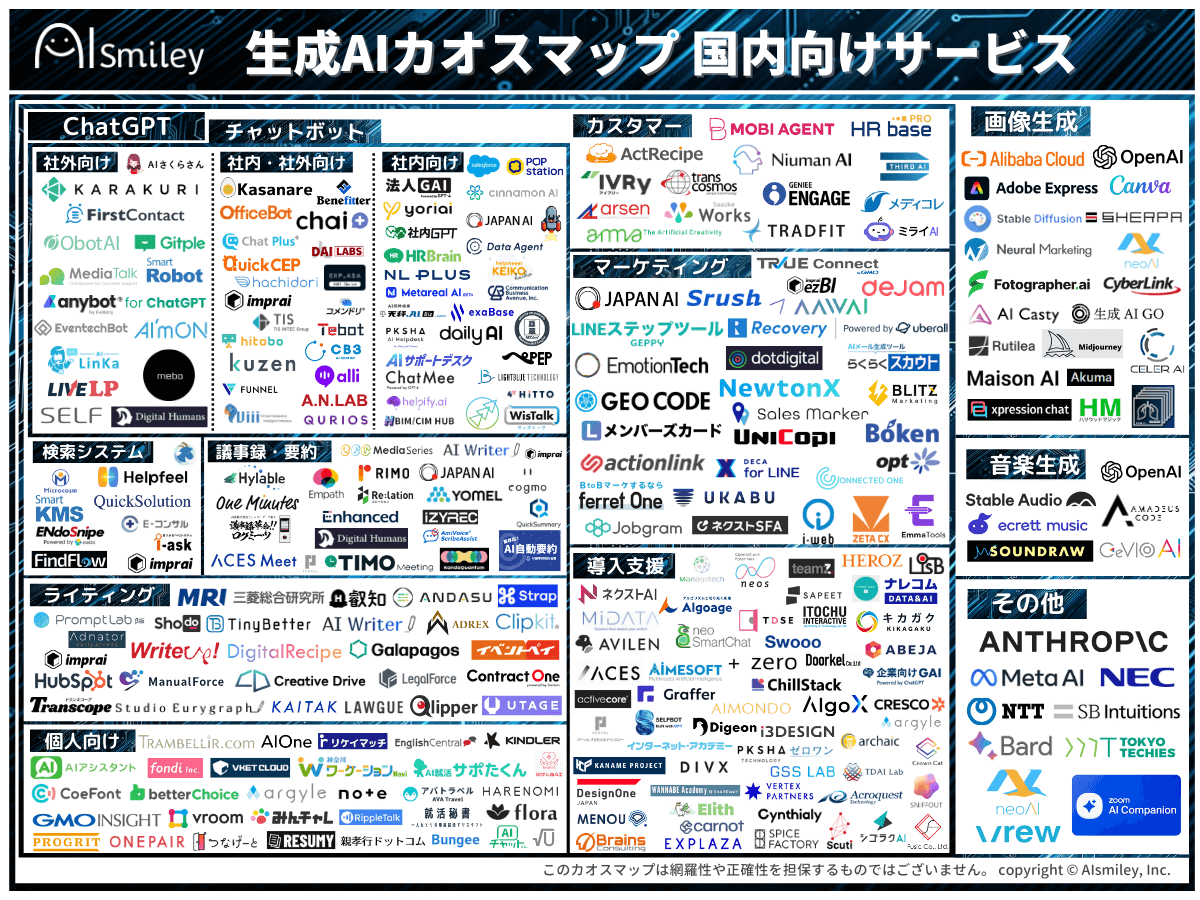
最終更新日:2024/02/22
 AIで農業を自動化!
AIで農業を自動化!
これまでの農業においては、人の力に頼る場面が大半を占めている状況でした。もちろん、トラクターなどの機械を活用することで効率化を図ることもできていましたが、あくまでも作業の極一部でしかなく、作業の自動化にはつなげられていなかったのです。
しかし、近年はAIを導入するケースが多くなってきており、農業においても「自動化」が現実的に可能になり始めています。具体的にどのような技術を用いることで、自動化が実現されているのでしょうか。今回は、農業の自動化を加速させるAIの仕組みについて詳しくご紹介していきます。
AIの活用事例について詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
AI・人工知能の利用例を解説!機械学習を活用した身の回りの実用例

近年注目され始めているのは、農業において特に負担の大きい「収穫」や「仕分け」といった作業の自動化を図るAIです。そのAIが注目を集めるきっかけとなったのは、静岡県湖西市の農家、小池誠氏のAIを活用した取り組みでした。
小池氏は、もともと自動車部品メーカーでソフトウェアエンジニアとして勤めていた経歴の持ち主であり、その経験を活かしてキュウリの仕分けを行う機械を自作したといいます。ここで注目すべきなのは、この機械にAIが搭載されているという点です。ディープラーニングによる画像認識技術を用いることによって、本来であれば膨大な時間が必要となるキュウリの仕分け作業を自動で選別できるようになったのです。
その仕組みとしては、はじめにベテランが仕分けたキュウリの画像を教師データとしてAIに学習させ、AIがキュウリの等級を見分けていくというもの。使い方も非常にシンプルで、アクリル板の上にキュウリを乗せるとカメラが自動で撮影を行い、その画像データから「長さ」「太さ」「曲がり具合」などを解析して出荷基準を満たすか判別していきます。
はじめから高い精度で見分けられたわけではないそうですが、改良を重ねることで8割程度の正答率まで高めることができたといいます。最終的な選別は小池氏が行っているため、あくまでもサポート役という位置付けではありますが、このAIを導入したことによって作業効率は4割ほど高まっているそうです。
蓄積するデータの量が増えるにつれて判別の精度も高めていくことができますから、今後さらにこのAIの正答率も高まっていくでしょう。

一見、農業の作業はシンプルな作業ばかりのように思えるかもしれませんが、熟練の技が求められる部分も数多く存在するといいます。収穫前に「あと何日くらいでベストな収穫時期に達するか」を見極めるためには、視覚や触覚を駆使していかなければなりません。当然、その判断基準となるものは経験によって培われていくものであるため、新規就農者にとっては大きなハードルとなってしまうのです。
こういった点が大きな壁となり、離職してしまう若手が増えてしまえば、農家としても大きなダメージとなります。だからこそ、経験が求められる作業をいかにスムーズに行えるようになるかが、農家にとっては大きな課題となっていたわけです。そのため、小池氏が開発したAIは、まさにその大きなハードルを取り除くことができる手段のひとつといえるでしょう。ベテランが仕分けた画像をAIに学習させることで、「経験が求められる判断」のサポートを行えるようになるため、経験が浅い人でも効率的に作業を進められるようになるからです。
特に近年は、少子高齢化に伴う人手不足が深刻化しているため、このような形で未経験者がスムーズに業務へと溶け込める環境を整えていくことは、大きな価値があるといえるのではないでしょうか。

小池氏は、仕分け作業だけでなく別の作業にもAIを活用していく予定だといいます。現在検討されているのは、キュウリ収穫の見落としを減らすことを目的としたAIです。そもそもキュウリは傷みやすい野菜のため、収穫時期としてベストなのは数日間しかないといわれています。また、キュウリは葉や茎と色が同じということもあり、どうしても1割程度は見逃してしまうことがあったそうです。
そのため、カメラで撮影した農場の映像をAIが分析し、キュウリの位置を正確に把握するシステムの開発を進めているといいます。このシステムの開発に成功し、実用化された場合、仮に見逃しているキュウリがある場合にはアラートで知らせてもらうことが可能になるため、確実にキュウリを収穫できるようになるのです。
これまでは、収穫後に再度見回りをするなどしてキュウリの見落としを確認する必要がありました。その方法でも収穫忘れを防ぐことはできるかもしれませんが、やはり効率的とはいえません。その点、AIを活用すればより効率的に収穫忘れを防げるようになりますので、人手不足が課題となっている農家にとっては特に大きなメリットといえるのではないでしょうか。
農業においてもAIを活用する余地があることがお分かりいただけたかと思いますが、農業ならではの注意点があるのも事実です。農業の場合、品種や季節、栽培の方法などで作物の形は大きく異なるため、それらを踏まえた上で柔軟に対応していかなければなりません。そのため、最低でも1年間分のデータを収集した上で、季節に応じた適切な方法を導き出していく必要があるでしょう。
ディープラーニングを最大限活用するためには質の高いデータが必要不可欠ですが、完璧と呼べるレベルの精度を出すことは決して簡単ではなく、手間もかかります。しかし、小池氏は必ずしも完璧を目指す必要はないという考えのもと、AIの開発を行っているそうです。それは、小池氏自身が開発したAIが7〜8割ほどの精度であったものの、作業効率の向上を実現できたからに他なりません。
そして何より、質の高いデータの収集という問題は「時間」が解決してくれるものでもあるため、7〜8割ほどの精度の状態から実用化を始め、データの蓄積を進めていくという方法は極めて合理的なものといえるのではないでしょうか。
多くの農家が人手不足を課題としている昨今において、AIの導入・活用は大きな可能性を秘めていることがお分かりいただけたかと思います。今後、どのような形でAIが農家をサポートしていくのか、ますます目が離せません。
AIについて詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
AI・人工知能とは?定義・歴史・種類・仕組みから事例まで徹底解説
業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。
メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。
AI製品・ソリューションの掲載を
希望される企業様はこちら