生成AI

最終更新日:2024/04/04

AI・人工知能の技術は急速に発展を続けており、医療や農業、防犯などといったさまざまな業界での導入も進んでいる状況です。そんな中、AIを活用したユニークなサービスを提供する企業も増えてきており、ますますAIが身近な存在へとなりつつあります。
そんなAIを活用したサービスの中でも、特に注目を集めているもののひとつに、J.scoreが提供している「AIスコア」が挙げられるでしょう。この「AIスコア」は、ユーザー個人の可能性をスコア化(診断)し、提示するというサービスです。
では、この「AIスコア」を活用するとどのような「可能性」を可視化することができるのでしょうか。今回は、可能性の診断を行うことができるJ.scoreの「AIスコア」について詳しくみていきましょう。
AIの活用事例について詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
AI・人工知能の利用例を解説!機械学習を活用した身の回りの実用例
冒頭でもご紹介したように、AIスコアとは、ユーザー個人の可能性や信用力をスコア化し、提示できるサービスのことです。日本ではまだあまり馴染みがないため、具体的なイメージが湧かない方も多いかもしれません。しかし、アメリカや中国などの海外ではすでにAIスコアが日常生活に定着しており、そのスコアを活用したさまざまなサービスも展開されている状況なのです。
たとえば中国では、スコアが高い人に対してホテルを優遇するサービスが存在していたり、ビザ取得の優遇措置が設けられていたりします。また、シェアリングサービスにおけるデポジットの免除やスマホの無料バッテリー貸し出しなど、さまざまなサービスが設けられている状況です。
このように、海外ではすでに一般的となりつつあるAIスコアですが、日本でも本格的に導入され始める可能性が高まっています。2019年頃からはテレビCMやインターネット広告などでも頻繁にAIスコアが流れるようになり、注目度も高まりつつあるのです。
そんなAIスコアは、FinTechの代表的なサービスのひとつと言っても過言ではありません。FinTechとは、Finance(金融)とTechnology(技術)という2つの単語を組み合わせた造語です。その名前の通り、金融サービスと情報技術を結びつけた革新的な動きのことを指します。ブロックチェーン技術を用いた仮想通貨や、スマホを活用した送金サービスなどは、まさにこのFinTechに該当するわけです。
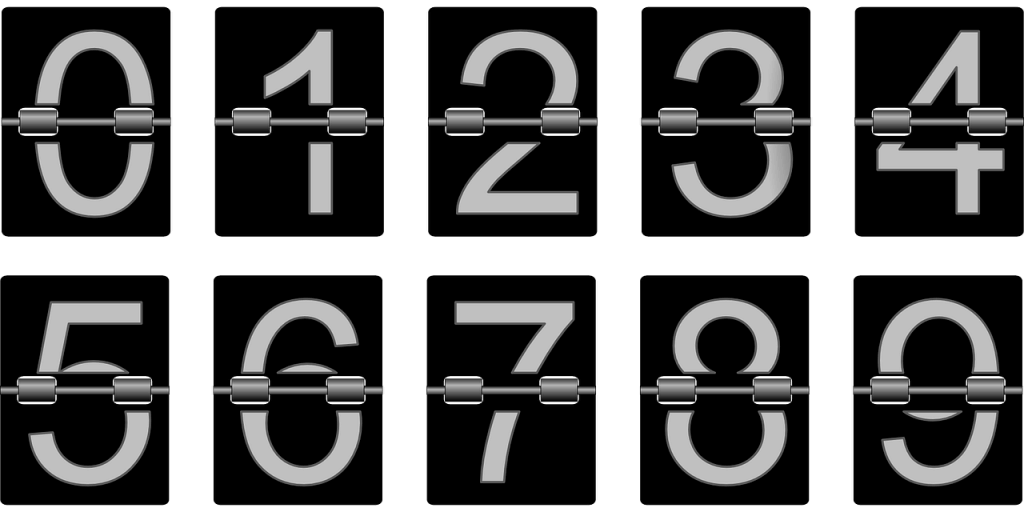
冒頭でもご紹介したように、「AIスコア」というのはJ.scoreが提供している「ユーザーの可能性をスコア化するサービス」です。そのスコア化は、ビッグデータとAIの活用によって行われます。AIによる高い精度での分析が可能ということもあり、ユーザーの可能性は1000点満点でスコア化されます。そのため、ユーザー一人ひとりの診断結果も大きく異なり、より自身の本質に迫った診断結果が得られるといえるでしょう。
この「AIスコア」では、算出を行うために、「性別」「学歴」「職種」「年収」「結婚の有無」といった一般的な情報の入力を行います。ただ、特徴的なのはこういった一般情報だけでなく、「自身の性格」「ライフスタイル」といった、よりパーソナルな情報の入力も行っていくという点です。こういった細かな情報まで提供していくからこそ、分析の精度を高めることができているともいえるでしょう。ただし、本名や住所などといった個人を特定できてしまう情報の入力は必要ありませんので、その点は心配無用です。
ちなみに、この「AIスコア」を提供しているJ.scoreは、みずほ銀行とソフトバンクの2社によって設立されたFintechベンチャーで、AIに関する専門知識を持ち合わせたメンバーによって開発されました。そのような点からも、スコアの信頼度は高いといえるのではないでしょうか。また、診断にかかる時間も最短2分と非常に短く、その手軽さも評価されているポイントのひとつです。
では、具体的にどうやってAIスコア診断を行なっていくのか、その方法についてみていきましょう。

ユーザーの可能性をスコア化する「AIスコア診断」は、パソコンはもちろんのことスマホでも手軽に行えます。ただし、AIスコア診断を行うためにはJ.scoreのアカウントが必要になりますので、まずはアカウントの作成を行いましょう。
アカウントを作成し、ログインすると、「AIスコア診断」の画面が表示されます。この画面はチャット形式になっているため、相手の質問に答えていくような形で入力していけば問題ありません。ここで用意されている質問は18個ほどで、「生年月日」「性別」「職業」「入社年」「学歴」「年収」といった項目です。数字を入力する必要がある項目は自身で入力しなければなりませんが、それ以外はすべて選択肢から選ぶ形式になっているため、スムーズに入力を進めていくことができるでしょう。
そして、これらの項目の入力が完了したら、現在のスコアが1000点満点方式で表示されます。ここで「レンディング」をクリック(タップ)すると、そのスコアに応じた「融資額の目安」を知ることが可能です。
一般的に銀行などの金融機関から融資を受ける場合、審査の内容を知ることはできず、自身の職業や年収などが、どのように審査結果に反映されているのかを知ることはできません。その点、この「レンディング」を活用すれば、自分自身の個人情報を明かさずに、自身の「社会的信用度」を客観的に把握することができるのです。
しかし、AIスコア診断の機能はこれだけではありません。というのも、そもそもこの段階で入力が完了しているのは全体の5%ほどに過ぎないからです。
そのため、ここからさらに詳細な情報を入力していくことで、より詳細なスコアを知ることができるようになります。もちろん、18問ほどの質問からでも大まかなスコアリングは可能ですが、これだけの質問では詳細なスコアリングはできません。そのため、時間に余裕がある方はぜひ詳細な質問項目への回答も行ってみてください。
ちなみに、追加で行われる質問の項目としては、ショッピングを行う際に「デザイン」「価格」「ブランド」のどれを重視するかという質問や、所有しているゲーム機の種類やプレイ時間、車やバイクの所有台数など、非常に具体的なものもあります。
これらの質問がスコアにどう影響するのかは明記されていませんが、質問に回答していくごとにスコアにも少しずつ変化が生まれるので、その変化を楽しみながら質問への回答を行っていくのも良いのではないでしょうか。
ちなみに、詳しい情報を任意で追加入力すれば、スコアが変化し、場合によっては数値が上昇する可能性もあります。18問ほどの質問に答えた段階では、まだ全体の5%ほどに過ぎませんので、より詳しい情報を入力して数値を高めていくのもひとつの手段といえるでしょう。
「スコアアップ」のページを開くと、「生活」「性格」「ウォレット」「ファイナンス」「プロフィール」「情報連携」という6つのジャンルが表示されます。数値を上昇させたい場合には、これらのジャンルの質問にもより詳しく回答してみましょう。
もちろん、人間は常に変化し続ける生き物であり、成長していく生き物ですから、診断をするたびにスコアが変化する可能性もあります。先ほどご紹介した質問項目の「車やバイクの所有台数」「ショッピングのこだわり」なども、少しずつ変化していくことは決して珍しくありません。
そのため、AIスコアでは「スコアヒストリー」という形で、自分自身のスコア変動をグラフで確かめることができるようになっています。「昨日できなかったことが、今日できるようになった」ということは日常的に起きることであり、その都度スコアも変化していくということなのです。まさに、自身の成長をリアルタイムで可視化できるツールといえるのではないでしょうか。
多くの方は、「自分のことは自分がいちばん理解している」といった考えをお持ちかもしれませんが、自身を客観的に判断できているかどうかは分かりません。だからこそ、AIスコアのようなツールを活用して「自分自身を客観的に見つめ直すこと」には大きな価値があるといえます。わずか2分の診断で自分自身の可能性をスコア化することができますから、ぜひこの機会にAIスコアを活用してみてください。そのスコアは、自己実現やキャリアアップにも役立てていくことができるはずです。
ちなみに今回ご紹介した「J.score」は、国内外のデータ解析コンペティションにおいて入賞した実績を持つ、極めて優秀なメンバーによって独自のAIスコアとして創り上げられています。
日本ではまだ馴染みがないため、「質問に答えただけで信頼できる数値が算出されるのだろうか」といった疑問を持たれている方もいらっしゃるかもしれませんが、海外では実用化が進んでいる国もあるほどなので、ぜひこの機会に目を向けてみてはいかがでしょうか。
AIについて詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
AI・人工知能とは?定義・歴史・種類・仕組みから事例まで徹底解説
業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。
メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。
AI製品・ソリューションの掲載を
希望される企業様はこちら