生成AI

最終更新日:2024/04/04

近年、さまざまな分野の企業がAI・人工知能を導入しており、これまでAIとは関連性が薄いように思えた業界でもAIを活用するケースが増えている状況です。そんな中、AIの活用によって工場のスマート化を図る事例も増えてきているのをご存知でしょうか。
工場内での作業が少しずつ機械化されてきているというイメージをお持ちの方は多いかもしれませんが、最近ではAIによって「予知保全」を行う工場も増えてきているのです。では、この「予知保全」とは一体どのようなものなのでしょうか。今回は、予知保全について詳しく解説していくとともに、予知保全を行っている企業の事例についてもご紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
予知保全について詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
予知保全とは?予防保全との違いやメリットとおすすめサービスを紹介
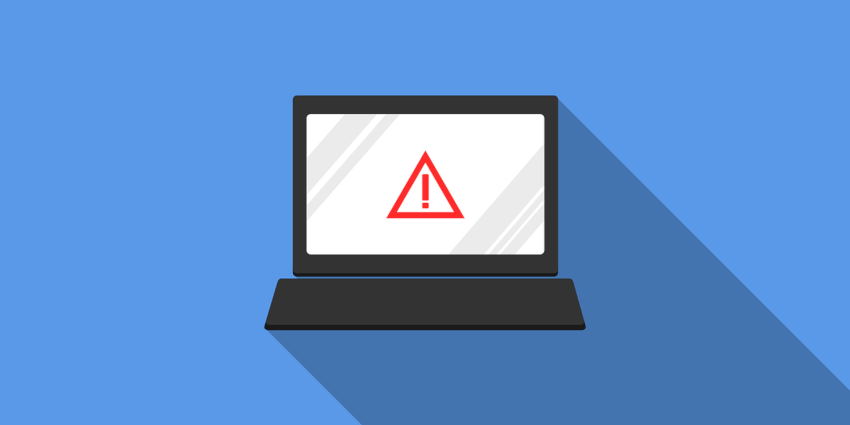
「予知保全」という文字から何となくの意味は理解できる方も多いかと思いますが、具体的に予知保全がどのようなものなのかご存知ではない方も多いでしょう。予知保全とは、工場にある機械や設備の故障を予知し、その機械や設備を最適な状態で管理することを指します。「予防保全」という言葉もあり、混同されている方もいらっしゃるかもしれませんが、予知保全と予防保全は少し異なります。
これら2つの大きな違いは、「保全のタイミング」です。予防保全の場合、自分自身やメーカーの経験をもとに「これくらい使用すると壊れる可能性がある」といった線引きを行い、大まかな使用回数や使用時間を設定して部品交換などの保全を行います。一方の予知保全は、「壊れる可能性がある」という兆候が出た段階で保全することによって事故を防ぐのです。
どちらも故障する前に保全するという意味では同じなので、これら2つを混同してしまう方もいるわけですが、予防保全の場合には「他と比べて調子が悪い部品」などには対応できないという弱みがあります。調子の悪い部品であれば、あらかじめ設定されていた交換タイミングよりも早く壊れてしまう可能性も否めません。また、それとは逆に、まだまだ使える部品であるにも関わらず「交換タイミングに達しているから」という判断で交換しなければならないケースも出てくるでしょう。
その点、予知保全であれば、仮に調子の悪い部品があったとしても「壊れそう」というタイミングで交換することができますし、予防保全では交換タイミングに達していた部品でも「まだまだ問題なく使える」といった判断を下すこともできるわけです。
このような点を踏まえると、予知保全のほうが多くのメリットを持っていることがお分かりいただけるかと思いますが、その分難易度は高くなる方法といえるでしょう。予知保全を行うためには、故障の傾向を的確に察知する「技術」と「経験」が求められるからです。そのため、予知保全システムの構築に着手しても、検討や開発の段階で躓いてしまうケースは決して少なくありません。
せっかく予知保全による業務効率化を目指していても、その予知保全システムが適切に動作しなければ意味がありません。したがって、予知保全システムの構築を行う場合には、適切な形でデータを計測し、そのデータを有効活用していく力が求められるでしょう。
ここまで、予知保全がどのようなものであり、予防保全とは何が違うのかをご紹介してきました。ここからは、実際に予知保全を導入している企業の事例をいくつかご紹介していきます。
産業用液晶ディスプレイや車載用液晶ディスプレイの開発、製造、販売を行っているメルコ・ディスプレイ・テクノロジー株式会社では、ドライポンプモータの予知保全を行うために、三菱電機株式会社が提供している汎用シーケンサ「MELSEC-Qシリーズ」用電力計測ユニットを導入しています。このユニットを導入したことによって、電流の変化からモータの故障を事前察知することができるようになりました。これまで、モータが故障した場合には修理に膨大な費用がかかってしまっていましたが、この予知保全によって故障する前にメンテナンスを行えるようになったそうです。また、コスト面だけでなく生産管理や予算管理といった部分においても効果を発揮し始めているといいます。

電気機器の製造や販売、開発などを行っている株式会社竹中電気では、予知保全によって切削工具の交換頻度を減少させるための加工異常検出装置を提供しています。この装置を工作機械に導入することによって、加工負荷時の状況が波形で確認できるようになり、ワークの加工不良を検出することが可能になるそうです。また、ツールの消耗具合を検出し、適正な交換タイミングを確認することもできるといいます。
なお、この加工異常検出装置による効果が確認できた事例として、機械1台あたりの不良ワーク数が月200個だったものが月20個までに減少し、90%の品質・生産性アップを実現したケースがあるそうです。また、これまで年間の刃具経費が1億円かかっていたところを3300万円にまで削減でき、約60%のコストダウンを実現したという例もあるといいます。
予知保全は工場内のトラブルを未然に防ぐ上で極めて大きな役割を果たしていることがお分かりいただけたのではないでしょうか。工場の生産性を高める上で、もはやAIを活用した予知保全によるスマート化は必要不可欠なものと言っても過言ではないかもしれません。
しかし、予知保全に関する知識を持たずに自動化システムの構築を進めていっても、効果的に予知保全を行えるシステムを作り上げることは難しいでしょう。そのため、予知保全システムの導入を検討していく際には、まず予知保全に関連する知識をしっかりと身につけていくことが大切になります。
対象や目的を明確にしないまま予知保全システムの構築を進めてしまうと、理想的な形で予知保全を行うことができず、システムの構築コストが全て無駄になってしまう可能性も否めません。そのような事態を避けるためにも、まずはAIやIoTに関する知識を深め、より適切な形でデータ計測を行っていく体制を整えていくことが大切なのです。ぜひ、明確なビジョンと的確な戦略を持った上で、予知保全システムの構築を行ってみてはいかがでしょうか。
AIソリューションについて詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
AIソリューションの種類と事例を一覧に比較・紹介!
AIについて詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
AI・人工知能とは?定義・歴史・種類・仕組みから事例まで徹底解説
業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。
メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。
AI製品・ソリューションの掲載を
希望される企業様はこちら