生成AI
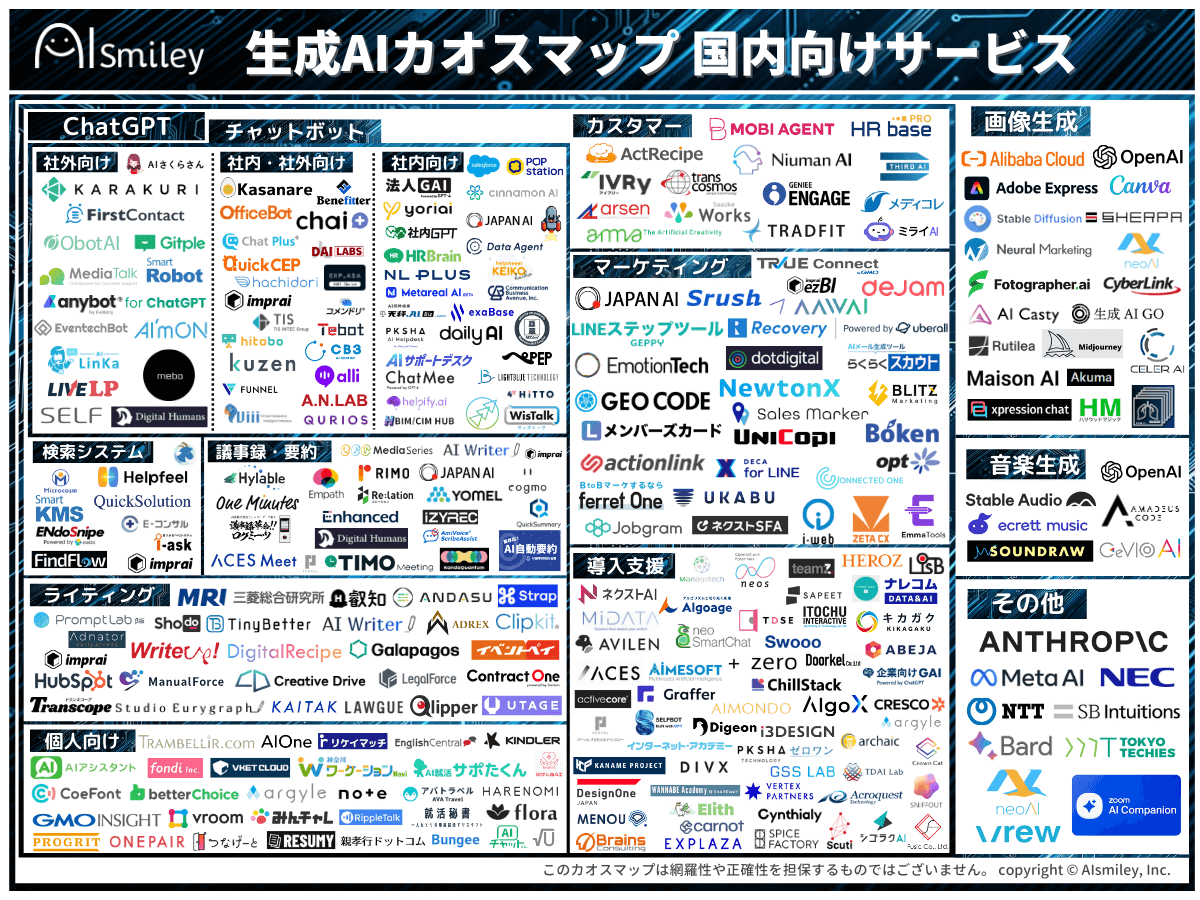
最終更新日:2024/04/03

いちユーザーとしてWebサイトを利用しているとき、クーポンや広告が表示されて、正直「うざいな」と思ってしまうことはありませんか?もしかしたら、あなたのサイトもユーザーから同じように思われているかも?「うざい」と思われないために、WEB接客を企画するマーケ担当者が気をつけるべきポイントについて見ていきましょう。
WEB接客について詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
WEB接客ツールはECサイト以外でも使える!活用法とツールの種類を紹介

少し前の調査になりますが、2014年にインターネット広告代理店のオプトとグルーバーがスマートフォン・タブレットをふだん使用している20~69歳の男女1,000人を対象に実施した調査では、「スマートフォン上の広告は邪魔なものが多い」と回答した人が8割にも上っています。2015年には、iOSのアップデートにより「広告ブロック」の設定が簡単になったことが話題を呼びました。広告ブロックツールが急成長していることからも、「ウェブ閲覧を邪魔しないでくれ」というユーザーの思いは強固だといえます。一方、WEB接客の基本は「おもてなし」。おもてなしですから、ユーザーに対して心地よいWEB体験を提供するのが目的です。ウェブ閲覧画面にのさばる広告との決定的な違いはここにあります。

しかし、「おもてなし」のはずなのに、Web接客ツールを導入したことで「うざい」と思われてしまう理由はどこにあるのでしょうか。それは、ユーザー目線を失っているから。企業側としては「離脱防止」「コンバージョン率改善」などを目的にWEB接客を導入するわけですが、正直サイトを利用するユーザー側にとっては「知らんがな」でしょう。「離脱防止」「コンバージョン率改善」はあくまで企業側の指標であって、ユーザー側の目的ではありません。とくに、ユーザーに能動的に訴求する「ポップアップ型」のWEB接客ほど、「うざい」と思われるケースが多いようです。具体的には以下のようなものがあります。
・タイミングが合わない
・興味がない内容が表示される
・頼んでもいないのに表示される
・いつも同じ内容が表示される
例えば「タイミングが合わない」というもの。サイトにアクセスするやいなや「SNSにイイね!してね」という内容のポップアップが出てきたらどうでしょうか。「見ず知らずのお店(サイト)に足を踏み入れただけでイイね!を強要された!怖い!」と感じる人が多いのではないでしょうか。これがおなじみのお店(サイト)なら「何度も購入しているし、SNSも見てみようかな」と感じるかもしれません。このように、同じ訴求内容でも、ユーザーとの関係性や訴求するタイミングによって受け取り方が変わってくるのです。
一方、「興味がない」「頼んでいない」と感じられてしまうのは、訴求すべきユーザーのセグメントを誤っているからです。例えば、「ちょっと見るだけ」のつもりでサイトにアクセスしたのに、「1万円以上でキャッシュバック!」といったポップアップが何回も表示されたらどうでしょうか。「1万円以上も買うつもりないのに……」と不満に感じる人が多いのではないでしょうか。これがもし、あとちょっとで1万円に達しそうなユーザーに対して「1万円以上でキャッシュバック!」と表示したら、キャッシュバックを受けるための「ついで買い」を誘発できるかもしれません。
さらに、「いつも同じ内容が表示される」のは、情報の鮮度が古いからです。こまめにPDCAを回さずに同じ情報ばかり使い回していると、ユーザーに飽きられてしまいます。表示内容は日々見直すべきでしょう。
このように、WEB接客で「うざい」と思われるポイントは、実店舗での接客にも通じるところがあります。ただ、実店舗ではユーザーの表情や雰囲気から判断できるのに対し、顔が見えないWEB上の「おもてなし」はさらに難易度が高いといえます。「ユーザーのセグメント」「タイミング」「内容」「情報の鮮度」に留意して、ユーザーが心地よく感じる導線づくりを心がけましょう。
チャットボットについて詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
チャットボットとは?意味やメリット、活用事例を徹底紹介
業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。
メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。
AI製品・ソリューションの掲載を
希望される企業様はこちら