生成AI

最終更新日:2024/03/04
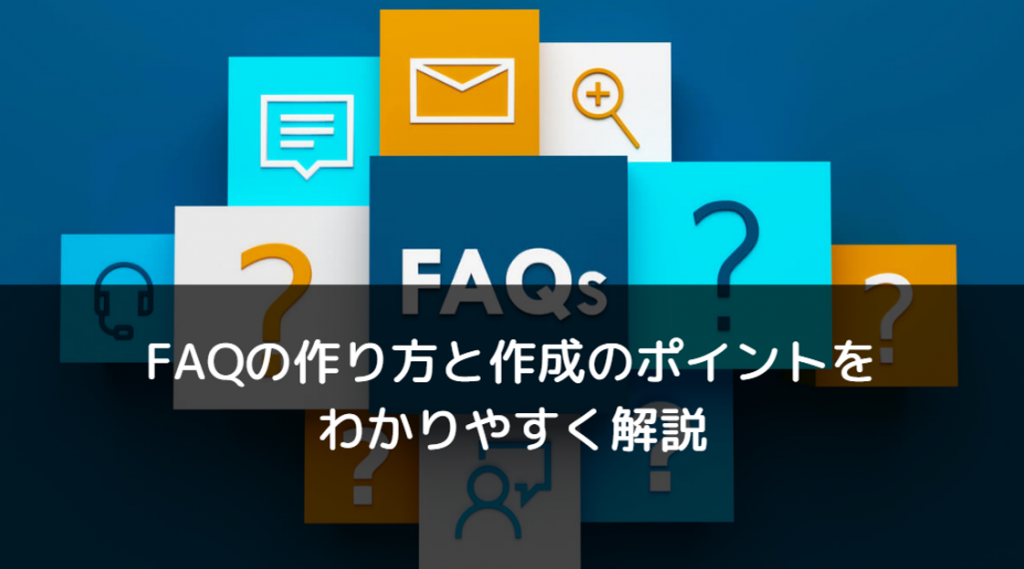 FAQの作り方を解説
FAQの作り方を解説
コールセンターやコンタクトセンター、また社内向けのヘルプデスク業務における施策として、FAQを導入する企業が増えてきました。このFAQの導入によって、カスタマーサービス部門などの業務効率化にもつながり、顧客の利便性向上も期待できます。
本記事では、FAQの概要や導入するメリット、具体的な作り方などについて解説します。FAQの導入を検討している企業、また業務効率化と業務品質向上を同時に実現したいと考えている企業はぜひ参考にしてください。

FAQとは、「Frequently Asked Questions」の略であり、日本語では「頻繁に尋ねられる質問」を意味します。企業のWebサイトやECサイトなどに設置されている「よくある質問」がそれに該当します。
FAQは、頻繫に寄せられる質問と回答がセットで掲載されているのが特徴で、顧客など外部向けのもの、また社内の従業員を対象にした内部向けのFAQがあります。
FAQと混同されやすいものにQ&A(Question and Answer)がありますが、大きな違いはよくある質問をピックアップして掲載しているかどうかです。簡単に言えば、FAQは、Q&Aの中でも、特に寄せられる頻度が高い質問と答えを抽出したものになります。
FAQをWebサイトに導入することによって、どのようなメリットが得られるのでしょうか。ここからはFAQを作るメリットについて詳しくみていきましょう。

FAQを導入することで、日々寄せられる電話での問い合わせ件数を削減できます。これまで、ユーザーからの問い合わせは、「電話」と「メール」に限られていました。ただ、メールでは、一般的に回答を得るまでに時間を要することから、コールセンターへの電話での問い合わせが集中してしまうケースが多々ありました。
コールセンターに問い合わせが集中すれば、オペレーターの負担が増します。その結果、対応のクオリティにも悪影響を及ぼし、顧客の満足度低下を招いてしまうおそれが考えられます。
その点、FAQを導入し、あらかじめ、よくある質問と回答を示しておけば、顧客からの問い合わせ件数を削減させられます。オペレーターは、FAQでは解決できなかった顧客の問い合わせだけに対応すれば良いため、負担軽減につながるのです。
加えて、コストを削減できることもメリットに挙げられます。FAQを設置すれば、ユーザーは自身が知りたい情報をFAQから取得できるため、有人対応のリソースを減らすことができます。その結果、従来よりも少ない人員で業務を遂行できる環境が整い、コストダウンにもつながります。
FAQの設置によって「頻繁に寄せられる質問に回答していく」という定型的な業務が削減できれば、オペレーターの負担も軽減し、よりひとつひとつの問い合わせに対して丁寧な対応を行えます。
一人ひとりに丁寧な対応を行うことで、顧客の企業に対するイメージアップが期待でき、その結果、長期的な企業ブランディングの面でも大きなメリットが得られます。

FAQページを設置し、顧客がそのページの存在を認識すれば、FAQページへのアクセス数の増加が期待できます。結果的にWebサイト全体のPV数が増加し、直帰率の低下につながるため、SEO施策(検索エンジン対策)としても有効です。
自社のWebサイトが検索エンジンの上位に表示されれば、より多くのユーザーの目に触れるため、新規顧客の獲得にもつながります。
FAQを導入すれば、問い合わせ担当者同士、あるいは他部署のスタッフとの知識共有も行いやすくなります。過去に寄せられた問い合わせ内容や対応履歴を自社サイトに蓄積していくことによって、知識のないスタッフでも蓄積された情報を活用できるようになるためです。
また、こうした仕組みを構築しておけば、「ベテランの退職によって難しい問い合わせに対応できる人がいなくなってしまう」といった事態も避けられます。あらゆる問い合わせ担当者がスムーズかつ安心して実務を行うためにも、FAQでの情報の蓄積には大きな価値があります。
FAQを作成してスムーズに運用へつなげるため、正しい作り方や手順を把握しておきましょう。
まずは、FAQに記載する質問を洗い出します。過去の問い合わせ履歴などを保存しているのなら、そこからも頻繁に寄せられている質問を抽出しましょう。また、メールやチャットでやり取りをした記録、電話の録音内容、Webフォームから寄せられた質問なども集めます。
質問を集める際には、あらかじめ寄せられそうな質問を予測しつつ洗い出すのも有効です。説明書や仕様書の内容をチェックしたり、実際に製品やサービスを使用したりして、疑問に思う点を事前にまとめておくのも良い方法です。
なお、問い合わせ履歴はFAQの導入後最適化にも役立つ重要な情報です。コールリーズン分析やVOC分析にも活用でき、FAQの最適化やオペレーターの効率的な育成にもつながります。もし、問い合わせ履歴を収集、蓄積できる仕組みがない場合は、その構築も併せて検討しましょう。
質問を収集する際に、企業によっては、膨大な情報が集まるかもしれません。それらをすべてFAQに反映させるのは現実的ではないうえに、ユーザーが使いにくいものに仕上がってしまうおそれもあります。
次のステップでは収集した情報の取捨選択や優先順位づけを行います。この作業を丁寧に行うことで、ユーザーに有益であり、なおかつ従業員の負担軽減にもつながる優れたFAQの構築が可能です。
情報を取捨選択する際には、ABC分析の活用が有効です。ABC分析は重点分析とも呼ばれる手法で、複数の指標に対し優先度や重要度を評価します。
FAQに掲載する質問を抽出したら、回答作りのための情報を収集します。マニュアルやカタログ、仕様書、Webサイトなどから、正しい情報を集めましょう。
なおFAQに提示する回答は、専門的かつ具体的であったほうが、ユーザーの満足度は高まります。そのため、回答情報を集める際には、FAQ作成担当者のみならず、他の関係部署と協業し、できるだけ広範的に集めるようにします。
こうした社内のコミュニケーションは、運用後FAQをブラッシュアップするためにも重要になってきます。適宜情報のやり取りや共有を行うことで、変更が必要な場合もスピーディーに対応できます。
FAQを作成する前に、レギュレーションを作りましょう。レギュレーションとは、守るべき規則や統一すべき表現、また禁止事項などをまとめたものです。チームでFAQを運用するケースでは、レギュレーションを決めておかないと文章表現や呼称、用語などが不統一のまま表記され、結果として、ユーザーが混乱してしまうことも予想されます。実際にFAQを作り込む前に、レギュレーションを整備し表現を統一する必要があります。
特に、専門用語に関するレギュレーションは重要です。素人には分かりにくい専門用語を多用することは、ユーザーに親切とは言えません。また、FAQでは解決できず、結局窓口へ電話する、といったことも起こり得ます。レギュレーションとして、あらかじめ専門用語の代替表現を用意しておけば、分かりやすいFAQを作ることができ、また導入後の業務効率化にもつながるわけです。
レギュレーションを踏まえながら、FAQを作成していきます。一般的に、FAQは質問文と回答文がセットになっており、また、補足として関連するFAQを表示するケースもあります。
FAQに誤った回答や必要な情報の漏れは、クレームにつながることもあります。そうしたことを防ぐため、回答については、それぞれ関係する部署の人間に作成を依頼するのも良い方法です。
FAQの作成後は、必ず、複数人で最終チェックを行いましょう。複数人によるチェックで、回答に間違いや漏れがないかをしっかり確認できます。また、FAQは作成して公開すれば、お終いではありません。公開後も定期的に効果検証を行い、より分かりやすいように改善を繰り返すことも大切です。

実際にFAQを作成・運用していくには、いくつか覚えておくべき大切なポイントがあります。ここからは、FAQを作るときに注意すべきポイントについて詳しくみていきましょう。
FAQを作るうえで最も重要なポイントは、「顧客から頻繁に寄せられる質問を掲載する」という点です。先ほどもご紹介したように、FAQは「よくある質問」を掲載し、担当者の負担を軽減させることが目的なので、頻度の少ない質問を掲載してもあまり意味がありません。また、質問と回答が多すぎるとかえって、ユーザーにとって使いにくいものになってしまう可能性も危惧されます。また、社内向けFAQでも同様で、従業員からよく寄せられる質問をピックアップしましょう。
なお、FAQを作る際は、既存のQ&Aを活用するだけでなく、過去に受けた問い合わせを参考にしたり、顧客や従業員へのアンケート・インタビューを実施したり、スタッフが実際に使用した際の疑問点を集めたりすると、より効果的なものが作成できます。
FAQの回答は、誰が読んでも理解できる内容にしなくてはなりません。難解な専門用語や業界用語を多用している回答や、やたらと文章が長い回答はFAQに相応しくないため避けるべきです。
FAQを利用するユーザーの知識レベルはさまざまであることを前提に、専門用語は分かりやすい言葉へ換え、いたずらに文章のボリュームも増やさず、要点を押さえつつ簡潔に解説するようにしましょう。
分かりにくいFAQになってしまう原因のひとつは、レギュレーションの整備不足です。呼称や用語に関する表記ルール、言い換え表現をきちんと定めることで、分かりやすいFAQを作成できます。
顧客の中には、複数の疑問を抱えている人も存在します。そのため、関連する質問同士をリンクで連携させ、簡単にアクセスできるようにしておくのも良い方法です。疑問を解決しやすいサイトは、顧客満足度アップにもつながりやすくなるため、企業ブランディングの面でも有効です。
フィードバックボタンを設置すると、顧客がFAQで疑問を解決できたかどうかを可視化できます。FAQページ内に「問題は解決しましたか?」といった質問に回答してもらうアンケートを設置しておくことで、実際の質問と回答の精度、また実際に顧客の役に立っている項目は何なのかを把握できます。
このような形で定期的にフィードバックを確認し、FAQの内容をブラッシュアップすることで、より実用性が増し、更なる顧客満足度向上につなげられます。
FAQは、基本的に顧客自身が「自分が解決したい疑問」を探し出さなくてはなりません。そのため、質問を分かりやすく分類しておくことも重要です。そうでないと、顧客が該当ページに辿り着けずに離脱してしまう可能性があります。
そのためには、質問項目をカテゴリ分けしたり、検索機能を設置したりするなど、使いやすさ工夫を施し、顧客がスムーズに疑問を解決できる仕組みを構築することが大切です。
提供する製品(サービス)がアップデートされると、顧客や従業員が抱く疑問も変化するケースがあります。それにもかかわらず、FAQに古い情報を掲載し続けていると、ユーザーの混乱を生み、満足度低下を招いてしまうおそれがあります。
そのような事態を避けるためにも、FAQの定期的な更新・メンテナンスによって、最新の情報を提供できるようにしておくことが重要です。なお、FAQページに検索機能を設置している場合は、更新するごとに検索の精度が変化してしまうケースもあります。検索機能で適切な回答を示すためにも定期的なメンテナンスの実施が大切です。
電話での問い合わせに対応する場合、すべて口頭での説明となります。そのため、完璧に理解してもらうのは難しいケースも出てきます。その点、FAQであれば図や画像を用いて分かりやすく説明できるため、より顧客の疑問を解消しやすいWebサイト構築が可能です。
スムーズに疑問を解決できるだけでなく、電話での問い合わせ以上に分かりやすいFAQページを設置できれば、顧客満足度の向上にもつなげられます。
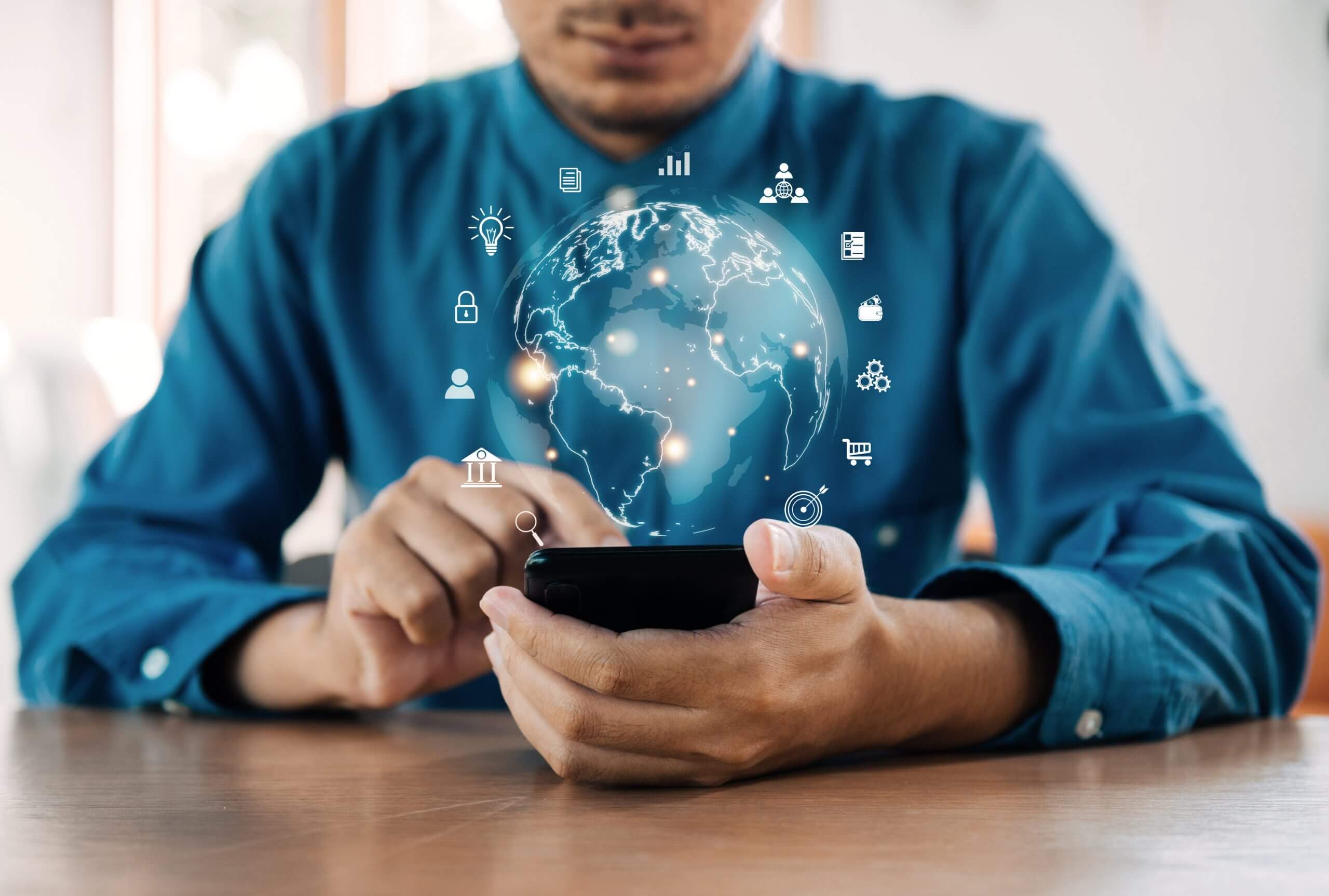
頻繁に寄せられる質問に対応するおすすめのツールに、チャットボットが挙げられます。チャットボットとFAQを組み合わせれば、よりユーザーに寄り添った対応が可能です。また、FAQの効率的な管理と運用を実現できるFAQシステムの導入も検討してみましょう。
チャットボットは、ユーザーの問いかけに対しテキストで回答を表示するロボットです。ユーザーは、FAQで問題を解決できなくても、チャットボットで質問できるためスムーズに求める情報を取得できます。顧客対応だけでなく、社内の問い合わせ対応にも使える便利なツールです。
AIを搭載したタイプであれば、自動的に学習するためどんどん回答の精度が高まります。ただし、使用頻度が低いとデータの蓄積や学習ができません。そのため、同時に使用頻度を高めるための取り組みも必要になります。
また、チャットボットの運用には一定の知識が求められます。社内に、運用が可能な人材がいるか、費用対効果はどうかといった部分も考える必要があります。加えて、チャットボットのサービス提供者が、どのようなサポート体制を整えているのかも事前に確認しましょう。
チャットボットについて詳しく知りたい方はこちら
FAQシステムは、よくある質問と回答を効率よく管理、運用できるシステムです。プログラミング知識がなくてもFAQのデータベース化が可能で、質問と回答をスピーディーに見つけ出す機能や情報共有機能などを備えたシステムが多くを占めています。
顧客対応を前提とした製品から、社内ヘルプデスクに適したシステムまでさまざまなツールがリリースされており、シーンに応じて導入可能です。製品によって機能も異なり、解析機能を実装したものもあります。
導入には費用がかかるため、事前の確認が必須です。また、サービス提供者によって、実装されている機能や操作性、サポート体制なども異なるため慎重に選ぶことも大切です。
なお、社内FAQシステムについて詳しく知りたいのなら、以下の記事がおすすめです。システムの概要からメリットまで詳しく解説しているので、ぜひ目を通してみましょう。
社内FAQシステムとは?問い合わせ対応に活用するメリットやおすすめのツールを紹介
近年は少子高齢化に伴い、多くの企業で人手不足が深刻化しています。そのような状況だからこそ、FAQの活用によって問い合わせ件数を削減することに、大きなメリットがあります。
FAQの作成と運用によって、問い合わせ対応を行う担当者の負担軽減につながるだけでなく、業務効率化やコストダウンも可能です。顧客向けのFAQであれば、スピーディーに求める情報を取得できるため顧客満足度の向上にもつながります。
ちなみにアイスマイリーでは、チャット形式で顧客の質問に自動回答できる「チャットボット」の利用料金・初期費用・無料プラン・トライアルの有無などを比較できる資料を無料でお配りしています。業界や規模、目的などから最適なチャットボットを比較検討できますので、チャットボットの導入をご検討の際はぜひご活用ください。
チャットボットについて詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。
メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。
AI製品・ソリューションの掲載を
希望される企業様はこちら