生成AI
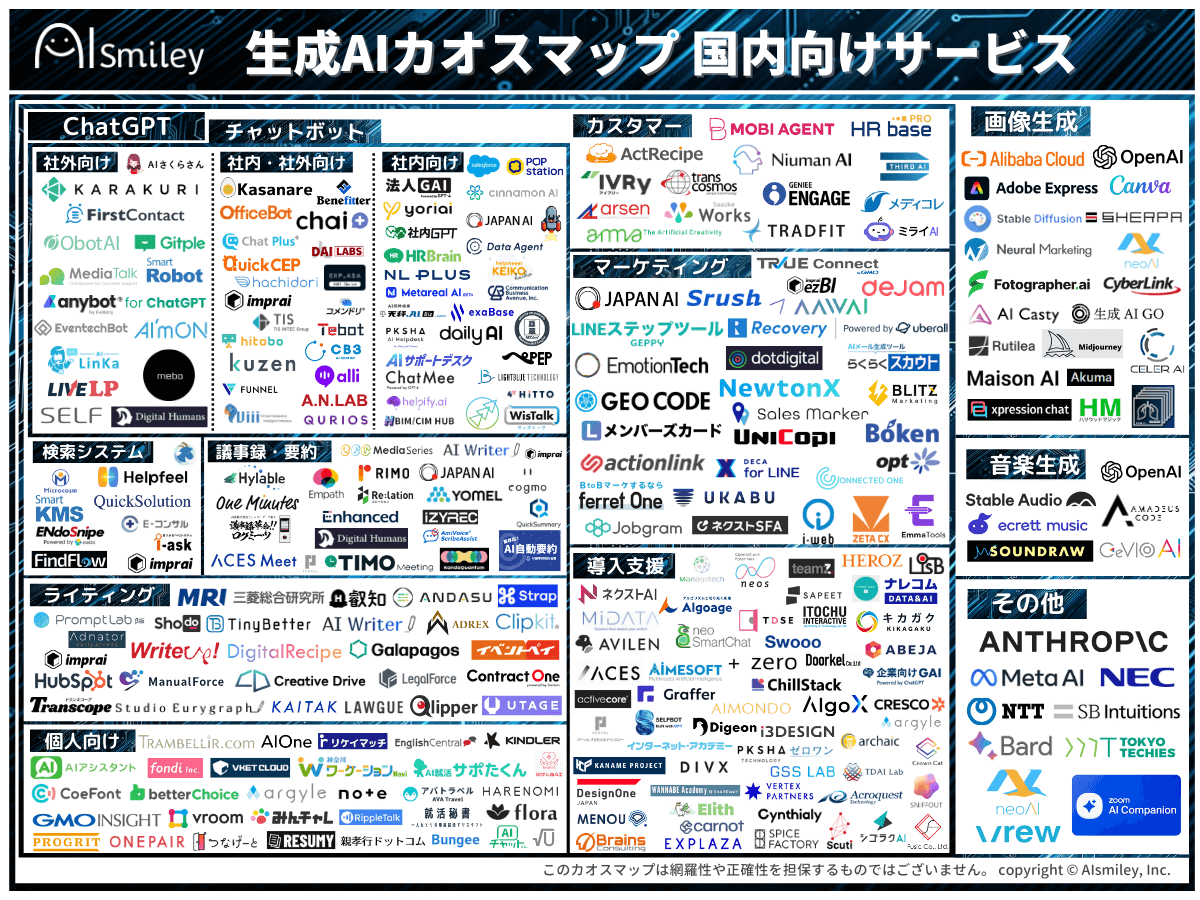
最終更新日:2024/04/11
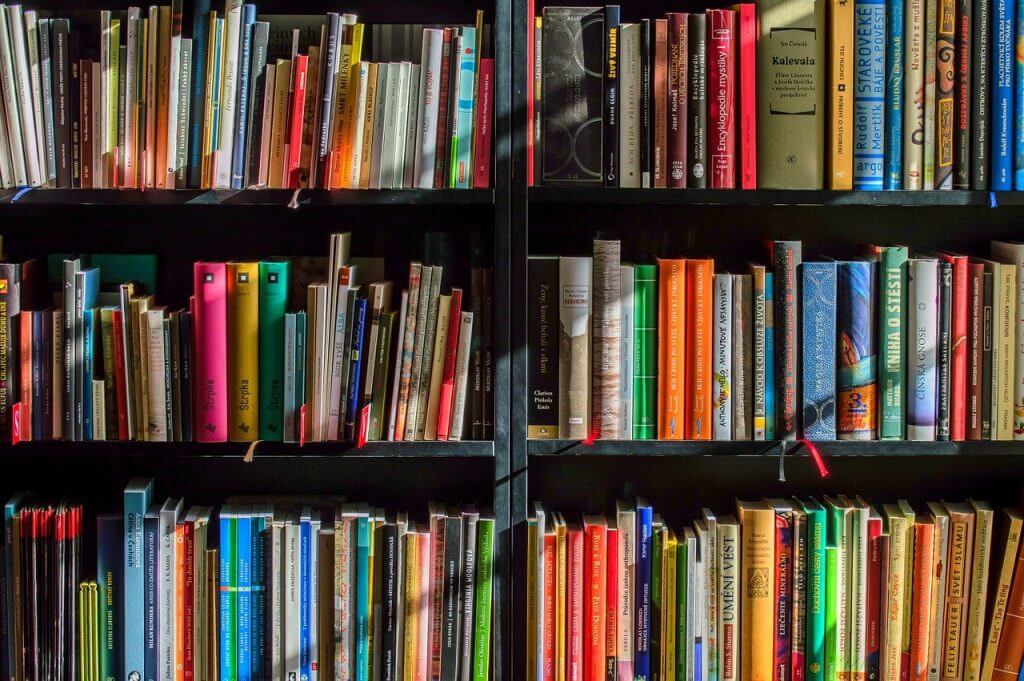
研究者や受験生をはじめとした一般市民の利用者に図書の貸し出しを行う図書館。そんな図書館での業務に高度な専門知識が求められることは、すでに多くの人が認識されているかと思いますが、実は重い本を扱うことも多いため、重労働でもあるのです。
そういった背景もあり、最近ではAIの活用によって図書館業務の効率化を図るケースが多くなってきています。今回は、図書館業務におけるAIの活用事例について詳しく解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
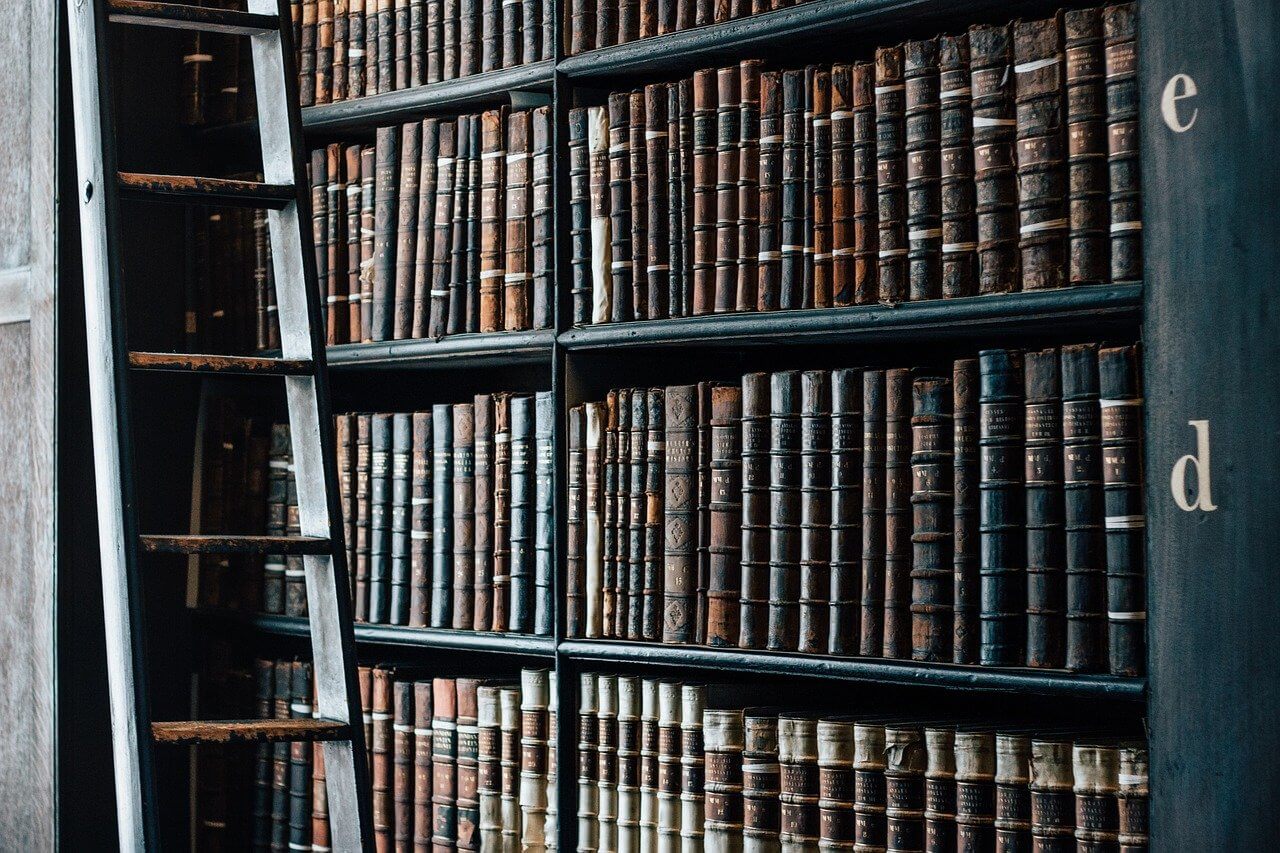
図書館は、教育基本法の精神に則り、社会教育法に基づいて図書館の設置および運営に関して必要な事項を定めた「図書館法」によって設置されています。そんな図書館の役割として挙げられるのは、以下の4点です。
・図書や記録、その他必要な資料の収集
・整理、保存
・一般公衆への利用提供
・教養、調査研究、レクリエーション等に資すること
また、図書館法第三条の中では「図書館の職員が図書館資料について十分な知識を持ち、その利用のための相談に応ずるようにすること」と定められていることから、職員には専門的な知識が求められていることも分かります。
なお、図書館の歴史は非常に古く、メソポタミアのアッシリアには粘土板の図書館が存在していたといわれています。また、古代最古の図書館とされるアレクサンドリア図書館(エジプト・紀元前300年頃)には、すでに所蔵資料の目録が備えられていたそうです。
ただ、現在のように多くの人が図書館を利用できるようになったのは、1439年頃にグーテンベルクの印刷機の発明によって本が大量生産されるようになってからであり、それまでは庶民とは程遠い存在だったといいます。
そんな、長い歴史を持つ図書館ですが、最近はAIが導入され始めたことで大きな注目を集めています。ここからは、図書館業務にAIを導入することで生まれる変化について、詳しくみていきましょう。
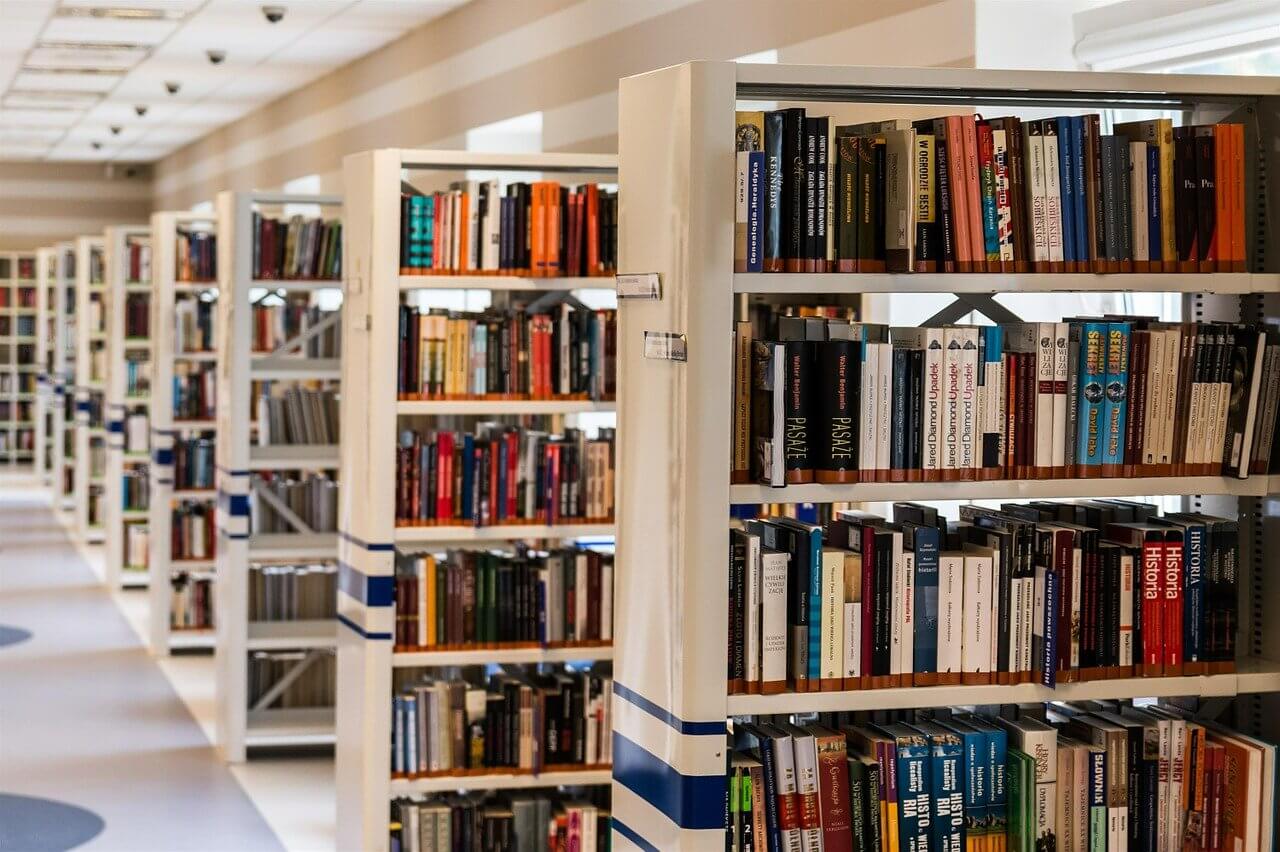
そもそも、図書館業務にはどのようなものがあるのでしょうか。主な図書館業務と、AI導入によって生まれる変化についてご紹介します。
図書や雑誌、新聞、地方行政資料、郷土資料といった紙の資料に加え、レコード、フィルム、美術品などの収集も義務付けられています。AIを活用した場合、この収集作業に必要となるデータを整理しやすい形式で保存できるようになるため、後々の作業の効率化が期待できるのです。
図書館資料は利用を前提に収集されるため、適切に整理されていなければ利用価値が薄くなってしまいます。また、資料ごとに、日本目録規則に従った目録が必要になり、この目録によって図書館を越えた検索なども可能になるわけです。
ただ、AIを活用すれば、資料にICチップを搭載させることが可能になり、そのICチップによって「入手」「整理」「保存」「提供」のすべての履歴をシステム上で管理できるようになるのです。また、所在情報の追跡なども管理できるようになるため、大幅な負担軽減が期待できます。
図書館資料は、材質に応じて適切な方法で保存しなければなりません。希少本や美術品などは、補修や修復、複製の必要も出てくるケースがあります。ただ、この業務にAIを活用すれば、画像での保管が可能になるだけでなく、3Dスキャンによって立体データ化することも可能になります。また、高精度の複製品も制作できるようになるのです。
図書館業務において最も重要と言っても過言ではないのが、情報提供です。しかし、国宝や希少価値の高い資料などでも少しずつ劣化してしまうため、扱い方には注意しなければなりません。
その点、AIやVRといった技術を活用すれば、原本に多く触れることなく研究に使用したりすることも可能になります。
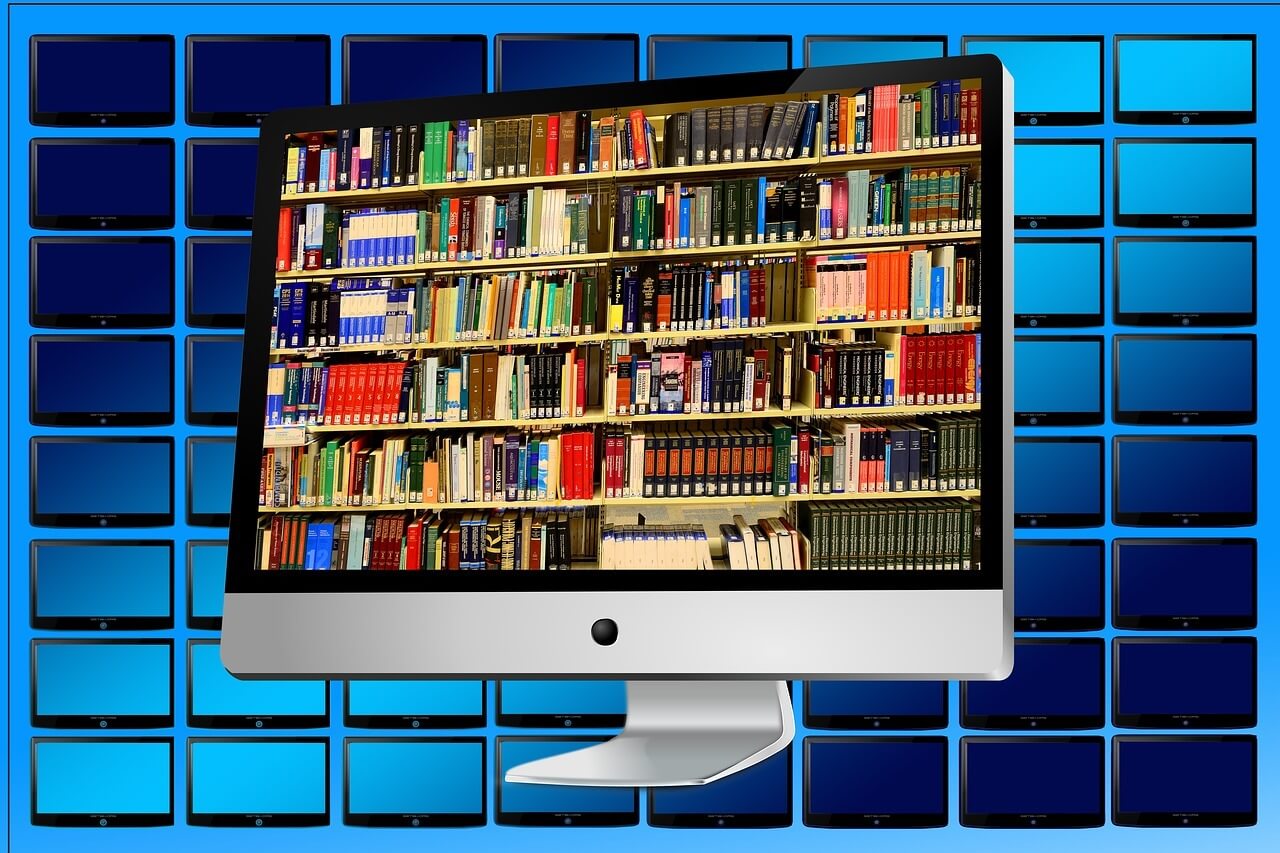
現在の蔵書点検は、バーコードリーダーやRFIDなどを用いて行うのが一般的です。しかし、これらの方法で行う点検作業は人手が必要になるため、決して効率的とはいえません。また、蔵書が多ければ休館日が長くなってしまう傾向もあるため、利用者にとってデメリットが大きい方法なのです。
ただ、最近では画像認識AIを活用した蔵書点検が少しずつ増えてきており、この方法であれば大幅な工数削減を実現することができます。画像認識AIによる蔵書点検の仕組みとしては、まずスマートフォンやタブレット端末などを利用して図書館の書架一面を撮影し、その画像データを画像解析AIに取り込んでいくというもの。そして、画像に写っている複数冊の書誌の背表紙から、タイトルや著者、分類番号などをAIが自動で読み取り、図書館が保有しているデータベースとのマッチング(照合)を行っていくわけです。
この方法であれば、これまでのように手作業で蔵書点検を行う必要がなくなるため、担当者の負担を大幅に減らすことができます。一見、図書館業務は力作業が少ないように思えるかもしれませんが、この蔵書点検では重い書誌を扱うことも非常に多いため、特に負担の大きな業務とされてきました。
その業務の負担を軽減できるという点は、人手不足が深刻化している昨今において非常に大きなメリットといえるのではないでしょうか。
今回は、図書館業務におけるAI・人工知能の活用事例についてご紹介しました。図書館を利用する側の人からすれば、図書館業務は力作業が少ないように思えるかもしれません。しかし、重い書誌を持ち運ばなければならない業務も多く、それらは大きな負担となっていたのです。
しかし、今回ご紹介した事例のように、AIを積極的に活用すれば、より効率的に蔵書点検などの業務を進めていくことが可能になります。一人ひとりの負担が軽減されれば、ストレスも少しずつ解消されていき、離職率の低下などにつなげていくことも期待できますので、人手不足が深刻化する現代においては特に大きなメリットといえるでしょう。
AIは現在も進化を続けていますので、今後さらに業務負担の軽減を実現するサービスが登場するかもしれません。これからAIがどのような形で図書館業務をサポートしていくのか、ますます期待が膨らみます。
業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。
メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。
AI製品・ソリューションの掲載を
希望される企業様はこちら