生成AI

最終更新日:2024/04/11

少子高齢化に伴い、近年は人手不足がますます深刻化しており、その中でも医療分野では医師不足が大きな課題となっています。特に高齢化が急激に加速している地方では、現役の医師が不足していますので、その解決が最優先の課題と言っても過言ではない状況です。
このような課題の解決策として、近年はIoTやAIに注目が集まり始めています。そこで今回は、医療分野におけるIoTの活用事例を詳しくご紹介していきます。ぜひ参考にしてみてください。
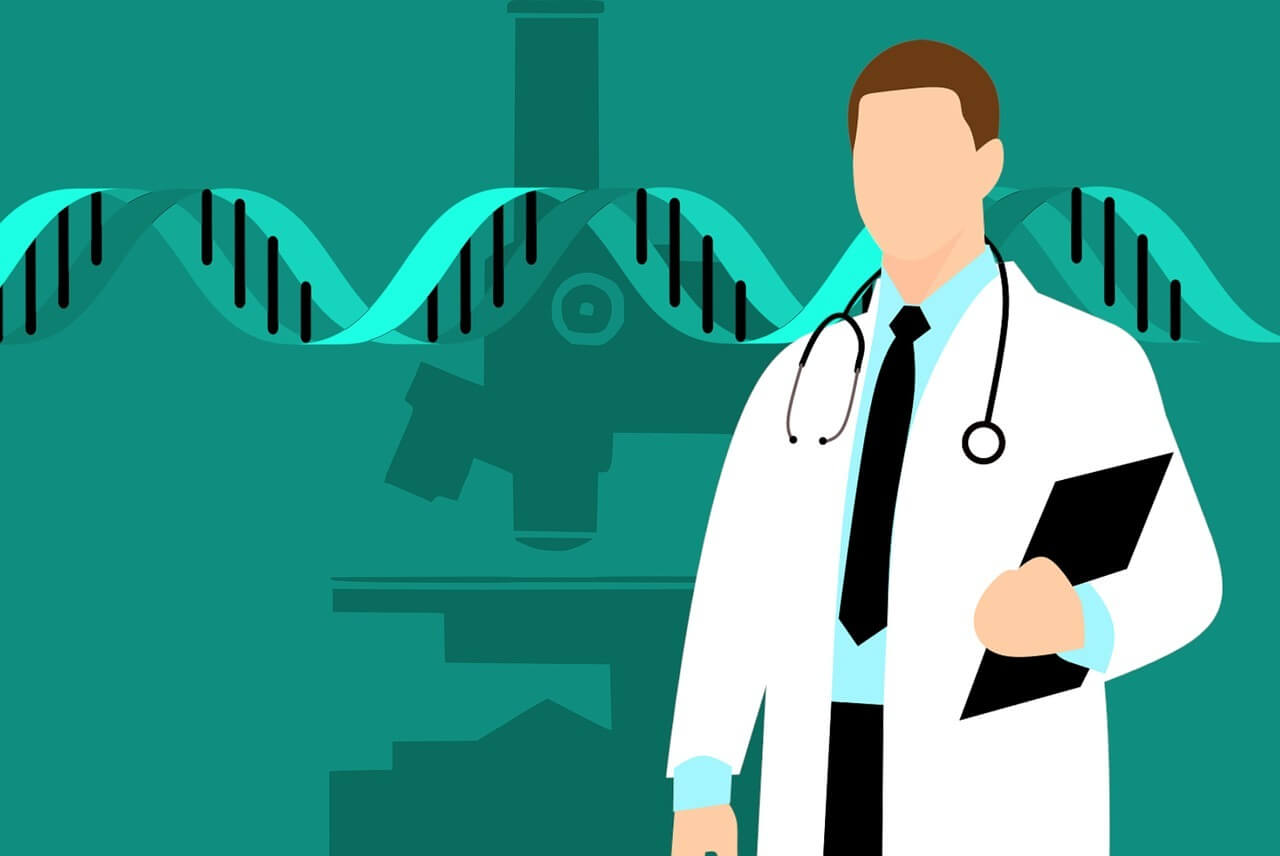
現在、日本には約32万人の医師がいると言われています。これは過去最大の数字であるため、一見「医師不足」とは無縁のように感じられるかもしれません。しかし、熊本県のある介護老人保健施設では、常勤医師が不在していた2018年の3ヶ月間で11人の入居者が死亡するなどの事件もありました。このような医師不足が原因とみられる事件が数多く発生している状況なのです。
では、医師の数が過去最大であるにも関わらず、なぜこのような事件が発生してしまうのでしょうか。その原因として考えられるのは、「東京をはじめとする大都市に医師が偏在してしまっていること」です。つまり、大都市ばかりに医師が集まっており、人口の少ない地域では依然として医師不足が続いているということが考えられます。
それに加え、日本では少子高齢化が急激に加速しているという点も大きな要因といえるでしょう。たとえ、2025年には団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となり、医療費や介護費も急激に増加していくことが予想されます。これは「2025年問題」とも言われており、今後いかに少子高齢化に伴って増加する「医師の負担」を軽減させられるかどうかが重要なポイントといえるでしょう。
そして、医師の負担を軽減させるための方法として、最近特に注目されているのがAI(人工知能)やIoTといったサービス・ソリューションなのです。ここからは、医療分野で活用されているIoTサービスについて、事例を詳しく見ていきましょう。

「MOVEBAND(ムーヴバンド)」は、睡眠や歩数、消費カロリーなどを常時計測することができるウェアラブル端末です。腕に装着するだけで簡単に計測でき、データはスマートフォンで確認することができます。
運動やダイエットのモチベーション維持につなげることもできるため、高齢者の健康維持といった目的だけでなく、さまざまな世代の健康管理にも役立てることができるアイテムです。例えば、ストレス・飲酒・喫煙・運動などが深く関与し、発症の原因となる生活習慣病を防ぐためにも、「MOVEBAND(ムーヴバンド)3」のような端末を活用して自己管理を行っていくことは有効といえます。
自分自身でしっかりと健康管理を行い、生活習慣病の予防につなげられるという点は、医師不足が不安視される今後を見据えると大きなメリットがあるといえるのではないでしょうか。

病院に慣れていない外来患者の場合、必ずしも診察室や検察室にスムーズに辿り着けるとは限りません。また、外来患者の近くに院内スタッフがいない可能性もあるでしょう。そのような外来患者の案内をサポートすることができるのが、富士通が提供している「NAVIT」という小型端末型のIoTソリューションです。
NAVITは、「診察の進み具合」「次に行くべき場所」「待ち時間」「待ち時間を有効に過ごせる施設の場所」などを表示させることができます。そのため、外来患者はNAVITの表示を見ながら行動することができるようになるわけです。これまでは院内スタッフがサポートする必要がありましたが、IoTによる自動化を図れるようになるため、人手不足の解消にも大きく貢献していくかもしれません。

街中で倒れている人、意識を失っている人を発見したとき、とっさに適切な行動を取れる人は決して多くないでしょう。むしろ、パニックに陥ってしまう人のほうが多いかもしれません。そのような緊急事態の際に役立つIoTも存在します。それが、「MySOS」という救命・救急補助スマートフォンアプリです。
MySOSには、倒れた人を見つけたときや、子どもに急な病状が出たとき、患者のプロフィールや病歴が分からないときなどに、スムーズな対応をサポートしてくれる機能が備わっています。例えば、「一次救命処置ガイド」を選択すると、倒れている人を発見したときの一次救命処置の流れを確認することが可能です。状況によっては胸骨圧迫などが必要になる場面もあるため、その際の適切な手順を素早く確認することができます。
また、「成人・小児救急ガイド」を選択すれば、病状やケガが「緊急に受診する必要があるものなのか、それとも様子を見て良いものなのか、判断の目安となるポイントを知ることができます。症状によって3〜5段階で緊急度が表示されるため、より冷静に対応するためのサポート役として貢献してくれる機能といえるのではないでしょうか。
さらに「応急手当ガイド」を選択すれば、日本赤十字社提供の応急手当ガイドを確認することができます。骨折、脱臼、火傷といったケガの処置方法や、事故を防止するための注意点などが確認できるため、万が一のトラブルに備えて読み込んでおくとパニックに陥らずに済むでしょう。
なお、緊急連絡先に登録してある人にSOS発信できる機能や、救援依頼を行いながら119番に発信できる機能なども備わっていますので、ぜひこの機会にインストールしてみてはいかがでしょうか。
今回は、医療分野におけるIoTの活用事例についてご紹介しました。一見、医師の数は増加しているように思えますが、東京をはじめとする大都市に偏在してしまっているため、依然として地方では医師不足の状態が続いています。そのため、今後はいかにIoTを活用して医師の負担を軽減させられるかが重要なポイントといえるでしょう。
今回ご紹介したIoT以外にも、さまざまなサービス・ソリューションが登場してきており、より医師の負担を軽減させられる環境が整い始めている状況です。また、それと同時に一般市民もスマートフォンのアプリなどを活用して、救命救急時に落ち着いた対応を取れるよう準備しておくことが求められています。
万が一の事態にもしっかりと対応できるよう、ぜひこの機会にIoTに関する知識を深めてみてはいかがでしょうか。
業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。
メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。
AI製品・ソリューションの掲載を
希望される企業様はこちら