生成AI

最終更新日:2024/01/29
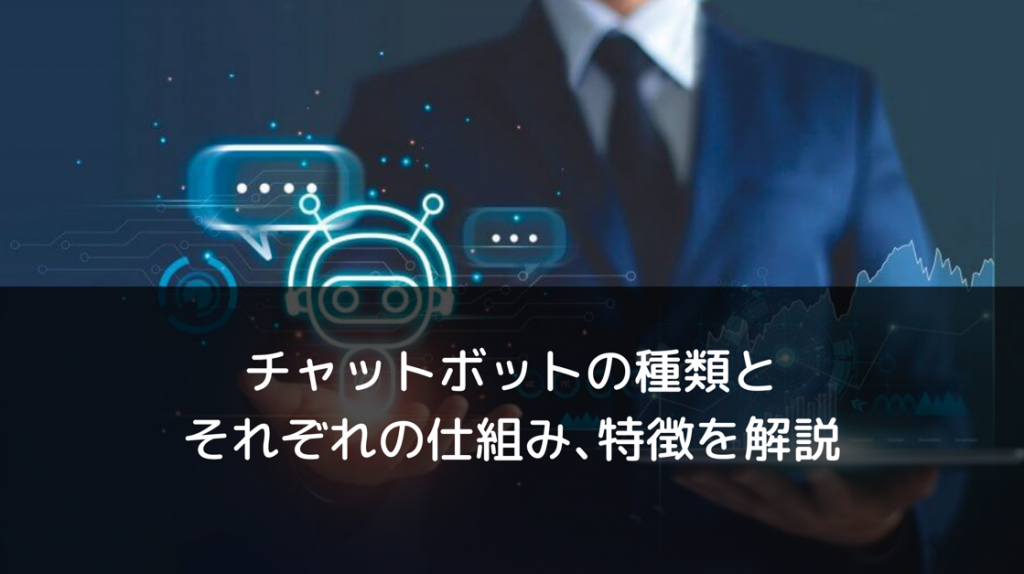 チャットボットの種類は?
チャットボットの種類は?
顧客対応の自動化に伴う業務効率化や生産性の向上など、チャットボット導入によって得られるメリットは多々あります。ただ、チャットボットには多様な種類があり、それぞれ特徴も異なるため、慎重に検討を進めなくてはなりません。本記事では、チャットボットの種類やそれぞれの仕組み、特徴などについて解説します。
チャットボットとは、テキストや音声を用いて自動的にやり取りを行えるツールです。チャットは会話を、ボットはロボットを意味しており、近年では企業のコーポレートサイトやECサイトなどに設置されるケースも増えてきました。
チャットボットを導入するメリットは、営業時間外の問い合わせ対応が可能な点です。プログラムが自動的にやり取りを行うため、営業時間外でも問題なく対応でき、機会損失を最小限に留められます。また、ユーザーは任意のタイミングで問い合わせができ、スムーズに知りたい情報を得られるため、顧客の不満を解消できるというメリットがあります。
また、チャットボット導入は業務効率化にも有効です。チャットボットに問い合わせ対応の一部を任せられるのなら、有人対応のリソースを削減でき、オペレーターの負担軽減にもつながります。リソースの削減はコストダウンを実現し、生産性の向上に寄与します。
デメリットは、運用を開始するまでに手間がかかる点です。導入するチャットボットの種類によるものの、最初にルールやシナリオ設定をしなければならず、手間と時間がかかります。また、チャットボットには多様な種類があり、それぞれに特徴やメリット・デメリットがあるため、それらを把握したうえで自社に最適なものを選ばなくてはなりません。
チャットボットについて詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
チャットボットとは?意味やメリット、活用事例を徹底紹介

チャットボットには、AI搭載型と非搭載型があります。導入を検討しているのなら、それぞれの特徴を把握しておきましょう。
AI非搭載型は、よく寄せられる質問であれば対応を自動化でき、カスタマーサポート部門などの業務効率化が可能です。一方、イレギュラーな質問には対応できない、機械的な対応になりやすいといったデメリットがあります。
AI非搭載型は、AI技術が使用されていないタイプで、ルールベース型とも呼ばれます。あらかじめ設定したルールやシナリオに沿って、ユーザーとやり取りを行う点が特徴です。
たとえば、「送料はいくら?」という問いに対し、「送料は〇〇円です」のような回答が可能です。事前に送料はいくら、と聞かれたときにどう回答するのかを、ルールとして決めておくことで答えられます。ただ、事前に定めたルールやキーワードにしたがってやり取りを行うため、「輸送費はいくら?」と問われた場合に、「輸送費」というキーワードを事前に登録していないケースでは質問に答えられません。
なお、このタイプは表示された選択肢のなかから、ユーザーが該当するものを選んで会話を続けるパターンがほとんどです。次々と表示される選択肢から選ぶことで、最終的に求める答えへと誘導します。
AI非搭載型は、頻繁に寄せられる問い合わせへの対応を自動化できます。たとえば、自社サービスの予約方法や商品に関する説明などです。あらかじめ、これらの情報を登録しておけば、問い合わせ対応を自動化できオペレーターの負担も軽減できます。
AI型と比べると、構築しやすい点もメリットです。定型の質問と模範的な回答を登録するだけなので、難易度はそれほど高くありません。比較的構築が容易なため、運用開始までの時間も短縮できます。
AI非搭載型は、イレギュラーな事態に対応できない点がデメリットです。事前に設定したシナリオ、ルールに則った回答しかできないため、ユーザーが登録されていない質問をしてしまうと、やり取りがそこで終了します。かえって、顧客満足度の低下を招くリスクもあるため注意しましょう。AI非搭載型では、限られた選択肢からしか選べません。ユーザーが、自分の本当に知りたい情報も得られず、結局オペレーターへ質問する羽目になる、といったことも考えられます。ユーザーに余計な手間をかけることになり、顧客満足度が低下した結果、顧客の流出につながるかもしれません。
機械的なやり取りになりやすいのも懸念点です。このタイプは、あくまで事前に登録した内容にしたがったやり取りしかできません。そのため、人間とやり取りしているような自然さはあまり感じられず、ユーザーによっては不満を抱くおそれがあります。
定型のやり取りを自動化するのに、AI非搭載型チャットボットは有効です。答えが限られており、シナリオで導けるのであれば、問い合わせ対応を自動化できます。
また、チャットボットを運用しつつ有人対応できる体制も整っているケースにおいても、AI非搭載型を活用できます。ユーザーからの問い合わせに対し完璧な回答を提示できなくても、オペレーターがサポートできるようなケースです。
AI搭載型は、AIが自動的に学習してくれるタイプであり、幅広い質問に対し柔軟な対応が可能です。一方で、運用開始までに教師データを用意する必要があり、時間がかかるなどのデメリットがあります。
AI搭載型は、人工知能を搭載したタイプです。非搭載型のように、運用側がルールやシナリオの設定をするのではなく、自ら学習しながら成長していく点が大きな特徴です。
運用の過程で情報を蓄積し分析も行います。より多くのデータに触れるほど成長が早まり、回答精度も高まります。複雑なシナリオを構築するような必要もなく、いくつもの答えが存在するような問い合わせに対しても柔軟な対応が可能です。
これまで対応したことがない質問であっても、過去のやり取りを参照しつつ回答する、といったこともできます。AI非搭載型の場合、登録されていない質問には回答できません。
定型文だけでなく、さまざまな質問に対応できる点がメリットです。搭載されたAIが学習と成長を続けるため、以前は答えられなかった質問にもやがて対応できます。初めのうちは異なる回答をしてしまうケースがあるかもしれませんが、運用を続けるなかでブラッシュアップされていくため、回答の精度が着実に高まります。
AI搭載型であれば、高度かつ専門的な問い合わせへの対応も可能です。より幅広い質問に答えられる、ユーザーはチャットボットだけで課題を解決できます。その結果、これまでより少ない人員で問い合わせ対応業務を遂行できる環境が整い、コストダウンにもつながります。
AI非搭載型に比べて、運用の手間が少ない点も魅力です。その都度、ルールやシナリオを設定する必要がなく、AIが自動的に成長を続けてくれるためです。
AI搭載型のデメリットとして、運用開始までに多大な労力と時間を要する点が挙げられます。AIチャットボットを導入するにあたり、まずは社内の運用体制を整えなくてはなりません。運用体制を整えていないと、いざ運用を開始してもいきなり躓いてしまうおそれがあります。
運用を始めるまでにデータの準備も必要です。AI搭載型は、面倒なルール・シナリオ設定こそ必要ないものの、ベースとなる教師データをインプットしなければなりません。教師データとは、問い合わせに対する模範的な回答を整理したデータベースです。
また、問題なく稼働するかどうかのテストも必要です。質問に対し適切な回答を提示できているか、誤解を与えるような回答をしていないか、などを確認します。ここまできて、やっと本格的な運用を始められるため、運用開始までに相当な時間と労力がかかります。
定期的にメンテナンスを行う必要があるのも注意点です。AI搭載型は、運用のなかで自動的に成長を続けるものの、いっさいメンテナンスが不要なわけではありません。稼働状況をモニタリングしつつ、問題が発生した箇所については改善を行う必要があります。
AI搭載型は柔軟な対応が可能であるため、さまざまなシーンで活用されています。たとえば、ECサイトでユーザーの希望にマッチしそうな商品を提案する、カスタマーサポート部門で問い合わせ内容に応じたFAQページへ案内する、といった活用例が挙げられます。
多言語案内も可能なので、顧客に外国人が多い企業にもおすすめです。たとえば、ユーザーが入力した言語をAIが判定し、同じ言語で回答を提示するといった活用ができます。ほかにも、悩み相談や長い説明が必要なもの、どのような質問をされるか分からないようなケースでもAI搭載型が役立ちます。
チャットボットの種類には、ログ型や選択肢型と呼ばれるものをはじめ、辞書型、選択肢・辞書型などがあります。自社にマッチしたチャットボットを導入するため、それぞれの特徴を把握しておきましょう。
ログ型とは、AIを実装した機械学習型のチャットボットを指します。ユーザーとのやり取りを通じて学習と成長を続けるタイプで、多くのやり取りを経験するごとに回答のクオリティも高まります。
会話経験が増えるほど、回答の精度が高まりナチュラルな会話が可能です。ただ、やり取りがあまり発生しない、といった環境で運用していると、そこまで大幅な精度の向上は見込めません。
そのため、ログ型は多くのやり取りが発生すると考えられる環境での運用が適しています。会話量が多いだけでなく、多岐にわたる質問をされるような環境で運用すれば、AIが効率よく学習し、さまざまな問い合わせに適切かつ自然な対応を行えるよう成長します。
選択肢型とは、ルールベース型チャットボットのことです。AIを搭載しておらず、事前にシナリオやルールを設定することでそれに則った対応を行えます。
ユーザーは、提示された選択肢からあてはまる項目を選びながらやり取りを進めます。答えが限られているのなら、シナリオを通じてスムーズにユーザーを回答へ導ける点が特徴です。メンテナンスがそこまで面倒でないのもメリットです。
ただ、顧客満足度の低下を招くリスクがあるため、そこは注意しなくてはなりません。提示された選択肢から該当する項目を選びながら会話をしますが、そもそも選択したい項目が用意されていない、といったこともあります。また、選択肢から適切な項目を選んで会話を進めたにもかかわらず、結局課題を解決できなかった、となると顧客の不満を高めてしまいます。
辞書型は、キーワードと回答をセットで登録し運用するタイプです。たとえば、「金額・価格」といったキーワードを登録しているケースで、ユーザーが「金額を教えてほしい」と入力した場合、「商品価格について」や「解約金の説明」など、あらかじめ登録してあったコンテンツを表示します。
辞書型のメリットとして、ユーザーが知りたい情報へスムーズにアクセスできる点が挙げられます。入力したキーワードから解析し、適切な回答へ導くためです。また、ユーザーが入力しているキーワードを分析すれば、そこから顧客の深いニーズもくみ取れます。
デメリットは、キーワードと回答の登録に多大な手間を要する点です。登録対象となるキーワード、回答が多くなればなるほど膨大な手間と時間がかかります。
選択肢型・辞書型は、双方の良いところだけを併せもったハイブリッド型です。選択肢も提示しつつ、キーワードから回答を導き出すこともできるため、ユーザーの課題を解決しやすくさまざまな企業が導入しています。
デメリットは、双方の弱点も併せもっていることです。AIを搭載したログ型ほどの柔軟性は期待できず、幅広い問い合わせに対応したいのなら膨大な量のキーワード、回答を登録しなくてはなりません。導入の準備に多大な手間がかかるため、運用を開始するまでに相当な時間を要するおそれもあります。
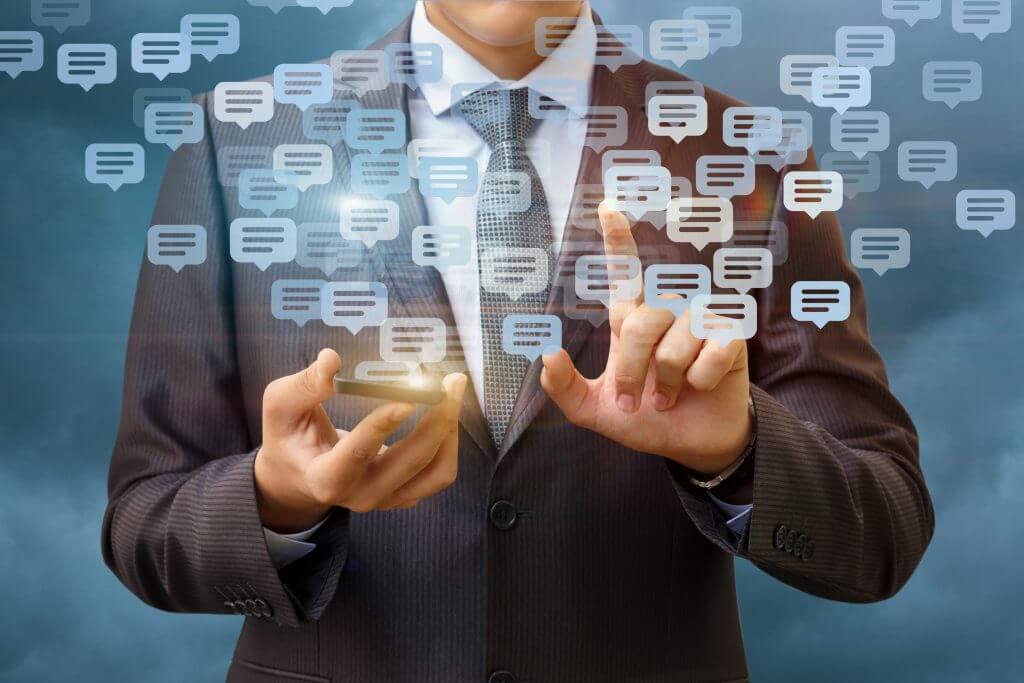
チャットボットには多様な種類があり、それぞれ異なる特徴があるため活用方法も変わってきます。機能で分類すると、FAQ型、処理代行型、配信型、雑談型などが代表的です。
FAQ型チャットボットは、FAQの機能を有したチャットボットです。FAQとは、頻繁に寄せられる質問と回答を整理したコンテンツです。コーポレートサイトやECサイトなどでよく目にするFAQですが、求める情報へたどり着くまで手間と時間がかかるデメリットがありました。FAQ型チャットボットは、そのデメリットを解消できる点が魅力です。
このタイプなら、チャットボットに質問すればFAQから適切な回答を提示してくれます。わざわざ、膨大なFAQのなかから求める答えを探し出す必要がなく、チャットボットが自動的に最適解を見つけ出してくれる点が利点です。
ユーザーは、スムーズに求める情報へアクセスでき、迅速に課題も解決できるため満足度向上にも有効です。FAQのなかから最適解が見つからないときは、オペレーターへ接続することもでき、シームレスな顧客対応を行えます。
FAQを導入しているものの、あまり利用してもらえない、効果を実感できない、といった企業にはFAQ型チャットボットの導入がおすすめです。なお、FAQ型のおすすめチャットボットについてもっと詳しく知りたいのなら、以下の記事にも目を通してみましょう。
チャットボットにも種類がある!自社に活用できる製品の特徴とは?
処理代行型は、ロボットがユーザーとやり取りするだけでなく、必要に応じたアクションを起こすタイプのチャットボットです。このタイプがよく用いられているのは予約の処理です。
チャットボットがユーザーとやり取りしつつ、得た情報をもとに予約を行います。ユーザーは誰かと会話することなく予約を完結でき、企業は予約処理の自動化と業務効率化を実現できます。
予約処理だけでなく、さまざまな業務の自動化が可能です。たとえば、スケジュールの調整や商品の受注業務などです。これらを自動化できれば、業務効率化につながります。これまで、オペレーターが処理していた業務を自動化できるため、業務効率化と生産性の向上が可能です。
オペレーターの離職率低下につながる可能性があるのも魅力です。カスタマーサポートや予約対応などを担うオペレーターの業務は激務になりやすく、ときに理不尽なクレームに晒されることもあるため、人材がなかなか定着しないといったケースも珍しくありません。
チャットボットを導入し、業務を効率よく遂行できる環境が整備されれば、オペレーターにかかる負担も軽減できるため、定着率の向上につながります。働きやすい職場である、との口コミが広がれば、「働きたい」と考える人が増え、採用力の強化につながる点もメリットです。
配信型チャットボットは、情報発信に特化したチャットボットです。このタイプは、ユーザーとのやり取りを目的としておらず、あくまで情報を発信するために用いられます。たとえば、自社商品やサービスに関するキャンペーンやセール情報、新製品発売の告知、顧客への配送日通知などです。
メルマガの運用をイメージすると分かりやすいかもしれません。違いは、メールではなくチャットを利用する点です。リアルタイムで情報を発信できるチャットを用いることで親近感を抱いてもらえる可能性が高く、うまく活用すればブランディング強化にもつながります。
顧客を対象とした活用ではなく、社内で運用するケースも考えられます。たとえば、大切なミーティングなどの前に行うリマインドです。実施の決定から当日までに時間があるミーティングの場合、メンバーが忘れているかもしれません。配信型チャットボットでミーティング参加者へ一斉にリマインドを配信すれば、上記のようなリスクを回避できます。
雑談型チャットボットは、ユーザーとのやり取りを目的としたチャットボットです。このタイプはAI搭載型がほとんどで、AIとさまざまな話題でコミュニケーションを図れます。
代表的な雑談型チャットボットとして、日本マイクロソフト社がリリースした「りんな」が挙げられます。2015年にLINEでお披露目されたりんなは、AIとは思えぬ軽快なトークを楽しめると多くのユーザーのあいだで話題になりました。
ただし、ほかのチャットボットに比べ、収益に直結しづらい点が特徴です。そもそも、このタイプはユーザーとのコミュニケーションを目的としているため、運用によって直接的な収益を得ることとは相性がよくありません。
ただ、運用によって結果的に売上や利益の拡大につながる可能性はあります。たとえば、ユーザーがやり取りを通じて雑談型チャットボットに好印象を抱いたり、ファンになったりすれば、そこから自社商品やサービスの購入につながる可能性があるためです。
商品やサービスの購入につながらずとも、さまざまな人々とコミュニケーションを図ることで企業イメージの向上につながり、いずれ自社の顧客になってくれるかもしれません。

チャットボットの導入と運用を成功させるには、自社にマッチしたツールを選ばなくてはなりません。現在では、さまざまなチャットボットがリリースされており、ツールによって機能や操作性、費用、できることなども変わります。適当に選ぶと後悔しかねないため、慎重に検討を重ねましょう。
基本的には、自社が何を実現したいのかで選びます。たとえば、せっかく構築したFAQをもっと活用したい、といったケースであればFAQチャットボットが有効です。既存顧客へキャンペーンやセール情報を一斉に送りたいのなら配信型を、コミュニケーションを介して顧客と良好な関係を構築したいと考えるのなら雑談型を、といった具合に検討します。
自社が求める機能を実装しているかどうかもチェックしましょう。チャットボットの代表的な機能としては、自動学習や有人対応、レコメンド、聞き返し、多言語対応などが挙げられます。たとえば、海外からの問い合わせが多いのなら多言語対応機能を、オペレーターも組み合わせたシームレスな対応をしたいのなら有人対応連携機能を、といった具合です。
また、導入するチャットボットによって、初期費用やランニングコストが大きく変わってくるため、そのあたりも踏まえたツール選びをしなくてはなりません。予算が明確に決まっているのなら、その範囲内に収まるものを選びましょう。
サポート体制も要チェックです。チャットボットを初めて導入するケースでは、疑問点がいくつも湧きあがるかもしれません。サポート体制が充実しているベンダーであれば、アドバイスを受けつつ導入、運用を行えるため安心です。実際にどのようなサポートを提供しているのかは、各社で大きく異なるため、事前にしっかり確認しておきましょう。
チャットボットには多様な種類があり、それぞれに役割や機能が異なります。自社に合ったものを選び、運用することで業務効率化や生産性の向上に寄与します。今後、チャットボットを導入したいと考えているのなら、本記事でお伝えした内容をぜひ参考にしてください。

チャットボットは幅広いニーズに対応できるように発達してきましたが、種類によって機能が異なります。導入にあたっては、自社が何をしたいのか、どのような機能を求めているのかを明確にしたうえで選定を進めましょう。なお、チャットボットサービスを比較しながら選びたいのなら、以下の記事がおすすめなので、ぜひご覧ください。
業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。
メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。
AI製品・ソリューションの掲載を
希望される企業様はこちら