生成AI

最終更新日:2024/01/18
 AIで業務効率化
AIで業務効率化
業務効率化の推進は、多くの企業にとって重要な取り組み1つです。働き方改革が求められる状況では、無理なく業務効率を改善させる方法が求められます。そこで近年注目を集めているのが、「AI」による業務効率化です。
この記事では、AIによる業務効率化の重要性やメリット、導入におけるポイントなどについて解説します。
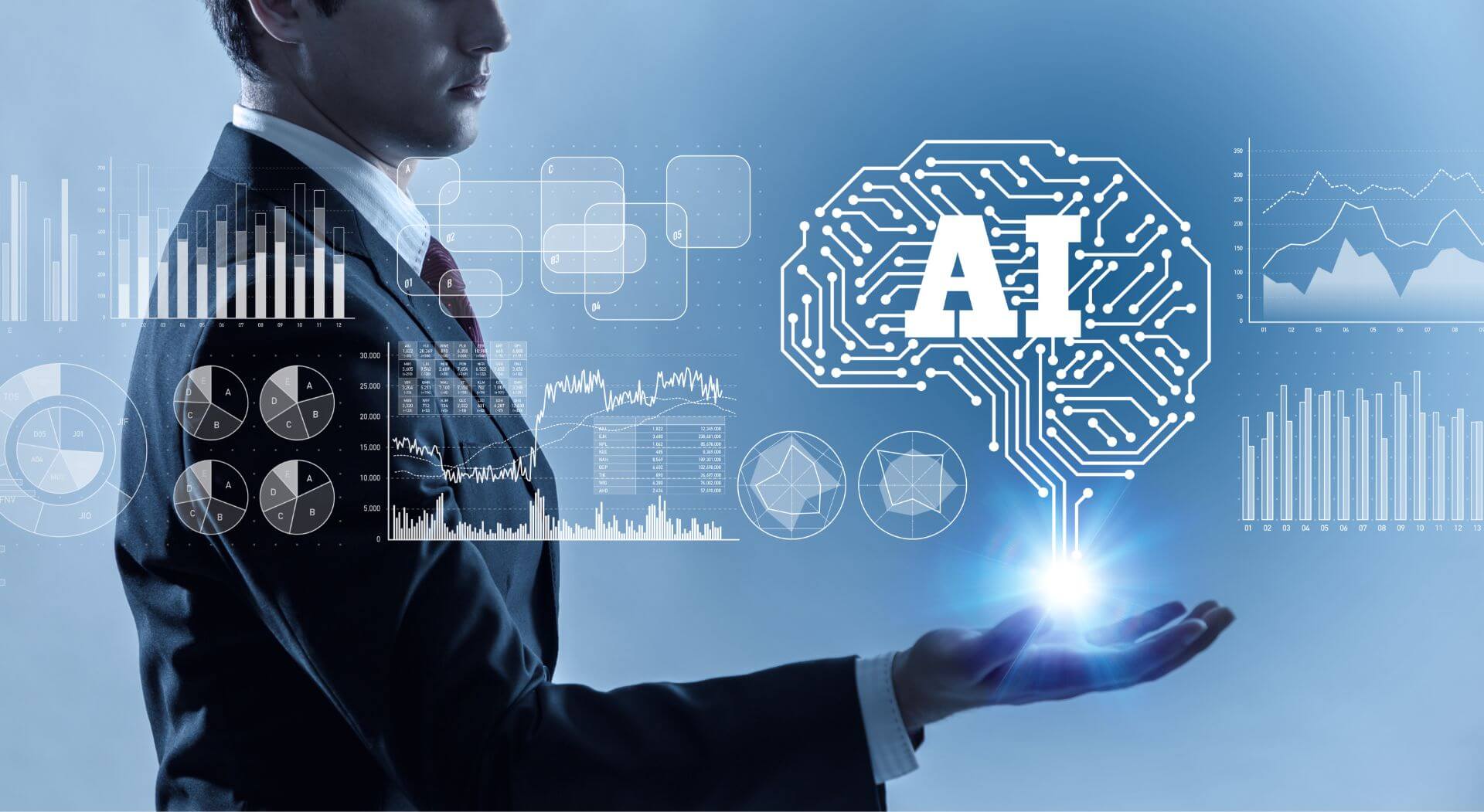
AIとは、人間が持つ知能と同様の機能を、コンピューターによって実行するシステムや機械のことです。「Artificial Intelligence」の頭文字を取った言葉であり、日本語では「人工知能」を意味します。近年ではさまざまな研究者によって異なった定義がなされているため、統一の明確な定義があるわけでありません。
しかし「人間の知能をコンピューターによって再現したもの」と理解しておけば、幅広い文脈において応用が利くでしょう。
AIについて調べるうえで混同されやすい言葉として、ディープラーニングと機械学習が挙げられます。しかし上記はそれぞれ以下の意味を持つ、別の言葉です。
【AI・機械学習・ディープラーニングとは】
上記から、「AIの学習方法が機械学習であり、機械学習の手法の1つがディープラーニングである(AI>機械学習>ディープラーニング)」といえます。
RPAとは、人間が業務において行っている作業を、ロボットを活用することで自動化することを指します。AIとRPAは、以下の点で異なる概念です。
【AIとRPAの違い】
「人間による事前の設定が必要かどうか」が両者の大きな違いだといえるでしょう。また近年では、RPAを進めるにあたってAIと組み合わせるケースもあります。
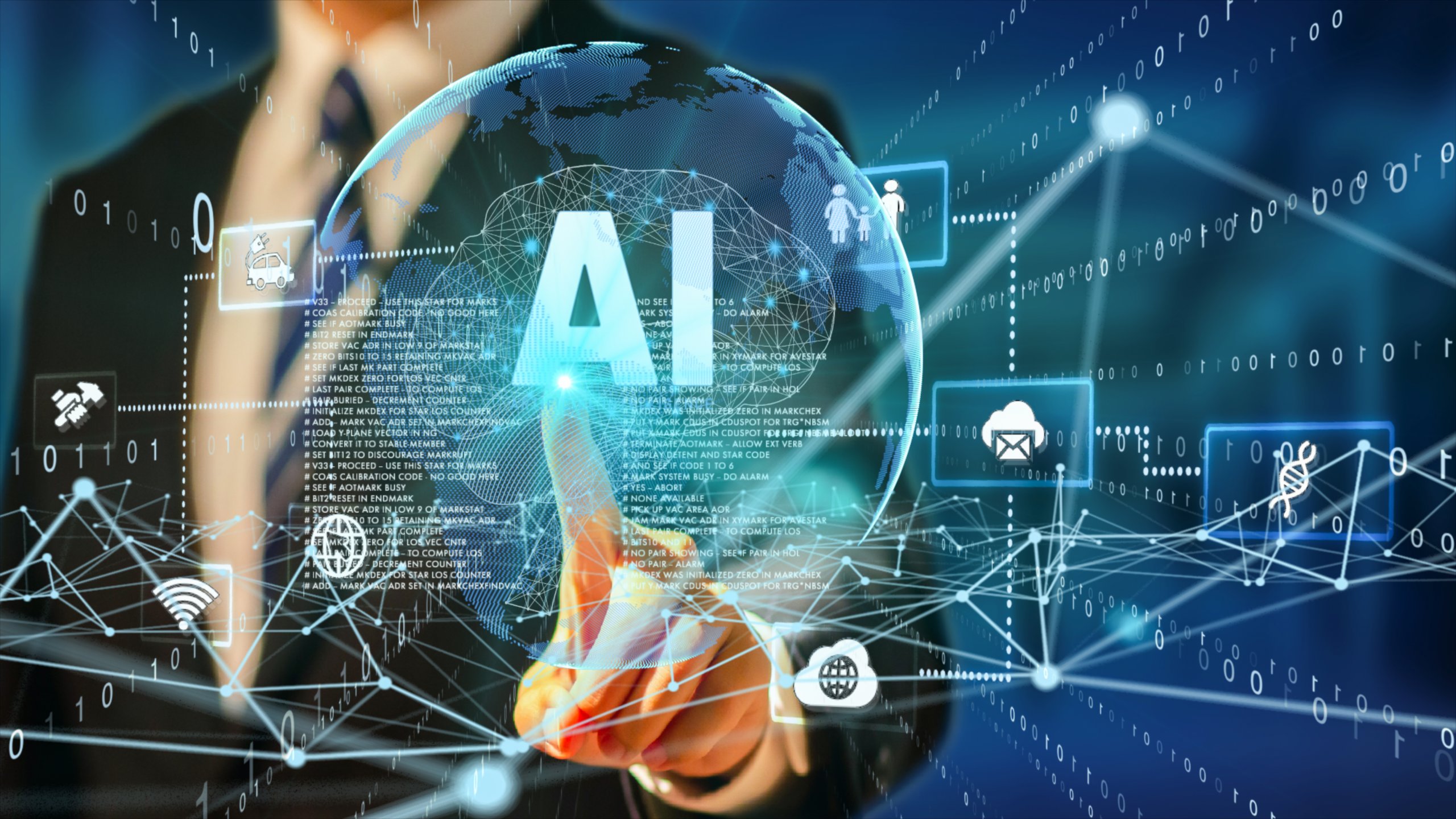
AIによる業務効率は、現代日本における企業運営において重要だといえます。AIを活用することで、以下の効果を期待できるためです。
【日本企業がAIによる業務効率化を進める意義】
AIが自ら判断して業務を行ってくれることで、人間がするべき業務の量を減らせます。少ない従業員数でもより多くの仕事をこなせるようになり、短い時間で最大限の成果を上げることにもつながるでしょう。

AIによる業務効率化には、「アノテーション」が重要です。
アノテーションは、日本語で「注釈」と訳されます。IT分野におけるアノテーションとは、画像や音声、テキストなどのデータに、それぞれタグやメタデータなどの情報を付けて「教師データ」を作る工程のことです。
教師データとは、例題とその答えがセットで用意されているデータのことを指します。「これは何?」との例題に対して「これは〇〇です」との答えを用意することで、AIに対して指導を行い、学習の精度を向上させるのです。

AIの活用について具体的にイメージするためには、AIが効率化できる業務の種類について理解しておくのがおすすめです。AIが効率化できる業務と具体例としては、以下が挙げられます。
【AIが効率化できる業務の例】
AIを活用できる業務としては、顧客対応や問い合わせ対応がまず挙げられます。音声認識や自然言語処理を活用したシステムを活用することで、これまで人間が行っていた顧客対応や問い合わせ対応を効率化可能です。
AI活用の事例としては、チャットボットが挙げられます。顧客からの問い合わせのなかで頻度が高く定型化ができるものについては、チャットボットを活用することでオペレータの業務を減らすことが可能です。
ある企業では、AIチャットボットの導入によって年間1,000万円近いコストの削減が見込まれています。またコスト削減だけでなく、問い合わせへの自動応答や24時間対応が可能になる点も、チャットボットの優れているポイントでしょう。
製造業務や品質管理にも、AI導入による業務効率化が見込めます。製造業務にAIを導入することで作業者ごとの仕上がりムラを防げて、不良検知ツールによって品質の安定化が図れるでしょう。
製造・品質管理が安定すれば、業務効率化を図れます。
ある企業の食品工場では、製造ラインへの不良品検品システム導入が進められています。従来のシステムでは、野菜をはじめとした「個体ごとの大きさ・形差が大きいもの」に対して、AIによる検品が困難です。そのため工場スタッフが原料検査を目視で1つ1つ行わなくてはならず、労総環境の改善がなかなか叶わずにいました。
しかしAIの判別精度・速度が向上することで、現場への導入が現実的になり、スタッフの負担軽減と業務効率改善につながると期待されています。
営業の現場でも、AI導入によって業務効率化が期待できます。顧客ごとに属性や購買履歴などのデータを蓄積・分析することで、さまざまなことが可能になるのです。
データの活用により成約確率の高い見込み顧客を抽出できる、属性に適した商品をすすめられるなど、営業効率アップにつながります。
ある企業では、自社ホームページに「Web接客ツール」と呼ばれるAIシステムを導入しています。Web接客ツールでは、ホームページに来訪した顧客の属性や各種情報に合わせて、最適な接客を実施可能です。
顧客に合わせたキャンペーンやお得情報などを表示させることで、商品の購買率向上につながります。また、AIがすべてを自動的に判断して行うため、担当スタッフの労力が減り他の業務に回すことも可能になりました。
AIによる業務効率化が見込める業務としては、人事関連業務も挙げられます。従業員の人事評価や勤怠管理、キャリアプランの設計などに対し、既にAIが活用されています。また、採用現場においても、エントリーシートのチェックをはじめとする各種業務にAIを導入することで、業務効率化につなげることが可能です。
ある大手生命保険会社では、人事評価・異動に対して社員情報を一元管理するシステムを導入しています。このシステムにより、社員は相互に経歴や自己開発状況などを確認しキャリア設計に役立てられるようになりました。
さらに社員検索機能も付いており、人事担当目線では適材適所の人材配置を効率的に行うことにつながっています。
社員のデータを「見える化」して蓄積していくことで、人事制度の透明性の高さも確保可能です。

ここでは、AIで業務効率化・業務改善を図るメリットについて解説します。主なメリットとして考えられるのは、おおむね以下の通りです。
AIによる業務効率化のメリットとしてまず挙げられるのが、単純労働の削減です。定型的で時間がかかる作業をAIに任せてしまうことで、人間は別の新しい分野や企画・設計などのクリエイティブな仕事に時間を任せるようになります。
また、単純作業に追われることがなくなれば、それだけ短い時間で業務を終えられることにもつながるでしょう。働き方改革の推進においては、AIの導入が効果的だと考えられます。
業務の属人化の解消も、AIによって実現を期待できます。AIの場合、一度システムを整えてしまえば休むことなく同じ要領で業務を遂行可能だからです。ある業務のスキルや知識が特定の人材に偏ってしまうと、その人材が不在になった際に、業務効率が著しく落ちてしまいます。
AIを導入することで、人間の判断や業務編習熟度の差などに左右されずに一定の精度・品質で業務を遂行できるようになるでしょう。
AIが持つ強みとしては、カスタマイズ性の高さも挙げられます。アノテーションによって、人間が求めるように自由にAIを指導できるからです。自社の業務や今後の展望に合わせてAIをカスタマイズすることで、比較的コストをかけずに業務効率化を進められます。
自社の業務に合わせて人材育成を行う場合、どうしても手間と時間がかかってしまうでしょう。しかしAIであれば、自社が求める業務形態に合わせて柔軟に対応させることが可能です。
AIであれば、時間を問わず稼働し続けられます。人間とは異なり、AIは肉体的・精神的に疲労することがないためです。そのため、働き続けても作業効率が下がることがなく、いつでも迅速・正確に作業を続けられます。
単純労働をAIに任せると、人間が別の仕事に集中できるだけでなく、任せた単純労働に関する生産性も大きく向上するでしょう。AIを導入することで、人間の労力を抑えつつ業務効率・生産性を向上させられるのです。

業務効率化を目的としてAIを導入する際には、以下のポイントを押さえることが重要です。
以下で、上記について解説します。
AI導入にあたっては、活用する目的を明確にすることが大切です。目的が明確になっていないと、AIの導入自体が目的になってしまいます。
また、導入後にどのような成果を期待するのかが明確になっていなければ、業務効率化を果たせたのかどうか効果的な検証ができなくなる点も問題です。漫然と技術検証を繰り返していても、本来求めている成果を求めるのは難しいでしょう。
AIに活用できるデータ量を把握しておくことも、導入時には大切なことです。AIに学習させるデータ量が不十分だと、AIの学習結果が不正確になって充分なパフォーマンスを発揮できません。データ不足によって誤った判断をされてしまえば、AIを導入する効果は薄くなってしまいます。
そのため、事前に社内のデータ量を把握し、AIの導入に充分な量であるかを把握しておくことが重要です。どんなに優れたAIであったとしても、データ量が不足すれば業務効率化につながらない可能性もあるでしょう。
AIを導入する際には、AIを利用できる人材を確保するのも重要です。AIを最大限活用するためには、適切な運用や状況に合わせた改善ができる専用人材が求められます。業務効率化を進めるには、AIそのものに対する知識だけでなく業務に関しても詳しいことが重要です。
そのため外部の専門家ではなく、できるだけ社内の人材を登用することが理想的でしょう。ただし、社内の人材を育成する余裕がなければ、社外の専門人材に頼る方法も考えられます。

AIを導入することで、業務効率化の推進に役立ちます。単純労働をAIに担当させると、労働力不足の解消や働き方改革の推進が可能です。顧客対応や問い合わせ対応、製造業務や営業など、さまざまな業務にAIを活用でき、属人化している業務の解消や生産性の向上も期待できるでしょう。業務効率化の推進には、AIの導入をご検討ください。
業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。
メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。
AI製品・ソリューションの掲載を
希望される企業様はこちら