生成AI

最終更新日:2024/04/11
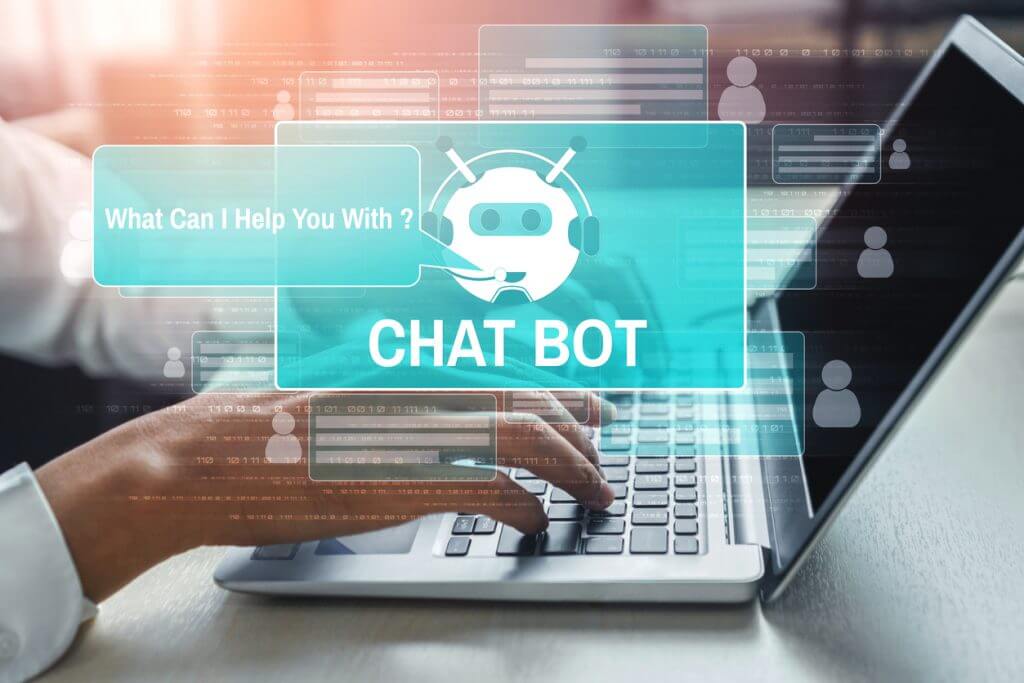
さまざまな業種で活用され始めているチャットボット。スマートフォンでも手軽に利用することができるため、実際に利用したことがあるという方も多いかと思います。もはや私たちの生活に馴染んだ存在と言っても過言ではありませんが、チャットボットは具体的にどのような仕組みで成り立っているのでしょうか。
今回は、チャットボットの仕組みや活用事例を分かりやすく解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
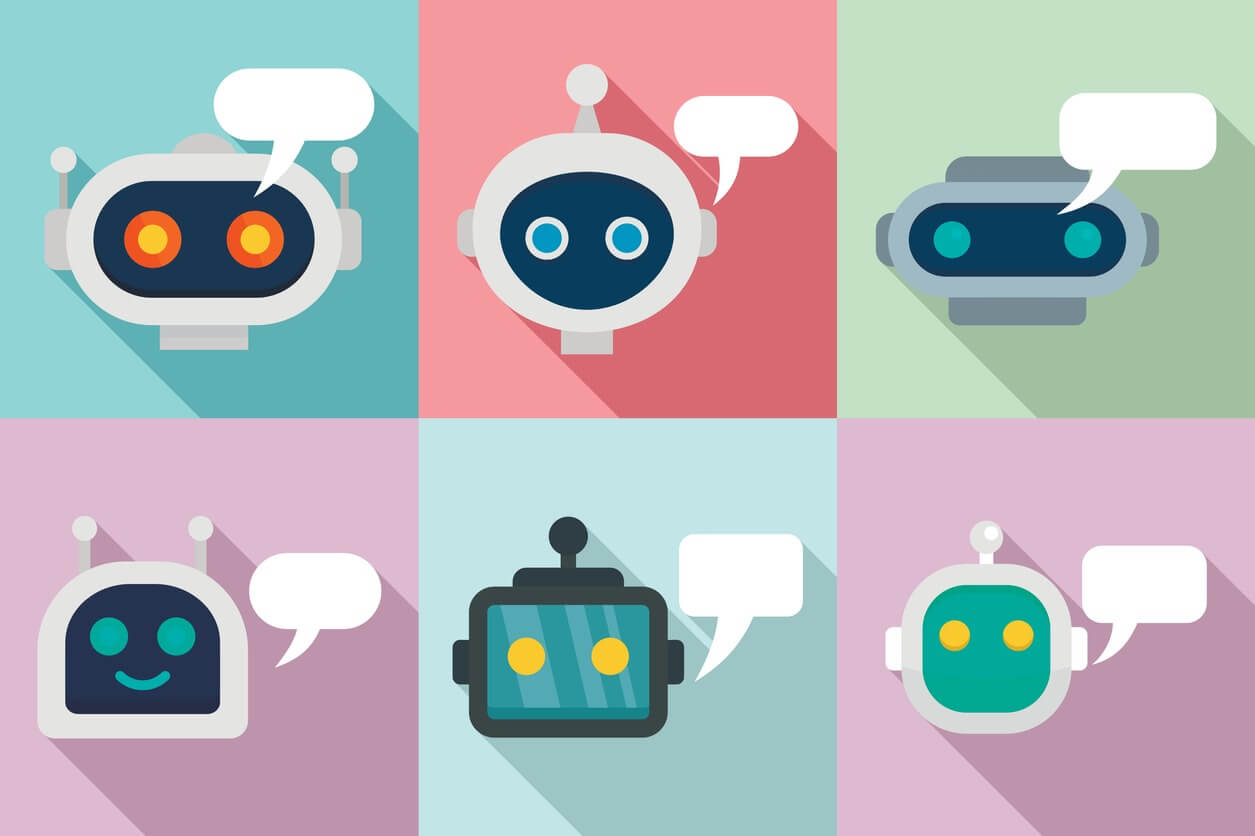
チャットボットとは、「チャット(Chat)」をする「ロボット=ボット(bot)」のことです。チャット形式で、打ち込んだ文章に自動回答してくれるものをイメージされる方が多いかもしれませんが、最近では「AIスピーカー」という音声会話タイプのものも存在しています。
そんなチャットボットは、大きく分けると「AI型」と「シナリオ型」という2つの種類が存在します。「チャットボット=AIが搭載されているもの」という認識を持たれている方もいらっしゃるかもしれませんが、必ずしもすべてのチャットボットにAIが搭載されているわけではありません。シナリオ型のチャットボットに関しては、AIが搭載されていないのです。
では、AI型とシナリオ型ではどのような違いがあるのでしょうか。それぞれのチャットボットの特徴を詳しく見ていきましょう。
その名前の通り、AIを搭載したチャットボットです。「機械学習型」といわれる仕組みを採用したチャットボットで、文章全体の意味を理解した上で回答を返すことができるという特徴を持っています。また、機械学習型の場合、過去のデータを蓄積して学習していくため、その学習を重ねるごとにチャットの回答精度が向上されていくのが大きな特徴です。
シナリオ型チャットボットにはAIが搭載されていないため、「Aという単語が含まれていたらBを返答する」といったルールを人間が事前に設定しておかなければなりません。また、AI型のように学習を重ねていくわけでもないため、不適切な返答が行われてしまう場合には、担当者が自ら修正を行う必要があります。
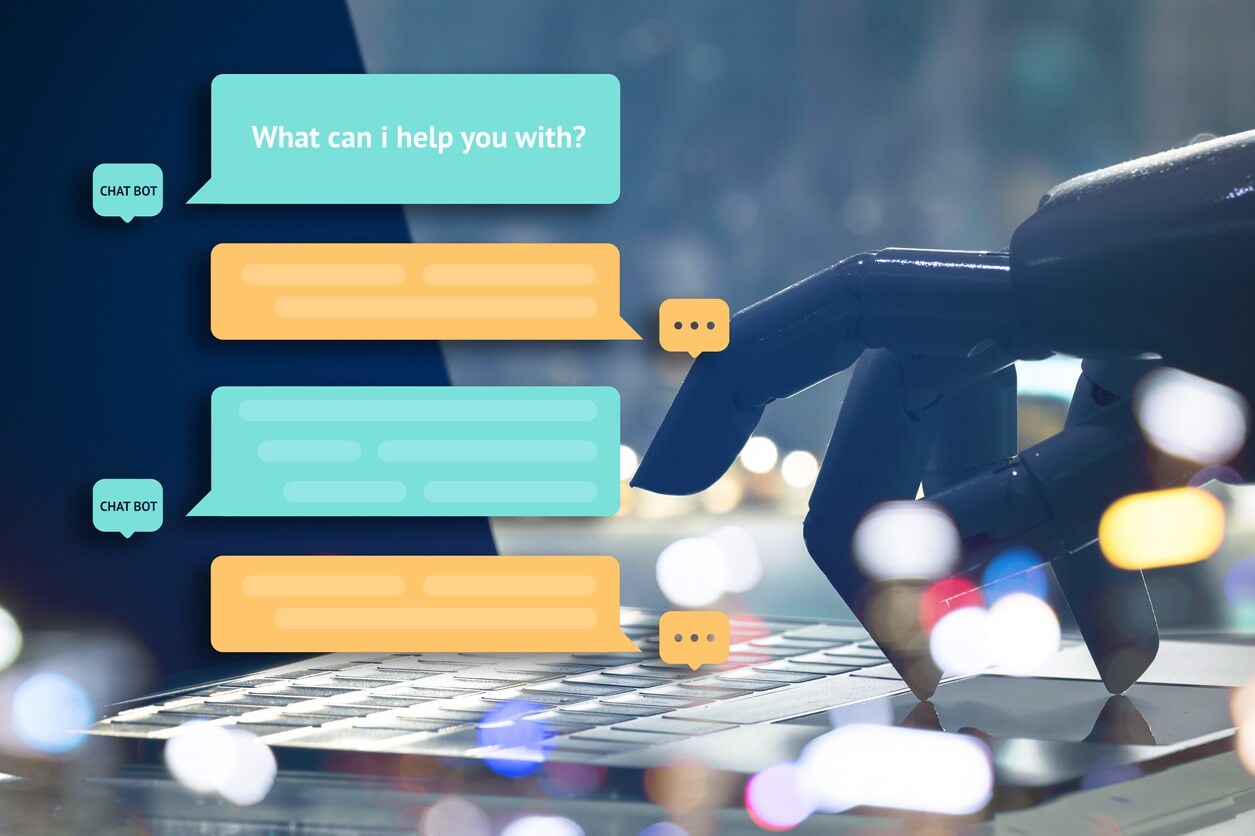
では、なぜチャットボットは人間同士の会話と同じように、ユーザーへの回答を行うことができるのでしょうか。それは、先ほどもご紹介したように人間があらかじめ「Aという単語が含まれている場合にはBを返答する」といったルール決めを行っているからに他なりません。これは、シナリオ型チャットボットにおいてもAI型チャットボットにおいても必要不可欠なものです。
また、キーワードを分析する機能も、チャットボットの機能を実現する仕組みとして欠かせません。多くのチャットボットは、ユーザーが行った入力からキーワードを抜き出し、そのキーワードに対する回答を行っているからです。
そのため、ユーザーが入力した単語の中から最も重要なキーワードを選ぶことができれば、常に正確な返答を行うことができます。とはいえ、必ずしも重要なキーワードだけを選べるわけではありません。だからこそ、AI型チャットボットは「重要ではないキーワードを選んでしまったときのデータ」も蓄積・学習することで、返答の精度を継続的に高めていくことができるというわけです。
なお、チャットボットには自分で言葉を組み立てる能力がなく、データベースから回答を選んで返答するのが一般的となっています。そのため、この「データベース」をいかに充実させているかという点も、チャットボットの精度に大きな影響を与えるポイントといえるでしょう。
最近ではユーモアのある言葉遣いで返答するチャットボットも多くなってきていますが、これはまさにデータベースを充実させているからこそ実現できているものなのです。
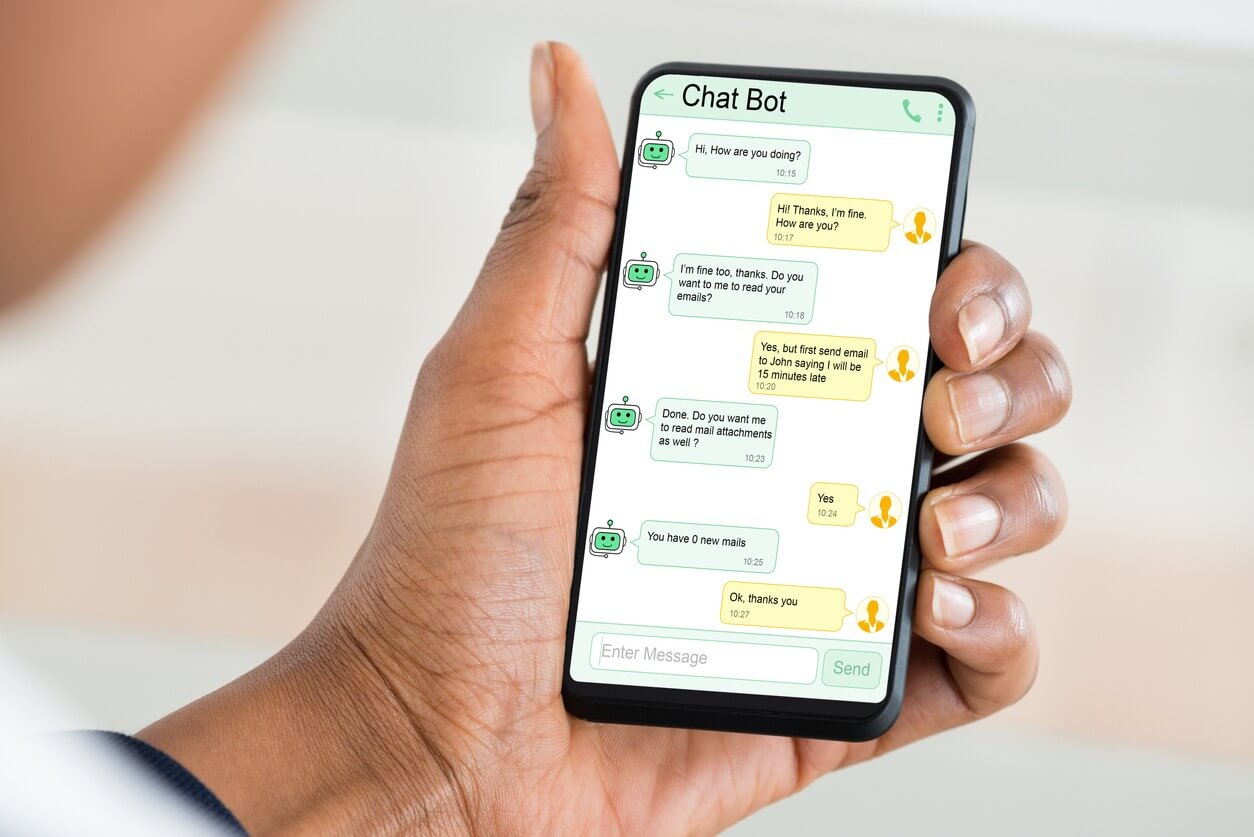
最近では大手企業や自治体も積極的にチャットボットを活用し始めています。ここからは、代表的な活用事例をいくつか見ていきましょう。
ポイントメディアサイト「Potora(ポトラ)」の運営を行っているNTTコムオンライン・マーケティング・ソリューションでは、チャットボットの導入によってスマートフォンユーザーの回遊率を高めることに成功しています。また、スマートフォンからの商品の申込数も増加したとそうです。そのような点を踏まえると、スマートフォンユーザーの悩みを解消しやすいサイトの環境構築に成功した事例といえるのではないでしょうか。
建設・工事業向けERPパッケージ「e2-movE」の販売を行っている三谷商事株式会社では、チャットボットの導入によって、課題だった人手不足を解消につなげることに成功しています。これまで、「e2-movE」に関する問い合わせは有人対応で行っていたものの、チャットボットの導入によって、人件費削減につなげることができたそうです。今後、少子高齢化に伴う人手不足はさらに深刻化していく可能性が高いため、チャットボットによる業務効率化に着手する企業も増えていくのではないでしょうか。
会津若松市では、AIチャットボットの導入によって、土日や夜間の問い合わせ対応の自動化を実現しています。休日の医療機関案内や、ゴミ出しの方法、各種証明書の案内などを知名集合で自動回答できるようにしたことで、職員も問い合わせ対応に追われてしまうことが無くなったそうです。
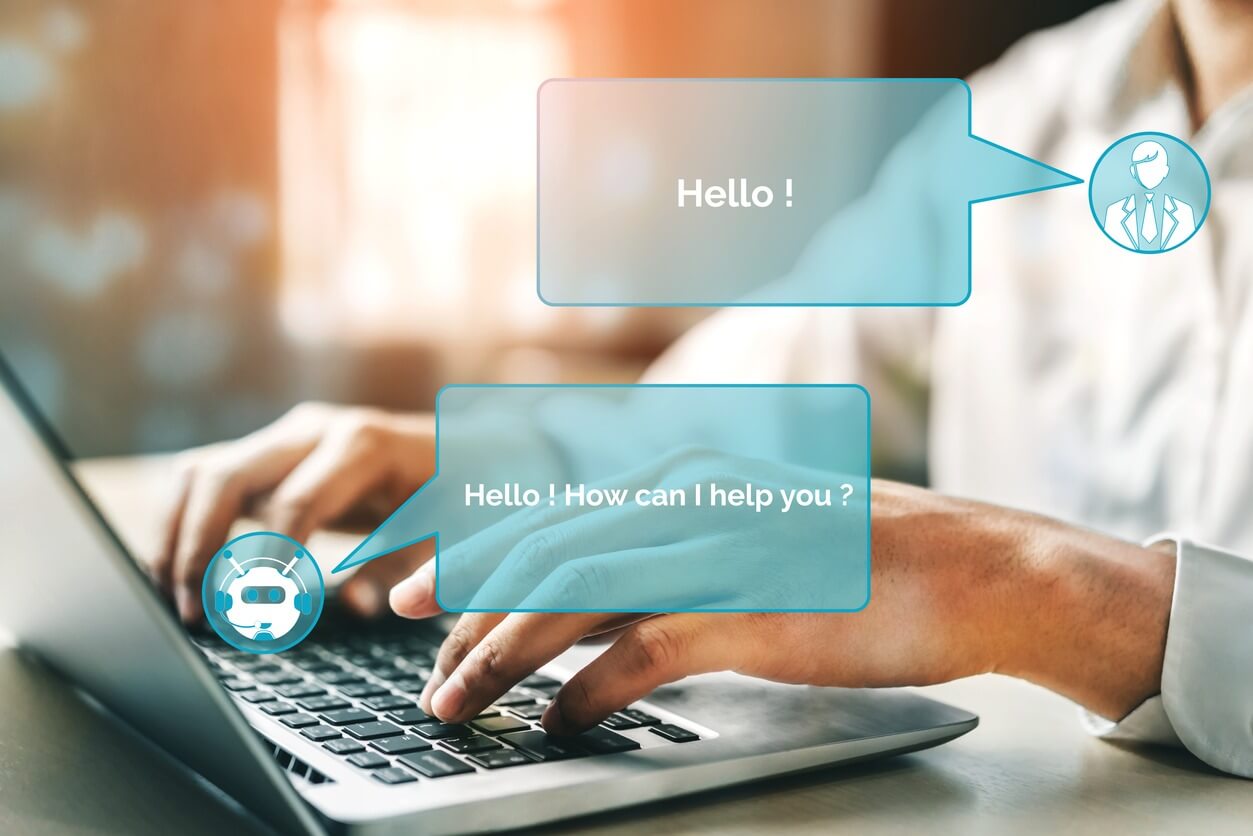
チャットボットには多くの魅力があることがお分かりいただけたかと思いますが、企業がチャットボットを導入するメリットとしては、どのような点が挙げられるのでしょうか。ここからは、チャットボットを導入することで得られる代表的なメリットについて見ていきましょう。
チャットボットを導入することで得られる最大のメリットと言っても過言ではないのが、24時間365日対応できるという点です。スマートフォンの普及に伴い、ユーザーはいつでもインターネット検索を行えるようになりました。そのため現在は、深夜に「この商品についてもっと詳しく知りたい」と思い立つケースも少なくないのです。
そのような場合に、チャットボットを設置しておけば、ユーザーの疑問を解消することができるため、顧客満足度向上にもつなげていくことができます。低コストで問い合わせ対応の環境を整えられるという点は大きなメリットといえるでしょう。
ユーザーから似たような問い合わせが頻繁に寄せられることは決して珍しくありません。その質問に毎回担当者が回答していくのは、決して効率的とはいえないでしょう。その点、チャットボットであれば問い合わせ対応を自動化できるため、従業員は他の業務へ力を注ぐことが可能になります。
問い合わせの窓口が電話やメールのみの場合、問い合わせというアクションを面倒に感じてしまい、離脱してしまうユーザーも少なくありません。その点、チャットボットであれば普段の友人とのチャットと同じ感覚で質問することができます。また、「相手がロボット」という認識があるため、ユーザーもより気軽に問い合わせを行うことができるのです。
今回は、チャットボットの仕組みや活用事例について詳しくご紹介しました。すでにチャットボットはさまざまな業界で導入され始めており、さまざまなメリットをもたらす存在であることがお分かりいただけたのではないでしょうか。
近年は人手不足が深刻化しているため、多くの企業にとって「業務効率化」は重大な課題となっていくでしょう。そのような事態を避けるためにも、ぜひチャットボットによる業務効率化にも目を向けてみてはいかがでしょうか。
業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。
メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。
AI製品・ソリューションの掲載を
希望される企業様はこちら