生成AI

最終更新日:2024/02/07

新たな可能性を生み出す技術として、さまざまな業界で注目を集めているAI・人工知能。一見、AIとは無縁のように思える「漫画」の世界でも、AIが活用され始めているのをご存知でしょうか。
漫画の神様とも言われる手塚治虫の新作が、AI技術の活用によって31年ぶりに生まれたことで大きな注目を集めているのです。
では、具体的にどのような方法で漫画が生まれたのでしょうか。今回は、漫画を作り出すAI技術の仕組みについて詳しく解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
画像認識の事例について詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
【最新】画像認識AIの導入活用事例10選!各業界企業の課題と導入効果まとめ
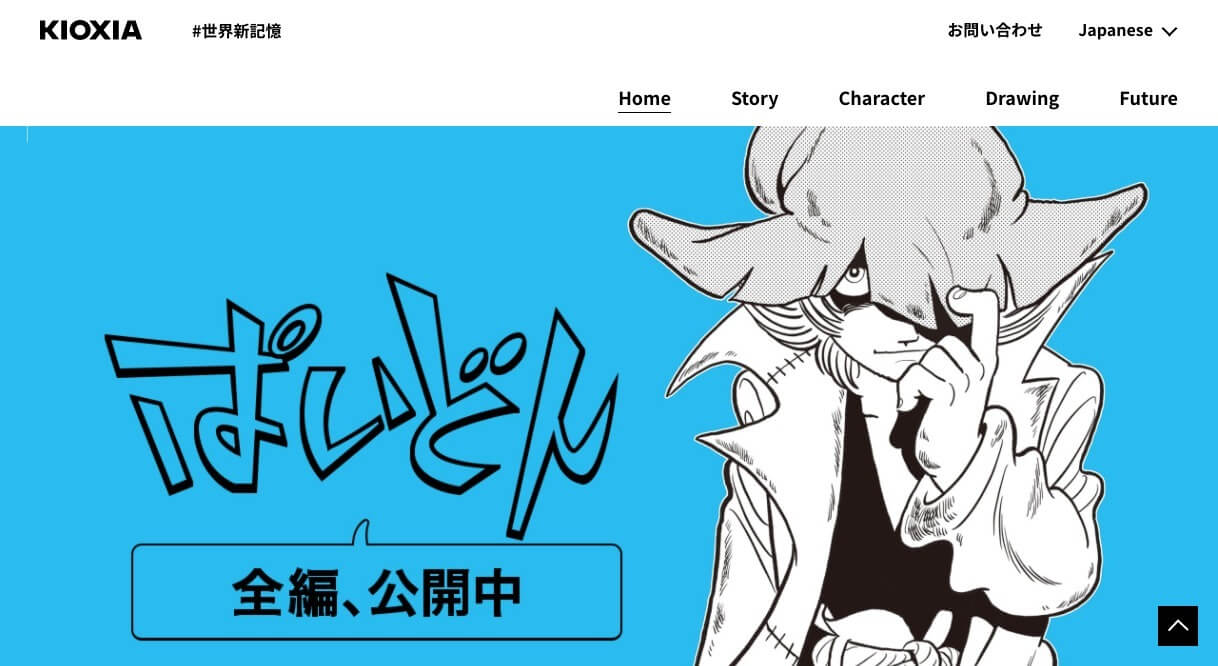
2020年2月27日発売号の週刊モーニング(講談社)に、手塚治虫の新作「ぱいどん」が掲載されました。この「ぱいどん」という作品は、2019年10月に東芝メモリ株式会社から社名変更したキオクシア株式会社のブランドキャンペーンとして生み出されたもので、AI技術を用いて新作を生み出したことから大きな注目を集めました。
「ぱいどん」は、2030年の東京・日比谷が舞台になっている漫画です。都会のど真ん中でホームレス生活を送る主人公のぱいどんが、小鳥型ロボットの「アポロ」と人型ロボットの「預言者」とともに、とある娘2人からの「失踪した父を探してほしい」という依頼を受けて捜査を進めていく物語です。
そんな「ぱいどん」では、あらすじ作りとキャラクター作りにおいて、2種類のAIが活用されているといいます。そもそもこのプロジェクトにおいては、AIがすべてのシナリオを細かく作ったわけではありません。ある程度AIを活用しながら、人も作品作りに関わっていたといいます。
そのような中でキオクシア株式会社が注目したのは「そもそもシナリオが枯渇している」という点だったそうです。昨今は、テレビドラマやソーシャルゲーム、そしてNetflixの自作品など、数多くの作品が存在しています。当然、世の中にはシナリオライターも数多く存在しているわけですが、決して潤沢に人がいるというわけでもありません。
そのため、シナリオライターと一緒に研究を続ける中で、「人間が生み出すシナリオのバリエーションはあまり多くない」という発見があったことから、このシナリオ作りという部分においてAIを活用していくことを決めたそうです。
物語には起承転結が存在するわけですが、大きな幕構成としては「発端」「展開」「結末」の3つに分けることができ、そこからさらに「日常」「事件」「決意」「苦境」「支援」「成長」といった計13のフェイズに分けることができます。
そのフェイズの各パーツを利用しながら、一貫性のあるシナリオを構築していくのは決して簡単なものではありません。そこで、13のパーツから新たなあらすじを生み出していくプロット生成の作業にAIを活用することで、より多様なプロット生成を実現することができたのです。
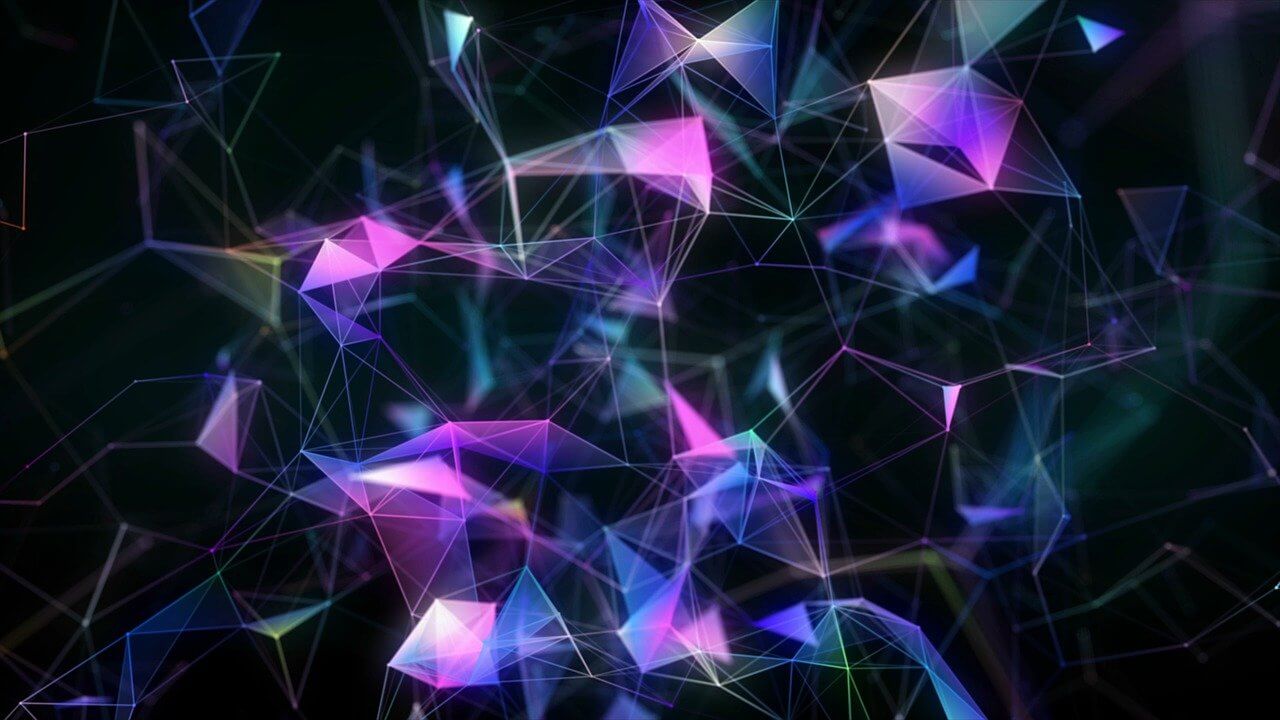
また、キャラクター生成においてもAIを活用したといいます。手塚治虫作品は合計700タイトルに上り、ページ数としては約15万枚にも上るそうです。一見、膨大なデータが存在しているため、キャラクター生成も比較的簡単に行えるように思えるかもしれませんが、実際に着手してみると、なかなかスムーズには進まなかったといいます。
そこで、キャラクターを生成するために最新のディープラーニングを活用し、昨今話題となっているディープフェイクによってキャラクター生成を行っていきました。ディープフェイクは生成モデルの一種であり、「ジェネレーター(generator)」と「ディスクリミネーター(discriminator)」という2つの種類のAIを活用して画像の生成などを行っていきます。
ジェネレーターは偽物を作ろうとするAIのことであり、ディスクリミネーターは偽物を見破るAIのことです。ジェネレーターは画像を何枚も生成するのですが、最初はディスクリミネーターに偽物であることを見破られてしまいます。しかし、少しずつジェネレーターの学習量が増えていくことで画像の精度が高まり、ディスクリミネーターも偽物であるかどうかを見破るのが難しくなってくるのです。
この仕組みによって、AIはさまざまな画像を生み出すことができるようになります。そして「ぱいどん」においても、これらのAI活用に加えて「転移学習」という技術を用いることで、過去の手塚治虫作品をもとにしたキャラクター生成が実現できたのです。

漫画業界では、「ぱいどん」の制作以外でもAIが活用され始めています。その一例としては、東大発ベンチャーのMantraが開発した漫画特化型の他言語翻訳システム「Mantra Engine」が挙げられるでしょう。
この「Mantra Engine」というシステムは、AIを活用することで、漫画らしい表現の自動翻訳が実現できるというもの。また、すべて同じブラウザ上で完結できるため、スピーディーに翻訳できるという点も大きな魅力のひとつです。
具体的な仕組みとしては、出版社側がクラウド側にアップロードした漫画の画像ファイルから自動でテキストが認識されると、Mantraの開発した機械翻訳エンジンが指定された言語で「漫画的な表現」に翻訳するというものです。
ただ、まだ完璧な翻訳ができるわけではなく、割合としては3割程度しか完璧に翻訳できないといいます。残りの7割に関しては修正の必要があるため、今後少しずつ改善されていくことが期待されます。
また、翻訳の精度は漫画のジャンルによっても大きく異なるそうですが、今後少しずつデータが蓄積されていくことで、翻訳の精度も高まっていくでしょう。
今回は、漫画を作り出すAI技術の仕組みについてご紹介しました。AIを活用することで、新たな漫画を制作できる可能性もあるということがお分かりいただけたのではないでしょうか。もちろん、すべてをAIに任せるだけで漫画を生み出せるわけではありませんが、人間の制作活動をサポートする役割として、AIも活用され始めていることがお分かりいただけたかと思います。
今後、より多くのデータが蓄積されることで、より革新的な作品が生み出される可能性もあるでしょう。どのような形でAIが漫画制作に携わっていくのか、ますます期待が膨らみます。
画像認識について詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
画像認識とは?AIを使った仕組みや最新の活用事例を紹介
業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。
メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。
AI製品・ソリューションの掲載を
希望される企業様はこちら