生成AI

最終更新日:2024/04/11

近年は多くのメディアでAIが取り上げられるようになり、AIに対する注目度も非常に高くなっています。また、実際にAIを導入する企業も増加傾向にあるため、その流れに乗ってAI導入すべきか悩んでいる企業も多いのではないでしょうか。
しかし、必ずしもAI導入によって望んだ成果を得られるようになるわけではありません。場合によってはAIを有効活用することができず、失敗に終わってしまうケースもあるのです。では、AI導入が失敗してしまう企業にはどのような原因があるのでしょうか。
今回は、AI導入に失敗してしまう企業の原因について詳しくご紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。

第3次AIブームといえる現代において、AIの導入を検討している企業は決して少なくないでしょう。しかし、AIに関する専門知識を持った担当者がいない企業の場合、「そもそも何をすれば良いのか分からない」「どのように運用すれば良いのか分からない」といった壁にぶつかってしまうケースも少なくありません。
AIの導入は、他社との差別化を図る上でも大きなチャンスとなり得る武器ですが、その一方で、導入に至るまでの苦労やリスクといったデメリットも把握しておくことが大切になります。導入に至るまでの苦労やリスクを知らずにAI導入を開始してしまうと、それらのデメリットに挫折してしまう可能性が高くなるからです。だからこそ、AIに関する知識をしっかりと蓄え、適切な方法で導入を進めていくことが大切になります。
また、AI導入に失敗してしまう企業に多く当てはまるものとして、「AIの導入自体を目的にしてしまうこと」が挙げられます。AIの導入はあくまでも手段であり、それ自体が目的になってはいけません。AIの活用によって何かしらの「成果」を上げるということが、本来の目的でなければならないのです。
そのため、もしAIの導入プロジェクトにおいて、導入すること自体が目的になってしまっているのであれば、今一度何のためにAIを導入するのか明確にしておいたほうが良いでしょう。
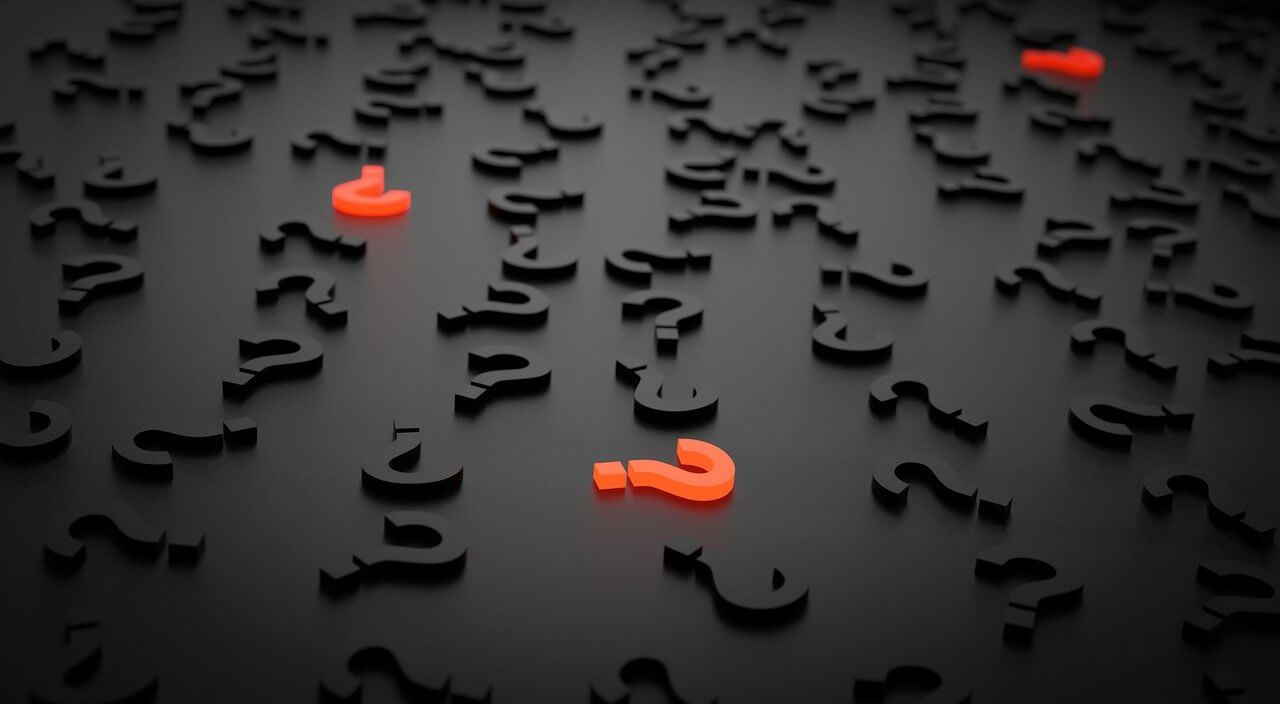
また、AIを導入する企業の中には、「AIに何ができるのか」「そもそも何にAIを使うのか」といった点を把握できていないまま導入してしまっている企業も少なくありません。そして、それらの企業の多くは「AIは何でもできる」と勘違いしてしまっている傾向にあるのです。
言うまでもなく、AIにも得意な分野と苦手な分野があるため、企業が抱えるすべての課題を解決に導けるわけではありません。しかし、その部分を勘違いしたままAI導入の計画を進めてしまう企業が意外と多く存在しているのです。では、そのような認識のままでAI導入を進めた場合、企業はどのような状況に陥ってしまうのでしょうか。いくつか具体的なケースをみていきましょう。
たとえば多くの営業部隊を抱える企業の場合、営業や接客の支援としてチャットボットの導入を検討することもあるでしょう。チャットボットを適切な方法で活用すれば、より高い精度で顧客とのコミュニケーションが図れるようになるため、営業や接客の効率化を実現することも可能です。
しかし、チャットボットを有効活用するためには「回答精度」を高めなければなりません。そしてその回答精度を高めるためには、教師データが必要不可欠となります。開発当初の段階で適用範囲を拡げすぎてしまうと、その教師データを収集するための労力も増大してしまうため、「結果的に人が問い合わせ対応したほうが良い」という結論に至ってしまうケースがあるのです。
AI導入の効果は、必ずしも短期間で現れるわけではありません。しかし、AI導入の経験が少ない企業の場合、短期的なKPIでチャットボットの効果を評価してしまい、AIの導入を失敗と決めつけてしまうケースもあるのです。
KPIを達成することができていない状況でも、その裏で別の効果が生まれている可能性は十分に考えられます。たとえばチャットボット運用において「クレームの件数を半年で3割減少させること」を目標にしている企業が目標達成に至っていない状況でも、導入以前には寄せられていなかった新たな声(質問)が寄せられるようになるなど、別の効果が現れている可能性があるわけです。また、チャットボットの導入によって24時間365日の対応が可能になれば、顧客満足度にも影響が現れているかもしれません。
このように、現場からみえる効果と数値的な効果は必ずしも一致しているとは限らないため、AI導入は長期的な視野で判断していくことも大切になるのです。
工場の生産ラインにAIシステムを導入した場合、そのシステムの導入によって不良品の特定をよりスピーディーに行っていくことが可能になります。当然、その特定スピードを早められれば生産性向上にもつなげられるわけですが、不良品の検出を高精度かつスピーディーに行えるようになった場合、不良品を取り除く作業も同時にスピードアップしなければなりません。
AIによって不良品の検出スピードを高めることができても、不良品を取り除く作業のスピードが追いつかなければ意味がないため、これまで以上に多くのリソースが必要になるわけです。場合によっては産業用ロボットの追加購入なども必要になるため、あらかじめ生産ラインの業務全般をしっかりと把握した上で、AI導入を検討していくことが大切になるでしょう。
今回は、AI導入に失敗してしまう企業の原因について詳しくご紹介しました。AI導入に失敗してしまう企業の多くは、「AIに何ができるのか」を把握できていないことがお分かりいただけたのではないでしょうか。
AIを有効活用すれば業務効率化や生産性向上につなげることができるのは事実ですが、すべての問題を解消してくれるわけではありません。AIにも得意なこと、苦手なことは存在しますので、そのメリット・デメリットをしっかりと把握したうえで導入を検討することが大切になるでしょう。
業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。
メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。
AI製品・ソリューションの掲載を
希望される企業様はこちら