生成AI

最終更新日:2024/04/04

AI・人工知能の技術はさまざまな分野で活用され始めており、精度の高い分析・予測によって多くの企業が製品(サービス)の品質向上を実現しています。そんな中、AIの導入は医療分野でも進んでおり、AIを活用した医療機器の開発なども行われているのです。
その中でも特に大きな注目を集めているのが、東京を拠点とする株式会社AIメディカルサービスです。2019年10月4日に、4,290万ドル(日本円で約46億円)の資金を調達したことを発表しました。AIメディカルサービスでは、この資金をもとに「内視鏡の動画からがんの兆候を発見するソフトウェア」の臨床実験や製品開発を行っていくことも発表していますが、具体的にどのようなプロダクトなのでしょうか。今回は、AIメディカルサービスの「内視鏡AI」について詳しくみていきましょう。
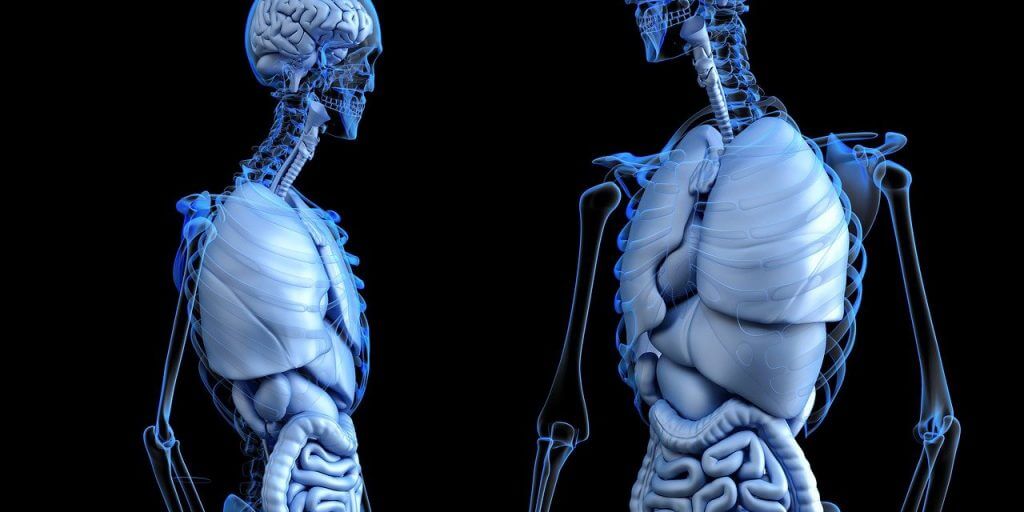
株式会社AIメディカルサービスは、2017年の設立以降、5,700万ドルの資金調達を行っています。先ほどご紹介した2019年10月の資金調達以前にも、2018年8月にインキュベイトファンドから900万ドル(日本円で約10億円)を調達しました。
これらの資金をもとに開発が進められている内視鏡ソフトウェアは、食道や胃、腸といった消化器における「がんの兆候」を見つけ出すことを目的にしているといいます。AIを活用することで、これまで医師などが時間をかけて行ってきた画像チェックの時間を大幅に削減することが狙いなのです。それを実現するため、AIメディカルサービスでは現在約80の医療機関と協力する形で研究を進めています。
AIメディカルサービスCEOの多田智裕医師によれば、内視鏡の市場は毎年10%ずつ成長を見せているといいます。そして、その市場の70%は日本のメーカーによって占められているというのです。そのためAIメディカルサービスでは、内視鏡AIの製品開発だけでなく、タイ、インドネシア、シンガポールといった胃がん発生率が高い傾向にあるアジア諸国への海外展開も見据えているといいます。

また多田医師によれば、これまでの医療現場では、医師の処理能力を大幅に上回ってしまうほど仕事量が多くなっていることが大きな課題になっていたといいます。多田医師は、東京大学医学部付属病院や虎ノ門病院などでの勤務を経て、2006年に自身のクリニックを開業しました。このクリニックでは年間約9000件もの内視鏡検査が行われているといいます。
また、多田医師の所属している医師会では、月に何度か専門の医師によるダブルチェックが行われているそうです。しかし、ひとりの医師が1時間あたり3000枚近くの内視鏡画像を確認しなければならないケースもあり、医師の負担が非常に大きくなってしまっていたといいます。さらに、日中は通常の業務を行わなければなりませんから、これらの業務は基本的にすべての業務が終了した後の夜間に行われていたそうです。
さすがにこのような業務体系では身体的にも精神的にも限界が訪れてしまう可能性があることを感じ、多田医師はAIを活用した内視鏡画像診断に着目したといいます。そのきっかけとなったのは、2016年に参加した東京大学・松尾豊氏の講演会でした。
松尾豊氏は講演会で「AIによる画像認識能力の進歩」についての話をしており、多田医師はその話を聞いたときに「AIが画像診断を得意としているのであれば、内視鏡画像のチェック業務にも活かせるかもしれない」というアイディアが思い浮かんだといいます。
とはいえ、その時点で「内視鏡にAIを活用する」という取り組みを行っている人は存在していませんでした。そのため、多田医師は後輩から紹介で知り合ったAIエンジニアや、知人の医師、地元のクリニックなど協力する形で、内視鏡AIの概念実証に自ら取り組み始めたのです。
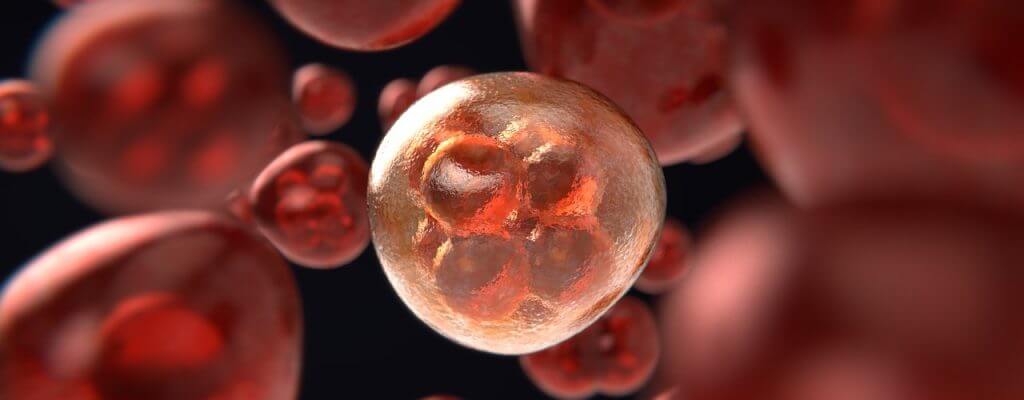
多田医師が始めに取り組んだのは、胃がんの原因とされているピロリ菌の有無を区別するためのAI開発です。約4〜5ヶ月にわたる研究によって開発された製品は正答率約9割と、医師の平均を上回るものでした。人間の医師を含めたテストでは、23人中4位という極めて優秀な結果も残したといいます。
とはいえ、ピロリ菌の診断を高い精度で行えるだけでは十分とはいえないことから、次は胃がんを診断するAIの開発に着手しました。当時は個人で取り組むだけの小規模なプロジェクトだったものの、より本格的な研究開発を進める必要があったため、2017年9月にAIメディカルサービスを設立。ついに会社としての挑戦がスタートしたのです。
AIメディカルサービスの開発した内視鏡AIでは、撮影された画像から「何が、どこにあるのか」を判別することができ、その上で画像のカテゴリ分けを行っていくことが可能です。
なお、2018年1月には静止画から6mm以上の胃がんを約98%という高い精度で発見することに成功したという研究成果を発表しました。また、このAIは高い精度で画像の識別を行えるという点だけでなく、「画像1枚あたり0.02秒」というスピード感での診断も実現しているのです。
まさに、先ほどご紹介した多田医師の課題を解消することができるAIであることがお分かりいただけるでしょう。仮に3000枚の内視鏡をチェックするとしても、AIであればわずか60秒で終えることができてしまうわけです。これまでは、医師が1時間かけてこの作業を行ってきたわけですから、業務効率化という面でも大きな貢献をしていることが分かります。
ちなみに現在は、静止画だけでなく動画からリアルタイムで胃がんを検出できるAIの開発にも着手しているそうです。動画でリアリタイム検出を行う場合、静止画に比べて難易度が高まってしまうため精度は少し落ちてしまう傾向にあるものの、検出の精度は92%ほどを誇っています。
また、多田医師は食道がんや大腸がんの研究にも着手しており、まずは製品化の第一弾として胃がんを検出するAIのリリースを計画しているそうです。数多くのがんが存在する中で胃がんを選択したのは、「専門医でも見分けるのが難しい場合も多く、現場のニーズが一番大きいから」だといいます。
実際、胃がんは1割ほど見逃されていると推定されており、その結果重症化してしまっているケースも少なくないそうです。仮に、内視鏡AIによって初期段階から胃がんの可能性に気づくことができるようになれば、より医療の質も高まり、患者さんの安心感につなげられるでしょう。当然、技術的なハードルは高くなりますが、多田医師は実際に現場を経験しているからこそ、胃がんから始めることにこだわりを持っているのです。
これについて、多田医師は以下のように語っています。
「内視鏡AIのイメージとしては、優秀なアシスタントがついてくれるようなものです。今まで見落としてしまっていた病変にもしっかりと気づくことができるようになれば、より医療を実現できます。患者さんは今までよりも高精度の検査を受けることができるようになりますし、医師が検査を行う負担も減少させることができるでしょう。」
現在、AIメディカルサービスは、約80の医療機関と共同で研究開発を進めています。当初は、プロダクトの構想を話した際に「医師がいらなくなるのではないか」といった声も多く上がったそうですが、時間の経過とともに「便利そうだね」といった声が多くなってきたといいます。
AIはあくまでも診断の補助となる確率を示すだけであり、確定診断を下すわけではありませんから、医師プラスAIといった構造で良い医療を実現していくことが大切になるでしょう。
多田医師がAIに着目するきっかけとなった2016年の講演会から3年が経過し、新たなプロジェクトも次々と立ち上がり始めているといいます。さまざまな企業で内視鏡AIの研究が行われるようになったわけですが、それぞれの内視鏡AIが対応している症例やフォーマットは大きく異なるため、一概にこれらを比較するのは難しいといいます。ただ、その中でひとつ大きなポイントを挙げるとすれば、「教師データの量・質」ということになるでしょう。
これは内視鏡AIに限った話ではありませんが、AIの精度を高めていくためにはその教師データを大量に集める必要があります。当然、量だけではなく質も伴わなければなりません。つまり、その教師データを集めるためには専門医の協力が必要不可欠であるということです。
その点を踏まえると、現在約80の医療機関とタッグを組んでいるAIメディカルサービスは、「AIの精度を高めていくための環境が整っている」といえるでしょう。何より、多田医師自身も約20年間にわたって内視鏡医を続けてきているわけですから、誤った教師データでAIが学習してしまうというリスクも回避できると考えられます。したがって、AIメディカルサービスの内視鏡AIが、日本だけでなく海外へ進出していく可能性も十分にあるといえるのではないでしょうか。今後のAIメディカルサービスの動向に注目が集まります。
業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。
メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。
AI製品・ソリューションの掲載を
希望される企業様はこちら