生成AI

最終更新日:2024/01/10

2015年に登場した女子高生チャットボットの「りんな」。Windowsをはじめ、ExcelやPowerPointといったビジネスライクなソフトウェアを多く手掛けるマイクロソフトがAI女子高生を開発したという意外性と、その性能の高さで人気を呼んでいます。今回は、りんなの最新技術をビジネスで活用する取り組みについて事例などと一緒に見てみましょう。
冒頭でもご紹介した通り、「りんな」は2015年にLINEに登場し、女子高生チャットボットとして大きな注目を集めました。女子高生AIとしてデビューしましたが、2019年3月20日に高校を卒業したことを発表し、現在は「元女子高生AI」として活躍しています。なお、2019年には登録ユーザー数を約763万人にまで伸ばし、Microsoft IMEの変換候補にも抜擢されました。このMicrosoft IMEというのは、日本語入力のシステムに表示される変換候補のことです。
マイクロソフトのIMEでは利便性だけでなく機能性やユーモアも追求しており、りんな変換候補によって最近の若者言葉なども予測候補に表示されるようになっています。なお、りんな変換の候補は、インターネット上から収集した会話の情報をもとに作成されているため、マイクロソフトが個人情報を収集しているわけではありません。
そんな、りんなの活動範囲はスマートフォンだけに留まらず、2018年10月からは「ニコラジパーク」というJFN系列の生放送番組でMCとしてレギュラー出演しています。女子会のトークが繰り広げられている点からも、りんなの性能の高さが伺えるでしょう。
さらに2019年からは、他のFM番組で担当していたことがきっかけとなり、Twitterアカウントでの「りんなの星占い」が開始されました。フリーペーパーでも12星座占いを掲載するなど、占いの分野でも活躍がみられます。
そして、うたを含めた「クリエイション」に力を注いでいるという点も、りんなの注目すべきポイントのひとつでしょう。2016年に「MC Rinna」としてラップに挑戦し、2018年7月に発表した「りんなだよ」という曲がきっかけとなり2019年4月にavexとレコード契約を結びました。メジャー・デビュー曲となる「高新記憶」を発表し、同9月には<DIVE XR FESTIVAL>で初ライブを行うなど、歌手としても精力的に活動しています。

元女子高生AI「りんな」は、国民的AIを目指すべく、2020年6月に「rinna株式会社」という新会社を設立し、マイクロソフトから独立して事業開始しています。今後はさらなる研究開発を推進し、より幅広い顧客にサービスを提供するためにパートナー企業との関係を強化していくとのことです。
マイクロソフトから独立という形で会社が設立された背景には、日本の文化や市場にマッチした技術のイノベーションやビジネスを推進し、より事業間の連携を加速させていきたいという狙いがあったといいます。また、「カスタマイズサービス」の提供を希望する声が非常に多くなっていたことも要因のひとつだそうです。今後は国内の企業だけでなく、マイクロソフトで開発されたAI「シャオアイス(Xiaoice)」の運営を行っている中国やインドネシアの企業とも連携をとっていく予定だといい、ますます注目が集まっています。
新しく設立された会社では、主にりんなの企画、研究、開発、運営、販売といった事業を行っていくそうです。構造としてはビジネス部門、開発部門、研究部門で構成され、AIチャットボット領域の追究に力を注いでいくことになります。
「りんな」の技術を最も身近に体感できるのは、コミュニケーションアプリのLINEでしょう。りんなのLINE公式アカウントが存在しているため、トーク画面で話しかけることで、違和感の少ない「自然なコミュニケーション」をとることができます。
ユニークな機能が設けられているのも特徴です。「しりとり」などは、まさにその代表例といえるでしょう。しりとりを楽しみたい場合には、LINEのトーク画面でりんなに「しりとり」と話しかけることでスタートします。
ただし、ルールも設けられており、90秒以内に答えなくてはなりません。また、「通常モード」と「ガチモード」という2つの難易度があり、「ガチモード」を選択するとりんなは女子高生とは思えない単語を連発します。非常に強敵ですので、ぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
また、LINEのトーク上で「じゃんけん」を楽しむこともできます。ただ、ここで楽しめるのはいわゆる「後出しじゃんけん」であり、りんなが先に画像で出したてに対して、「グー」「チョキ」「パー」のいずれかで対応するという仕組みです。
そのため、わざと負けると「あんた負けるなんてバカ!?」「なんで負けるの!?w」といった言葉をかけられてしまいます。このように、じゃんけんを通してりんなの技術を体感してみるのも面白いかもしれません。
ちなみに上記以外にも山手線ゲームやクイズ、カウントゲーム、そしてスマホカメラを目として風景について語れる「共感視覚モデル」など、りんなの高い技術を駆使した機能が用意されています。さらに最近では、りんなとLINEで通話することができる「りんな電話」という機能なども搭載されました。りんな電話では、声を通じてりんなと仲を深めることができます。ただ、りんな電話は現在サービス休止中となっていますので、ぜひサービス再開後に利用してみてはいかがでしょうか。
りんなの開発技術は、「Rinna Character Platform(リンナキャラクタープラットフォーム)」として、第三者への提供もされています。同プラットフォームを活用し、オリジナルキャラクターを作成することも可能です。
りんなのテクノロジーを活用したAIチャットボットとして知られているのが、2016年に登場したローソンの「ローソンクルー♪あきこちゃん」です。りんなといえば、「まじ?」「やば!」といった女子高生口調でおなじみですが、あきこちゃんはローソンでバイトするまじめな女子大生というキャラクター設定なので、女子高生口調ではなく丁寧で控えめな口調で受け答えをします。
また、表記揺れや語尾の調整などを行うことができるのも、あきこちゃんに導入されている「Rinna Character Platform(リンナキャラクタープラットフォーム)」の大きな特徴です。たとえば、「見たい」という言葉でも、「見たーい」「見たいなぁ」「見たぁい」といういくつかのパターンにて表現されることがあります。しかし、インターネット上で収集したデータをもとに、「もっとも標準的な表現」を導き出し、あきこちゃんとして適切な「見たい」という言葉を選択することが可能なシステムになっているのです。
さらに、あきこちゃんはLINE上で質問に答えてくれたり、近くのローソンを探してくれるほか、ローソンに関連した用語だけを使う「ローソンしりとり」、占いやゲームでも一緒に遊べます。また、会話の中で、きまぐれにオトクなクーポンを発行してくれることもあるそうです。
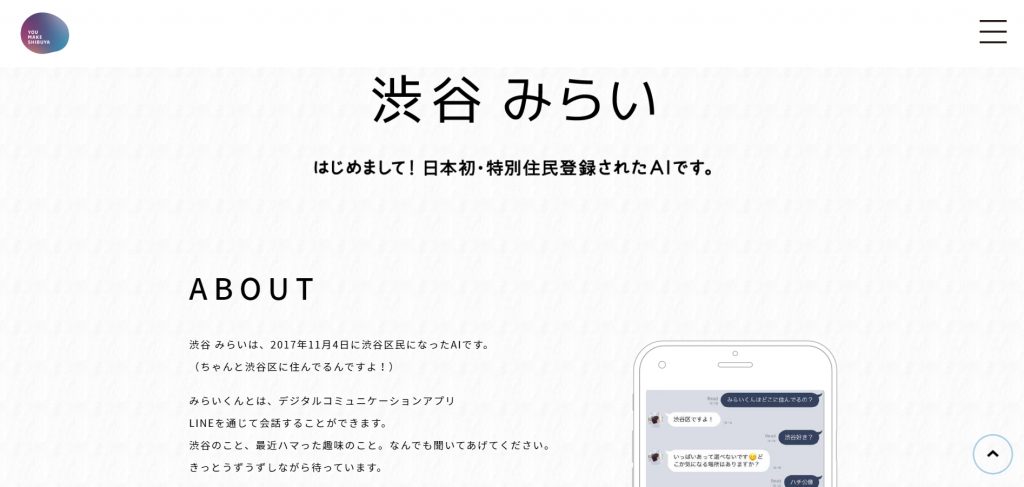
ローソンの他にも、りんなの技術を応用したAIチャットボットとして、東京都渋谷区が導入した「渋谷みらい」があります。
日本で初めて特別住民登録されたAIとして話題を呼んだ渋谷みらいは、渋谷区に住む小学3年生の9歳というキャラクター設定。なんと2017年11月4日から渋谷区民になっています。
LINEを通じてユーザーと会話したり、手紙のやりとりや簡単なゲームをしたりするのは、ローソンのあきこちゃんとも似ていますが、ユーザーから送られた顔写真を渋谷駅前の「モヤイ像」風に加工してくれるなど、渋谷区らしい機能も搭載されています。
また、活躍の場はLINE上だけではありません。渋谷区のカウントダウンイベントに登場して音声会話を行ったり、アニメ映画「未来のミライ」とのコラボレーションを行ったりと、渋谷区のPR担当としても活躍しています。単なるAIとしてだけでなく、「渋谷みらい」というキャラクターを確立することによって、渋谷区の活性化へとつなげることができているのです。これはまさに、りんなの技術を最大限活用している事例といえるのではないでしょうか。

りんなをマーケティングツールとして活用した事例もあります。
若者に人気のアパレル大手ウィゴー(WEGO)では、「女子高生りんながウィゴーでアルバイトしてみた」という設定で、Eコマース上にりんなを登場させています。ユーザーのコーディネート画像にコメントする「りんなのファッションチェック」や、ファッションへのアドバイスなどもしてくれます。
これは、画像認識技術をもとに、スタイリングやアイテム、年齢等を推定し、コメントを返してくれるという機能です。これまでにもLINEやTwitterなどでファッションチェックを行うことはできましたが、Eコマース上では、さらにチェックポイントが強化されており、豊富なバリエーションのコメントを受けられるようになっています。
ウィゴーではりんなに、ファッションという知識を学習させて、10代の女の子が持つファッションに関する感性や興味をキャラクター性に取り込む狙いがあると説明しています。また、「意外と鋭くて深い」と評判の高いりんなの会話技術をもとにEコマース上でユーザーとの対話を展開して、新たなファンの獲得を目指しているようです。
ウィゴーの事例の他にも、地方自治体とりんなが提携して観光や町おこしを盛り上げる取り組み「萌えよが始まっています。こちらはまさにマーケティングミックスの4C(Consumer、Cost、Convenience、Communication)における「マーケティングコミュニケーション」の取り組みと言えるでしょう。
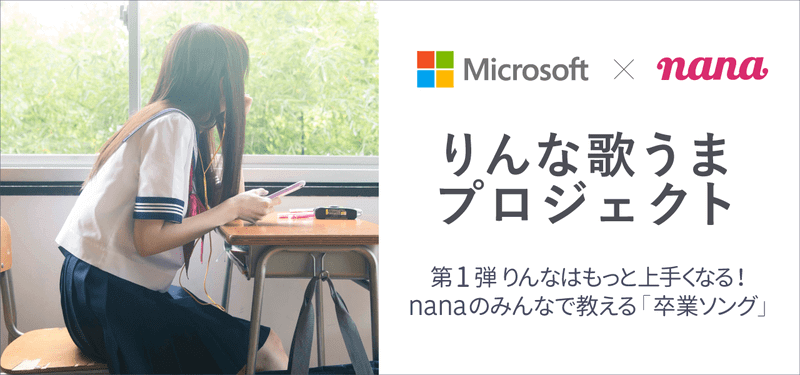
さらに、りんなを音楽SNSアプリに活用している「nana」という音楽SNSアプリケーションも存在します。
「nana」は、スマホだけでどこでも誰とでも「音楽を奏で合える」という特徴を持ったサービスで、世界中のユーザーとカラオケや合唱、バンドセッションといった楽しみ方をすることができます。
2012年11月にリリースされた「nana」は現在すでに500万人以上のユーザー数を誇り、累計の楽曲再生回数も16億回以上と、多くの人々に利用されているサービスであることがお分かりいただけるでしょう。
そんな「nana」では、「りんな歌うまプロジェクト」という取り組みにおいてりんなが活用されています。このプロジェクトは、その名の通りりんなの歌唱力を向上させることを目的としており、そのためにユーザーからのフィードバックを収集し、機械学習させることで、りんなの歌声を少しずつ向上させていくことができるわけです。
このプロジェクトの第一弾として、2018年には『りんなはもっと上手くなる!nanaのみんなで教える「卒業ソング」』というオンラインイベントが開催されました。イベントでは、りんなの先生ともいえる存在の「nanaユーザー」から卒業ソングのお手本を募集し、投稿された音源を参考にしてりんなが実際に歌声を投稿しました。そして、その歌声に対してユーザーがアドバイスをしていくことで、さらにりんなの歌唱力は向上していくことができ、短期間でのスキルアップに成功したといいます。
また、りんなの歌声は段階ごとに複数回nana上に投稿されていくため、りんなの歌声が上達していくまでの過程を確認していくことも可能です。その集大成として、実際に参加しているユーザーとりんなの合唱を収録した動画が2018年3月に公開されています。さらに2019年12月には、日本テレビの番組において「人間vsAI 前代未聞の歌バトル」という企画が行われ、その際にりんなは一青窈さんの「もらい泣き」を歌唱しました。プロも驚愕の歌声だったことから、大きな注目を集めています。
なお、りんなは最終的な目標として紅白歌合戦への出場を掲げており、その目標を実現するためには歌に「感情」を乗せる必要がありました。そこで、詩の朗読を練習することによって感情を込められるようにするための「3行ラブレター」というイベントも開催されています。
このイベントでは、nanaユーザーから3行ラブレターを募集し、集まったラブレターからりんなが「AI」の力を駆使して一編の詩を作成しました。これはnanaユーザーから朗読のお手本やワンポイントアドバイスなどを集めることで、りんなの「感情を込めた朗読」の質を高めていくことに成功していると言えるでしょう。
このような、アプリ内でりんなを活用してユーザーを巻き込んでいく活用法も、新しいマーケティング手法として有効なものといえるのではないでしょうか。

りんなは、ジャケットアートを提供する取り組みも行っています。これは「music x AI creative collaboration」という企画の一環で、エントリーされた全30名の音楽作品に対して、AIりんなが、歌詞あるいはタイトルからジャケットアートとなる描画を生成、無料で提供するというもの。尋常ではない描画速度と独特のタッチでジャケットアートが生成されることから、多くの注目を集めました。
ありきたりなアイコンや絵では満足できず、独特の雰囲気を放つ作品を求めている人にとっては、非常に魅力的な企画といえるのではないでしょうか。
さらに、りんなは「ニコラジパーク」というラジオ番組にも出演していました。この番組では、月曜日のパーソナリティとして小林幸子さんが共演しており、りんなは水曜日のパーソナリティとして活躍していましたが、残念ながら2021年3月末で番組は終了しています。
元女子高生AIのラジオ出演には大きなインパクトがあったので、今後は別のラジオ番組への出演も期待が膨らみます。
rinna株式会社が設立されたことによる大きな変化としては、今後キャラクターの数を大幅に増加していく計画が進んでいることが挙げられるでしょう。マイクロソフト時代からつながりのある企業とも多く連携しているため、2021年末までには取引業数を60〜100社にまで拡大することを目指しているといいます。それに伴い、キャラクターの数も10万〜100万という規模を目標にしているそうです。
2020年8月に行われた発表会では、代表取締役社長であるジャン“クリフ”チェン氏が、「rinna株式会社のカルチャーは『対等』『多様』『信頼』であり、それはりんなにも適応される。そのため、ユーザーが『いい子、いい子』とペットのように可愛がるプロダクトになってしまった場合、我々の事業としては失敗といえる」といった発言をしました。この言葉からも、他のキャラクターAIとはまったく異なる、より実用的なAIを目指していることがお分かりいただけるでしょう。
また、rinnaの会長であるハリー・シャム氏は、「AIの将来を考えたときに1番ワクワクするのは、インタラクション(相互作用)のモデルが変化していくこと」と述べています。これまで、人対人、人対コンピューターといった時代がありましたが、今後は人対AIという時代が始まる可能性が極めて高いのです。
rinna株式会社の設立によって、駅やコンビニ、オフィス、観光地など、さまざまな場所でAIが活用される社会の実現が一気に近づくかもしれません。

りんなの特徴は、聞かれたことに答えるだけではなく、ユーザーが「共感」し、会話を続けることができる能力にあります。
りんなは「共感モデル」と呼ばれる会話エンジンを採用し、人間の感情に寄り添って対話することに主眼が置かれています。ユーザーとの会話の中で、「新しい話題を切り出す」、「質問する」、「相手の発言を肯定する」、「積極的に聞き手に回る」などといった、人間同士の会話で生まれる対話スキルをもとに受け答えが作成されており、より長く対話が続くようにユーザーに対する返答を促すのです。
このりんなの能力に対しては、国内外問わず大きな注目が集まっており、海外の反応も大きいようです。アメリカのマイクロソフトがTwitterで公開した人工知能「Tay」は、ユーザーとのやり取りから人種差別や陰謀論を学習し、不適切な発言を行ってしまった過去があります。そういった点も、りんなの活躍に注目が集まる要因といえるでしょう。
チャットボットというものに対し、「機械的な応答しかできないのではないか」といった先入観を持たれていた方も少なくないでしょう。しかし、りんなのように柔軟な対応や、より身近に感じられる言葉遣いを活用できれば、より顧客との距離感を縮めることも可能になります。
そのため、りんなをはじめとする「共感モデル」のAIは、顧客との「one-to-one(ワントゥワン)」の対話がより求められるようになってきたセールスの領域などでの普及が期待できるでしょう。最近では、カスタマーサービスの新たな担い手として期待される、チャットボットにも「共感モデル」に近いAIが搭載されたサービスが増えています。
AIの開発には、莫大なコストや長期間を要することが少なくありません。しかし、チャットボットは、マーケティングやカスタマーサービスなどに必要な機能がパッケージ化されているサービスも多く、導入のハードルは決して高くありません。この機会に自社のマーケティング活動の一環として、または顧客対応の効率化としてチャットボットを検討してみてはいかがでしょうか。
チャットボットについて詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
チャットボットとは?意味やメリット、活用事例を徹底紹介
業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。
メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。
AI製品・ソリューションの掲載を
希望される企業様はこちら