生成AI

最終更新日:2024/02/08
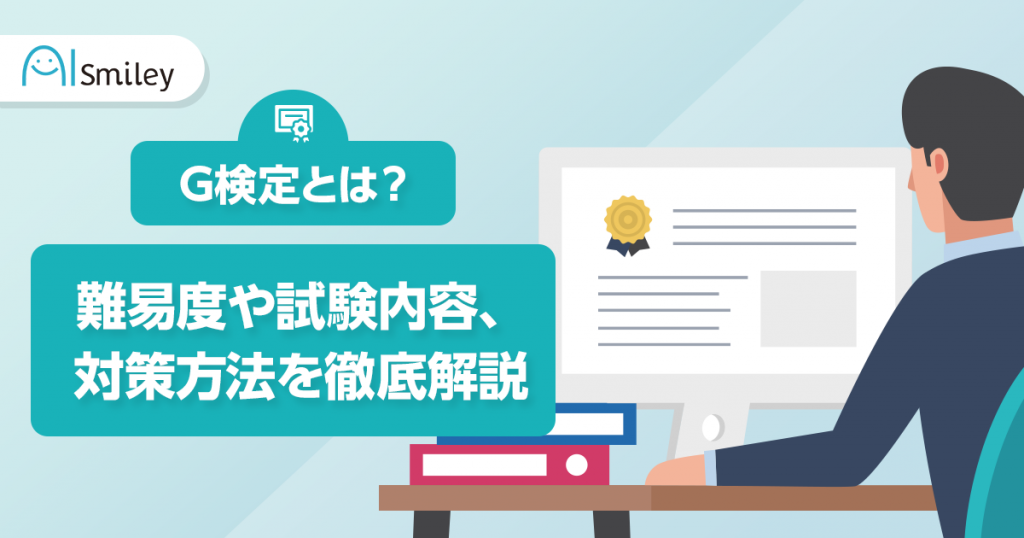 G検定とは?難易度・試験内容・対策方法をご紹介
G検定とは?難易度・試験内容・対策方法をご紹介
働き方改革やDX推進は企業が解決すべき重要な課題となっており、さまざまな企業でAIやディープラーニングの知識を身につける必要性が生じています。AIやディープラーニングの知識を身につける方法にはさまざまなものがありますが、近年、多くの企業が推奨している「G検定」の受検がおすすめです。
本記事では、G検定の概要や難易度、試験内容、対策方法などについて徹底解説します。これからG検定の受検を検討している人は、ぜひ参考にしてください。
ディープラーニングについて詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
ディープラーニングとは?特徴や仕組み、活用事例をわかりやすく解説

G検定(ジェネラリスト検定)とは、一般社団法人ディープラーニング協会が主催している、AIやディープラーニングに関する検定試験です。
G検定を通して、ディープラーニング(深層学習)の基礎知識を習得し、知識やスキルを活用して適切な活用方針を定め、ビジネスに活用する能力を測ることができます。
試験時間は120分で、220問程度の多肢選択式の知識問題が出題されます。オンラインによる自宅受検なので、会場に足を運ばなくても、インターネットに接続できる環境があれば受検が可能です。正式な合格ラインは公表されていませんが、70%程度が目安と言われています。
試験日程や開催回数は毎年異なりますが、2023年は3、5、7、9、11月の合計5回開催される予定です。直近では、2023年3月3日(金)16:00〜・4日(土)13:00〜の2日間(受検申込受付期間:2022年12月1日(木)〜2023年2月22日(水))となっています。
受検料は一般が13,200円、学生が5,500円(ともに税込)ですが、2年以内の再受検の場合は、受検料が半額になります。申込前に試験概要をよく確認し、早めに必要な手続きを済ませましょう。

近年ではDX推進やAI活用を重視する企業が増えてきており、AIやディープラーニングの基礎知識、活用方法などを学ぶことの重要性は、以前に比べて高まっています。2022年9月に帝国データバンクが行った調査でも、DXに取り組んでいる企業は8割を超えており、このことから、AIリテラシーを学べるG検定の需要も高まっています。
JDLAが2022年に実施したアンケート調査では、G検定の受検を推奨している企業は249社にのぼり、業種や職種にかかわらず、さまざまな企業で導入が加速しているのが現状です。
このような背景から、2023年にはG検定の開催回数を前年の3回から5回に増やすなど、JDLAでもAIやディープラーニングの学びの機会を増やす施策を展開しています。

G検定を受検することで、機械学習やディープラーニングの具体的手法を体系的に理解できます。また、AIを深く知ることによって、AIができること、できないことを理解でき、現場の運用に活かす効果も期待できるでしょう。
また、AIを活用した新たなビジネスの創出に役立てたり、課題解決やバリュー向上の施策を打ち出したりする際にも役立ちます。ここでは、G検定を受検する6つのメリットについて分かりやすく解説します。
G検定のシラバスには、機械学習やディープラーニングの手法に関する内容が定義されています。したがって、G検定対策を進めることは、機械学習やディープラーニングの具体的な手法を理解することにもつながります。
機械学習やディープラーニングを活用して現場の課題を解決したり、新たなサービスを生み出したりするためには、そもそもこれらの技術がどのような手法で成り立っているのかを理解する必要があります。
機械学習やディープラーニングに初めて触れる人や、これからさらに深く活用していきたい人にとって、G検定の学習を通して知識を身につけることは非常に重要です。
G検定の学習を通してAIの特徴を学ぶことで、AIにできることとできないことが分かるようになるというメリットもあります。
AIはこれまで人間の手で行っていたさまざまな業務を代行し、多くの作業を効率化できますが、全ての業務を担えるわけではありません。このことから、AIに任せられる部分は機械化を進めてリソースを削減し、従来のように人間の判断が必要な部分に重点的にリソースを割り当てる運用方法を確立することが重要になります。
AIのメリットを最大限に活かすためには、AIが代行できる範囲を正しく理解して、効率的なマネジメントを行うことが重要です。
AIの特徴を正しく理解していれば、自社ビジネスのどの部分にAIを活用できるのかを具体的にイメージしやすくなります。
AIは、膨大なデータを処理して最適な回答を自動的に導き出したり、人間の代わりに接客をしたり、発注数量を予測したりと、さまざまな分野に活用できます。用途が広いからこそ、AIがどのような目的で使われるのかを使用者側が理解しておかなければ、AIを効果的に事業活用するためのアイディアは湧きにくくなります。
AIは人間をはるかに超える速度で思考できますが、AIを運用するのはあくまでも人間であり、使用者側がAIの使い道を具体的に理解しておくことが大切です。
G検定では、AIの基礎知識や機械学習、ディープラーニングといった、AIに関連する幅広いカテゴリの問題が出題されます。それぞれのカテゴリについて詳しく理解することで、自社のビジネス上の課題を解決する際の施策や実装方法の選択肢が増え、バリュー向上の手段も広がります。
ひと口に「AIを活用する」といっても、選択する手法によって施策は大きく変わってきます。AIに関連する知識を幅広く身につけておくことで、自社の課題への多角的なアプローチが可能になり、よりバリューの高い運用を実現できます。
近年では多種多様な業界でAI活用が注目されており、DX推進担当者などを配置する企業も増えてきています。しかし、知識やスキルが不十分な人材をやみくもに担当者として任命しても、施策が順調に進まなかったり、そもそも何をして良いのかが分からなかったりする可能性があります。
このような観点から、AIを最大限に活用するためには、十分なスキルを持った人材を現場に配置する必要があります。G検定の勉強を通してAIに関するさまざまな知識を身につけることで、現場を適切に運用するためにはどのような人材が求められているのかを理解できます。
G検定の資格取得によって、AIや機械学習、ディープラーニングに関する知識が十分であることを証明できます。このことから、就職や転職などの場面でAI人材やDX人材としてアピールできるのも、G検定のメリットといえるでしょう。
働き方改革やDX推進の機運が高まっていることを背景に、さまざまな企業でAIに精通した人材が求められています。しかし、AI人材やDX人材は不足しており、市場で取り合いになっている現状があります。現場で活躍できるだけの十分な知識やスキルを身につけている人材は、業種・業態を問わず重宝されます。
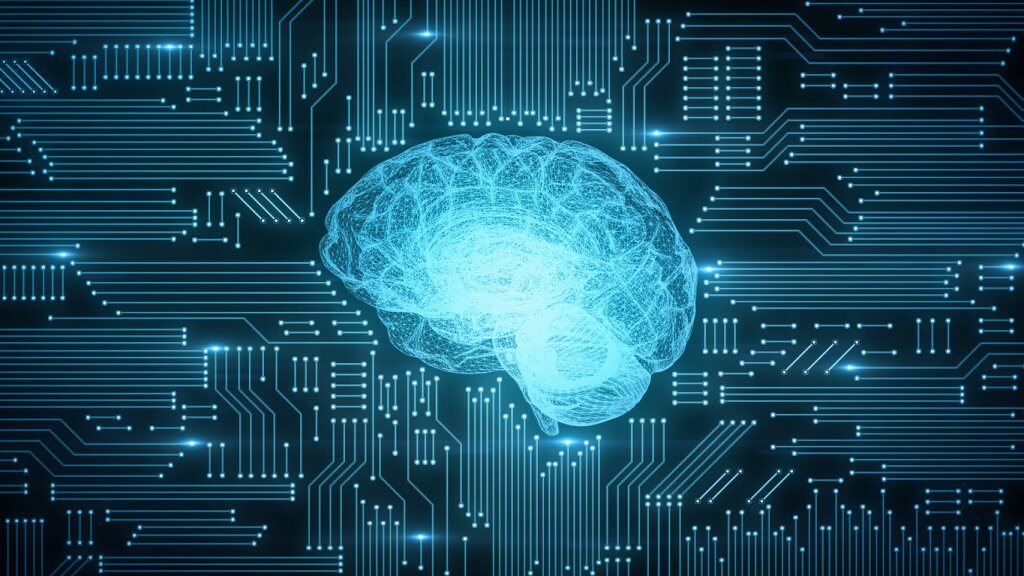
G検定の試験範囲は、独自に設定された「シラバス」に則ります。シラバスの5つのカテゴリは、次のようになっています。
「1.人工知能(AI)」では、AIの基礎知識や、人工知能分野の諸問題などについて問われます。機械学習やディープラーニングの基礎となるため、初めてG検定対策に臨む方は、AIの知識から学び始めることをおすすめします。
「2.機械学習」では、機械学習の基礎知識やニューラルネットワークなどの具体的な手法のほか、統計学によるデータ活用や精度評価などが出題されます。
「3.ディープラーニングの基礎概念と応用技術」以降の3つのカテゴリは全てディープラーニングに関連する出題範囲となっており、ディープラーニングの基礎知識や、強化学習および深層強化学習などの応用問題、社会的な課題など、さまざまな関連問題が幅広く出題されます。

G検定は、AIの初学者でも合格できる可能性があります。しかし、AI関連の話題・流行に疎い学習者にとっては難易度が高い試験です。
そもそもG検定の受検者層は、受検者の職業との関連性が高く、現場でAI開発や運用を行っている人が多く見受けられます。また、学生であっても、大学や大学院などの機関で専門的に学んでいる人が中心です。
2022年にJDLAが公表したデータによれば、合格者全体のおよそ4割がソフトウェア業や情報処理・提供サービス業、コンピュータ及び周辺機器製造または販売業に属していることからも、専門性の高さが窺えます。
また、G試験は出題範囲が多岐にわたるため、AIや機械学習、ディープラーニングの幅広い知識を身につけておかなければなりません。試験時間120分のなかで220問程度の問題に回答する必要があるため、スピード感のある回答が求められる点も、難易度が高いといわれる理由です。このことから、G検定を受検するのであれば、事前の対策が必要不可欠です。

2022年11月4日(金)、5日(土)に開催された第3回G検定は、7,502名の受検者数のうち、検定合格者数は4,964名だったという結果が公表されています。受検者に対する合格者の割合は66.17%で、資格試験としては比較的高めの数値が出ています。
年代別に見ると、20~40代の合格者が最も多く、20代が35.35%、30代が29.15%、40代が22.42%で、全体の86.92%を占めています。次いで多いのが50代の10.68%で、G検定の受検者層はビジネスパーソンが大半だといえるでしょう。
職種別では、研究・開発職が22.76%、情報システム・システム企画職が21.41%で、全体の44.17%となっています。営業・販売職や企画・調査・マーケティング職、生産・製造職も受検者が比較的多い職種です。
また、学生の合格者が8.70%ほどいることからも、実務に就いていない人でも学習量や学習方法によっては合格できる試験であることが分かります。
G検定は、AIや機械学習、ディープラーニングに関する知識やスキルが問われる試験となっています。したがって、AIやディープラーニングの基礎知識を学びたい人や、AIエンジニアとして現場で活躍するための知識を身につけたい人におすすめです。
また、勤務している職場でAI活用が進んでいたり、これからAIツールの導入を控えていたりする場合に、AIの仕組みを理解する目的でG検定を受検するのも有効です。
近年では、IT企業やAI研究・開発の現場だけでなく、さまざまな企業でAI活用が広がってきています。このような背景から、専門的な職種に限らず、今後AIに触れる人であれば、誰でもG検定を受検する意義があると考えられます。
G検定の対策や勉強法には、検定対策講座や本などを活用して学ぶ方法が有効です。講座にはさまざまな種類があるため、内容や特徴をよく比較した上で、自分に合ったものを受講することが大切です。本を活用して学ぶ場合は、内容を比較しながら、自分のレベルに合わせた内容のものを購入しましょう。
また、G検定対策アプリを活用し、自学自習によって検定対策を行う方法もあります。ここでは、おすすめのG検定対策・勉強法について詳しく解説します。
講座を受講して学ぶ方法は、講師による現場目線の豊富な知識を吸収できる点が強みです。疑問点もその場で質問できるため、分からない部分があっても速やかに解消できます。ここでは、G検定対策に対応している講座を3つ紹介します。
「AI STANDARD」では、株式会社STANDARDがAIプロジェクトに必要な人材を育成するためのさまざまな講座を提案しています。デジタル変革に対応できる人材を育成する「AIリテラシー講座」は、プロジェクトに取り組むすべての人材に対応しており、G検定の出題範囲に対応した講義内容となっています。
AI基礎知識、AI技術知識、AIビジネス知識の3つの分野について学べるため、これからAIについて学び始める方にもおすすめです。受講方法はオンラインなので、自宅やオフィスからでも気軽に参加できる点もメリットです。
確認テストの実施や質問フォームの設置によって、疑問を効率的に解消でき、確実に知識が身につきます。
AI For Everyoneは、一般社団法人ディープラーニング協会が主催するAIリテラシー講座です。全てのビジネスパーソンを対象としており、AIやディープラーニングを知ることを目的とした初心者向けの講座で、エントリー料は無料です。
全世界で延べ60万人以上が受検した人気のコースに、日本向けの編纂を加えたオリジナル講座となっています。まずはAIやディープラーニングがどのようなものなのかを知りたいという方におすすめです。
また、別途49ドルを支払うことで、学習内容の確認テストを受検し、修了証を取得することもできます。修了証を取得した人は、G検定の受検料が30%割引になります。基本的に受講期間に制限はありませんが、修了証取得コースのみ、180日以内の修了が必須となります。
「AI For Everyone」で文系新入社員がAIの基礎をゼロから学んでみた!
株式会社SIGNATEでは、実戦形式でAIについて学べる「SIGNATE Quest」を提供しています。1,300以上もの豊富な学習教材を活用し、AIを初めて学ぶ人から、より高レベルな経験を積みたい人まで、さまざまなニーズに対応できる講座です。
多種多様な業界が抱える課題を疑似体験できるため、実践的な対応力が身につきます。回答形式は一問一答で、一問ごとに詳細な解説が用意されているため、分からない部分を都度確認できるのもポイントです。
3つの有料プランが用意されており、月額プラン、半年プラン、年間プランのなかから自分に合ったものを選択できます。基礎から集中的に学びたい人や、実践課題を中心に学びたい人まで、幅広く活用しやすい内容となっています。
SIGNATE Quest | 実践形式で学ぶAI / データサイエンス
G検定対策として、本を購入して独学する方法も考えられます。G検定を運営している「JDLA」という団体が監修している公式テキストを活用すると、本番の出題傾向に沿った例題を解きながら、効率よく学習できます。試験対策だけでなく、ディープラーニングの入門編としても充実した内容となっています。
また、JDLAが監修した公式テキスト以外にも、G検定対策問題集は数多く出版されています。内容を比較して、自分に合ったテキストを選ぶと良いでしょう。
ただし、全く知識のない状態で本を使って学ぶと、分からない部分が出てきたときにつまずいてしまう可能性があります。演習問題が掲載された本の前に、AIやディープラーニングの基礎知識を網羅的に学べる本を1冊読んでおくのもおすすめです。
空いた時間を有効に使える試験対策として、G検定対策アプリの活用も効果的です。G検定対策アプリには、G検定の最新シラバスに準拠した問題が320問収録されています。スマートフォンがあればどこからでもオリジナル問題にチャレンジできるため、待ち時間や移動中などを勉強時間として有効活用できます。
学習の進捗率が表示される機能や、カテゴリ別の理解度チェック機能などが用意されているため、自分の学習状況を視覚的に把握できるのもメリットです。得意分野を伸ばし、苦手分野を補うための効率的な試験対策が可能です。
料金は1,200円(2023年1月現在)で、買い切り型となっているため、一度購入すれば半永久的に利用できます。
DX推進やAI活用の需要が高まっている背景から、IT企業や研究開発職だけでなく、業種・業態を問わないさまざまな企業でAI知識を身につけることの重要性が高まっています。
AIやディープラーニングの知識を深めるためには、一般社団法人ディープラーニング協会が主催する「G検定」の受検が有効です。受検の際は、講座の受講や書籍の購入、アプリの利用など、自分に合った方法で試験対策を行うことをおすすめします。
G検定以外にも、AIに関する理解を深めたり、自社ビジネスへの応用方法を考えたりする方法はいくつかあります。これからAI人材の育成や教育を検討している方は、AIsmileyの「AI人材育成・教育サービスの比較」を活用し、自社に合ったサービスを見つけてください。
機械学習について詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
機械学習とは?種類や仕組み、活用事例をわかりやすく簡単に説明
AIについて詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
AI・人工知能とは?定義・歴史・種類・仕組みから事例まで徹底解説
業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。
メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。
AI製品・ソリューションの掲載を
希望される企業様はこちら