生成AI

最終更新日:2023/12/25
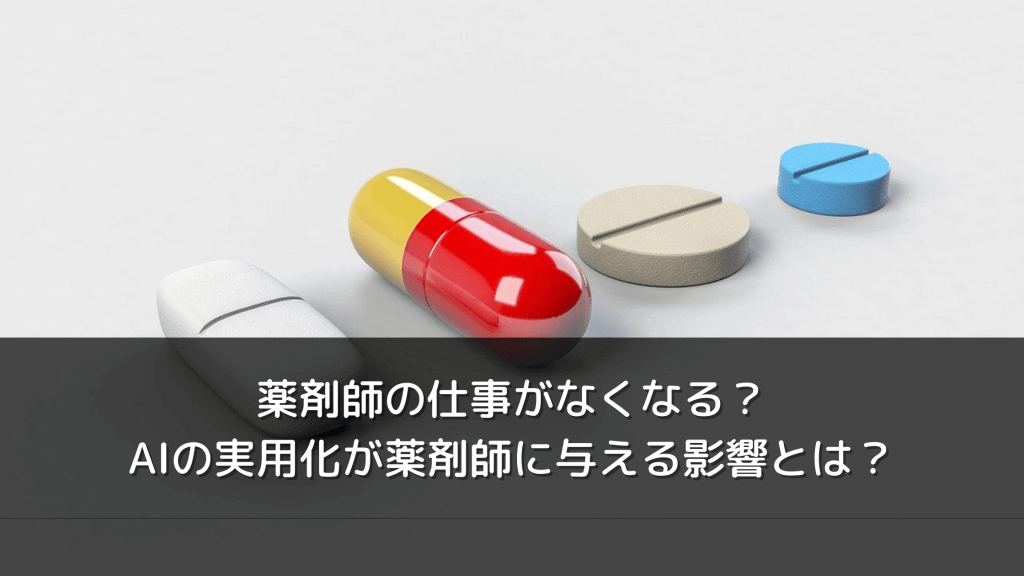 AIが薬剤師に与える影響とは?
AIが薬剤師に与える影響とは?
昨今はさまざまな分野でAI・人工知能の実用化が進んでおり、私たちの日常生活において欠かせない存在になりつつあるといっても過言ではありません。そのため、最近では「将来的にAIに仕事を奪われてしまう職業」を予測した記事なども多くなっています。
薬剤師の仕事においても電子化は進んでいるため、「将来的にはAIに仕事を奪われてしまうのではないか」といった不安を持たれている方も少なくないでしょう。そのため、今回は薬剤師にスポットを当て、「AIが将来的にどのような影響を与えるのか」という点を詳しくご紹介していきます。ぜひ参考にしてみてください。

AIが薬剤師に与える影響についてご紹介していく前に、まずは薬剤師の業務内容がどのようなものなのか、詳しくみていきましょう。
基本的に、薬剤師の業務内容は就職先によって異なります。一般的に薬剤師と接する機会があるのは病院や薬局ですが、これらの場所以外でも多くの薬剤師が働いています。たとえば、製薬会社や化粧品メーカー、食品メーカー、保健所などです。しかし、こういった場所で薬剤師と接する機会はほとんどないため、やはり「薬剤師=病院、薬局」というイメージを持たれている方が多いかと思います。
そんな薬剤師ですが、近年はこの業界でも積極的にAIが活用され始めています。その代表歴な例として挙げられるのが、薬学生向けの学力診断「メディセレAI模擬試験」です。
2021年12月1日にリリースされた「メディセレAI模擬試験」は、社内に蓄積された国家試験対策に関わる独自のビッグデータをAI技術で分析することで、よりスピーディーかつ的確に薬剤師国家試験の苦手範囲を導き出すことができるというもの。薬剤師になるための試験対策という領域でAIが活用されているわけですが、今後は薬剤師の実務にもAIが導入されるようになるかもしれません。
ここからはそんな薬剤師の主な業務内容についてみていきましょう。

調剤業務とは、病院で発行された処方箋をもとに薬を調剤する業務のことです。この業務が薬剤師の中心的な業務となります。基本的に、処方箋には先発品が記載されていますが、患者さんが希望する場合などには後発医薬品(ジェネリック医薬品)を処方するケースもあります。場合によっては、いくつかの薬剤を調剤した上で患者さんに提供するケースもあります。
服薬指導業務とは、患者さんに処方した医薬品の服用方法を説明する業務のことです。どのタイミングで服用するのか、一度にどれだけの量を服用するのかなど、適切な服薬の方法を説明する必要があるため、特に重要な業務といえるでしょう。また、飲み合わせや副作用が存在する場合には、その説明もしっかりと行う必要があります。
薬剤管理とは、患者さん一人ひとりの処方状況や、次の調剤タイミングなどを保存・管理する業務のことです。患者さんに適切な処方を行う上で重要な業務であることは言うまでもありませんが、在庫を適正化するという点においても重要な業務といえます。より的確な服薬指導を行うためにも、薬剤管理によって記録をしっかりと残しておくことが大切になるわけです。
上記3つの業務がメインですが、それ以外にも在宅医療やOTCの販売・相談といった業務が存在します。

薬剤師の業務にAIを活用することで、さまざまなメリットを得られます。代表的なものとしては「業務効率化」が挙げられるでしょう。薬剤師には、調剤業務や服薬指導、薬剤管理など、さまざまな業務が存在します。そのため、一つひとつの業務を効率的に進めなければ、別の業務にも支障をきたしてしまう可能性があるのです。
その点、AIを活用することによって、クラウドで効率的に薬剤管理を行ったり、音声入力で薬歴入力を効率化したりすることができるようになります。薬剤師に限った話ではありませんが、近年は少子高齢化に伴う人手不足が深刻化していることもあり、限られた従業員の数でいかに効率良く業務を遂行できるかが重要なポイントとなっている状況です。
そのような中で、AIの活用によってさまざまな業務を効率化・自動化できることは、薬剤師一人ひとりの負担軽減にもつながります。その負担は、肉体的なものだけではなく精神的なものもあるため、AIの活用が「離職率低下」という大きな成果にも繋がっていくのです。

薬剤師の業務にAIを活用することでさまざまなメリットが得られますが、必ずしもメリットばかりとは限りません。
たとえば、AIを導入することで「情報漏洩のリスク」が少なからず生じる点は、一つのデメリットといえるでしょう。もちろん、注意深く対策を行うことによって、情報漏洩のリスクを極限まで下げることはできますが、ネットワークを利用する以上、リスクは伴います。そのため、常に「情報漏洩を未然に防ぐ」という意識を持ってAIを活用していくことが大切になるでしょう。
また、AIを活用するためには導入コスト、ランニングコストが発生してしまうという点も、一つのデメリットといえます。実際にはそれらのコスト以上の成果に繋がる可能性もあるため、一概にデメリットとは言い切れません。しかし、現状の課題解決に繋がらないAIを導入してしまった場合、導入にかけたコストが無駄になってしまう可能性があるため、「課題を解決する上で最適なAIは何なのか」をしっかりと検討していく必要があるでしょう。
では、先ほどご紹介した薬剤師の業務が、AIに奪われてしまう可能性はあるのでしょうか。
たとえば、「大量のデータを処理する業務」「大量のデータを利用した予測作業」「統計処理」といった業務に関しては、AIの得意分野といえます。そのため、薬剤師における「調剤業務」や「薬歴管理」といった業務は、AIが得意とする分野の業務なのです。実際、AIを活用した音声入力や予測変換などの機能が備わった薬歴システムなども活用され始めているため、こういった分野は今後さらに発展していく可能性が高いでしょう。
こういった点を踏まえると、「将来的にすべての業務をAIに奪われてしまうのではないか」と不安に感じてしまうかもしれません。しかし、AIにも苦手とする分野が存在するため、すべての業務を奪われてしまう可能性は低いと考えてよいでしょう。
例を挙げるならば、人間とのコミュニケーションが求められる業務や、共感したり強調したりするスキルを求められる業務、創造性(クリエイティビティ)を求められる業務などは、AIが苦手とする分野といえます。

それこそ、体調が悪くなったときにAIに心配されるのと、これまでに何度もコミュニケーションをとってきた信頼できる薬剤師に心配されるのとでは、安心感が大きく異なるでしょう。患者さんとコミュニケーションをとって信頼を深められるというのは、薬剤師だからこそできるものなのです。
株式会社新生堂薬局では、薬局ロボットを設備した調剤薬局「新生堂薬局 地下鉄筑紫口改札前店」を2021年7月1日に開局しました。薬の入庫と払出を自動で行う薬局ロボット「BD Rowa™ Vmax」と、市販薬をデジタルサイネージで表示することができる「BD Rowa™ Vmotion デジタル・シェルフ」、そしてQR コードをスキャンするだけで処方薬を受け取れる「BD Rowa™ ピックアップターミナル」が設備されています。
便利な点は、閉店後でも「処方せん受付ポスト」に処方せんを投函するだけで、翌日処方せんを受付し、服薬指導終了後にピックアップターミナルで受取れるという点です。昨今は人手不足が深刻化していることもあり、今後はこのような形態の薬局がさらに増加していくかもしれません。
クラフト株式会社では、展開するさくら薬局など約 50 店舗の調剤薬局において「薬剤師支援 AI ソリューション」を導入しています。「薬剤師支援 AI ソリューション」は、処方鑑査、疑義照会、服薬指導といった薬剤師が調剤薬局で担当している業務を支援するソリューションです。
特徴としては、これまでに蓄積された膨大な調剤データ、疑義照会や服薬指導の記録などを、AI技術のパターン学習で解析することができる点が挙げられるでしょう。これにより、処方の確認や疑義照会の必要性などを把握することができます。薬剤師の業務品質を高めつつ、作業効率化も図っていくことができる点は大きな魅力といえるでしょう。

今回は、AIが薬剤師に与える影響について詳しくご紹介しました。AIが得意とする業務に関しては、今後AIが担っていく可能性が高いものの、AIが苦手とする分野に関しては薬剤師が担っていくであろうということがお分かりいただけたのではないでしょうか。
患者さんとコミュニケーションをとったり、共感・強調したりするスキルに関しては人間のほうが優れているため、このような分野で力を発揮できる人材が重宝されていく可能性が高いでしょう。
服用指導業務において、ただ薬の服用方法を説明するだけでは、患者さんとのコミュニケーションによって必要な情報を得ることはできません。患者さんの声のトーンや表情などを読み取りながらコミュニケーションを取ることこそが、患者さんとの信頼関係を深めていくことにつながるのです。
相手の気持ちを汲み取りながらコミュニケーションを取ることは、患者さんの精神面を支えることにもつながるため、極めて重要な役割といえます。したがって今後は、AIがデータ処理や解析などの業務を担い、薬剤師がコミュニケーションを必要とする業務を担うという棲み分けが進められていく可能性が高いでしょう。
業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。
メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。
AI製品・ソリューションの掲載を
希望される企業様はこちら