生成AI

最終更新日:2023/12/22
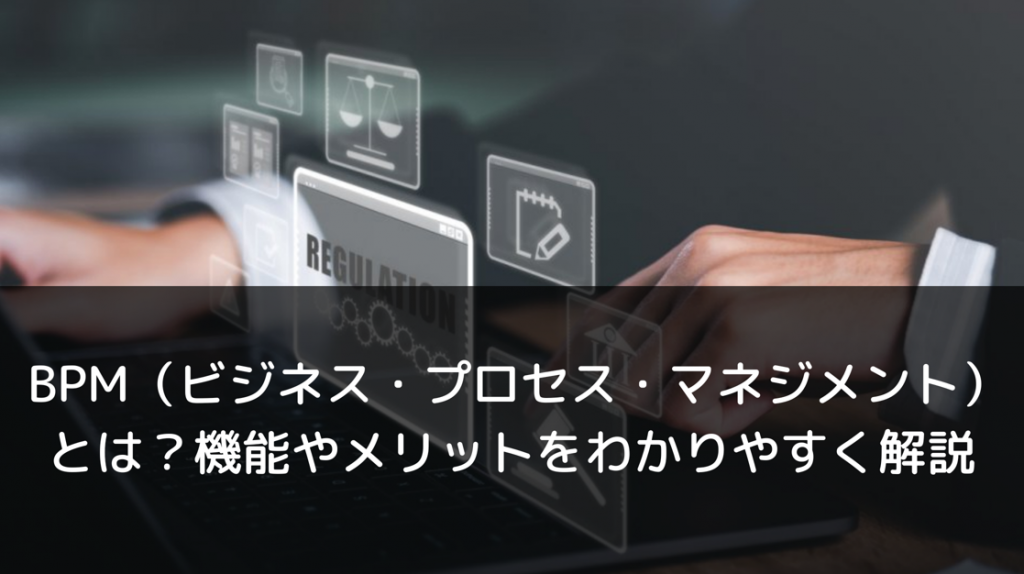 BPMとは?
BPMとは?
ビジネス環境の変化に対応していくためには、継続的に業務プロセスを改善していくことが重要です。「業務プロセスを改善していきたいが、そもそも業務プロセスがブラックボックス化していて全体像が掴めていない」といった悩みを持つ企業も少なくありません。このような悩みを解決する方法として、BPMの活用が挙げられます。
本記事では、BPMの概要や注目されている理由、主な機能、メリット、デメリットなどを解説します。

BPMとは「Business Process Management」(ビジネス・プロセス・マネジメント)の略であり、業務プロセスを継続的に改善していくための管理手法を指します。BPMの主な目的は、継続的な業務プロセスの改善を通じて、業務効率化やコスト削減、属人化の解消などを実現することです。
BPMSとは「Business Process Management Suite/System」(ビジネス・プロセス・マネジメント・スイート/システム)の略であり、BPMの推進を支える情報システムを指します。BPMSの主な目的は、情報システムによって業務プロセスの可視化や再設計、プロセス実施状況の管理などを行うことです。
BPMが業務プロセスを改善するための管理手法を指すのに対し、BPMSはBPMを効率的に実行するためのツールである点に違いがあります。
BPMNとは「Business Process Model and Notation」(ビジネス・プロセス・マネジメント・アンド・ノーテーション)の略であり、ビジネスプロセスをモデル化する際の表記法を指します。BPMNの主な目的は、記号やアイコンなどの表記法を使ってビジネスプロセスをわかりやすく視覚化することです。
BPMで業務プロセスを改善するためには、継続的にPDCAサイクルを回していくことが重要です。BPMNによって業務プロセスを視覚的にわかりやすく表記することで、継続的なBPMの実行に役立ちます。
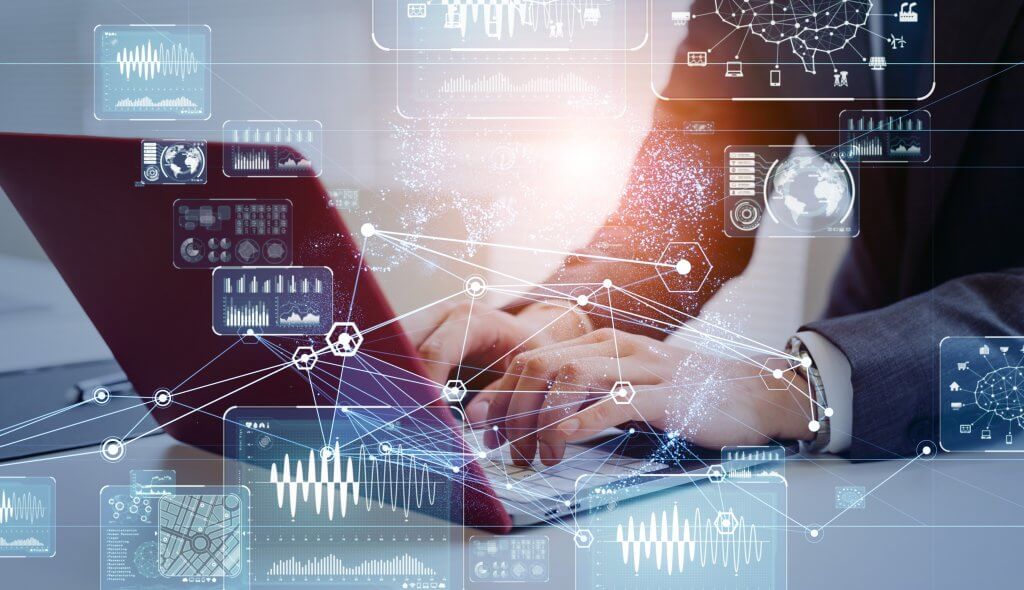
BPMが注目されている主な理由として、ビジネス環境の急激な変化が挙げられます。
近年では、グローバル化やデジタル化などビジネス環境の変化が著しく、顧客ニーズの変化に対応していくためには業務プロセスを柔軟に改善していくことが必要です。また、コロナ禍に伴うリモートワークの普及など、働く環境の大きな変化も起こっています。
変化の激しい環境において企業の競争力を維持・強化していくためには、常にPDCAサイクルを回しながら業務プロセスを改善していく取り組みが不可欠です。このような背景から、継続的に業務プロセスを改善していく管理手法であるBPMに注目が集まっています。

BPMの主な機能として、以下の4つがあります。
それぞれについて解説します。
モデリング機能は、業務プロセスを可視化・再設計できる機能です。業務プロセスをフローチャートなどで表現することで、これまで見えていなかった業務全体の流れを俯瞰できるようになります。
フローチャートなどで業務プロセスの全体像を可視化できれば、無駄な業務や重複している業務を見つけやすくなります。改善すべきプロセスについてはフローチャートの再設計を行うことで、業務プロセス全体の見直しを図れます。
シミュレーション機能は、業務プロセスを変更したことで生じる可能性のある影響を予測する機能です。モデリング機能によってフローチャートの再設計を行った場合、画面上では問題ないように見えても、実際に業務を行った際に想定外の影響が生じる場合もあります。
業務への影響を防ぐためには、事前に再設計後の業務プロセスのシミュレーションを行うことが大切です。また、シミュレーション機能によって、業務影響を未然に防ぐことに加えて業務プロセス変更による改善効果を検証することもできます。
モニタリング機能は、モデリングによって再設計された業務プロセスを監視する機能です。実際の業務活動で生じるログを取得することで、業務プロセスの監視や状況把握を行えます。
モニタリング機能によって、再設計された業務プロセスが想定通りに機能しているかを確認でき、問題がある場合はモデリングの改善につなげることができます。
連携機能は、BPMと他のツールとの間でデータの送受信を行える機能です。連携機能を活用することで、ツール同士を連携させるためのプログラム作成の手間削減や複数の業務プロセスの効率的な連携につながります。

BPMを導入するメリットとしては、主に以下の点が挙げられます。
BPMを導入することで、業務の本質的な課題を明確化できます。BPMで業務プロセス全体を俯瞰的に可視化することで、これまで見えていなかった業務の無駄や非効率な部分を浮き彫りにすることが可能です。
業務の無駄や非効率な部分が発生している原因を関係者全員で話し合うことで、業務の本質的な課題を抽出することができます。業務上の課題が明らかになれば、たとえば「同じデータの転記作業をなくす」など、業務効率化や作業工数の削減に向けた具体的なアクションにつなげられます。
ビジネス環境の変化に対応できる点もBPMを導入するメリットです。BPMでは、フローチャートなどによって業務プロセス全体をプロセスごとにわかりやすく管理できます。
ビジネス環境に変化が生じた際でも、各業務プロセスの内容を追加・変更することによって、柔軟に変化に対応していくことが可能です。不確実性の高い現代のビジネス環境においては、業務プロセスの柔軟な見直しができるBPMの導入メリットは大きいといえます。
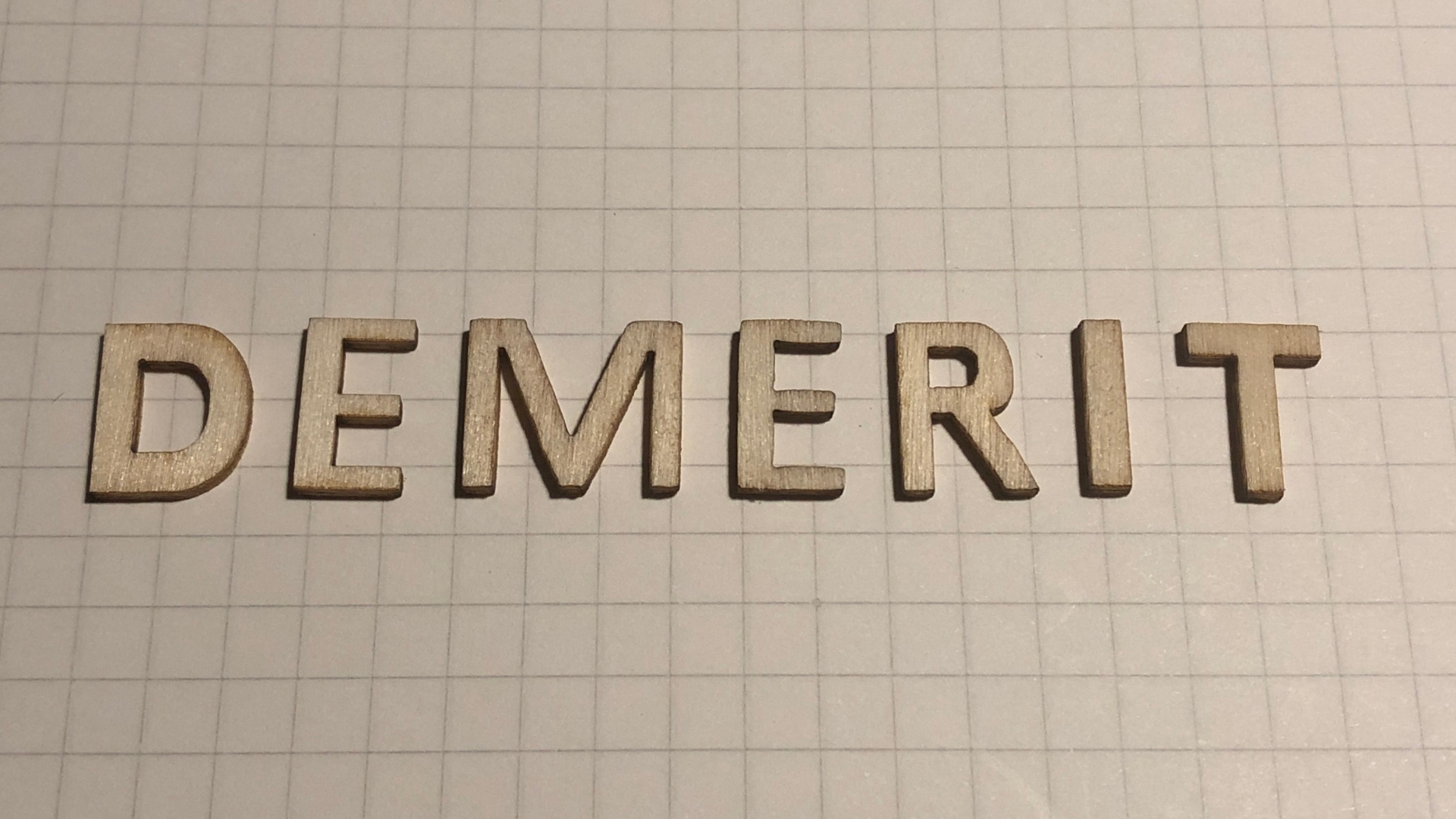
BPMには前述したメリットがある一方で、以下のようなデメリットも存在します。
BPMを導入する際は、担当者の業務負担が一時的に増加する可能性がある点がデメリットです。BPMでは、現行業務に関するさまざまな情報を集め、業務プロセスを可視化していくことが求められます。
担当者は、日々の本業に加えて業務プロセスの全体像を可視化していく作業も必要となるため、一時的に負荷が高まることが想定されます。
しかし、BPMによって業務プロセスを改善していく効果を考えれば、一時的な業務負担の増加は許容範囲内であると捉えることもできます。
BPMの導入にあたっては、社員への教育も必要です。BPMによって業務プロセスの可視化や再設計、導入後の業務運用を行うのは現場の担当者となるため、BPMの目的やツールの利用方法などをしっかりと説明していくことが求められます。
社員への教育が不十分である場合、現場業務において混乱が生じ、計画通りに業務を進められなくなるおそれもあります。現場トラブルを防止し、社員がスムーズにBPM導入後の業務を遂行できるようにするために、定期的な説明会や研修などを開催していくことをおすすめします。

これまで述べたように、BPMの業務改善ではPDCAを回すことが大事なポイントです。ここでは、BPMでPDCAを回す流れについて、以下の手順に沿って解説していきます。
まずは業務プロセスの再設計を行います。本工程はPDCAの「P」(計画)にあたる段階であり、業務プロセスのなかで改善余地のある部分を抽出し、プロセスの追加や変更を検討していきます。
プロセスを再設計する際は、5W1Hの観点で業務の目的や内容、担当者、期限、方法などを明確にすることがポイントです。また、「作業時間を○○時間短縮する」など、定量的な目標を設定しておくことで業務プロセスの改善効果を検証しやすくなります。
プロセスを再設計したら、実際に業務プロセスの運用フェーズに入ります。本工程はPDCAの「D」(実行)にあたる段階であり、再設計した業務プロセスにしたがって業務を進めていきます。
業務プロセスの運用においては、運用中の気づきや課題について適宜メモを取り、後で振り返りの際に確認できるようにしておくことがポイントです。
業務プロセスの運用後は、運用結果を分析して見直すフェーズに入ります。本工程はPDCAの「C」(検証)および「A」(改善活動)にあたる段階であり、運用中の気づきや課題などを基に業務プロセスの改善策を検討していきます。
分析・見直しにおいては、プロセスの再設計(Plan)で設定した改善目標の達成状況を確認することがポイントです。目標の水準に到達していない場合は、関係者間で原因などを話し合い、さらなる業務プロセスの改善に向けたアクションを打ち出していくことが大切です。
また、各業務プロセスの細かい内容にこだわりすぎず、視点を広げて業務プロセス全体の見直しを改めて考えていくことも大事なポイントとなります。

BPMは、業務プロセスを継続的に改善していくための管理手法であり、業務効率化やコスト削減、属人化の解消などを主な目的としています。BPMを導入することで、業務の本質的な課題を明確化できるとともに、ビジネス環境の変化に対応できるようになります。
一方、BPMの導入にあたっては、現場担当者の業務負担が一時的に増加する点や社員への教育が必要となる点には注意が必要です。
BPMでは、PDCAサイクルを回しながら継続的に業務プロセスを改善していくことが大事なポイントとなります。プロセスの再設計や運用、運用結果の分析・見直しを繰り返しながら、業務プロセスの最適化を図っていきましょう。
業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。
メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。
AI製品・ソリューションの掲載を
希望される企業様はこちら