生成AI

最終更新日:2025/06/05
 正則化とは?
正則化とは?
機械学習やAIの導入が進む中で、「正則化(Regularization)」というキーワードを耳にする機会が増えてきました。特に、過学習(オーバーフィッティング)のリスクを避け、モデルの汎化性能を高めるうえで欠かせない技術です。本記事では、正則化の基礎から具体的な手法、実務での活用例までを分かりやすく解説します。AIやDXの導入を検討している企業担当者の方にとって、正則化の理解は極めて重要ですので、ぜひご覧ください。

正則化とは、機械学習モデルの過学習(オーバーフィッティング)を防ぎ、汎化性能を向上させるための手法です。特に、モデルが学習データに過剰に適合し、新しいデータに対する予測精度が低下することを防ぐ役割を果たします。
正則化とは、モデルが学習データに過度に適合しすぎる「過学習」を抑えるために、損失関数に制約を加える手法です。目的は、未知のデータに対する予測精度を向上させることです。もともと機械学習モデルは、複雑にするほど訓練データへの適合度が高くなりますが、その結果、汎化性能が低下し、現実のデータに対して不正確な予測を行うことがあります。これを防ぐために、モデルの複雑さにペナルティを与える正則化が用いられます。
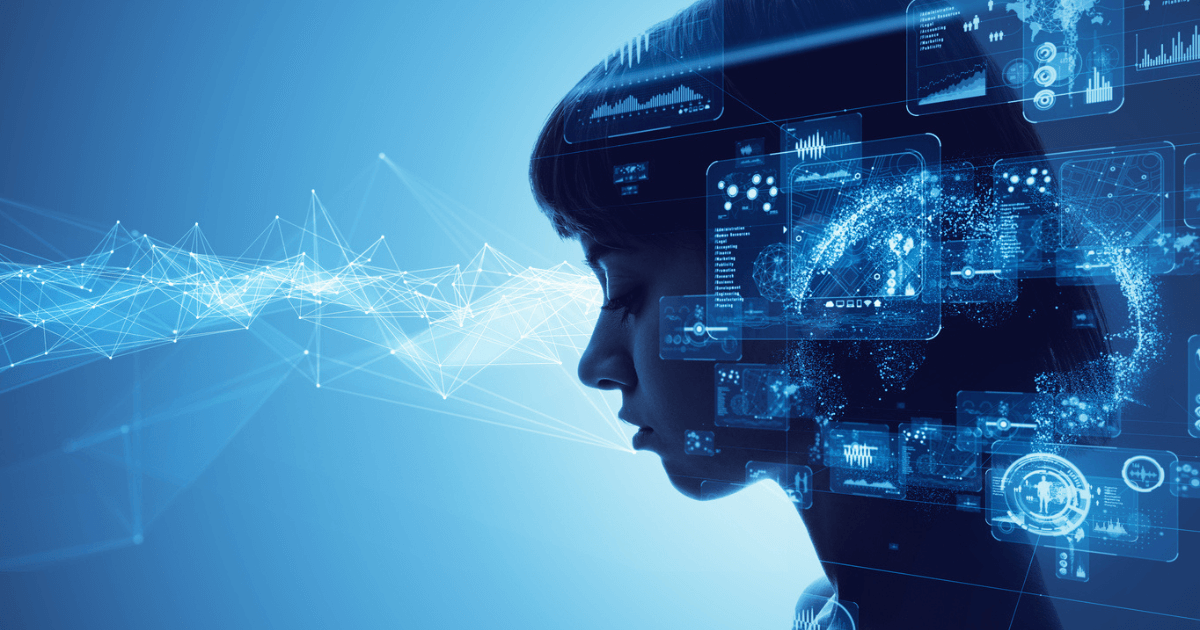
代表的な正則化の手法には、以下のようなものがあります。
L1正則化では、損失関数に係数の絶対値の総和($||w||_1$)を加え、重みの絶対値の合計をペナルティとする手法です。不要なパラメータを削除する、特徴選択としても有効です。
メリット:スパースなモデルを作成できる
デメリット:パラメータの急激な変化が発生しやすい
L2正則化では、損失関数に係数の二乗和($||w||_2^2$)を加えます。パラメータの値を小さく抑えられる点が特徴です。
メリット:過学習を防ぎ、安定した学習が可能
デメリット:不要なパラメータをゼロにはできない
L1正則化とL2正則化を組み合わせた手法です。
メリット:スパースなモデルを作成しつつ、パラメータの安定性も確保
デメリット:ハイパーパラメータの調整が必要
ニューラルネットワークにおける正則化手法の一つで、学習時にランダムに一部のニューロンを無効化します
メリット:過学習を防ぎ、汎化性能を向上させる
デメリット:学習に時間がかかることがある
検証データの損失が増加し始めた時点で学習を停止する方法です。
メリット:最適なタイミングで学習を終了できる
デメリット:停止のタイミングの判断が難しい場合がある
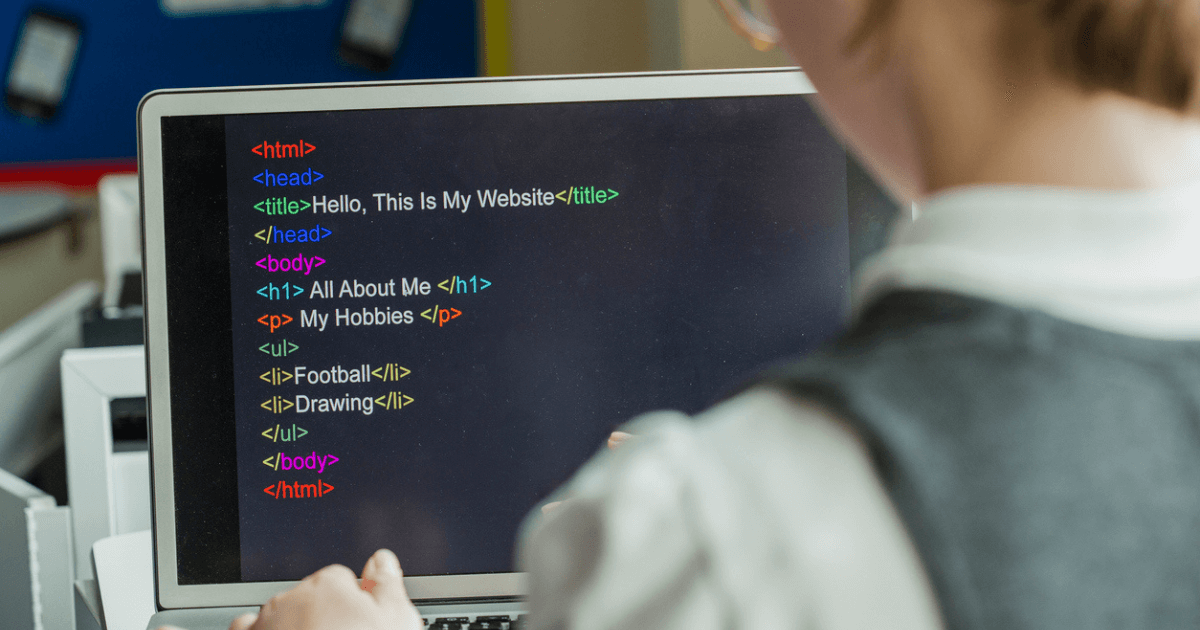
実際に正則化がどのようにビジネスに活用できるのか、事例に基づいて説明しましょう。
たとえば、どの広告チャネル(テレビ、SNS、メールなど)が売上に影響を与えているかを分析するモデルを作るとき、変数(特徴量)が非常に多くなります。この際に、似たようなデータが多く、過学習のためにモデルが過剰に反応してしまいます。
そこで、L1正則化(Lasso)を使うと、使わなくていいデータを自動的に「ゼロ(無視)」にでき、シンプルで分かりやすい予測モデルが作れます。すると、不要なデータの影響を小さくして、本当に重要な広告チャネルだけをピックアップできます。
金融機関で個人の信用スコアを予測するモデルでは、多くの数値データ(年収、勤続年数、過去の延滞履歴など)を使います。この際に、データが複雑すぎて、モデルが特定の顧客に偏る可能性があります。
そこで、L2正則化(Ridge)を使えば、モデルの数値のばらつきを抑えて、安定した与信判断ができます。極端なデータに影響されず、全体としてバランスの取れた予測を行えます。
天候や曜日、キャンペーンなど、複数の要因を使って商品やサービスの需要を予測する際、データが多岐にわたります。そうなると、関係の薄い変数までモデルが拾ってしまい、予測が不安定になってしまいます。
そこで、Elastic Net(L1とL2の併用)で、関係の薄い要因は排除しつつ、全体として滑らかなモデル構造を保つことができます。本当に意味のある要因にフォーカスして、精度の高い需要予測が可能になります。
患者の検査結果をもとに疾患リスクを予測するAIでは、多くの数値・項目(血液検査の値、体温、血圧など)を使います。しかし、重要な特徴が埋もれてしまい、AIの診断にばらつきが出る点が課題です。
そこで、L1正則化で不要な項目を削除し、医師が理解しやすい「説明可能なAIモデル」を作れます。これによって、医療的に意味のある特徴を際立たせることができるようになるでしょう。
カスタマーサポートのチャット履歴をAIで分類(苦情・問い合わせ・感謝など)するとき、膨大な単語が特徴量になります。そうなると、重要でない単語が大量に入り、処理が重くなり、精度も下がってしまいます。
そのような場合に、L1正則化を使って、重要なキーワードだけを残す分類器が構築されます。すると、意味のない単語を除外して、処理を軽く、結果も見やすくなります。
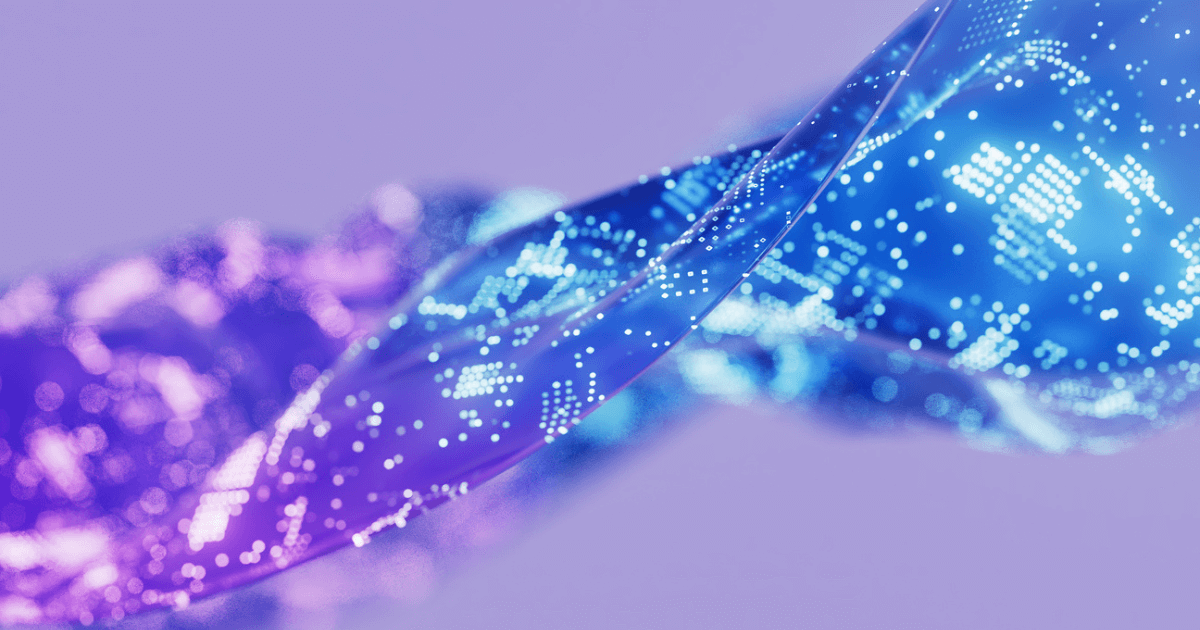
ディープラーニングでは、正則化と併せてドロップアウトを使用することが一般的です。ドロップアウトはランダムにノードを無効にすることで、異なるアプローチで過学習を抑制します。
一方、ベイズ的な視点から見ると、L2正則化は事前分布としてガウス分布を仮定することに相当します。このような理論的な背景を理解することで、モデル設計の幅が広がります。
画像や音声認識では、正則化だけでなくデータ拡張技術を併用することで、さらに汎化性能が向上します。
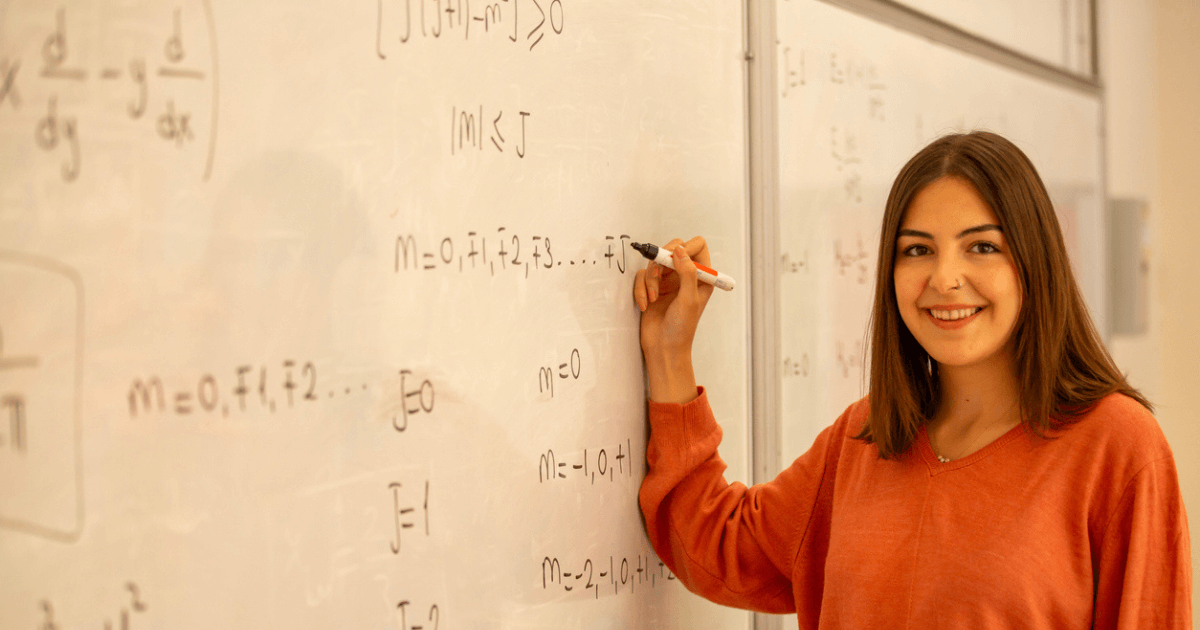
それぞれの正則化の手法の特徴・メリット・デメリットを簡単にまとめると、以下のようになります。
| 正則化手法 | 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| L1正則化 | スパース化(特徴選択) | 重要な特徴を抽出できる | パラメータの変化が急激 |
| L2正則化 | パラメータの抑制 | 過学習を防ぎ安定した学習 | 不要なパラメータが残る |
| Elastic Net | L1とL2の組み合わせ | バランスが良い | ハイパーパラメータ調整が必要 |
| ドロップアウト | ニューラルネット向け | 過学習を防ぐ | 学習時間が長くなることがある |
| 早期停止 | 学習途中で停止 | 最適なモデルを得やすい | 停止タイミングの判断が難しい |
特徴量が多く、相関関係が複雑な場合にはL1またはElastic Netが有効です。逆に少ないデータでモデルが過学習しやすい場合、L2正則化による滑らかな制約が役立ちます。
L1正則化により特徴量を間引くことで、解釈しやすいモデルを構築できます。

正則化には、いくつか注意点があります。この注意点について解説しましょう。
正則化は、モデルの複雑さを抑え、過学習を防ぐために用いられます。しかし、過度な正則化をかけると、モデルが「重要な特徴量に対しても罰を与える」状態になってしまい、モデルの学習能力が制限されすぎます。たとえば、L1正則化では影響の小さい特徴量をゼロにしますが、正則化が強すぎると、有効な特徴量までゼロになりかねません。
これを防ぐためには、クロスバリデーションを使って「正則化の強さ(ハイパーパラメータλ)」を検証し、過不足のないバランスを取ることが大切です。適切なλを選ぶことで、性能と汎化能力の両立が可能になります。
正則化を効果的に機能させるためには、すべての特徴量が同じスケール(桁や単位)であることが前提です。たとえば、「年収(数百万円)」と「年齢(数十歳)」という2つの特徴量があると、年収の値の方が大きいため、モデルは自動的にそちらを「重要」と判断しがちです。正則化をかけた場合、数値の大きい特徴に過剰なペナルティがかかり、モデルの学習に偏りが出ます。
この偏りを避けるために、特徴量は標準化(平均0、分散1に変換)または正規化(0〜1にスケーリング)してからモデルに入力しましょう。これにより、すべての特徴量が平等に扱われ、正則化が正しく機能します。
正則化には主にL1、L2、Elastic Netの3種類がありますが、それぞれ向いているデータやタスクが異なります。一律に適用するのではなく、慎重な検討が必要です。選択を誤ると、精度が上がらなかったり、過学習が残ったりする可能性があります。
そのため、データの性質(例:特徴量の数、相関性、ノイズの多さ)に応じて、最適な正則化手法を選びましょう。可能であれば複数の手法を比較し、モデル評価指標(AUC、精度、F1スコアなど)を見ながら選定するのが理想です。
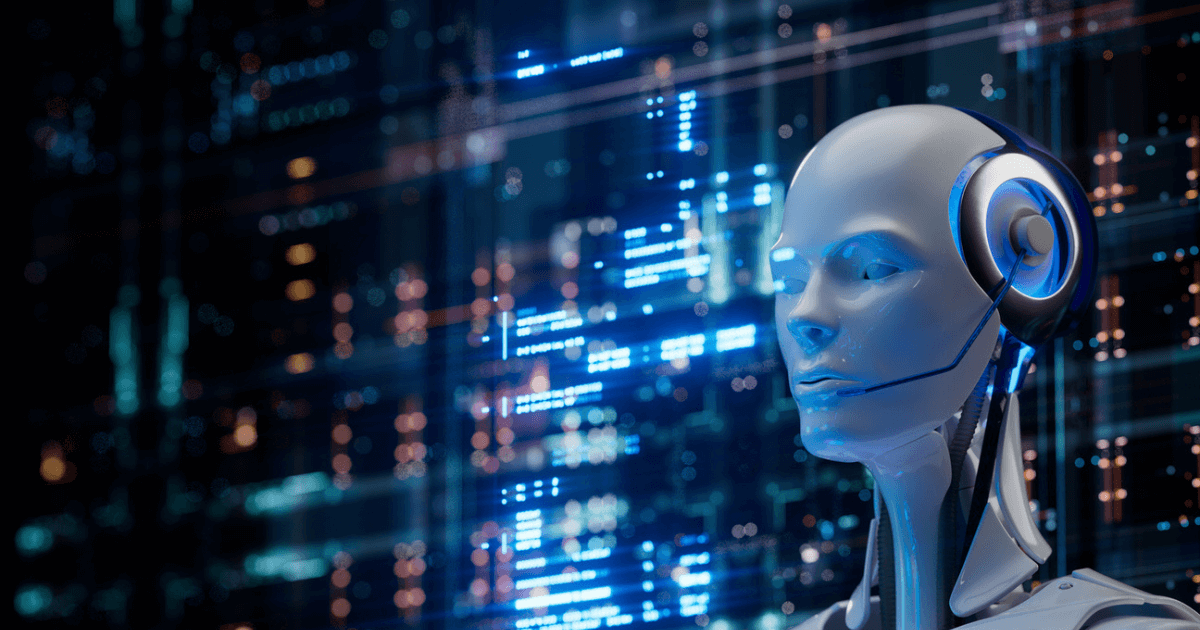
正則化は、AIや機械学習モデルをビジネスに活用するうえで、過学習を防ぎ、安定した性能を発揮するために欠かせない技術です。L1・L2・Elastic Netといった主要な手法の特徴と使い分けを理解し、実データに応じた最適なアプローチを選ぶことが求められます。
アイスマイリーでは、AIモデル開発・機械学習支援のサービスとその提供企業の一覧を掲載しています。自社でのAI導入やモデル最適化に活用できる、最適なAIサービスを選定するためにぜひご活用ください。
業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。
メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。
AI製品・ソリューションの掲載を
希望される企業様はこちら