生成AI
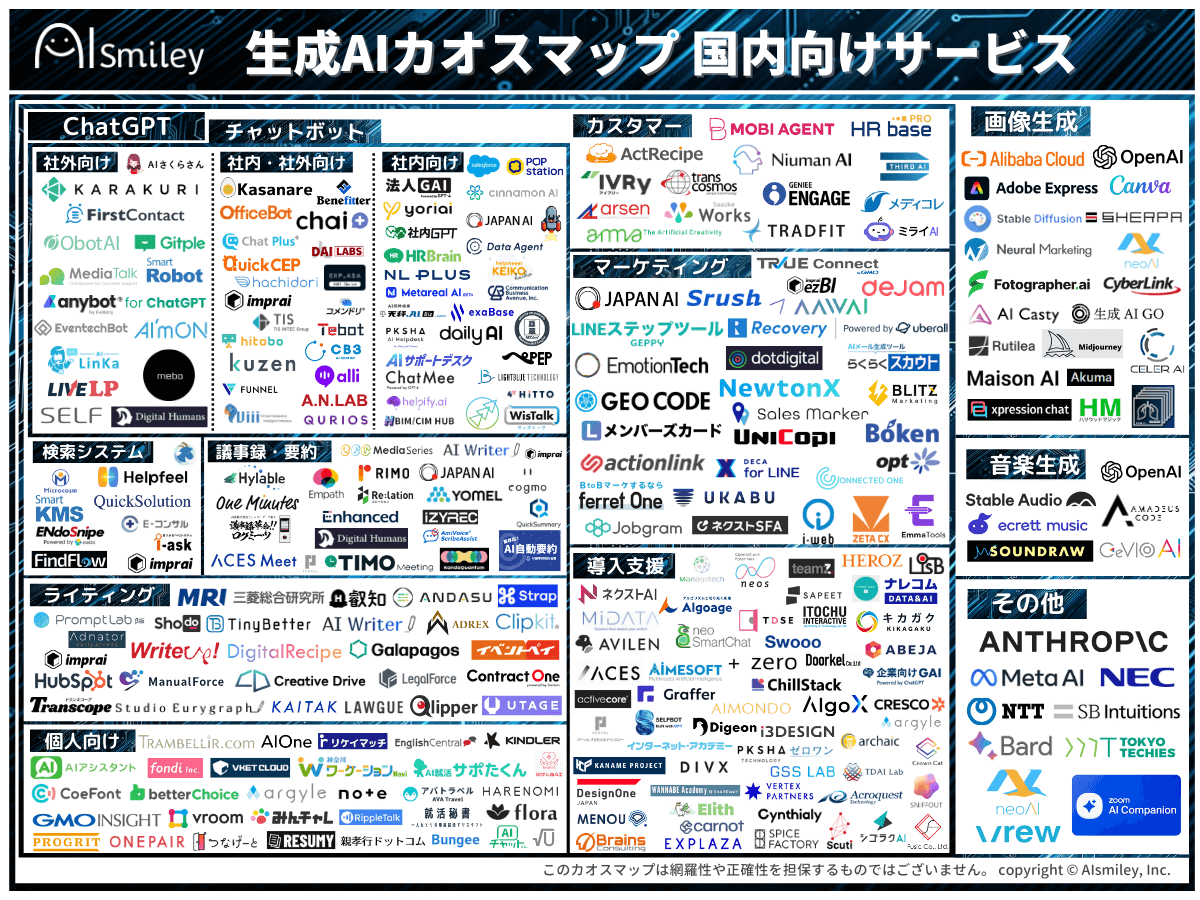
最終更新日:2024/04/23
 JDLA松尾豊氏より年始の挨拶
JDLA松尾豊氏より年始の挨拶
2023年8月26日「CDLE AII Hands 2023」にて講義を行う松尾 豊教授
ディープラーニングを中心とする技術による日本の産業競争力の向上を目指す「日本ディープラーニング協会(JDLA)」の松尾 豊 東京大学大学院工学系研究科教授から、新年の挨拶がありました。
このAIニュースのポイント
ディープラーニングを中心とする技術による日本の産業競争力の向上を目指す「日本ディープラーニング協会(JDLA)」の松尾 豊 東京大学大学院工学系研究科教授から、新年の挨拶がありました。
日本ディープラーニング協会は、ディープラーニングを事業の核とする企業が中心となり、ディープラーニング技術を日本の産業競争力につなげていこうという意図のもとに設立されました。ディープラーニングを事業の核とする企業および有識者が中心となって、産業活用促進、人材育成、公的機関や産業への提言、国際連携、社会との対話 など、産業の健全な発展のために必要な活動を行っています。
――松尾教授
皆様、あけましておめでとうございます。
昨年はまさに生成AIに始まって生成AIに終わった年でした。昨年の年頭所感では、リリースされて間もないChatGPTが大きな産業上の可能性をもつと述べました。しかし、実際には、予想を大きく超えて、全世界を巻き込んだ巨大なブームとなりました。OpenAIのSam Altman氏は、TIME誌の2023年のCEO OF THE YEARに選ばれました。11月にあったAltman氏の解任劇は、映画のような展開でしたが、こんなことが起こる1年になると誰が予想したでしょうか。
昨年1年を通して大きなニュースが続きました。OpenAIからは、GPT-4, ChatGPTプラグイン、Code Interpreter,(Advanced Data Analysis), GPT-4V, GPT-4 Turbo, GPTsなど、発表が相次ぎました。MicrosoftからもCopilot Studio, Azure OpenAI Serviceが、Googleからは3月にBard、12月にはGeminiが発表されました。MetaからはLLaMAが2月に、LLaMA 2が7月に公開されました。これらがわずか1年の間にすべて発表されたわけです。まさに、息をつく暇もない1年でした。
AIに関しての安全性等の議論も世界的に活発になりました。欧州は、AI Actの議論が進み、特にリスクの高いAIに関しての規制の議論が行われました。米国は、10月にAIに関する大統領令を発表し、AIの安全性確保、活用促進に力を入れることを表明しました。11月に英国で開かれたAI Safety Summitでは、28の国と地域が賛同したブレッチリー宣言が採択されました。日本でも、年始から早いスピードで議論が進み、5月にはAI戦略会議が立ち上がりました。G7で、生成AIの活用や規制に向けたルールづくりを目指す広島AIプロセスが立ち上がり、12月には国際指針が合意されました。また年末には、米国や英国と並んで、日本にもAI Safety Instituteが年明けにも作られることが発表されました。
私は、AI戦略会議の座長として、5月から全7回の会議で司会進行を務めました。注目度も高く、毎回の議題が盛りだくさんで大変でしたが、国際的なスピード感とほぼ同じスピードで、この1年、日本全体のAI政策は進んでこられたのではないかと思います。政府の関係者、特に岸田総理はじめ、高市大臣や村井官房副長官、また内閣府や各省庁の方々など、関係各位のご尽力によるところが大きいですが、デジタル・AIの最先端のイノベーションに対して、日本がここまで早く反応できたことは過去にないことで、大変素晴らしいことだと思います。特に、世界中の国や組織がGPUの獲得競争をしているなかで、昨年1年、日本でも着実にGPUの拡充を進めることができ、今後の生成AI時代に向けての足元が多少なりとも整ってきたことは大変に大きかったと思います。
そういったなか、JDLAにおいても、生成AIに関する取り組みをタイムリーに進めてきました。昨年3月に開催したオンラインセミナー「生成AIの衝撃」は、事前申し込み6500人を超え、アーカイブ再生数も約50万回と、多くの皆様にご参加いただきました。5月には、「生成AIの利用ガイドライン」を発表し、様々な企業・団体のガイドライン策定の参考にしていただきました。さらに、生成AIに特化した知識や活用リテラシーの確認のためのミニテスト「Generative AI Test」を開催しました。6月の初回には約1000名、12月の2回目にはその倍近い方に受験いただき、生成AIを活用するための全体像をつかんでもらうことができました。次回は本年6月に開催予定ですが、引き続き良いものにしていきたいと思っています。
今まで行ってきた試験も順調に成長しています。G検定の合格者は73,929名となり、E資格の合格者は7,018名となりました。社内推奨資格として取り入れている企業・団体も350社を超え、資格試験としての認知度や価値も向上しています。
また、高専生を支援する高専DCONは4回目を迎え、海外から初の出場校(モンゴル科学技術大学付属高専)を迎えました。高専生の事業プランは、魚介類の養殖から健康医療、そしてESGまで広がり、ハードウェアとディープラーニングの融合がさらに進んでいます。DCON発スタートアップは現在6社に増え、高専全体の起業が注目されるなか、引き続き高専生のチャレンジを促進していきたいと考えています。
こうした活動の結果、JDLAの正会員は41社、有識者会員23名、賛助会員48社、行政会員は25団体に増加し、さらに広範なネットワークを築くことができました。今後、さらに日本の産業競争力の向上に資するべく、人材育成や活用事例の発信、また業界全体の意見の取りまとめ等にますます力を入れていく所存です。引き続き、協会へのご支援とご指導を賜れますよう、よろしくお願い申し上げます。
今年一年が、皆様にとって良いものとなりますよう、また、ディープラーニング・生成AIの技術が日本全体・社会全体に新しい希望をもたらすことを願って、新年のご挨拶とさせていただきます。
2024年第1回G検定は、1月13日(土)に、E資格は2月16日(金)~18日(日)の3日間実施予定です。
業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。
メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。
AI製品・ソリューションの掲載を
希望される企業様はこちら