生成AI
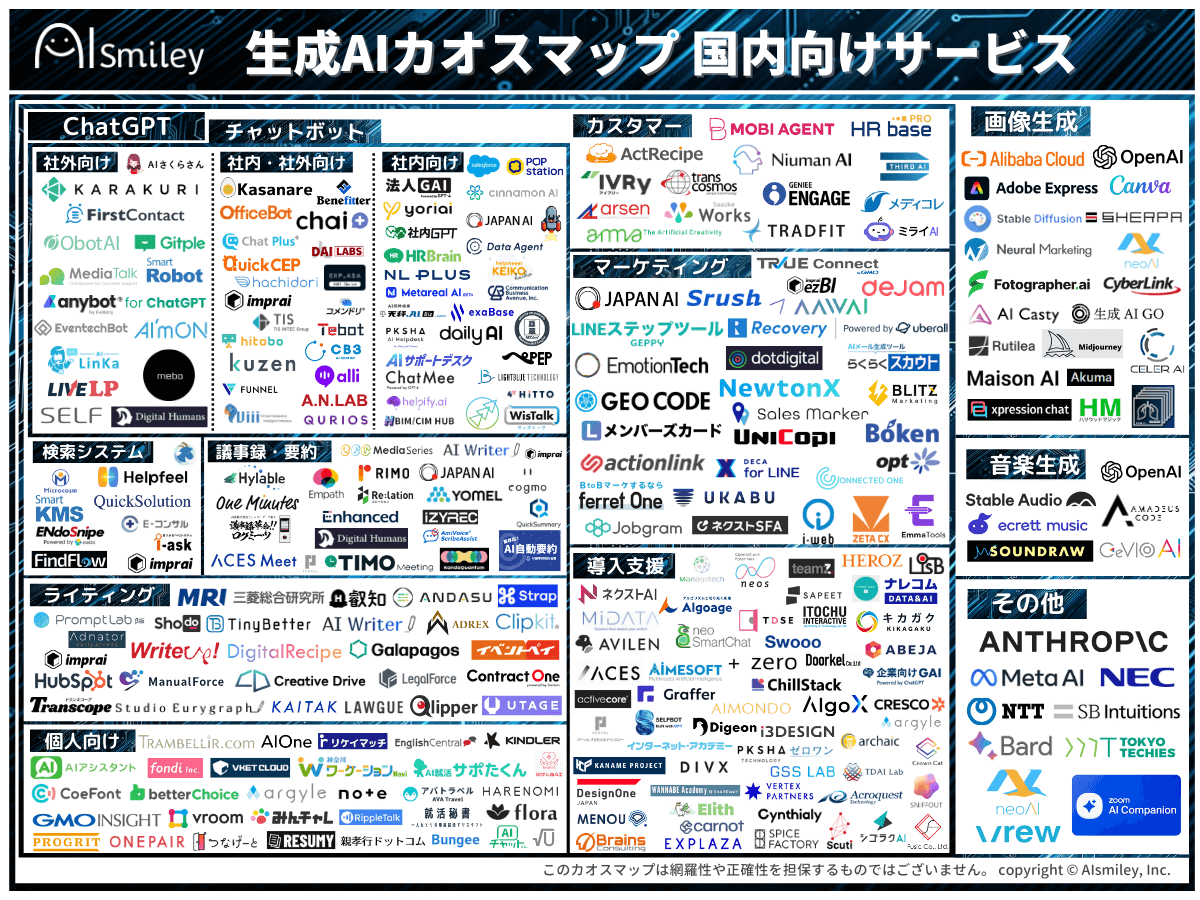
最終更新日:2024/04/05
 フレキシキュリティとは
フレキシキュリティとは
近年は少子高齢化に伴う人手不足が深刻化していますが、それと同時に「働きやすさ」という点にも注目が集まっているのをご存知でしょうか。人材が限られている現代において、より優秀な人材を雇用するためには、働き手が「ここで働きたい!」と思えるような環境の構築が欠かせません。
こういった背景もあり、最近では雇用の柔軟性を図る政策である「フレキシキュリティ」が積極的に進められています。今回は、このフレキシキュリティのメリット・デメリットや、各国で進められているフレキシキュリティの事例などを詳しくご紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
AIについて詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
AI・人工知能とは?定義・歴史・種類・仕組みから事例まで徹底解説

フレキシキュリティ(Flexicurity)とは、柔軟性に優れた労働市場を整備すると同時に社会保障によって労働者の生活を守る政策のことです。安全を意味する「フレキシビリティ(Flexibility)」、安全性を意味する「セキュリティ(Security)」の2つを組み合わせて生まれた造語であり、日本だけでなくさまざまな国で大きな注目を集めています。
では、「柔軟性に優れた労働市場」とは具体的にどのようなことを指すのでしょうか。この具体的な例として挙げられるのは、「雇用規制の緩和」「手厚い失業保険の給付」といった取り組みによって、より働き手がプライベートとの両立を行いやすくしたり、次の職場を探しやすくしたりすることです。
例えば、労働市場の規制を緩和し過ぎてしまった場合、同時に雇用調整が簡単に行えるようになってしまうため、景気が悪化した場合の失業率はさらに高まってしまうことが懸念されます。しかし、労働者の保護ばかりに重きを置いてしまうと、経営状態を悪化させてしまったり労働者のモチベーション低下を招いてしまったりしてしまうリスクも考えられます。
そのため、企業と労働者のどちらにもメリットが生じるよう、「雇用規制の緩和」と「労働者保護」のバランスを考えながら、働きやすい環境構築を進めていくことが大切になります。

フレキシキュリティと混同されがちな言葉の一つとして、ワークフェア(Workfare)が挙げられます。このワークフェアとは、働くことを条件に公的扶助を行うものです。働くことによって、精神的自立、経済的自立が促進できる(働くことでやりがいや生きがいを感じられる)といった考えに基づいています。
そもそもワークフェアという言葉は、労働を意味する「ワーク(work)」、福祉を意味する「ウェルフェア(welfare)」を組み合わせた造語です。ワークフェアを導入する場合、生活保護などの受給者には労働が課せられます。「働いた対価として給付する」という制度を導入することによって、精神的な自立を促進できるという考えがベースとなっているわけです。
また、働くことは訓練にもなるため、スキルを身につけられるという側面もあります。そのため、経済的な自立につながるとも考えられているのです。ただし、ワークフェアを取り入れる場合、生活保護の観点からは「働いた分だけ保護を受けられない(損をする)」という考え方が生まれてしまうため、生活保護と両立させるには仕組み自体の見直しなどをはじめ多くの課題があります。

フレキシキュリティには、企業にとっても従業員にとってもさまざまなメリットがあります。具体的なメリットとしては、以下のような点が挙げられるでしょう。
フレキシキュリティでは雇用の規制を緩和していくため、失業率を高めてしまうように感じる人も多いかもしれません。しかし、フレキシキュリティは失業率の改善につなげることが可能です。というのも、フレキシキュリティはただ雇用の規制を緩和するだけではなく、失業手当、再就職といった労働者保護にも力を入れていくからです。ただ失業手当を給付するだけでなく、効果的な職業訓練を実施したり、失業者が再就職するまでの支援を手厚く行ったりするため、失業率を改善することができます。
また、再就職を行う際には、失業者の希望やプライベートを優先しながら進めることが可能です。そのため、一人ひとりが「自分らしさ」を失うことなく長いスパンで働ける環境を整備できるようになります。
フレキシキュリティによって経済の成長が促されるという点も、大きなメリットのひとつです。高度成長期に確立した日本的雇用慣行は、そもそも労働の流動性を確保することが想定されていませんでした。終身雇用制度により、入社してから同じ会社で定年まで働き続けるという「安定雇用」での保障が期待されていたからです。
しかし、終身雇用制度の場合、キャリアアップを目的とした軌道修正(転職)が簡単ではありません。年功序列型の報酬制度、社歴によるキャリアアップなどは、個人が成長していくためのモチベーションを低下させる原因にもなりかねないものなのです。これらは、革新的なアイディアの創出が求められる業界においては、大きな弊害といえるものでした。
ただ、最近では終身雇用制度が崩壊しつつあります。誰もが自分のキャリアアップを長期的に捉えながら、前向きに転職を行えるようになりました。このような形で雇用の流動性が高まれば、一人ひとりのモチベーションアップにもつながりやすくなるため、さらなる経済成長が促されることが期待できるのです。
フレキシキュリティには、「自分らしい働き方を実現しやすい」というメリットもあります。昨今の新型コロナウイルスの影響によって、多くの企業のネット環境が整備され、働き方に多様性が生まれ始めました。実際に、新型コロナウイルスの影響によって、テレワークや地方への移住など、ライフスタイルに変化が生まれた人も多いでしょう。
そのため、自分のプライベートと照らし合わせた上で、新しい「働く環境」を手に入れたいと考えている人も多くなっていることが予想されます。フレキシキュリティを実現すれば、失業後の生活に困ることがなくなり、より前向きに転職活動を進めることもできるようになるのです。
フレキシキュリティにはさまざまなメリットがあることがお分かりいただけかたかと思いますが、必ずしもメリットばかりというわけではありません。フレキシキュリティについて正しく理解するためには、いくつか存在するデメリットについても理解しておくことが大切です。たとえば以下のようなデメリットは、フレキシキュリティを理解する上で重要なポイントといえるでしょう。
フレキシキュリティを実現した場合、企業側は労働者を解雇しやすくなりますが、常に労働力が不足してしまう可能性もあります。業種によっては、常に労働者不足の状況に陥っているにもかかわらず、2008年以降に訪れた世界的な不況によって失業者手当給付が急増するという事例もありました。
欧州労働同盟では、フレキシキュリティ戦略の背後にある意図として「企業が解雇を行う自由の拡大」と「現職の雇用保障の解消」の2つがあると考えられています。そのため、非正規雇用の拡大を強く警戒している状況です。
フレキシキュリティは、すでにさまざまな国で実現されています。ここからは、各国のフレキシキュリティについて詳しくみていきましょう。

デンマークの失業率は、4~5%程度とEU圏内では低い傾向にあります。また、就業率も約75%と高水準です。これらの数字を裏付けるものとして、デンマークのフレキシキュリティ制度である「黄金の三角形」が挙げられます。
この「黄金の三角形」とは、「解雇しやすい柔軟な労働市場」「手厚い失業手当」「充実した職業訓練プログラム」の3つを軸とした制度です。デンマークにおける失業手当は「前職の給与の約9割」となっており、最長で4年間が支給対象となります。
また、失業者向けの教育訓練制度、在職者向けの教育訓練などにも力が注がれているのも特徴です。失業者が特定の企業だけでなく外部労働市場においてもしっかりと活躍できるよう、重要なスキルを習得していく制度が整備されているのです。

オランダでは、フレキシキュリティによって失業率の低下や財政の赤字解消を実現しています。労働市場の柔軟性向上、そして低失業の維持を目的としてオランダが導入したのが、 1999年に施行された「柔軟性と保障法(The Flexibility and Security Act)」です。そのため、フレキシキュリティという概念そのものはオランダで生まれたとも考えられています。
オランダでは、フレックス労働者の労働者性や労働契約性の特定、そして労働期間が定められている労働契約から期間の定めのない労働契約への転換、派遣労働契約規制など、働きやすい環境を実現するための政策に力が注がれています。
今回は、北欧を中心に導入が進んでいる「フレキシキュリティ」のメリットやデメリット、各国の事例などを詳しくご紹介しました。新型コロナウイルスの感染拡大をきっかけに働き方が多様化し始めた現代において、非常に重要な考え方であることがお分かりいただけたのではないでしょうか。
フレキシキュリティは、労働者と企業の双方にさまざまなメリットをもたらすものであるため、正しく理解した上で「働きやすい環境」を整備していくことが重要といえます。なお、以下の記事では、業務で必要とされる新しい知識やスキルを学ぶことを指す「リスキリング」について詳しくご紹介していますので、ぜひこちらも併せてご覧ください。
業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。
メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。
AI製品・ソリューションの掲載を
希望される企業様はこちら