生成AI

最終更新日:2024/03/08
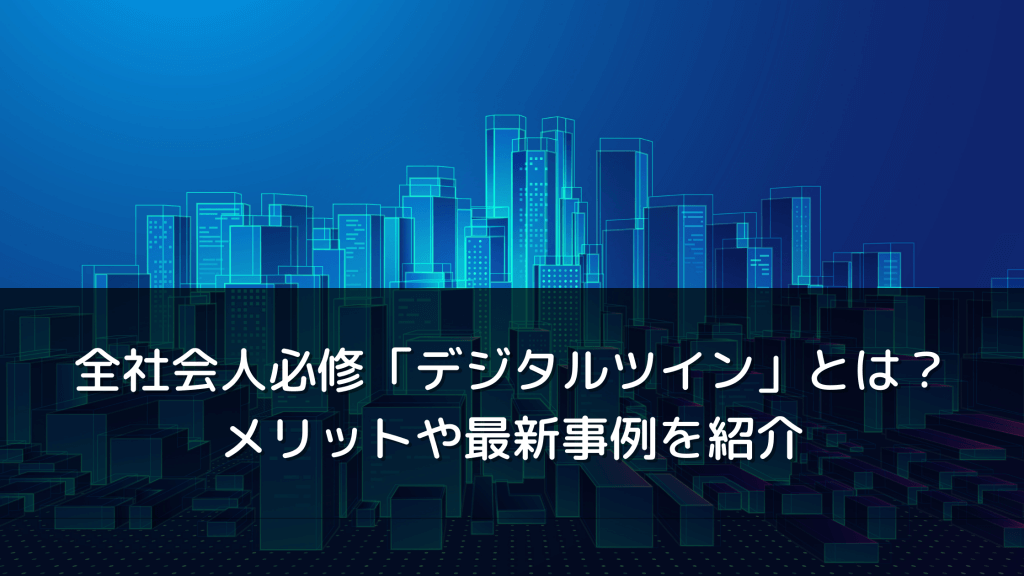 デジタルツインを解説
デジタルツインを解説
第三次AIブームと呼ばれる昨今、AI(人工知能)やIoTといったテクノロジー活用はますます活発化し始めている状況です。そのような中で、「デジタルツイン」に大きな注目が集まっているのをご存知でしょうか。
デジタルツインとは、直訳すると「デジタルの双子」という意味の言葉であり、IoT等のテクノロジーを活用することによって現実の生産設備などをデジタル上に再現する技術のことを指します。今回は、そんなデジタルツインのメリットや最新の導入事例などを詳しくご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
メタバースについて詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
メタバースとは?ビジネスへの活用メリットや今後の課題について解説

冒頭でもご紹介したように、デジタルツインとはIoT等のテクノロジーを活用することによって現実の生産設備などをデジタル上に再現する技術を指します。特徴としては、IoT等の最先端テクノロジーを活用することによって、現実の生産現場などで起きているリアルタイムの状況を「実際に現場にいるかのように詳しく把握できる」という点が挙げられるでしょう。
デジタルツインが大きな注目を集めるようになったのは、AI・IoTといった最先端テクノロジーの技術力が向上したからに他なりません。デジタルツインという言葉自体は古くから工学分野を中心にシミュレーション技術の一つとして使われていましたが、近年のAI・IoT、3Dモデリングといった技術が発展したことでさらに注目を集め始めたのです。
そんなデジタルツインですが、市場の成長という点でも大きな期待が寄せられています。Markets and Markets社が行った調査によると、2026年までに482億ドル相当の市場規模(日本円で約5兆5,000億円)になることが予測されています。
デジタルツインの基本的な内容についてはお分かりいただけたかと思いますが、中には「デジタルツインとシミュレーションでは何が違うの?」と疑問に持たれる方もいるかもしれません。
シミュレーションは、「現実世界で起こることを何かしらの手法によって再現すること」を指します。ただし、この「手法」はデジタル空間に限ったものではありません。
分かりやすい例としては、新型コロナウイルスの感染拡大のシミュレーションが挙げられるでしょう。新型コロナにおける「パンデミック」のような不確実な事象に対し、適切な「予測・対処」を行うために既存の感染データや数理モデル等を用いながらさまざまな検証が行われているわけです。当然、この場合のシミュレーションの「手法」はデジタル空間を対象には行われていません。
また、シミュレーションはビジネスシーンにおいても多く実行されます。イメージしやすい例としては、収益予測や戦略立案、リスクの分析などにおけるシミュレーションが挙げられるでしょう。
それに対し、デジタルツインは「シミュレーションを行うための一つの技術」といえます。そして、シミュレーションの大きな違いとして挙げられるのが 「リアルタイム性」「現実世界との連動」の2つです。
一般的なシミュレーションの場合、想定されるシナリオを仮定した上で設計が行われます。つまり、現実の事象を解析した上で仮定を置くことから現実の事象とリンクするわけではなくなり、リアルタイム性が低下してしまう傾向にありました。
その点、デジタルツインであればリアルタイムで稼働している「現実世界のデジタル情報」を再現し、その再現を参考にしながら将来予測を行うことができます。そのため、想定シナリオよりも「さらに現実的なシミュレーション」を行うことができるのです。
デジタルツインに注目が集まっている理由は一つではありませんが、その中でも特に大きな理由としては「AIやIoTといった技術の発展によってより高精度のデジタル空間をリアルタイムに構築・分析できるようになったこと」が挙げられます。デジタルツインを作成するためには物理空間のさまざまな情報が必要になるわけですが、これまではその情報を人の手作業によって集めていました。
しかし、AIやIoTといった技術の発展に伴い、より効率的に情報を収集できる環境が整い始めたのです。デジタルツイン作成の手間が少なくなったことは、大きなポイントといえるでしょう。
では、デジタルツインを活用した場合、具体的にどのようなメリットが得られるのでしょうか。ここからは、デジタルツインのメリットやできることについて、詳しく見ていきましょう。
デジタルツインを活用する上で、センサーデータや現場から報告されたデータを組み合わせる作業は欠かせません。これらがリアルタイムで設備と紐づけられ、正確に確認できるようになることで、初めてエラー・故障をはじめとする事象をデジタルツイン上でスピーディーに確認できるようになるわけです。そして、確認したデータをもとに、リアルタイムに対策を進めていくことが可能になります。
また、収集したデータとAI(機械学習)を組み合わせれば、デジタルツイン上でアラートを出すなどの仕組みを構築することも可能です。そのため、予知保全という点でも大きなメリットが得られます。
デジタルツインを導入すれば、ビッグデータ解析や可視化といった複合的要因の分析によって、これまで以上に高い精度での「不具合の特定」を実現することができます。
また、デジタルツインでは、現実空間では限界のあった試作・試験を仮説空間で何度も行うことができるというメリットもありますので、品質向上や顧客の満足度アップにも繋げやすくなるのです。
デジタルツインを導入すれば、デジタル空間での試作・試験が実現可能となるため、開発・設計段階でのコストを削減しやすくなるというメリットもあります。
また、新しい製品(サービス)の開発・設計に着手する前の段階で、必要となるコストや人員の試算も行えるため、無駄な予算を極力削減したい企業にとっては特に大きなメリットといえるでしょう。
デジタルツインを活用すれば、新製品の開発にかかる期間を短縮できる可能性も高まります。なぜなら、一般的なには製造業・建築業の企画・設計プロセスにおいては、設計図をもとにプロトタイプを何度も作成し、試験を行う必要がある一方で、デジタルツインでは「仮想空間上の3Dモデル」を活用して多くの試作・試験を行えるためです。これまでは、試験結果によっては設計図から作成し直す必要がありましたが、それらをすべて仮想空間上で行えるため無駄な工程を省くことができます。
物理空間でプロトタイプを作る回数も減らせることは、開発のコスト削減、製造のリードタイム短縮という点でも大きなメリットがあるのです。
デジタルツインの場合、サイバー空間上で開発する製品(サービス)のデモを作成できます。そのため、より多くの消費者に向けて製品(サービス)やブランドの価値を訴求することができるのです。
これまでは、遠方の見込み顧客に対しては製品(サービス)やブランドの価値を訴求するのが難しい傾向にありました。特に、実際に触れることで初めて価値を感じられる製品などは、「機会を移動させるのが難しい」という根本的な問題さえあったわけです。
しかし、デジタルツインであれば、実機を触ることができない場合や、機械の移動が難しい場合においても、多くの人に製品の接触機会を設けることができます。この接触機会の増加によって、顧客獲得・売上アップに繋げやすくなるという点は、大きなメリットといえるでしょう。
デジタルツインを導入すれば、サイバー空間での試作・試験を実現できるようになるため、開発・設計段階でのコストを削減しやすくなります。新しい製品(サービス)の開発・設計を始める前の段階で、コスト・人員の試算を行えるようになる点は大きなメリットといえるでしょう。
デジタルツインを導入すれば、製品(サービス)を顧客に販売した後も仮想センサーによってデータを取得し、製品の状況を把握したり寿命予測したりすることができます。また、バッテリー消耗具合や部品使用状況に応じて、最適なサポートを提供することも可能です。
状況に応じてサポート案内を自動で送信する仕組みを構築すれば、よりユーザーにとって快適な環境を実現できるでしょう。
デジタルツインにはさまざまなメリットがあることがお分かりいただけたかと思います。ただ、必ずしもメリットばかりというわけでもありません。デジタルツインにはいくつかデメリットも存在するため、それらをしっかりと把握した上で活用していくことが大切になるでしょう。
例えば、デジタルツインを実現するためには費用がかかるという点は、デメリットの一つとして挙げられます。リアルタイムでのモニタリングを可能にするためには、バーチャルセンサーを導入したり、IoTを活用したりする必要があるため、どうしてもコストが膨らんでしまう傾向にあるわけです。もちろん、事前に戦略を立てた上でデジタルツインを導入すれば、導入コスト以上の成果を得られる可能性は十分にあるため一概にデメリットとは言えませんが、導入コストが発生するという点は把握しておく必要があるでしょう。
また、都市におけるデジタルツイン導入などでは、個人情報が流出リスクするリスクがあるという点もデメリットの一つといえます。ただし、事前にこのリスクと向き合い、課題点・問題点をクリアした上で導入すれば、リスク以上のメリットを得られるでしょう。
デジタルツインは、さまざまな技術によって支えられています。具体的に、どのような技術がデジタルツインを支えているのか、詳しく見ていきましょう。

デジタルツインを支える代表的な技術の一つに挙げられるのが、IoTです。IoTとは「Internet of Things」の略であり、直訳するとモノのインターネットとなります。IoTは、モノがインターネットと接続して通信する機能を持つことで、相互に制御できるようにする仕組みのことです。
デジタルツインは、センサーや監視カメラ、ドローンなどを活用することによって、現実空間の建物、家電、自動車などからデータが収集され、収集されたデータはサイバー空間へと送信される仕組みになっています。このことからも、デジタルツインを実現する上で欠かせない技術であることがお分かりいただけるでしょう。

AI(人工知能)もデジタルツインを実現する上で欠かすことのできない技術の一つです。クラウド上に送られたデータはAIによって分析され、将来の推測に役立てられる仕組みになっています。これは、AIに「莫大なデータを高精度かつ効率的に解析できる」という特徴があるからに他なりません。
そんなAIができることは数多く存在しますが、代表的なものとしては「大量のデータ処理」「ルールに沿った作業」「共通点を見つける作業」「囲碁・将棋の対局」「画像処理や画像認識」などが挙げられるでしょう。
例えば、大量のデータを処理するスピードを比較した場合、人間とAI・人工知能ではスピードや正確さで勝負にはなりません。この分野については、圧倒的にAI・人工知能の勝利です。また、AI・人工知能は大量のデータを分析し、ある一定の「法則」や「傾向」を導き出すことも得意とします。
一方で、AI・人工知能には人間のような「ひらめき」はありません。「事実」や「ルール」のみを客観的に判断し、淡々と作業をこなしていくことに優れています。言い換えれば、限られたデータからのみしか判断できないということですが、人間のように感情によるバイアスを排除して作業を合理的に進めたい場合には、AI・人工知能が向いているといえるでしょう。
大量のビッグデータを元にサイトの訪問者をセグメント分けし、WEB接客の判断材料とするというような作業は、AI・人工知能の得意分野です。ただし、それはあくまでも「ある経験則に則って導いたデータ」でしかなく、必ずしも購買を保証するものではありません。
例えば、当初は靴を買いに来ていたのに、最終的にはハンドバッグを買って帰った顧客がいるとします。人間の販売員であれば、顧客の微妙な反応や表情、会話などから顧客の意向が靴からハンドバッグに変わったことを察知し、接客を軌道修正しつつ、顧客の最も求めている品物(ハンドバッグ)を提案することができるかもしれません。そうした感情を読む細やかさは、AI・人工知能よりも人間のほうが優れている分野といえるのです。

デジタルツインにおいて、現実空間とサイバー空間を繋げる通信手段として大きな期待を集めている技術が「5G」です。5Gという言葉自体は聞いたことがあるという人も多いのではないでしょうか。
5Gには、従来よりも高速・低遅延で大容量のデータを送受信できるという特徴があります。そのため、膨大なデータを扱うデジタルツインにおいては必要不可欠な技術の一つといえるでしょう。
サイバー空間で行われたデータ解析の結果を現実空間にフィードバックするために必要となる表現技法がARやVRをはじめとする「XR」です。XRとは、クロスリアリティを略した言葉であり、「現実世界と仮想世界を融合することによって現実にはないものを知覚できる技術」のことを指します。
ARとは、「Augmented Reality」を略した言葉であり、日本語では「拡張現実」と表現されることもあります。コンピューターを用いて現実を拡張しようとする試みのことです。例えば、スマートフォンのアプリの場合、撮影した画像や動画に写っている顔を簡単に加工することができます。これはまさに、アプリのARエフェクトによって加工が行われているのです。
VRとは、「Virtual Reality」を略した言葉であり、日本語では「仮想現実」と表現されることもあります。専用のゴーグルを用いて人間の視界を覆い、360°の映像を映すことによって「実際にその空間にいる感覚」を得ることができるという技術です。これらのVR、ARといった技術は、すべてXRに含まれます。
ARやVRでは、サイバー空間をよりリアルかつ視覚的に表現することが可能です。そのため、高い精度での分析によって「売上向上」や「コスト削減」などに繋げていく上で、非常に重要な役割を担っている技術といえるでしょう。
デジタルツインのメリット・デメリットや支える技術についてご紹介しましたが、実際にデジタルツインはどのような場所で活用されているのでしょうか。ここからはデジタルツインの活用事例についてご紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
デジタルツインが活用されている分野の一つに「インフラのメンテナンス」が挙げられます。遠隔で行うオペレーションの管理、目視での確認が難しい部位の劣化状況のシミュレーションなど、さまざまな目的でデジタルツインが活用されているのです。
その代表的な事例として挙げられるのがGE(ゼネラル・エレクトリック)です。GEでは風力発電インフラにおいてデジタルツインを活用しています。風車の寿命や劣化の予測を目視で行うと同時に、風向きに合わせることによって発電量を最大化しています。
ただ、海洋風車に関しては洋上にあるため、目視で確認を行うのは簡単ではありません。そのため、どうしても多額のコストがかかってしまう傾向にありました。そこでGEはデジタルツインを活用し、リモートかつリアルタイムでデータ分析を行うことで、モーターの交換時期の計画を効率的に立てられるようになったのです。
フロリダのウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートとカリフォルニアのディズニーランドリゾートでは、ショーやアトラクションの運用効率を高めるためのデータ駆動型ソリューションにデジタルツインを活用しています。
ディズニーリゾートでは日立と連携し、データ管理、分析、およびIoTソフトウェアがデータを収集および分析する仕組みを構築しています。ここで得た分析結果をもとに、公園の運営に関するリアルタイムの洞察へと繋げているのです。ディズニーが活用するソリューションには、予測機能やデジタルツイン、物理オブジェクトを表す仮想ソフトウェアモデルが含まれており、組織がパフォーマンスを理解して最適化するのに役立ちます。
デジタルツインの代表的な活用事例として広く知られているものの一つに、シンガポールの取り組みである「バーチャル・シンガポール」があります。バーチャル・シンガポールとは、シンガポール全体をバーチャル化していく取り組みのことであり、シンガポールの政府機関であるNRF(シンガポール国立研究財団)等が主導しているプロジェクトです。
具体的には、シンガポール全土の地形情報や建築物のデータ、交通機関をはじめとする社会インフラといった情報をすべて統合し、バーチャル空間に3Dモデルとして再現していくというプロジェクトです。
この3Dモデルに、交通情報や人の位置情報、水位といったリアルタイムデータを統合することによって「都市のデジタルツイン」の実現を目指しています。
シンガポールでは、2014年に「スマート国家(Smart Nation)」構想が打ち出されました。この構想では、「デジタル技術の活用によってより住みやすい社会を実現する」という理想が掲げています。その理想の実現に向けて、国土に関するさまざまな情報のデジタル化、そして各種センサーの整備が進められているというわけです。
東京都でもデジタルツインの活用が進められており、注目を集めています。少子高齢化や人口減少、人流・物流の変化、気候変動の危機、首都直下型地震への備えなど、さまざまな問題を抱えている東京都では、これらの課題を解決するための手段としてデジタルテクノロジーに着目しています。
東京都では、デジタルツインを産学官一体で実現することによって、上記のような課題の解決と、都民のQOL向上を目指しています。また、東京都がデジタルツインの社会実装の先駆けとなることによって、国内外他都市への波及が加速していくことも期待されているのです。
近空間も含めたリアルタイムでの人流可視化、スマートフォンを活用した3Dマップ更新検証など、社会実装に向けた検証も積極的に行われており、今後どのように東京都が進化していくかますます期待が膨らみます。
トヨタでは、代表的なプロジェクトの一つである「Woven City」開発のカギを握る技術として、現実とデジタルの両方で開発を進めていくデジタルツインに注目しています。近年は圧倒的なスピードで技術進化が続いており、都市の変化はテクノロジーの発達に追いつけなくなりつつある状況です。
そこで、トヨタではデジタルツインを利用し、リアルでつくる前に「デジタル上でさまざまなアイデアを試す」という点に着目したそうです。都市のように現実では一つしか作成できないものでも、デジタルであれば膨大な量をコピーしながらアイデアを試すことができます。
このデジタルツインによって、Woven Cityはこれまで以上のスピードで進化していく可能性が高まっているそうです。
本田技術研究所では、2014年に「VMC」(バーチャル・マニュファクチャリング・サークル)という大規模なプロジェクトを始動させました。このプロジェクトは、デジタル技術の活用によって効率的に開発を進められるようにすることや、知識・経験を最大限活用してHonda全体の開発力を高めてさらに魅力的な製品を生み出すことを目的としたものです。
そんな「VMC」の一環として、デジタルツインの実現が含まれています。近年は自動車の複雑性が増しており、それに伴ってリアルでテストする際の工数も膨大なものになっているのです。そのため、デジタルツインを活用することで工数を削減しながら、高い精度でテストを進めていくことが重要になるわけです。
そのため、今後さらに進化した製品を作り出す上で、「質」「効率」の両面を追求できるデジタルツインは極めて重要な役割を担っているといえるでしょう。
今回は、「IoT等のテクノロジーを活用することによって現実の生産設備などをデジタル上に再現する技術」であるデジタルツインのメリット・デメリットや活用事例などについてご紹介しました。データの重要性が高まっている昨今において、非常に重要な役割を担っている技術であることがお分かりいただけたのではないでしょうか。
デジタルツインの活用によって業務効率化や売上向上といった成果へと繋げていくためには、あらかじめ自社の課題を明確にした上で最適なソリューションを導入することが大切です。AIsmileyでは、さまざまなAIサービスの機能や料金を気軽に比較検討することができます。デジタルツインの活用について興味をお持ちの際は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
AIについて詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
AI・人工知能とは?定義・歴史・種類・仕組みから事例まで徹底解説
業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。
メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。
AI製品・ソリューションの掲載を
希望される企業様はこちら