生成AI

最終更新日:2024/04/03
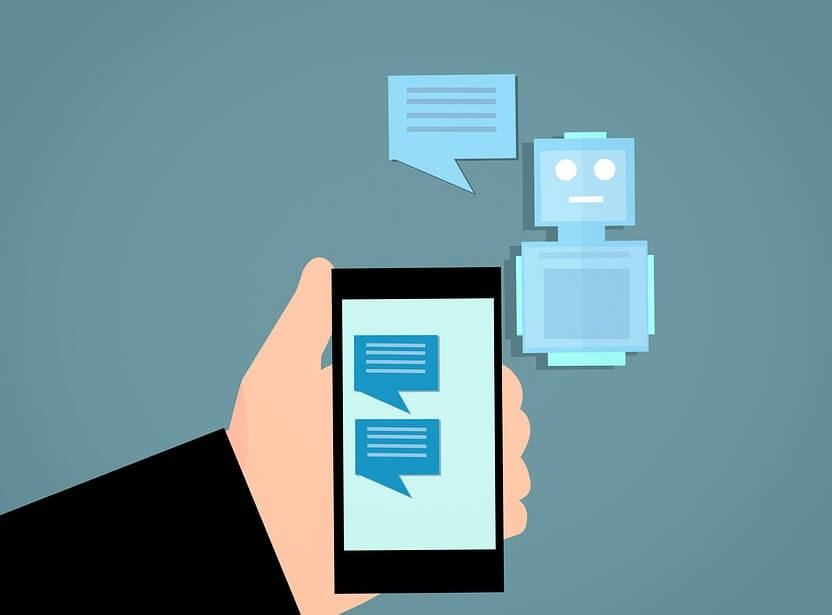
チャットボットとAI・人工知能アシスタントはよく混同されがちです。多くのチャットボットは、あらかじめ設定されたシナリオに沿って返答したり、作業を行ったりします。そのため、機械学習やディープラーニングで自ら会話の精度などを向上させていくAIと比べると、機能には限りがあるでしょう。しかし、最近ではAIを搭載したチャットボットも登場し、さらに進化を遂げ市役所など自治体への導入が進んでいます。
まずは、チャットボットとAIアシスタントの違いについて、基本的な点をおさらいしましょう。チャットボットは上述した通り、あらかじめ設定されたシナリオに沿って返答したり、作業を行ったりします。実はチャットボットは新しい技術ではなく、はじまりは1960年代に登場した「ELIZA(イライザ)」だと言われています。また、日本語環境でも、1990年代のインターネット黎明期には既にチャットボットが登場していました。かつてマイクロソフトのOfficeシリーズに搭載されていた「イルカ」をモデルにした、チャットボットを覚えている方は少なくないでしょう。
そして最近では、シナリオ型のチャットボットだけでなく会話のログを元に応答する「ログ型」、登録された単語で応答する「辞書型」などのチャットボットが存在します。これら「ログ型」や「辞書型」は会話が増えるほど応答の精度や範囲が広がり、機械学習に近くなっていきます。一方、AIアシスタントは人間との会話を通じて、人間が要望することなどに対する必要な作業をAIがその都度、会話を理解しながら行う点が特徴的です。これが、シナリオに沿っての返答や作業をする一般的なチャットボットとの大きな違いと言えるでしょう。
AIアシスタントの領域では、「Siri」(アップル)、「Google Assistant」(グーグル)、「Alexa」(アマゾン)などが主流です。これらは、スマートフォンやスマートスピーカーなどに搭載されていますので既に利用している方も多いでしょう。「Siri」などのAIアシスタントは音声認識技術によって、「Hey Siri」や「OK Google」などと呼び掛けることで起動し、インターネットの情報を検索したり、電話をかけたり、家電を操作したりします。このように現時点でのAIアシスタントは主に個人向けに活躍していますが、今後はビジネスシーンでの導入も期待され、研究が進められています。

既にカスタマーサポートやヘルプデスクに寄せられた、顧客からの問い合わせに自動で応答するチャットボットが活躍し、企業の省力化・省人化に貢献しています。しかし、一般的なチャットボットは、あらかじめ決められたシナリオに沿って返答する仕組みとなり、ルールから外れた質問には対応できません。そこで開発が進められ、最近になり、チャットボットとAIアシスタントの間を埋めるような、AIを搭載した高度なチャットボットが登場し始めました。
AIを搭載したチャットボットは言語を理解できますので、顧客からの問い合わせに対する対応の幅が大きく広がることが期待されます。ただ、AIチャットボットの開発には多くのコストが必要となり、さらに発展途上の技術ということもあり、誤作動なども考えられます。コスト面での課題が大きく、今のところ有人のカスタマーサービスほどの精度には達していないのが現状ですが、日進月歩で開発や研究が進み、多くのサービスが生まれていることも事実です。
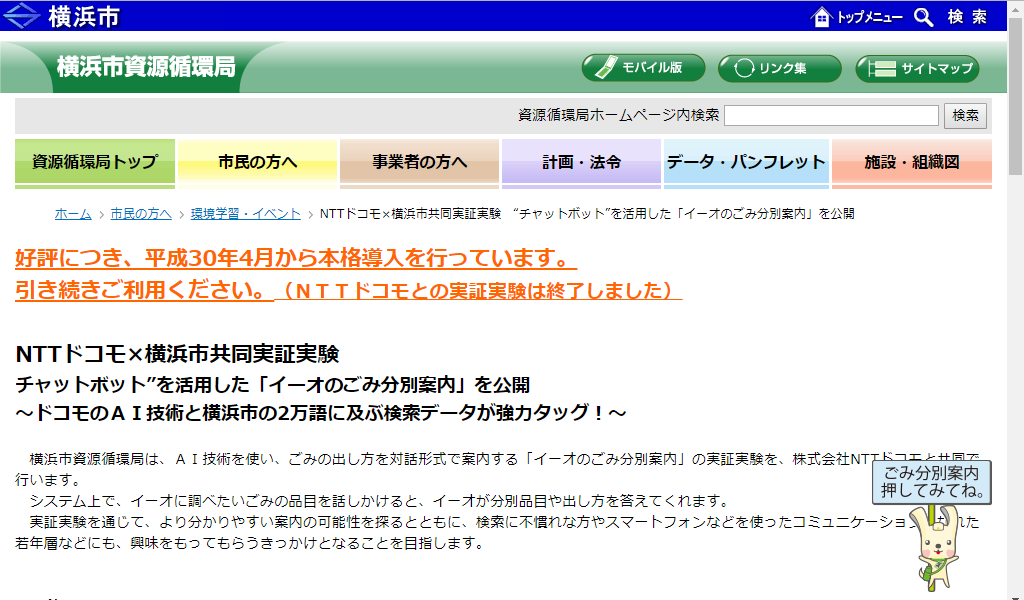
AIチャットボットの技術が発展する中で、これらを活用したユニークな事例も生まれています。例えば、NTTドコモと横浜市役所が共同実験して本格導入された「イーオのごみ分別案内」です。この事例では、「イーオ」と呼ばれるAIチャットボットが、横浜市の分別検索システム(ミクショナリー)で培った2万語以上の言語をもとに人間との会話を繰り広げています。
例えば、捨てたいごみの名前をイーオにチャット形式で入力すると、ごみの分別の方法を教えてくれます。このチャットを使って面白半分に、「旦那」と入力したユーザーに対する返答が話題を呼ぶなどしています。実は、ミクショナリーを構築する中で「旦那」や「嫁」といった、本来ごみではないはずの言葉が検索されていることが明らかになったため、横浜市役所の職員が返答のシナリオを作成したのだそうです。厳密には、AIが自ら考え出した回答ではありませんが、人間とAIの協業が実現している事例とは言えるでしょう。
また、AIチャットボットが多言語環境で活躍している事例もあります。英語や中国語に対応した、訪日外国人向けAIチャットボットの「Bebot」は、宿泊施設や観光地などで導入されてきましたが、昨今の自然災害の発生を受けて、災害発生時に取るべき行動や避難場所などの災害時サポート機能も提供され話題を呼んでいます。
今後は技術がますます発展し、AIチャットボットのサービスが増えてくることが予測されます。また、人間とAIの会話も、人間相手と区別できないほど自然なものになるかもしれません。また、フェイスブックやLINEなどといった身近なコミュニケーションツールがチャットボットのプラットフォームになっているサービスも増えていまうす。ますますチャットボットを利用するユーザーが利用しやすくなることは間違いないでしょう。
業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。
メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。
AI製品・ソリューションの掲載を
希望される企業様はこちら