生成AI

最終更新日:2023/12/06
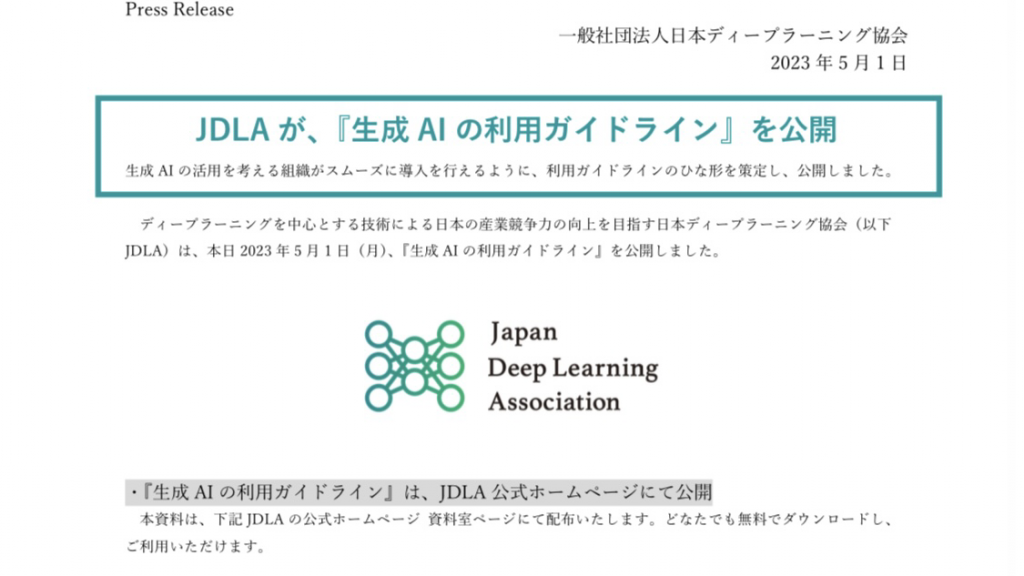 JDLA 生成AIガイドラインを公開
JDLA 生成AIガイドラインを公開
日本ディープラーニング協会(以下JDLA)は2023年5月1日(月)に「生成AIの利用ガイドライン」を公開しました。ガイドラインはJDLA資料室から閲覧可能です。
JDLA理事長の松尾豊氏は生成AI利用時の注意点を指摘。利用検討組織内での活用目的等に照らして、適宜、必要な追加や修正を加えて使えるひな型を公開しました。
組織や目的に応じたひな型 についても、順次公開していく予定です。技術の進展、業界動向に合わせて柔軟にアップデートを予定しており、ご意見・ご質問フォームも設置されています。
『生成 AI の利用ガイドライン』の作成にあたって(JDLA 理事⻑ 松尾豊氏より)

JDLA理事長 松尾 豊 氏
(2022年7月撮影)
――松尾 豊 理事長
ChatGPTなどの生成AIが急速に普及しています。個人にとっては大変便利であり、多くの人が活用をするようになってきました。同時に、さまざまな組織で生成AIの試行的な利用が始まっています。業務の生産性を上げる効果が期待されており、こうした新しい技術を積極的に使っていくことは既存事業での活用、新規事業の探索を考える上でも、大変重要です。今後、ますます多くの組織で活用が進んでいくものと考えられます。
ところが、生成AIを活用する際にはいくつか注意する点があります。たとえば、ユーザが入力するデータにおける懸念はないか。個人情報や秘密情報を入力してしまうリスクはどう考えればよいか。他人の著作物を入力してもいいのか。出力されたものの権利はどうなるのか、などです。こうした点については、どの組織でも共通するものであり、一般的な考え方を共有しておくことは大変有意義であると考えます。
このたび、日本ディープラーニング協会では、生成AIの活用を考える組織がスムーズに導入を行えるように、利用ガイドラインのひな型を作成し、公開することにいたしました。
本ガイドラインは生成AIの導入を考えている組織の方に参考にしていただければと思います。それぞれの組織内での活用目的等に照らして、適宜、必要な追加や修正を加えて使ってください。また、利用する組織や目的に応じたひな型についても、順次公開していく予定です。このひな型を用いることによって生成AIの利活用の促進、ひいては産業・社会実装が進んでいくことに貢献できれば幸甚です。
今回示したものは2023年5月公開の初版という位置付けですが、本ガイドライン内で具体例としているChatGPTをはじめとする大規模言語モデル(LLM)の技術的進化のスピードは加速するばかりであり、日々機能改善、機能追加、バージョンアップが行われています。本ガイドラインは技術の進展、業界動向に合わせて柔軟にアップデートしてまいりますので、さまざまなご意見、ご感想についてもお待ちしております。
業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。
メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。
AI製品・ソリューションの掲載を
希望される企業様はこちら