生成AI

最終更新日:2024/01/10

こんにちは。AIsmiley編集部です。
去る、2018/12/19 (水) に開催された「AIビジネスの最前線からお送りするAIと契約、知財、法律セミナー」に参加してきました。
今回はその模様をレポートさせていただきます。
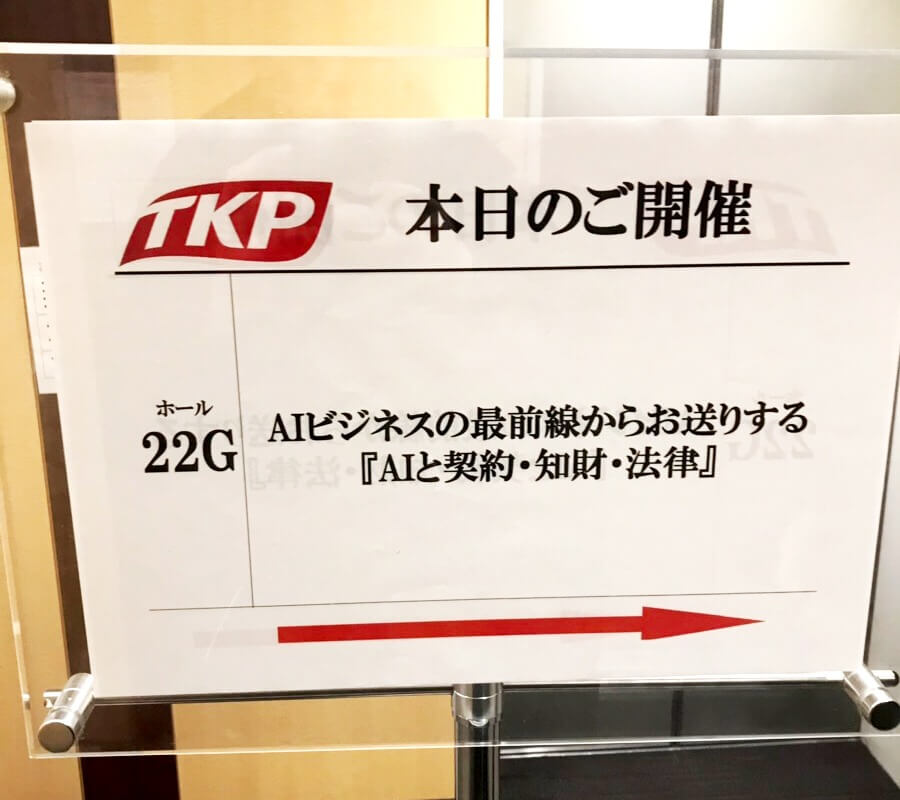 チャットボットやWeb接客・RPA等のAI・人口知能製品・サービスの比較・検索・資料請求メディア” width=”900″ height=”” />
チャットボットやWeb接客・RPA等のAI・人口知能製品・サービスの比較・検索・資料請求メディア” width=”900″ height=”” />
AI・人工知能が徐々に社会とビジネスに浸透しはじめ、画像認識・生成、異常検知、顔認証、生体認証など一定の分野においては徐々に実用化が進んでいます。
そのような状況にも関わらず、AI・人工知能の開発や保護、事故が発生した際の責任のコントロールについてはAIベンダー、AIユーザーともに試行錯誤している段階ということもあり、AI・人工知能の法律を得意とするSTORIA法律事務所がこれまで検討・提案してきた内容をもとに2018年末時点におけるいわば「AI法務の総まとめ」として「AIビジネスの最前線からお送りする『AIと契約・知財・法律』」と題するセミナーが開催されました。
主催:STORIA法律事務所
講師:弁護士 柿沼太一先生
開催場所は、東京大手町にあるTKPセミナーホールとなり、受講者は100名を超え、AI・人工知能と契約、知財、法律に対する関心度の高さを際立ちました。柿沼先生よりお話しいただいたプログラム内容は下記の通りとなります。
第1:AIと法律・知財に関する問題領域の概観~AIの適法な生成、保護、活用、法的責任~
第2:AIの生成に関する法律問題
1 様々なデータ(個人情報を含むデータ、著作権を含むデータ、肖像権を含むデータなど)を利用してデータセットや学習済みモデルを生成する場合の問題点
2 医療画像など個人情報を含んだ生データやデータベースから適法に学習用データセットや学習済みモデルを生成するには
3 第三者が著作権を有している生データやデータベースから適法に学習用データセットや学習済みモデルを生成するには
4 学習用データを収集するデータ作成者とAI学習を行う者が異なる場合、データ作成者からAI学習を行う者に対して学習用データを提供できるか
5 AI開発・研究でよく聞かれる質問についての回答
第3:AI開発契約に関する問題~AI・データ利用に関するガイドラインの解説~
1 AI開発契約において「性能保証」「検収」「瑕疵担保」についてはどのように定めればいいのか(性能保証、検収、瑕疵担保)
2 生成された学習用データセット、学習済みモデル、学習済みパラメータは誰がどのような権利を持っているのか(権利・知財)
3 AI開発・利用に際して生じる可能性のある損害について契約ではどのように定めたら良いか
第4:AIの活用~AIが自動的に生成したものを法的に保護するにはどうしたらよいか~
1 AI生成物の分類
2 AI生成物の保護
第5:AI活用による法的責任について
1 基本的な考え方
(1) AIが何らかの機器に搭載されて提供されている場合
(2) AIが純粋なプログラムとして提供されている場合
2 具体例:医療用AIが判断ミスをしたら
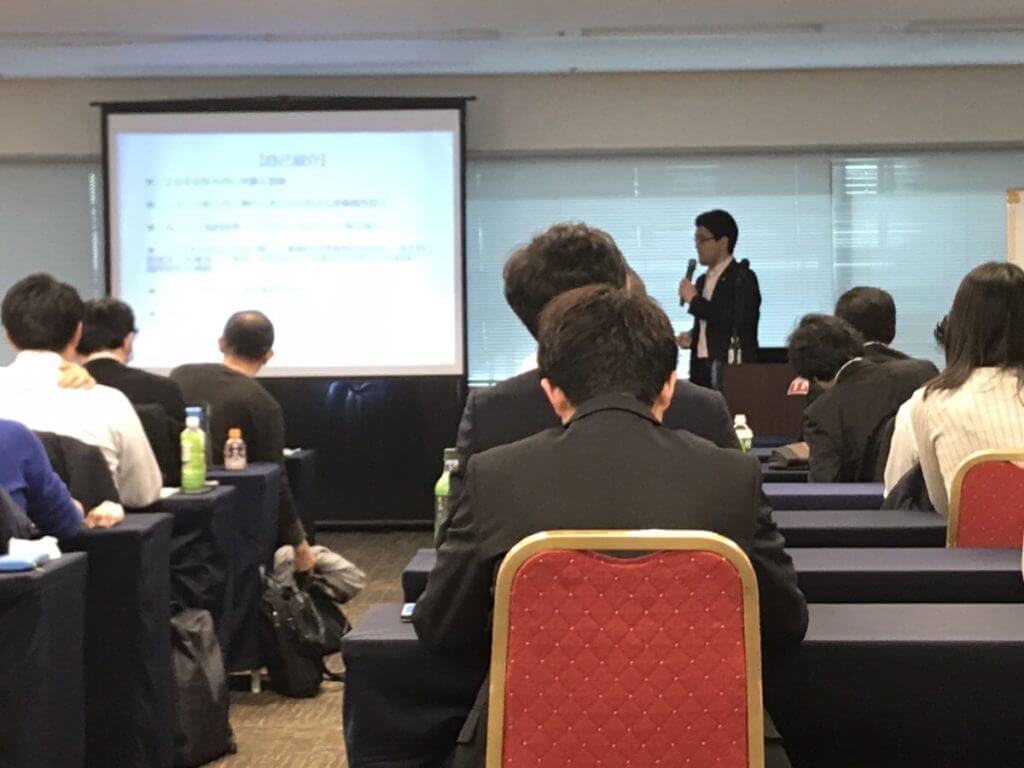
柿沼先生からはAIユーザー、AIベンダーそれぞれの視点によるの契約、知財、法律に関するお話しをお伺いすることができました。
AI開発案件は、要件定義フェーズやPoC(概念実証)フェーズ、開発フェーズがあり、細かく切って契約を締結することが重要であること。
契約はAIユーザーからの視点とAIベンダーからの視点がそれぞれあり、AI開発はシステム開発案件(請負契約)とは異なるため、事前に発注側、受託側の認識の擦り合わせが必須であること。
契約の前提には個人情報保護法、著作権法、特許法、不正競争防止法が存在しており、自組織のAI活用の際にどの部分が該当するのかイメージできたことが今回の成果でした。
今後も柿沼先生からはより進化したAI・人工知能の講義を受講できるものと思います。
業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。
メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。
AI製品・ソリューションの掲載を
希望される企業様はこちら