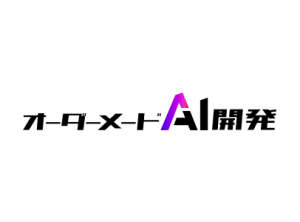
エムニのオーダーメイドAI開発
エムニの
オーダーメイドAI開発

国内外の製薬企業を支える受託製造(CDMO)を主軸に、品質と信頼を大切にしながら、多様な顧客や製品に対応してきた武州製薬株式会社。製造現場と事務部門が密接に連携し、高品質な医薬品を安定して届ける体制を築いています。
同社のDX戦略部では、業務効率化とIT活用を推進し、さらなる安定供給体制の構築を目指しています。その一環として、紙文化や属人化による業務負荷の解消に取り組み、AI社員を作成できるプラットフォーム「JAPAN AI AGENT」を導入しました。
現在では、主に事務部門での活用が進み、月266時間の業務時間の削減を実現。こうした取り組みは経済産業省からも評価され、「DX認定事業者」としての認定を受けています。
今後はAI活用社員数を200名規模にまで拡大、製造現場への展開も視野に入れた取り組みが進行中です。今回は、DX戦略部部長・上野拓真氏に、導入の背景や実際の活用状況についてお話を伺いました。

武州製薬は、「世界のヘルスケア産業の発展と人々の健康のために」というミッションを掲げています。その実現に向けて、DXを積極的に推進し、CDMO業界のデジタルリーダーを目指してきました。しかし現場にはITツールの操作に不慣れな社員も多く、「紙のほうが楽」「手書きのほうが早い」といった声が根強く残っており、DXやIT活用は思うように浸透していない実情がありました。
結果として、議事録や資料作成などの事務作業に多くの時間を割かれ、本来注力すべき業務に手が回りにくい状況が続いていたのです。
こうした中、DX推進の一環として全社的な業務課題の洗い出しを行ったところ、「生成AIで解決できないか?」という声が数多く寄せられました。顧客企業においてもDXが加速するなか、信頼の維持と競争力の確保の観点から、AIの導入はもはや避けて通れない必然の選択となっていたのです。

弊社では、顧客ごとに製造手順が異なる場合も多く、5つの工場であわせて3万件以上のSOP(標準作業手順書)を管理しています。同じ設備であっても製品ごとに手順が異なるケースが多く、紙や電子の検索に時間がかかるSOP・マニュアルが増え続けていました。結果として、現場での混乱を招く要因となっています。
必要な情報を探すのに時間がかかり、手順確認のために製造ラインが一時停止することもあります。欠品などの大きなトラブルには繋がってはいないものの、納期遅延等で顧客対応が逼迫する場面もありました。SOPや関連ドキュメントは現場に存在していても活用が難しく、「情報はあるのに使えない」という状況です。
この課題も、将来的にはAIによって解決できると見込めたことが、導入の大きなきっかけとなりました。

AIツールの選定にあたっては、有名サービスから新興サービスまで幅広く比較検討を行いました。その中で重視したのは「操作性」「連携性」「サポート体制」の3点です。
JAPAN AIは、特定のプラットフォームに依存せず、Google Workspace、Microsoft Office、Teamsなどあらゆるクラウド環境と連携できる柔軟性が魅力でした。UIはシンプルで直感的に操作でき、ITリテラシーに不安がある社員にも安心して展開できると感じられたため、高く評価しました。
また、展示会での相談時に、私たちの課題に対して真摯に耳を傾けてくれたのがありがたかったです。「できること・できないこと」を明確に伝えてくれたうえで、要望に対して具体的な提案や代替案を提示してくれたことが、大きな信頼につながりました。
さらに、時間をかければ工場現場での活用や個別開発にも対応可能であるという点も、長期的な視点から導入を決断する後押しとなりました。
JAPAN AI AGENTの大きな特長は、エージェント機能を一覧で確認できる視覚的なUXです。利用者は業務カテゴリーごとに整理されたエージェントから目的のものを選ぶだけでよいため、「まずエージェントを探す」が自然と定着しました。議事録作成、文書作成、文書チェック、メール作成、パワーポイント作成など、用途に応じたエージェントが豊富に用意されています。そのため、AIに不慣れな社員でも業務を通じて「何ができるのか」を体験しながら学べる仕組みになっています。
活用促進のための工夫としては、「生成AIを考える会」というTeamsのチームを立ち上げました。そこでは、使い方のコツや効果的なプロンプトに加え、「こうすると失敗した」といった具体的な事例まで積極的に共有されています。成功例だけではなく、うまくいかなかった経験も率直にシェアすることで、メンバー同士が気づきを得られるため、自然とリテラシーの向上につながっています。

導入から1年が経過した今、JAPAN AI AGENTは約90名の社員に活用されており、今月だけでも2週間で合計266時間40分(約16,000分)の業務時間を削減しました。中には、1人で月17時間分の業務改善を達成した社員もおり、個人レベルでも高い効果が表れています。
今や日常業務に欠かせない存在となり、ルーティン作業の多くを担ってくれています。たとえば議事録作成では、「文字起こし→要約→ネクストアクション抽出」という一連の工程がすべて自動化されました。以前は「この顧客にはこの形式でなければ」といったこだわりの声もありましたが、現在では「これで十分」と納得する声が増え、社内での信頼も着実に高まっています。
活用の幅も広がっており、メール文作成、翻訳、パワーポイント資料のたたき台作成など、提案・報告・連絡といった多様な業務をカバーしています。特に活用が進んでいるのが品質保証部門で、GMP省令の確認、教育資料の作成、文書レビューの業務をAIが支援しています。

日々の業務効率化にとどまらず、企画や戦略立案といった思考が必要な領域にも広がっています。経営企画部門では、従来、情報の収集・整理や資料作成などに多くの時間を割いていましたが、AIの導入によりそうした業務が削減され、考察・分析といった本来注力すべき業務に、より多くの時間を割けるようになりました。
そのほか、効果を発揮しているのが、戦略構想の初期段階のときです。「DX推進をどう進めるか」「協働ロボットを全工場に展開するにはどうするか」といった大局的なテーマに対して、AIが多様なアイデアや切り口を提示してくれるため、議論の出発点が明確になり、検討のスピードが飛躍的に向上しています。

最近は、画像生成AIの活用も進み、教育資料の表現方法に大きな変化が生まれています。品質保証部門では、トラブルの再発防止を目的に「リマインドシート」を紙資料として配布していましたが、従来の文字中心の構成では読まれにくく、現場への浸透が課題となっていました。
そこで思い切って、資料を漫画形式に変更。AIを用いて設備の写真や報告書をイラスト化し、視覚的にわかりやすく伝える取り組みを始めました。たとえば「容器の投入口のバルブを締め忘れ、中身がこぼれる」といった事故については、「粉が噴き出し、作業者が冷や汗をかいている様子」をイラストで表現。リアルなイメージが加わることで、注意喚起の効果が飛躍的に高まりました。
「見られない資料」から「見られる資料」へ。伝わるコンテンツづくりにAIが貢献しています。

AIの活用は、主に事務部門が中心ですが、製造現場への展開も視野に入れ、これから取り組みを加速していきます。大きな課題となっているのが、5工場にまたがり管理されている3万件超のSOPの存在です。
現状では、紙で保管されているものや、電子化されたデータも検索性が低く、必要な情報へのアクセスに時間がかかるため、トラブル対応や手順確認がスムーズに行えない場面が少なくありません。
この課題に対しては、画像データの文字情報をテキスト化するOCR技術と、JAPAN AIの自然言語処理を組み合わせた「業種特化型検索システム」を個別開発中です。トラブル発生時に「過去に何が起きたのか」「どのように対応したのか」といった履歴情報を即座に検索し、再発防止や迅速な対応につなげることを目指しています。
このシステムが実装されれば、業務の属人化を防ぎ、誰もが一定水準の業務を遂行できる環境に近づくでしょう。
AIに対して懐疑的な企業や、「今のままで特に問題はない」と考えている現場の方にこそ、ぜひ一度JAPAN AI AGENTを体験、導入していただきたいです。もし導入していなければ、私自身は、世の中の変化に気づかず、従来のやり方を続けていたかもしれません。
武州製薬では、「まず使ってみる」という文化を丁寧に育んできました。導入初期には不安の声もありましたが、安心して始められるサポート体制と、誰もが成果を出せるUX設計により、社内への定着は着実に進んでいます。
今後は、AI活用人材を200名規模にまで拡大し、全社的な本格運用を目指しています。業務効率の向上だけでなく、サービス品質や顧客満足度のさらなる向上にもつなげていきたいと考えています。
誰もがAIを業務で活用することで、人間は本来担うべき「考える仕事」に集中できるようになります。それは、働き方を根本から変える大きな一歩になると、私たちは確信しています。

武州製薬株式会社 様が導入したサービス
「JAPAN AI AGENT」をもっと知りたい方は
無料資料請求
こちらのフォームにお客様情報を入力後に製品の資料を送付させていただきます。
業務の課題解決に繋がる最新DX・AI関連情報をお届けいたします。
メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。
実際のメールマガジン内容はこちらをご覧ください。